動画を活用した情報発信が重要性を増すなか、企業が自社で動画制作に取り組むケースが増えてきました。
しかし、何から始めればよいのか、撮影や編集のやり方がわからないと感じる初心者の方もいるのではないでしょうか。
特に、社内に動画制作の専門人材がいない場合は、基本的な知識がないことでハードルが高く感じる方も少なくありません。
本記事では、動画制作のコツを基礎から丁寧に解説します。
初心者でも理解と実践をしやすいように、目的設定から編集までの各ステップの要点を紹介し、動画制作のコツが理解できる内容です。
社内での内製を検討しているBtoB企業の担当者にとって、今後の制作の第一歩となる情報をお届けします。
初心者にもわかりやすい動画制作のコツ

動画制作は、アイデア次第で誰でも始められますが、クオリティを高めるにはいくつかの基本的なコツを押さえる必要があります。
視聴者の満足度を向上させるポイントを理解することで、初心者の方でも、より効果的な動画制作が可能です。
以下に企画から構成、編集の土台となる重要なコツを紹介します。これから動画制作を始める方も、すでに取り組んでいる方もぜひ参考にしてください。
動画の目的を明確にする
まずは、なぜ動画を作るのか目的をはっきりさせることが重要です。目的が曖昧なままだと、視聴者にも伝わりづらくなります。
目的の明確化で動画全体のトーンや長さ、必要な撮影素材も決まります。
目的がはっきりしていれば、編集の際に余分な部分を削ぎ落としやすくなり、視聴者にとって価値のあるコンテンツに仕上げることが可能です。
ターゲットに届く内容を意識する

視聴者の年齢層や関心にあわせた内容にすると、再生数や反応が変わります。視聴者の目線を意識し、誰のための動画か常に考えて構成しましょう。
ターゲットのニーズや課題を先回りして汲み取り、解決策を動画に盛り込むことで、視聴者の心をつかみやすくなります。
フレームワークを使用して構成を作る
構成で悩んだら、起承転結やPREP法(Point→Reason→Example→Point)などのフレームワークを使ってみましょう。
伝えたい内容が整理され、視聴者にも伝わりやすい動画になります。フレームワークを活用すると、話の軸がぶれにくくなり、ストーリー性も演出しやすくなります。
特に初心者のうちは何をどこから話せばよいかわからない事態に陥りがちなので、構成の型をあらかじめ決めるのがおすすめです。
冒頭でインパクトを与える
動画の冒頭は視聴者の興味を引く重要な部分です。見たいと思わせる映像やテロップを入れることで、離脱を防ぎましょう。
例えば、問いかけのシーンや印象的なシーンのダイジェストを冒頭に差し込むことで、視聴者の注意を引くことができます。
冒頭で興味を持ってもらえなければ、冒頭以降の内容がどれだけよくても視聴されない可能性があるため、特に工夫が必要です。
コンパクトにまとめる
初心者にありがちなミスは、冗長な動画構成です。情報は簡潔にまとめ、必要なポイントに絞った編集を心がけましょう。
動画の長さは、目的やプラットフォームによって適した長さが異なりますが、多くの場合は3〜5分程度にまとめると視聴者の集中力を保ちやすくなります。
冗長な説明や繰り返しは避け、要点を絞って編集しましょう。1本の動画に詰め込みすぎず、シリーズ化することも効果的です。
動画制作に必要な機材

動画制作をスムーズに行うためには、適切な機材の選定が欠かせません。撮影や編集のクオリティは、使う機材の性能に大きく影響されます。
以下で初心者が揃えたい機材と、それぞれの役割や選び方を詳しく解説します。
無理に高額な機材を揃える必要はありませんが、自分の目的に合った機材を選ぶことが大切です。
カメラ
スマートフォンのカメラも年々進化しており、動画制作の入門としては十分な性能があります。
特に新しいiPhoneやAndroid端末であれば、4K撮影や手ブレ補正機能が搭載されており、高品質な映像が撮れます。
一方で、よりプロフェッショナルな見た目やボケ感のある映像を求める場合は、ミラーレス一眼カメラやコンパクトデジタルカメラの導入を検討するとよいでしょう。
機材に応じてレンズ交換もでき、映像表現の幅を広げることが可能です。
三脚やジンバル

動画のブレは、見にくさに直結します。三脚を使えば、固定カットをブレなく撮影でき、ジンバルを使うことで歩きながらの撮影でも滑らかな映像が撮れます。
三脚は、高さ調整や角度の自由度が高いものを選ぶと便利です。ジンバルはスマートフォン用の軽量モデルも多く、初心者でも扱いやすいタイプが揃っています。
動きのある映像にチャレンジするなら、積極的に取り入れたい機材です。
マイク
音声は視聴者の印象を左右する重要な要素となります。内蔵マイクは周囲の雑音も拾いやすいため、専用の外部マイクの使用がおすすめです。
屋内撮影にはピンマイク(ラベリアマイク)、屋外ではガンマイクが適しています。インタビューやナレーションなど、音声が主役になる動画では、音質のクリアさが動画の信頼性にもつながります。
照明

照明は映像の印象や被写体の見え方を大きく左右するため、自然光で撮れる日中の屋外以外では、人工照明を活用しましょう。
リングライトは顔を明るく均一に照らすのに便利で、Vlogや解説動画などに適しています。
シーンによってはソフトボックスやパネル型LEDライトなどを使って、明るさや色温度を調整できるとより映像の完成度が上がります。
パソコン
編集作業はパソコンの性能に大きく依存するため、メモリはできれば16GB以上、ストレージはSSDが理想です。
CPU性能もチェックし、可能であればGPU(グラフィックボード)も搭載されたモデルを選びましょう。
動画の書き出しやプレビュー時のスムーズさが変わるため、処理能力が高いほど効率的に作業が進みます。予算に応じて、長く使える性能を重視しましょう。
編集ソフト
初心者におすすめは、iMovie(Mac)やCapCut(スマートフォン)などの無料ソフトです。直感的に使えるインターフェースで、基本的なカットやテロップ挿入なども簡単に行えます。
より高度な編集が必要な場合、Adobe Premiere ProやDaVinci Resolveなどのプロ向けソフトを検討するとよいでしょう。エフェクトやカラーグレーディングなど、本格的な編集機能が充実しています。
覚えておきたい動画撮影のテクニック

動画を魅力的に仕上げるためには、機材だけでなく撮影時のテクニックも重要です。
視覚的な印象を左右する構図やカメラの動き、ブレの防止など、撮影の基本を知っておくだけで動画の完成度が大きく変わります。
以下が初心者に押さえてもらいたい撮影時のコツです。
構図
三分割法や対角線構図などの基本構図を意識すると、映像の見栄えが格段によくなります。
三分割法とは、画面を縦横3分割して交点に被写体を配置する手法で、バランスのよい画面構成を作るのに適しています。
また、背景とのコントラストや空間の使い方も重要です。主役が際立つように意識した構図が、視聴者の目を自然と誘導できます。
カメラワーク
映像に動きを加えることで、よりダイナミックな表現が可能になります。
パン(カメラを横に振る)やチルト(縦に動かす)、ズームインやズームアウト(拡大と縮小)などの基本操作を覚えましょう。
ただし、カメラワークを多用しすぎると落ち着かない印象になってしまうため、適度な使用が大切です。
視聴者にとって心地よいテンポや動きを意識した撮影がより魅力的な動画になります。
手ブレ対策
手ブレは動画のクオリティを下げる要因です。
三脚やジンバルの活用はもちろん、手持ち撮影の際には脇を締めて構える、壁や机に肘を乗せるなどの安定した撮影姿勢を意識しましょう。
スマートフォンやカメラには手ブレ補正機能が搭載されているモデルもあるため、設定を確認して活用するとより効果的です。
ブレの少ない映像は視聴者の集中力を妨げず、プロフェッショナルな印象を与えます。
動画編集で押さえるべきポイント

動画の魅力を引き出すためには、撮影だけでなく編集の工程も極めて重要です。
編集は単に映像をつなげる作業ではなく、視聴者に見やすさや伝わりやすさを提供するための工夫を凝らすプロセスです。
以下で初心者でも実践しやすい編集の基本ポイントを紹介します。
カット
不要な部分をカットし、テンポのよい構成を目指します。視聴者が飽きないようにリズムを意識した編集が重要です。
間延びしたトークや繰り返し表現、無駄な沈黙などを取り除くことで、動画のテンポがよくなり視聴者の集中力を保つことができます。
編集時には、秒単位で不要なフレームを削ると、より洗練された印象になります。視聴者が知りたい情報に素早くアクセスできるテンポのよい構成を意識しましょう。
テロップ
音が出せない環境でも内容が伝わるように、必要な部分にはテロップを入れましょう。情報の補足や強調にも有効です。
話す内容をそのまま文字に起こすだけでなく、重要なキーワードのみを抜き出して表示すると、視認性が高まります。
フォントや色の選び方、表示タイミングなどの工夫で、より見やすく印象的なテロップになります。視覚的なアクセントにもなるため、効果的な活用が重要です。
BGMや効果音
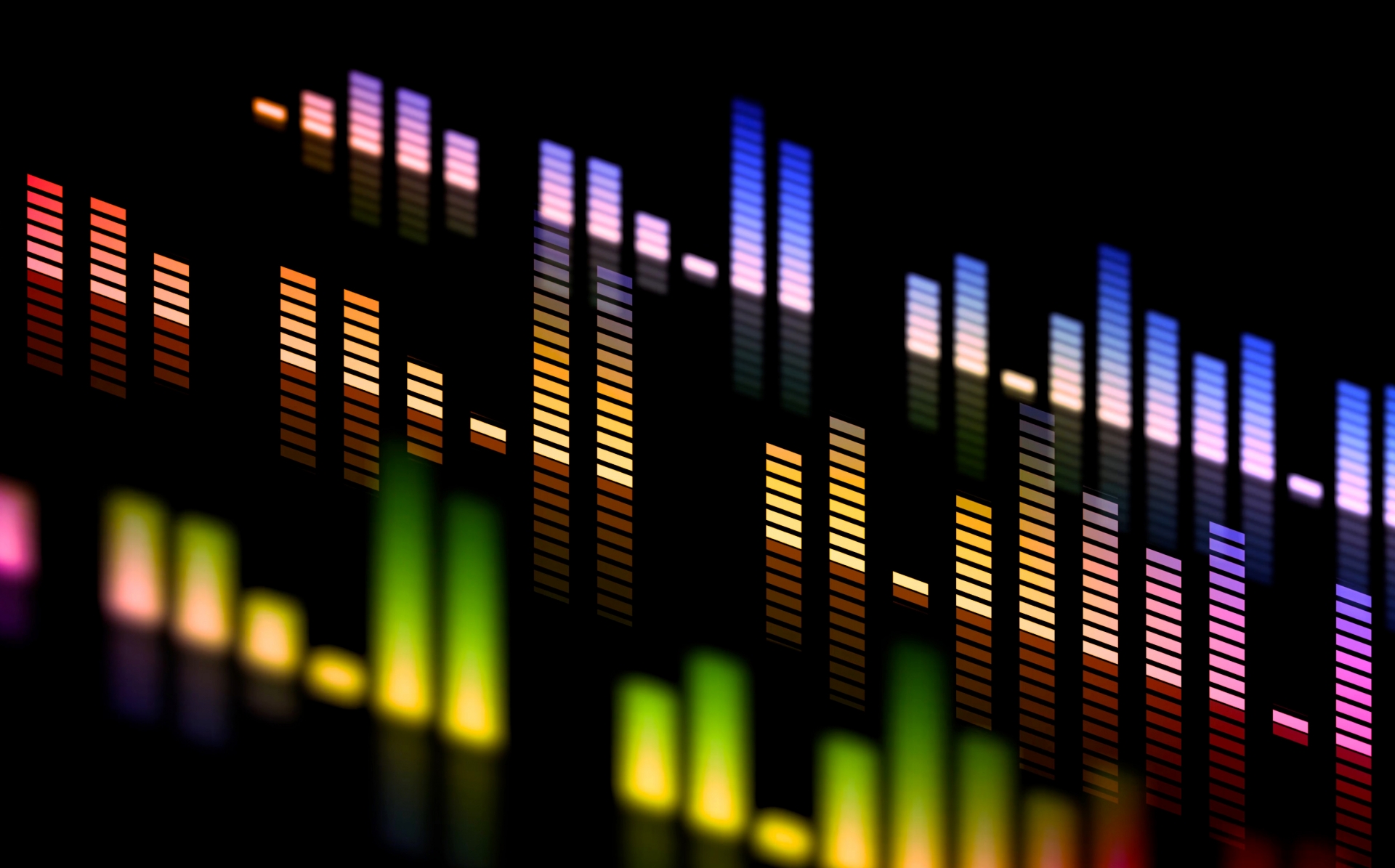
BGMや効果音は、動画の雰囲気を作る重要な要素です。著作権フリーの音源を使い、動画のテーマに合った音を選びましょう。
BGMは視聴者の感情に働きかけ、動画全体の印象を左右します。明るいシーンには軽快な音楽、感動的な場面には静かで抑えめの曲など、内容に応じた選曲を行いましょう。
また、シーン転換や強調したい部分に効果音を加えると、演出力が高まります。音量のバランスにも注意し、BGMが音声をかき消さないように調整するのも大切です。
動画制作がうまくなるコツは?

動画制作のスキルは、一度で身につくものではありません。経験を積み重ねながら、少しずつ見せ方や伝え方の精度を高めることが大切です。
最初は思うように撮れなくても、繰り返し作っていくうちにカメラの扱いや編集作業に自然と慣れていきます。
完成度にこだわりすぎず、小さな作品でも積極的に公開してみることで、上達につながります。
また、自分の視点では見えない課題を把握するためには、他者からのフィードバックをもらうことが有効です。
家族や友人、SNSでのフォロワーに動画を見せ、率直な感想を聞くことで改善点が明確になります。
特にどこで飽きたか、どこが良かったか具体的な視点で聞くと、次の制作に活かせるヒントが得られます。
魅力的な動画をたくさん見て、気になった表現や構成を真似してみることも大きな学びです。
注目を集めている動画やプロの作品を分析して映像のテンポやカットのタイミング、テロップ、効果音の入れ方など細部に注目すると自分の動画にも応用しやすいです。
視聴中に、なぜこの動画はおもしろく感じるか考えるようにすると、観察力と構成力が自然と鍛えられます。
特に、自分が目指すスタイルに近いクリエイターを見つけての模倣は、技術を効率よく習得するための近道となるでしょう。
動画制作の注意点

動画の制作は、単に作ればよいわけではありません。視聴者に見てもらい、信頼や共感を得るためには、避けるべき落とし穴や守るべきルールがあります。
特に、動画のクオリティと著作権の問題は、多くの初心者がつまずきやすいポイントです。あらかじめ理解して取り組むことで、安全に動画を作るためのコツを紹介します。
クオリティが低くならないように注意する
動画の画質や音質が低いと、視聴者はすぐに離脱します。たとえ内容が優れていても、ノイズの多い音声や暗い映像では、伝えたい情報が届きません。
必要な撮影機材を揃え、照明の当て方や背景の整備、静かな環境の確保など撮影条件を丁寧に整えることが大切です。
さらに、編集時にも注意が必要です。映像のつなぎ方に違和感がないか、テロップの文字が読みやすいか、BGMや効果音の音量バランスが取れているかをしっかり確認しましょう。
見やすく、聞きやすい動画に仕上げるには、視聴者目線でのチェックが欠かせません。公開前に、完成した動画を第三者に見せ、気付きにくいミスを事前に防ぐこともおすすめです。
著作権侵害などの違反をしないように注意する

動画内で使用する音楽や画像、映像などの素材にはすべて著作権が関わっています。
無断で使用した場合、著作権者からの削除申請や広告収益の差し止め、さらには損害賠償請求などの法的リスクを負うことにもなりかねません。
たとえネット上で無料ダウンロードできる素材でも、商用利用可やクレジット不要、改変可能などの利用条件を確認して条件を守ることが重要です。
違反なく使える素材は、著作権フリー(ロイヤリティフリー)の素材サイトの活用があります。
音源であればDOVA-SYNDROMEや効果音ラボ、Artlistなどがあります。画像や映像ならO-DANやPixabay、Pexelsなどが代表的な例です。
有料素材であっても、ライセンスが明確に保証されているものを使えば、後のトラブルを回避できます。
動画内で使用する全素材の出典の記載や必要に応じたクレジット表記など、制作側としての責任ある姿勢も大切です。
また、自分で撮影し録音したオリジナル素材の使用も可能です。手間はかかりますが、完全に自由な編集が可能になるうえ、作品の独自性も高まります。
万全な体制で制作する自信がない、あるいはクオリティや著作権まわりに不安がある場合は、無理せずプロに任せるのもひとつの方法です。
Funusualのように著作権管理や品質担保を含めてサポートできる制作会社であれば、初心者の方でも動画制作を進めることができます。
制作の初期段階から専門スタッフが伴走し、目的に沿った表現ができるだけでなく、著作権やライセンス面でも安全性の高い動画が完成します。
加えて、プロ仕様の機材や技術、編集体制によって高クオリティな仕上がりが期待できるのも大きなメリットです。
自分のアイデアをしっかり動画にしたい場合や、社外に向けた動画で失敗できない場面では、信頼できる制作パートナーの存在が心強い味方になるでしょう。
ぜひ一度ご相談ください。
動画制作が難しいと感じたら動画制作会社への外注がおすすめ

動画制作を始めたものの思ったように撮れない、編集に時間がかかりすぎる、クオリティに納得がいかないと感じることは誰にでもあります。
動画制作につまずいたら、動画制作会社に外注する選択肢を視野に入れてみましょう。
プロの制作会社には経験豊富なディレクターや編集者が在籍しており、企画から撮影や編集、納品まで一貫して対応できます。
伝えたいメッセージを効果的に届けるための構成力や、視聴者の心をつかむ編集技術は、やはりプロならではの強みです。
また納期が決まっている案件や企業動画、プロモーションなどの高い完成度が求められる場面では、外注するとクオリティを担保できます。
外注先を選ぶ際には、ポートフォリオや過去実績を確認しましょう。
制作目的やターゲットに合ったテイストが得意か、予算内で対応できるかどうかも事前に擦りあわせておくと、トラブルを避けられます。
初めて依頼する場合は、複数の会社に見積もりを取り、比較検討するのもおすすめです。
もし依頼先に迷っているのであれば、Funusualをご検討ください。
Funusualは企業向けの動画制作で豊富な経験を持っています。
企画からヒアリングや撮影、編集、モーショングラフィックスまでワンストップで対応できる体制が整っています。
特に伝えたいけれどどう表現すればよいかわからない段階からでも、プロの視点で適切な構成と演出の提案が可能です。
スピードとクオリティの両立を重視し、成果につながる動画を一緒に作ります。動画制作が難しいと感じたら、まずはFunusualへお気軽にご相談ください。
目的や課題に応じた柔軟な提案で、理想の映像を制作するお手伝いをします。
クオリティの高い動画を制作したいなら

視聴者に強い印象を残す高品質な動画を制作したいと考えている場合は、単に見栄えだけでなく企画力や構成力、技術力のすべてが問われます。
特に企業や団体が発信するプロモーション動画やブランディング動画、採用動画などでは成果や反響につながるクオリティが必要です。
Funusualはこれまで多くのBtoB企業に対して動画制作を行ってきた経験があります。
企画から構成や撮影、編集、CG制作までを一貫して請け負える体制を整えています。
漠然とした要望にも丁寧に耳を傾け、企業の魅力や目的に沿った動画を企画段階から提案できることが強みです。
さらに、限られた予算内でもクオリティを引き出す柔軟な対応が可能で、成果が出る映像を重視する企業担当者様から高い評価を得ています。
SNSや広告用のショートムービーから展示会、営業用の長尺動画まで目的や用途に応じて適切な映像表現を提案し実現します。
どの動画制作会社に外注すべきか迷っている方や企画から相談したいとお考えの方は、ぜひFunusualへご連絡ください。
見積もり作成や絵コンテ(構成案)の提案は無料で対応しており、予算やスケジュールに合わせた適したプランを一緒に考えます。
プロの手で、成果につながる動画を作りたいと思ったら、まずはお気軽にご相談ください。













