動画を社内で撮影、編集したいと考えていてもどのような機材が必要なのか、費用や選び方のポイントもわかりづらいため戸惑う方も多いでしょう。
ネット上には情報が溢れているものの、断片的で、実際のイメージがつかみにくいのが現状です。
本記事では、動画制作を始めるうえで欠かせない撮影、編集機材の基本や選び方を初心者でもわかりやすく丁寧に解説します。
実際の使用例や選び方のポイントを交えて、失敗を防ぎつつ効率的に動画制作をスタートできるようにサポートします。必要な準備が見え、次のステップに進めるはずです。
動画制作に必要な撮影機材

スマートフォン一つで手軽に撮影できる時代とはいえ、企業では画質や構図など一定の品質が求められます。
画質が荒かったり音声が聞き取りにくかったりすると、視聴者に不快感を与え、動画全体の信頼性を損ねてしまいます。まずは、企業動画の撮影で押さえておきたい機材の種類を把握しましょう。
カメラ
社内で動画を制作する場合、使用するカメラは画質と操作性のバランスがとれているかが重要です。
高解像度で撮影できるプロ仕様のシネマカメラでも、操作が難しければ作業工程が増え、かえって効率が下がります。
一方で、スマートフォンのカメラだけでは、企業として求められるクオリティを安定して実現するには難しい場合があります。
ビジネス用途でおすすめされるのは、ミラーレス一眼やハンディタイプの業務用カメラです。
これらは4K対応やマニュアル設定が可能なモデルが多く、背景のボケや色味の調整も柔軟に行えます。
また、外部マイクや三脚との拡張性も高く、社内撮影でも安定した運用が可能です。撮影する対象によって、適した性能も異なります。
例えば、セミナーやインタビューが中心なら、長時間録画と音声収録に強いモデルが適しています。
一方、商品紹介や操作説明など静止気味な被写体なら、軽量で画質のよい機種が扱いやすいでしょう。
必要な機材をすべて揃えるには、時間や予算の検討、さらに適切な機材選定と運用体制の構築も求められます。
自社での内製にはそれなりの負担が伴うため、途中で手が止まってしまうケースも少なくありません。
Funusualでは目的や予算、運用体制に応じた適切な機材構成のご提案はもちろん、使用目的別の比較や選定ポイントの解説まで、初めての方でもわかりやすくご案内しています。
初期段階での迷いや機材の過不足を防ぎ、効率的な動画制作をスタートさせたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
三脚

動画を社内で撮るなら、三脚は必須です。手持ちだとどうしてもブレが起きやすく、映像のクオリティが下がります。
特にインタビューや説明動画など、固定画が中心の撮影では欠かせません。動画用三脚では、滑らかな左右移動や上下移動が可能で、スムーズなカメラワークを可能にします。
カメラの重さに合った耐荷重のものを選び、使用シーンに応じて高さや持ち運びやすさも確認しましょう。
ジンバル
ジンバルはカメラ本体では補正しきれない微細なブレを3軸で物理的に制御し、プロが撮影したような安定感のある映像が撮影できます。
スマートフォン用からミラーレス、業務用カメラのサイズまで幅広く対応し、歩きながらの撮影や動く被写体を追いかけるシーンでは特に効果を発揮します。
ただし、セットアップには事前のバランス調節やキャリブレーションが必要で、操作にはある程度の練習や経験が必要です。
費用や運用の手間を考慮したうえで、映像表現の幅を広げたい場合に導入を検討するとよいでしょう。
マイク

スマートフォンに内蔵されているだけのマイクでは、雑音が入ったり声が小さく聞こえたりすると、視聴者の集中力が削がれ動画の印象も悪くなります。
特に企業のインタビューやプレゼンでは、声の明瞭さが信用に直結します。そのためまず取り入れたいのが、ピンマイクです。
胸元に装着する小型マイクで、話し手の声を一定の距離から安定して収音することが可能です。また有線タイプはシンプルかつ低コストで、ワイヤレスタイプは移動主体の収録に向いています。
実際に、サウンドハウスではスマートフォンやカメラに接続できるラべリアマイクがビデオ制作に適していると紹介されています。
用途や収録環境によって使いわけることで話し手の声を安定して届けることができ、企業動画の音声品質が向上し、視聴者にとっても聞き取りやすくなるでしょう。
照明

動画制作では、光の当て方によって、映像の明るさや雰囲気が大きく変わります。
室内撮影では照明を追加することで、カメラのISOを下げられ、ノイズを抑えたクリアな映像を得ることができます。
定点撮影やインタビューでは、安定光を提供するLEDライトなどの定常光を使うと不安定な自然光に頼らずに済み、構図や撮影時間も安定するでしょう。
また、撮影でよく使われるのが3点証明です。
- キーライト:被写体の顔を主に照らすメイン光
- フィルライト:影をやわらげる補助光
- バックライト:背景と被写体を分離して立体感を出す効果がある
この照明構成により、視聴者にとって見やすく、記憶にも残りやすい映像に仕上がります。
記録媒体
4K動画を安定して記録するには、V30以上のSDカードが必須で書き込み速度が不足すると、録画が途中で停止する可能性があります。
容量は128GB以上が望ましいです。長時間の撮影でも、途中で録画が止まるリスクを減らせます。さらに耐水や耐衝撃性能のあるカードを選ぶと安心です。
このように書き込み速度や容量、耐久性の3点を満たすメディアを選ぶことで、撮影の失敗を防ぎ編集作業までスムーズに進められます。
撮影に使用するカメラの種類とそれぞれの特徴

動画制作に必要な機材は、撮影する内容や求める動画の品質によって大きく異なります。
スマートフォンだけでも撮影は可能ですが音質や画角、画質の安定性などに限界があります。企業用途では画質や音声の安定性が不十分なケースもあるため、信頼性に欠ける可能性があるでしょう。
どこまでのクオリティを求めるか、どの頻度で運用するかによって、適切な投資の規模は変わります。
自社の動画をどう見せたいかを整理することで、必要な機材とコストバランスが見えてきます。
ビデオカメラ
ビデオカメラは、企業の動画制作において安定した映像品質と録画性能を備えた、信頼性の高い選択肢です。
長時間録画や高音質の収録が可能で、セミナーやインタビューなどの用途にも対応できます。
また外部マイクや三脚との接続性が高く、照明や音響などほかの機材との連携性も高いため、社内でも安定した品質で繰り返し撮影が可能です。
社外向けに発信する動画だからこそ、一定の品質を担保できる機材を選ぶことが重要です。
一眼レフカメラやミラーレス一眼レフカメラ
一眼レフやミラーレス一眼は、高画質な映像や背景ボケを活かした印象的な動画に向いています。
特に企業のプロモーションや採用動画など、映像の印象や演出が重視される場面で、高い効果を発揮します。
ミラーレスは、軽量で動画機能も充実しており、扱いやすさを重視する現場に適したカメラです。
一方、一眼レフは操作性とレンズの選択肢が豊富で、交換レンズによる多様な撮影表現が可能です。映像表現にこだわりたい企業にとっては、いずれも有力な選択肢といえます。
コンパクトデジタルカメラ

コンパクトデジタルカメラは、小型軽量で携帯性に優れ、日常的な社内記録や簡易的な動画作成に適した機材です。
4K動画に対応したモデルも増えており、社内イベントや簡易な商品紹介など、気軽に撮影したい場面で役立ちます。
センサーは1型以下が主流ですが、高性能モデルではスマートフォンより高画質な動画も撮影可能です。操作性は自動設定が中心で、初心者でも迷わず使える点が魅力です。
また固定レンズのため、構図の調節が容易で、屋外でも手軽に持ち運んで使用しやすい点が特徴といえます。コストや導入ハードルの低さから、社内映像の第2の選択肢として有効でしょう。
アクションカメラ
企業の動画制作で活用されるアクションカメラは、小型で軽量、防水や耐衝撃性に優れた特徴があります。
狭い場所や動きの激しいシーン、アウトドア撮影に強く、迫力のある映像を手軽に撮影可能です。固定しやすい設計のため、ドローンなど複数の視点から映像を撮影できるため、臨場感のある映像制作に向いています。
スマートフォン
スマートフォンは普段使いのデバイスで、起動が早く撮りたい瞬間を逃さず記録できるという大きな利点があります。
新しい機種なら4K動画対応で、手ぶれ補正や高フレームレートも備わっているため、まずは手元のスマートフォンで画質を試すのにおすすめです。
ただし暗所ではノイズが出やすく、ダイナミックレンジも限られるため、夜間や照明が不十分な場面では画質が低下する可能性があります。
編集も手軽にでき、SNS用の短尺動画や社内紹介動画など、簡易な用途に適しています。
スマートフォンは始めるには十分な機材です。画質や拡張性をチェックしながら、必要に応じてマイクや三脚と組み合わせることで、撮影の安定性や音質を向上させることが可能です。
動画撮影に必要な機材にかかる費用は?

動画撮影に必要な費用は、使用する機材のグレードや用途によって大きく異なります。
基本的にはエントリーモデルとミドルクラス、プロ仕様の3段階で考えると費用の目安が明確になり、導入計画を立てやすくなります。
エントリーモデルはスマートフォンに外付けマイクやミニ三脚、簡易証明を加えた構成で、30,000〜50,000円(税込)程度です。SNS投稿といった手軽な動画制作に適しています。
ミドルクラスでは、ミラーレス一眼や業務用ビデオカメラを使い、周辺機器も揃えるため150,000〜300,000円(税込)前後の予算が必要です。社外向けのインタビューや商品紹介に向いています。
プロ仕様ではシネマカメラや本格的な照明、音声機材を使うケースで、500,000円(税込)以上の投資が一般的です。
広告や企業ブランディングなど、映像の品質が重視される制作に適しています。
このように、導入目的に応じて段階的に機材を揃えることが可能なため、初期費用を抑えながら必要に応じて機材を拡張していく方法が現実的です。
動画編集に必要な機材

動画撮影を社内で進める際は、カメラやマイクといった撮影機材に加え、編集用のパソコンやソフトウェアも欠かせません。
編集まで見据えた機材構成を把握することで、不要な買い足しを防げます。
まず必要なのは、動画編集に対応できるパソコンです。ノートパソコンでも十分対応可能ですが、編集作業の効率化を図るためデュアルディスプレイの導入も有効です。
編集ソフトは、定番の有料ソフトや初心者でも扱いやすい無料ソフトも選択肢に入ります。予算や操作性を踏まえて選ぶとよいでしょう。
撮影機材の設備といっても、すべてを一度に揃える必要はありません。制作体制や用途に応じて、段階的に導入することで無理なく始められます。
必要な機材と費用の目安を把握することで、社内での動画制作をスムーズに始められます。
パソコン
動画編集は処理が重い作業のため、下限のラインは、CPUはcorei7以上でメモリは16GB以上がおすすめです。そしてストレージには読み書き速度が速く動画編集に適したNVMe SSDを搭載した機種が適しています。
これにより、4K素材でも編集作業の待ち時間が減り、全体の作業効率が向上するでしょう。
ノートタイプでも十分対応可能ですが、モニターはフルHD以上かつ色再現性に優れた機種を選ぶと、映像の細やかなチェックがしやすくなります。
さらに複数ウィンドウを開いて編集作業する場合は、デュアルディスプレイ化するのもおすすめです。複数の画面を同時に表示できるため、タイムラインや素材の確認がスムーズに行えます。
またポータブル用途が多い場合は、軽量かつバッテリー駆動時間の長いノートPC、スタジオやオフィスで据え置くならGPU付きのデスクトップPCという選び方も効果的です。
用途に応じて機種を選ぶことで、無駄なコストを抑えながら快適な編集環境を整えられます。
編集ソフト
編集ソフトは、制作するコンテンツの目的や編集者のスキル、使用環境によって適した選択肢が変わります。
企業の広報やマーケティング用途では、安定性と機能性のバランスが取れたソフトを選ぶことが重要です。
例えば業界標準とされるAdobe Premiere Proは、細かい編集やほかのAdobe製品との連携が可能で、本格的なプロモーション動画やブランドムービーに向いています。
一方、費用を抑えたい場合はDavinci Resolveの無料版でも十分対応でき、色補正やエフェクトなどの高度な処理も可能です。
操作性を重視する場合は、PowerDirectorといった初心者向けに設計されたソフトも有効な選択肢です。
Macを利用している企業であれば、Final Cut Proも操作性と処理速度の面で高く評価されています。
動画編集ソフトは、業務の目的や予算、スキルレベルに応じて柔軟に選ぶことが大切です。
Funusualでは動画の目的や社内の体制、操作スキル、今後の活用方針などをヒアリングしたうえで、適切な編集ソフトの選定から運用方法までを一貫してご提案しています。
例えば「社内で簡易編集をしたい」「プロモーション動画の品質を担保したい」など、目的別におすすめのソフトとその理由を明確にお伝えすることで判断に迷う時間を減らし、すぐに制作へ着手できる体制づくりを支援します。
また、編集ソフトとパソコンスペックのバランス、必要なプラグインや連携ツールの選定など、実務面でのサポートも可能です。
「何から準備すればよいかわからない」「無駄な出費を避けたい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度Funusualにご相談ください。
動画編集に必要な機材にかかる費用は?

編集まで含めた動画制作の費用は、撮影機材だけの場合に比べて編集費用は高くなりますが、選び方によっては初期コストを抑えることも可能です。
まず編集用のパソコンは、映像の解像度や編集ソフトの動作条件によってスペックが左右されます。
フルHD動画であれば、100,000〜150,000円(税込)程度のパソコンでも対応できますが、4K編集を視野に入れるなら200,000円(税込)前後のモデルが適正といえる価格帯です。
コストを抑えたい場合は、性能が足りていれば中古品や整備済製品も選択肢になります。編集ソフトについては、有料の代表格であるAdobe Premiere Proは月額3,000円台から利用できます。
買い切り型を望むならPower Directorや、Final Cut Proなどもあり価格は10,000〜40,000円(税込)程度です。一方、コストをかけずに始めたい企業には、DaVinci Resolveの無料版やiMovieのようなソフトも十分実用的でしょう。
編集にかかるコストは高く見えがちですが必要なスペックを見極め、中古機材や無料ソフトを活用すれば、初期投資を大幅に削減できます。
無理なく導入できる範囲から始め、必要に応じて段階的に機材を増やす方法が現実的です。
動画撮影や編集に使用する機材の選び方

動画制作の機材は種類が多く、迷いやすいですが大切なのは自社の制作目的や運用体制に合った基準で選ぶことです。
撮影の目的や使う場所、操作する方に合わせて必要な機能を絞り込めば、予算内で適切な機材が見つかるでしょう。すべてを高性能に揃える必要はなく、用途に応じた選定が成功のポイントです。
撮影したい動画に合わせて選ぶ
動画を撮影するときは、撮影対象に応じて必要な機能から機材を選定することが重要です。
まず動きがある動画を撮るなら、手ぶれ補正やフレームレート対応が重視されます。次にインタビューや静止対象が中心なら、三脚や照明への対応も重要です。
さらに予算と拡張性を見据えるなら、まず手持ちのスマートフォンで撮影を試し、慣れてきたら必要な周辺機器だけ交換していく段階的な導入が有効でしょう。
このように撮影の目的や撮影環境、将来の発展性を軸に考えることで、初心者でも迷わず自社に合った機材選びが可能です。
使い勝手のよさで選ぶ
使い勝手のよさで機材を選ぶ際は、操作に迷わずすぐ使い始められる機材かどうかを重視することが重要です。
まず、操作のしやすさは必須です。例えば液晶画面が見やすく、メニューが直感的、オート設定が充実している機種は初心者でも戸惑わずに操作できます。
またカメラやバッテリーが軽量で、持ち運びしやすいサイズであれば長時間の撮影でも負担を軽減できます。アクセサリーとの互換性も注目すべき点です。
マイクや三脚、照明などをすぐ接続できるモデルは、機材を増やしても使いやすさが維持されます。
操作が簡単な機材を選ぶことで、継続的な運用や担当者の引き継ぎもスムーズに行えます。
スペックに注目して選ぶ
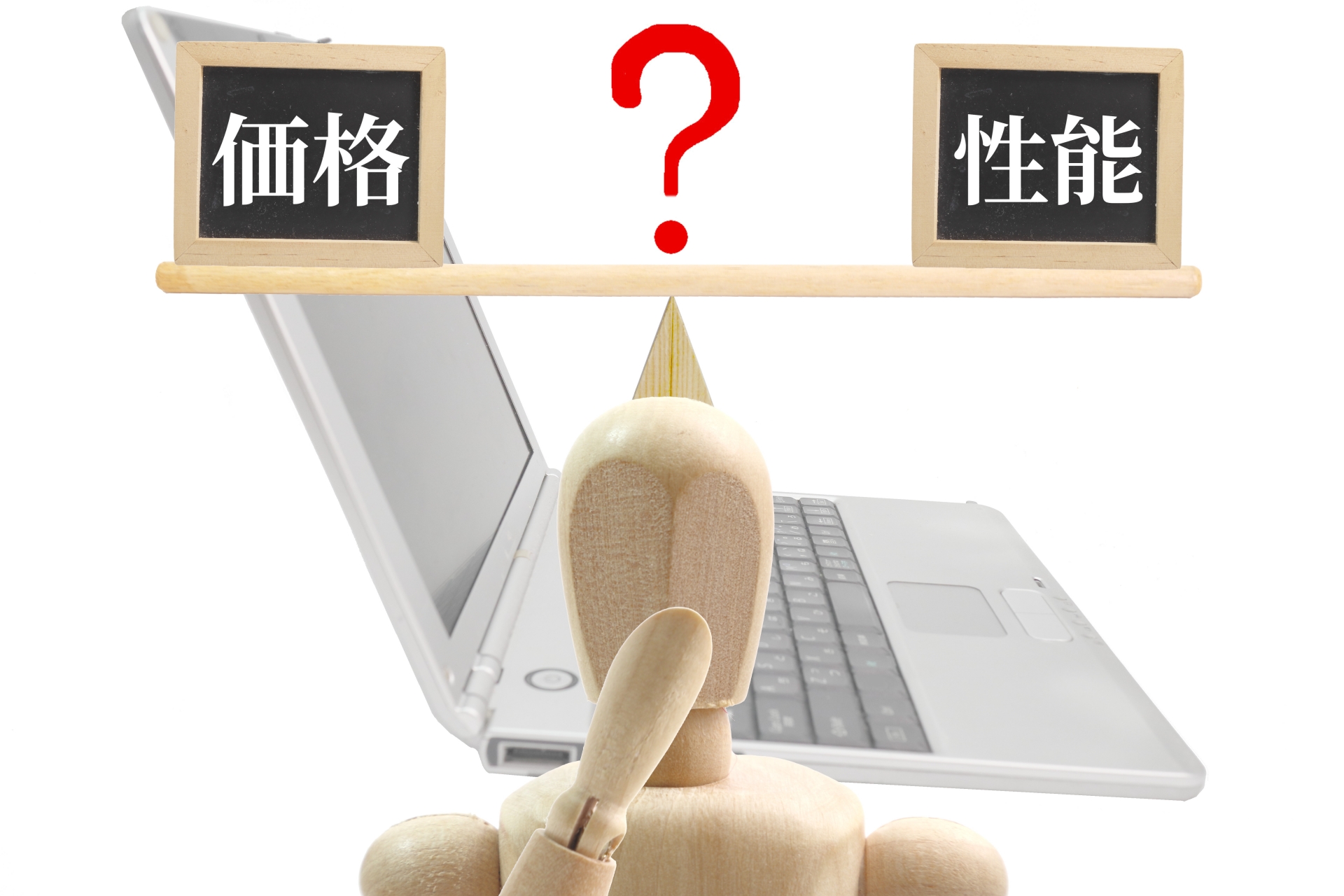
編集に使うパソコンは、性能によって作業効率が大きく変わります。まずCPUはCorei5が推奨で、可能であればCorei7以上が望ましいです。
メモリは16GB以上が推奨で、編集作業が安定します。ストレージは高速なSSDを選び、大容量の外付けSSDを併用すると、素材の保存やバックアップが効率的になります。
GPUは4K編集する場合に重要で、RTX3050以上が目安です。これらを満たす構成なら、初心者でもスムーズに作業が始められます。
ノート型でも十分対応可能ですが、長時間作業でもパフォーマンスを維持するために、冷却性能が高いモデルを選ぶことが重要です。
予算を考慮して選ぶ
動画制作を始める際は、まず何をどこまでやりたいかを整理したうえで初期投資額の上限を明確に設定することで、予算に応じた現実的な導入が可能になります。
撮影と編集の両方をカバーするとなると、費用は一気に膨らみますが、すべてを一度に揃える必要はありません。
例えば、編集環境は社内PCを活用して無料ソフトから始め、撮影機材から段階的に導入し徐々に編集環境を整備する方法も効果的です。
初期コストを抑える手段として、中古品やレンタルの活用は実用的な選択肢といえるでしょう。
重要なのは高価なものが正解ではなく、自社の制作体制や目的に応じてちょうどよい機材構成を選ぶことです。
完璧を目指す必要はなく、継続的な運用を見据えた選定こそが、失敗を防ぐポイントとなります。
初心者でもわかりやすい動画撮影のポイント

動画撮影に必要な機材を揃えるだけでは不十分で、映像の質は撮影の基本を押さえることで大きく変わります。
構図は、主体を中央に配置するか三分割法を用いることでバランスよく見せることができます。次に光は自然光を活かしつつ、逆光を避けるのがポイントです。
必要に応じて補助照明を使い、影を和らげると映像が引き締まります。また音声も映像全体の質に大きく影響します。
内蔵マイクより外部マイクの使用が望ましく、背景のノイズを減らす工夫も必要です。背景はシンプルに整え、視聴者が内容に集中しやすい環境を作るとよいでしょう。
基本を意識すれば、初心者でも質の高い動画撮影が可能です。慣れれば自然な映像表現ができるようになり、不安は軽減されます。
機材選びや撮影で失敗したくないなら

機材選びや撮影を進めるうえで、本当にこの判断でよいのかと迷う場面は少なくありません。
特に初めての動画制作では、スペックの見極めや撮影環境の整え方、編集の流れまでを一つずつ手探りになりがちです。
こうした不安を避けたいなら、動画制作の専門会社に相談するのがよりしっかりとした方法だといえます。
例えばFunusualでは、機材選定から撮影と編集、公開後の運用サポートまでワンストップで対応が可能です。
自社の目的や予算に合わせて、構成を提案できるため、機材の無駄買いや撮り直しといったトラブルも防げます。
失敗を避けたいと考えるのは自然なことです。だからこそプロと一緒に踏み出すことが、結果的に効率的な選択肢になるでしょう。
判断に迷った際は、一度専門家にご相談ください。プロの視点で適切な動画制作をご提案します。













