製造業では現場教育や品質管理が必要不可欠ですが、従来の紙のマニュアルやOJT(On-the-Job Training)では不十分です。
背景には、文字化しにくいベテラン作業員のノウハウが現場を支えている事実があります。また、現場の注意すべき点や危険な箇所も紙では共有しづらいでしょう。
本記事では製造業の動画マニュアルのメリットと重要性を解説した後に、動画マニュアルの活用事例を紹介します。動画マニュアル導入のポイントと活用方法を学びましょう。
製造業で動画マニュアルを活用するメリット
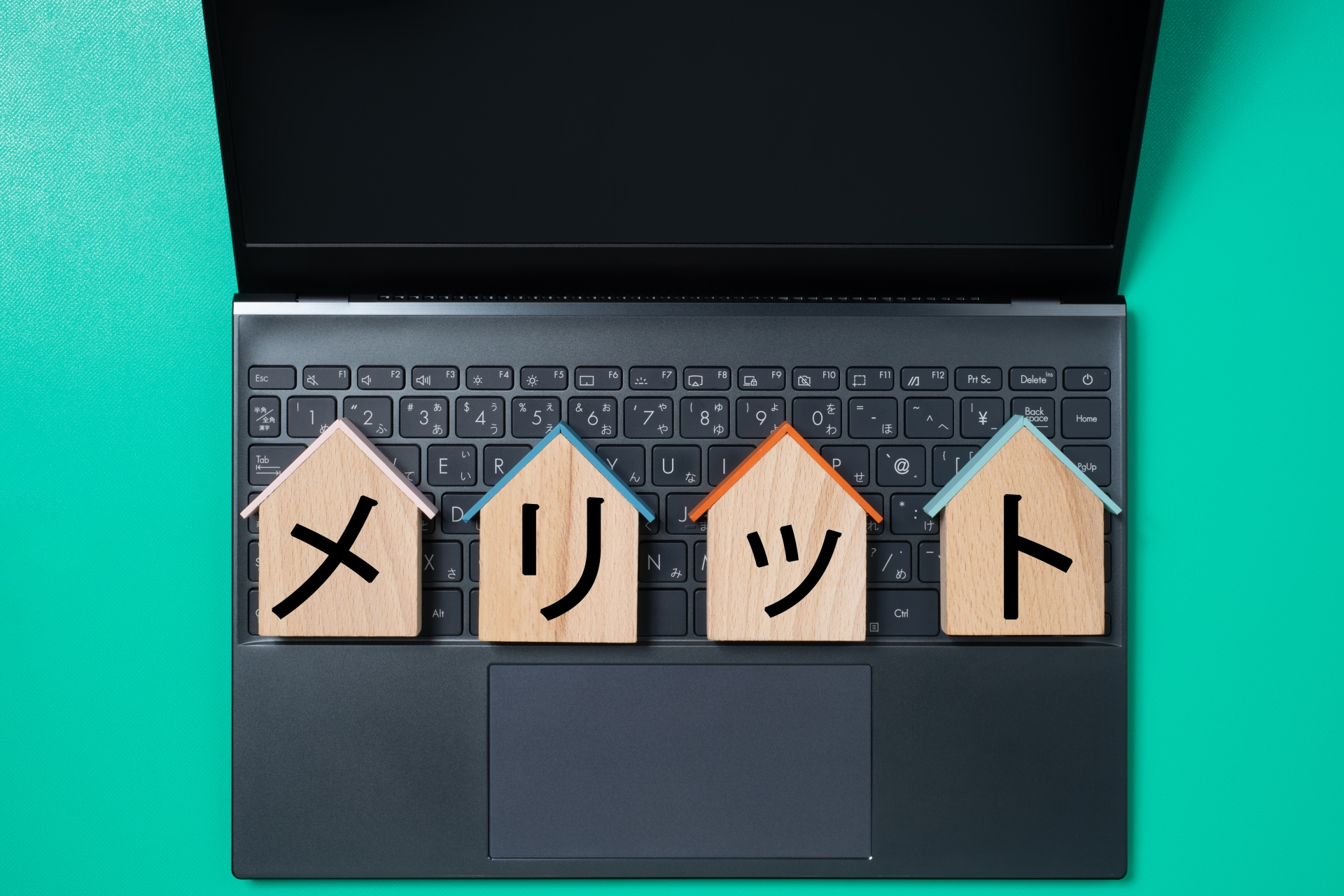
動画マニュアルを用いると、紙のマニュアルでは得られないメリットを享受できます。特に製造業では、研修を含めた現場全体の効率化を図れるでしょう。
- 言語化しにくい情報を伝えられる
- 短時間で多くの情報を伝えられる
- 言語の壁があっても内容が伝わりやすい
- 作成や管理の手間を省ける
動画マニュアルの導入によって得られる現場教育のメリットを学びましょう。
言語化しにくい情報を伝えられる
製造現場では職人による暗黙知が欠かせません。しかし、ベテラン社員のノウハウは本人ですら言語化しにくい情報です。
暗黙知の伝達は紙のマニュアルよりも動画マニュアルが便利です。動画であればベテラン社員の動作や力加減、品質の判断などを可視化できます。
また文書では不可能な音の収録が可能であるため、現場特有の機械の振動音や異常音の学習も可能です。
作業のポイントを字幕付きで補足すれば、作業の重要な箇所を正確に伝えることも可能でしょう。また、ベテラン作業員が直に補足説明を加えればより理解を深められます。
短時間で多くの情報を伝えられる
動画マニュアルでは多くの情報を一度に伝えられます。紙のマニュアルでは抽象的な説明や写真や図で情報を伝えますが、動画では視覚や聴覚などの認知機能を動員して情報を伝えることが可能です。
この特性により文字や写真ではイメージしきれなかった細かい動きや音を簡単に理解でき、短い動画で多くの情報を伝えられます。
復習も短期間で何度も繰り返せて紙のマニュアルよりも効率的です。また紙のマニュアルよりもイメージを共有しやすいため、より深い補足説明も可能です。
動画を見た方からの質問も紙のマニュアルよりも芯を食った質問となることが想定され、短期間に深く理解するでしょう。
言語の壁があっても内容が伝わりやすい
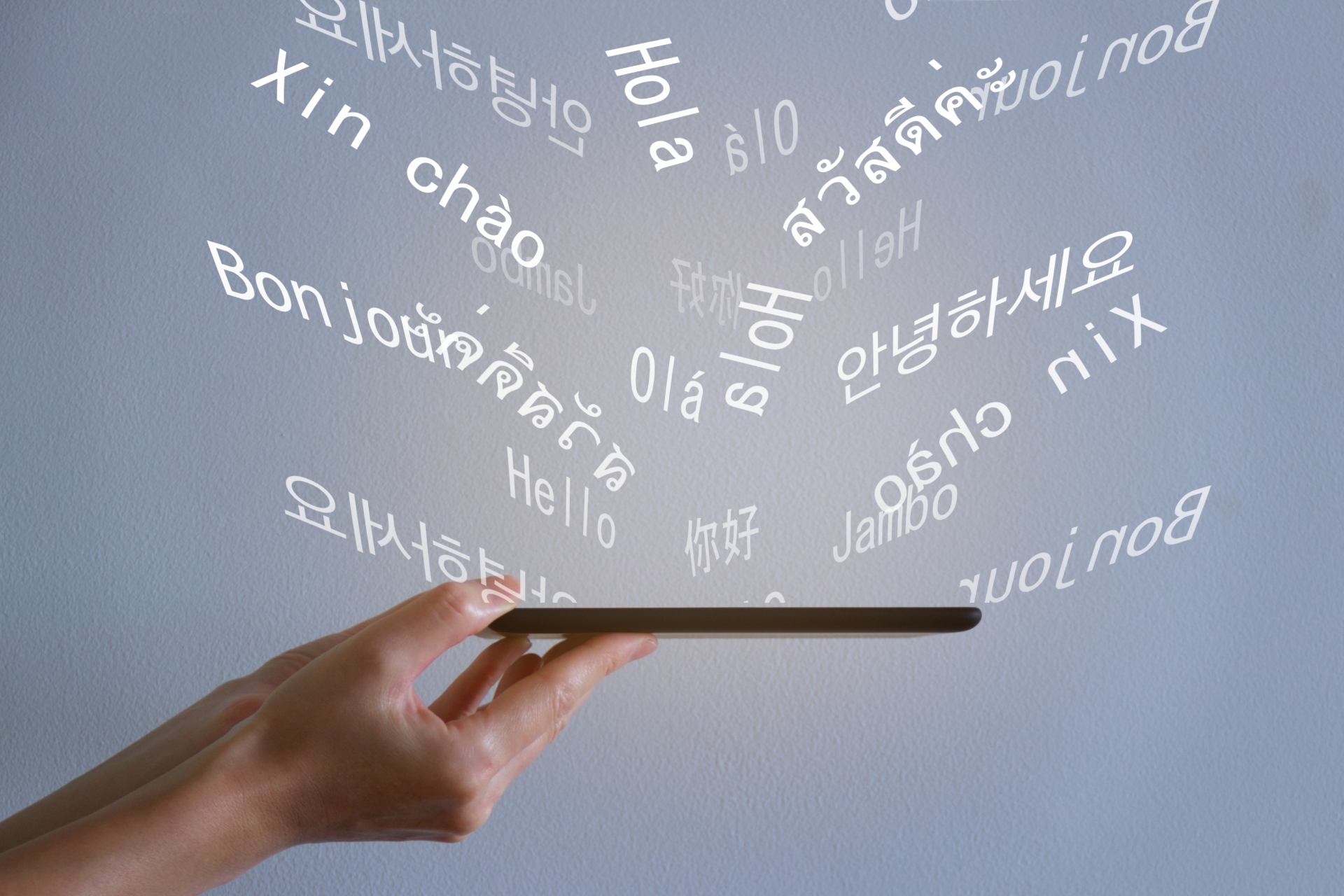
製造現場で外国人が働くことは珍しくありません。紙のマニュアルでも翻訳されたマニュアルを用意しなくてはならないでしょう。
すべてが文字ベースの紙のマニュアルでは労力がかかり、英語話者以外の方ではさらに負担が大きくなります。
動画マニュアルを用いると、外国の方でも視覚や聴覚を使った情報の伝達が可能となります。動画マニュアルでも必要に応じて言葉による説明をしますが、字幕を用いると理解は容易でしょう。
すべて翻訳しなければならない紙のマニュアルに対して、ポイントに絞って翻訳すればよい動画は効率がよいマニュアルです。
作成や管理の手間を省ける
製造業のノウハウを文字に落とし込もうとすると、正確に伝えるために多くの工夫が必要となります。文字や写真だけでは足りず、図の作成も求められるかもしれません。
そこまで労力を費やしても現場経験者と新人との理解が埋まりきることはないでしょう。加えて外国の方が現場に参加すると、これまでに作成したすべてのマニュアルの翻訳が必要となります。
紙のマニュアルの場合、データ化していなければ物理的な管理が必要となり、保管場所も確保しなければなりません。
こうした課題を動画マニュアルならば解決できます。動画マニュアルは現場の風景を撮影し、後からポイントごとに口頭での説明を加えるため労力は小さくなります。
また、データ化するため管理の手間も少なくなるでしょう。
製造業における動画マニュアルの重要性と目的

紙のマニュアルを用いると、人によって理解力に差が生まれます。理解力の差はコミュニケーションの齟齬や品質のばらつきにつながり、業務の効率化を阻むでしょう。
動画マニュアルの導入は、紙のマニュアルでは得られない効果が期待できます。
- 品質のばらつき防止
- 業務の効率化
- ノウハウの共有
- ミスやトラブルのリスク低減
動画マニュアルの導入が現場改善の鍵になることを学びましょう。
品質のばらつき防止
マニュアルは現場の担当者が変更しても、同じ作業をこなすために必要です。しかし、紙のマニュアルではイメージの共有をこなしきれずOJTが必要となるでしょう。
現場の担当者ごとに指導にばらつきが生じ、製品の品質にもばらつきが生じることとなります。
動画マニュアルは実際の現場の流れをそのまま伝えることができるため、指導にばらつきが生じにくいでしょう。またポイントごとに的確な説明を差し込めるため、重要な箇所が一目で理解できます。
また動画であれば、見ながら作業を遂行できるため理解も早いでしょう。よって担当者が変更しても、動画マニュアルであれば作業を同じように指導できます。
業務の効率化
紙のマニュアルでは、自分の担当工程以外を理解するのは大変です。現場全体への理解が及ばないまま効率の悪い作業に従事します。
動画マニュアルを導入すると、作業者は自分の担当以外の業務を視覚的に理解できるでしょう。現場の各工程のつながりを理解できるようになり、効率的に業務を遂行できます。
また現場を経験していない新人への研修でも、教育担当者が指導しなくても済みます。基本的な手順やポイントは動画が説明するため、より大事なポイントに絞って教育できるでしょう。
結果として現場フロー全体で従業員の理解が進み、理解度が高まった状態で作業を行えます。
ノウハウの共有
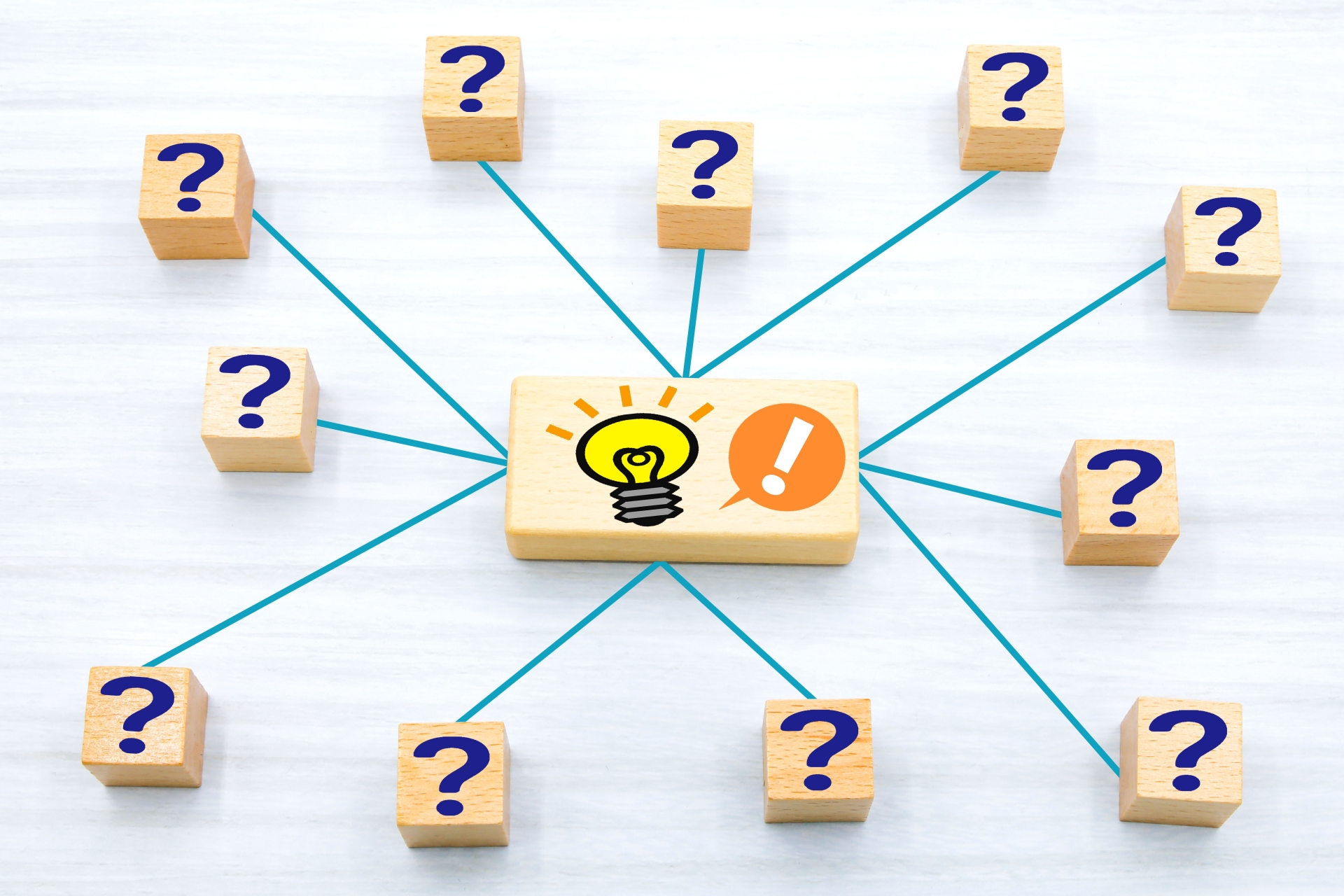
製造業ではベテラン作業員の暗黙知が重要な役割を持っています。会社になくてはならない財産であるため現場全体で共有したいですが、紙のマニュアルでは難しいでしょう。
また現場に限らず新人教育も担当者のノウハウによって遂行されるため、担当者によってばらつきが生じる結果となります。
動画マニュアルであればベテラン作業員や新人研修担当者のノウハウを、正確に保存できます。ベテラン作業員の細やかな動きやコツを記録するため、単なるマニュアルを超えた会社の資産です。
動画マニュアルを通じてノウハウを継承できれば、現場の業務全体の継続性が保たれるため製造プロセスを維持できます。また、新人研修にも継続性が生まれるでしょう。
ミスやトラブルのリスク低減
紙のマニュアルでは、注意点やポイントが写真や図とともに説明されます。しかし写真は動かないためイメージに頼ることになり、これが実際の現場との齟齬につながるでしょう。
マニュアルにしたがって作業しているつもりが、重大なミスやトラブルを招くことも少なくありません。
動画マニュアルでは、現場の実際の映像を見ながら作業できます。誰にとっても作業手順が明確となり、ミスの発生は低減するでしょう。
また重要なポイントや危険な場所では、動画を一時停止して説明できます。文字では理解できなかった危険な箇所を視覚で把握して、事故の発生を防げます。
製造業での動画マニュアル活用シーン

製造業の動画マニュアルには多くの利点があります。ここでは、具体的な動画の活用シーンを学びましょう。
製造業で動画マニュアルを扱う際は、新人研修や作業手順マニュアルのような現場を知らない方に向けたものが多いです。
これらは、現場を知らないがために経験者との間のイメージに齟齬が生まれることが多いからです。
- 作業手順マニュアル
- 新人研修
- 安全教育
各シーンの動画の活用法を学び、現場での実用性をイメージしましょう。
作業手順マニュアル
現場の作業手順の共有は、品質の担保に必要不可欠です。従来の紙のマニュアルでは現場を知るかどうかでイメージに齟齬が生まれ、正しく手順を伝えることができませんでした。
動画を使用すると、複雑な手順であっても文書に起こすことなく的確に伝えられるでしょう。また動画には字幕をつけられるため、理解が難しい箇所もその場で説明できます。
動画だけでは説明しきれない箇所がある場合は、紙のマニュアルを補足として作成すると手順に対する深い理解を促せます。
特に図を用いた説明は、動画の有無によって理解に差が生まれるでしょう。
新人研修
新人研修では現場の従業員がOJTで教えながら、動画マニュアルを併用できます。ひとつの作業ごとに動画を作成できるため、ポイントを絞って理解を促進できるでしょう。
動画マニュアルが存在するため、OJTで受けた研修箇所を忘れた新人も復習を容易にできます。また、新人は理解度が高まった状態で質問するため円滑に研修が進みます。
新人研修では、OJTの前に動画による業務手順の確認が望ましいでしょう。言語化しにくい箇所をスムーズに理解できるため、誤解を少なくしながらOJTができます。
動画を挟むことで理解しやすくなり、新人研修フロー全体の工数を抑えられます。
安全教育

現実の事故も紙のマニュアルではイメージを共有しづらい案件です。単に危険と書いてあっても現場に出たことがない方とそうでない方では、思い描く事故の規模や危険性は異なります。
動画を用いると危険な箇所や事故の再現映像を共有できます。加えて、事故を起こさないようにする手順やポイントも共有できる点がメリットです。
こうした安全性の高い教育は、製品の品質や生産性にもつながるでしょう。従業員の安全性の意識が高まることで、動画以外の現場の問題点や危険な箇所の共有もしやすくなります。
現場のさまざまな指標を改善したいのならば、動画の作成を推奨します。
製造業での動画マニュアル活用事例

製造現場の動画マニュアルは、主に複雑な機械の操作手順を伝えるために用いられるでしょう。
例えばイーグルブルグマンジャパン株式会社は、自動車やロケットなどで使用するメカニカルシールの製造に動画マニュアルを用いています。
また新人研修にも動画マニュアルは有用です。児玉化学工業株式会社ではヤスリでバリを取る作業を撮影し、動画マニュアルで共有しています。
単純な作業のように見えて多くの注意点の存在を認知でき、現場の作業に早く馴染むことができます。こうした動画マニュアルを通じて手順の誤りを削減し、不良を大幅に改善できるでしょう。
製造業の動画マニュアル制作の流れ

動画マニュアルを作成するには、まずマニュアルの目的やゴールなどの目標を明確にします。目標を明確にするとは、具体的に目標となる数字を掲げることです。
例えば、既存の文書マニュアルの工数3割削減や作業ミスの5割削減などです。
こうした目標を掲げた後は、動画マニュアルの活用機会を5W1Hで整理します。利用者の状況から逸脱せずにマニュアルを作成できるため、効果が期待できるでしょう。
目標と活用機会を明確化した後は、動画にする業務を決定します。すべてを動画にはできないため優先度をつけます。動画マニュアルを実際に作成するにあたって責任者を決めましょう。
構成案と台本を作成し、必要な要素を洗い出したら撮影します。撮影には機材と扱える人材が必要です。また動画編集も、字幕や業務のポイントを表示する図の差し込みが必要です。
Funusualは、動画制作のプロフェッショナルとして製造業の現場を理解した動画マニュアルを制作します。
「現場全体を効率化する動画マニュアルを作成したい」「ポイントや注意点を明確にする編集をしてもらいたい」そんなご要望をお持ちの方は、ぜひFunusualにご相談ください。
製造業で動画マニュアルを導入するときのポイント

動画マニュアルは紙のマニュアルではできない効率化を現場にもたらします。しかし、闇雲に作成すればよいわけではありません。
製造業に導入する動画マニュアルにはいくつかのポイントを盛り込む必要があります。
- 動画は短時間にまとめる
- NG例も動画に取り入れる
- 読み上げやテキストを活用する
- 作業者目線で撮影する
- 視聴環境を整える
- 動画制作業者に制作依頼する
現場で活用できる実用的な動画作成のポイントを理解しましょう。
動画は短時間にまとめる
動画マニュアルでは現場の動きを複数の工程に細分化し、それぞれをまとめて一本の動画マニュアルとしましょう。一つの工程は1分以内が目安です。
1分の理由は、人は1分を超えると集中力が低下するためです。せっかく現場の生の情報を動画マニュアルにしても、集中力の低下で見落としては意味がありません。
特に製造現場の動画マニュアルでは、危険な箇所を伝えることも多いでしょう。見落としの発生は大きな事故につながるため、コンパクトにまとめることを意識しましょう。
NG例も動画に取り入れる
製造業の動画マニュアル制作で特に重要なポイントは、作業の失敗パターンの収録です。正しい現場作業だけではなく、やってはいけないミスをあえて撮影します。
成功例だけでは失敗した際に何が起こるかを理解できず、注意点を過小評価するかもしれません。
部品の破損や作業工程の滞りなどが実際に発生した映像や、再現映像を撮影して危険性の理解を促しましょう。
こうしたNG例の撮影で危険性が強く浸透すれば、意識の改善につながり安全意識が高まります。
危険性を過小評価しなければ、失敗を未然に防ぎ重要箇所をより明確にできるでしょう。
読み上げやテキストを活用する

動画マニュアルは視覚と聴覚に働きかけることで、紙のマニュアル以上の理解を促せます。しかし、重要な作業ポイントでは音声による読み上げや字幕を活用しましょう。
音声を用いると、映像だけの重要ポイントを強調できます。字幕をつけると聞き間違いを防げるため、理解にばらつきが生じることも防げます。
より重要なポイントや危険な箇所は、映像を一時停止にして音声で解説しましょう。映像が急に止まることで、重要箇所を見逃しません。
また外国の方も利用する場合には、字幕の翻訳を通じて対応できます。新しい動画の撮影をしなくて済むため、効率的です。
作業者目線で撮影する
動画マニュアルの撮影では画角が重要となります。撮りやすい場所から撮るのではなく、作業者の目線に沿った撮影や作業全体を俯瞰できる位置からの撮影が望ましいでしょう。
これは、動画マニュアルを見る方の理解力に差が出るためです。縦型の製造装置では縦長の画角が適しており、横の動きが多いライン作業では横長の画角が適しています。
動きに沿った画角を選択しなければならないため、現場の作業員に確認してもらいましょう。
また機械や撮影者の影は視認性を悪化させるため注意が必要です。
視聴環境を整える
動画マニュアルで、動画画質は重要な要素です。画質の鮮明化に必要なものは専門機材ではなく、ピンボケや白飛びを防ぐ撮影技術です。
ピンボケや白飛びを防ぐために、カメラは固定しましょう。三脚がなくとも作業台に固定できれば、安定した映像が撮影できるでしょう。明るさも重要な要素で、照明を工夫し影を減らします。
こうした工夫で画質を鮮明にしなければ、製造業では特に危険なミスにつながりかねません。動画マニュアルを撮影する際は、細部まで作業が確認できるかどうかに注意しましょう。
また見にくさは目の疲れにつながるため、繰り返し視聴で目が疲れないかどうかも一つの基準となります。
動画制作業者に制作依頼する

効果的な動画制作には台本が必要となります。必要な工程を洗い出し、短くまとめて作業手順を段階的につなげる必要があります。
こうした過程は撮影に慣れていなければ難しいでしょう。自社での撮影が難しい場合は、専門の動画制作業者への依頼も候補に上がります。
動画制作依頼のメリットは、高品質な動画マニュアルを作成できることです。プロ仕様の高価な撮影機材を用いて、高い編集技術により見やすい映像を動画マニュアルにできます。
製造業の動画マニュアルに対するノウハウがあるため、懸念点などに理解を示しながら作成してくれるでしょう。
動画マニュアル作成にかかる費用の相場

動画制作会社に委託する場合は、初期費用は300,000円ほどです。
また動画一本の制作コストも300,000円ほどとなり、1ヶ月の運用費が50,000円ほどかかります。
コストを抑えたい場合は、ソフトを用いて自社で制作しましょう。動画作成の費用相場は、無料ソフトを用いた作成でおよそ20,000円ほどです。
これは担当者の作業時間を時給2000円ほどで換算したもので、初めて動画マニュアルを作成する場合はより多くかかるでしょう。
企業によっては有料ソフトを用いた撮影も候補となります。動画一本のコストは無料ソフトより安い14,000円ほどになりますが、初期費用が150,000円ほどになります。
無料であれ有料であれ、1ヶ月の運用コストは20,000円ほどかかるでしょう。
このように動画制作会社への依頼は安くありません。外注する際は、制作現場に理解がある会社への依頼が望ましいでしょう。
Funusualは企画から撮影までワンストップで対応するBtoB企業に特化した動画制作のプロフェッショナル集団です。
「現場の作業効率を向上させたい」「製造業を理解している制作会社に依頼したい」と希望の方は、ぜひFunusualへお問い合わせください。
動画マニュアル導入で製造業の業務効率化を図るなら

動画マニュアルは、文字にできないベテラン作業員のノウハウや現場の注意すべき箇所を漏らさず伝えられるツールです。
制作現場で動画マニュアルを用いると、紙のマニュアルでは得られなかった現場の効率化を実現できるでしょう。
動画マニュアルは社内でも制作できますが、動画の脚本作成や画像を鮮明にする撮影はプロでなければ難しいです。
もし動画マニュアルの制作に興味があるなら、Funusualにお任せください。
Funusualは単なる動画制作会社ではなく、製造業の現場改善をともに考えるパートナーです。
私たちはこれまで多数の製造業のお客様と伴走し、作業手順の標準化・新人教育の効率化・ミス削減といった具体的な成果を生み出してきました。
企画段階ではヒアリングを通じて現場の課題を丁寧に整理し、撮影では熟練作業員の動きや注意点を的確に映像化します。
編集段階では、字幕・図解・NG例を効果的に取り入れ、視聴する方が実際に現場に立っているように理解できる動画マニュアルを実現します。
企画から撮影・編集までワンストップで対応しつつ、導入後の活用方法まで伴走できるのがFunusualの強みです。
「新人教育の時間を短縮したい」「現場でのヒューマンエラーを減らしたい」「手順を標準化して品質を安定させたい」といった課題をお持ちの企業様に、適切な動画マニュアルを提供いたします。
製造業の現場改善と業務効率化を本気で実現したい方は、ぜひFunusualにご相談ください。













