「紙のマニュアルでは伝わりづらい」「指導者によるOJTだけでは教育が追いつかない」とお悩みの教育担当の方もいらっしゃるでしょう。
動画マニュアルを使えばわかりやすく安定した内容が伝えられ、指導者が教育に割く時間を削減できます。導入メリットや特徴を知れば、自社に取り入れた方がよいかどうかもわかるでしょう。
この記事では、動画マニュアルの特徴やメリット、自社制作や外注を行うときのポイントを解説します。自社で動画マニュアルを導入する際にお役立てください。
動画マニュアルとは?
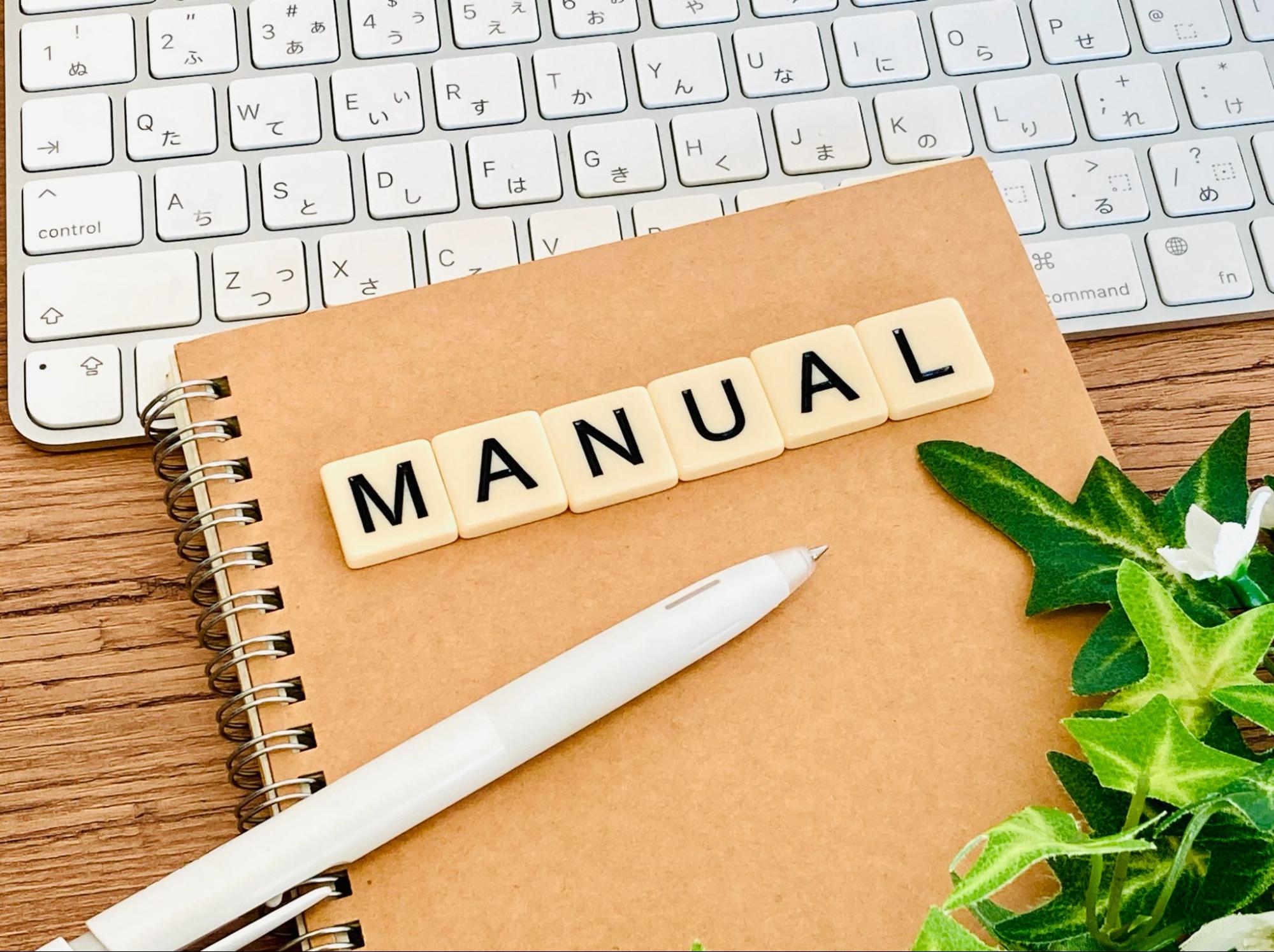
動画マニュアルとは、業務手順やシステムの操作方法、製品の使い方などを動画で説明したマニュアルです。
動画に音声やテロップを加えてあるものも多く見られます。
紙や静止画のマニュアルでは伝わりづらい内容を、よりわかりやすく解説するためのものです。
動画マニュアルの特徴と紙マニュアルとの違い
紙マニュアルはテキストと静止画で構成されているため、複雑な操作方法や動作を伝えにくいという難点があります。
一方で、動画マニュアルは複雑な操作や動作を映像で視覚的に伝えられるのが特徴です。
映像は見た方の記憶に残り、複雑な内容を文章や静止画よりもわかりやすく伝えられます。紙マニュアルと動画マニュアルでは理解のしやすさが大きく異なります。
動画マニュアルの主な種類と用途
動画マニュアルにはさまざまな種類と用途があります。大きく分けると、企業が社内の教育用に作成しているものと、顧客向けに作成しているものの2つです。
顧客向けのものは商品やサービスの使い方を説明する動画がほとんどですが、社内用は種類や目的がさまざまです。社内用は主に以下の用途があります。
- 新人研修用
- 業務手順の説明
- システム操作の説明
- 接客・対応スキルの向上
新人教育からステップアップのものまで、目的に応じた多くの種類があります。
動画マニュアル導入のメリット

動画マニュアルを社内に導入すると、紙のマニュアルにはない多くのメリットが得られます。主なメリットは以下の4つです。
- 視覚的で理解がしやすい
- 繰り返し再生でき習熟度が向上する
- 教育品質の統一化が可能になる
- コスト削減・ペーパーレス化につながる
社内業務にどのような影響があるのか、具体的に解説します。
視覚的で理解がしやすい
動画マニュアルのメリットの一つは、テキストや静止画だけのマニュアルよりも理解がしやすい点です。
複雑な動作や手順は文章で表すと難しく、十分に理解ができないケースも少なくありません。読み手によっては、理解するために同じ文章を何度も読まなければいけないこともあるでしょう。
動画なら複雑な動作を映像として見ることで、直感的に理解が可能です。
パソコンの操作マニュアルなら実際の画面を動画で見ながら学べ、体を使う作業なら手の動かし方や力加減なども把握できます。
機械やシステムの操作などは特に、静止画や言葉で説明するよりも、実際の動きを映像で見た方が早くて正確な理解ができるでしょう。
理解がしっかりとできることで仕事のミスや混乱を防げます。
動画マニュアルは言葉では伝わりにくい内容も、映像により視覚的な理解が可能です。
繰り返し再生でき習熟度が向上する

動画マニュアルなら何度でも繰り返し再生ができ、学習者が内容を習得するのに役立ちます。
一度きりの研修では理解が追いつかないこともあるでしょう。
社員が何度でも動画を見られるように社内システムなどにアップロードしておけば、必要なときに自由に視聴ができます。
理解を深めたい箇所を部分的に再生するなど、自身のペースにあわせて学習を行うことも可能です。
一度では覚えきれない多くの行程や複雑な作業を動画にすれば、繰り返し再生できるメリットが活かせます。
納得できるまで学習できる場が得られれば、社員の習得度が高まり業務の向上にもつながるでしょう。
何度も教え直さなければならない教育担当者や上司の労力も減ります。
繰り返し再生が可能な動画マニュアルは、会社にとっても社員にとってもプラスとなります。
教育品質の統一化が可能になる
動画マニュアルは安定したクオリティの学習内容を保てます。
教育係が研修を行うとその時々により取りこぼしてしまう箇所が出るなど、内容にムラが出かねません。
教育係が複数人いれば、内容の伝え方や説明のわかりやすさにもばらつきが出るでしょう。
しかし、動画なら見るたびに内容にばらつきが出ることはなく、一定のクオリティを保って教育が可能です。
動画に必要な内容がすべて組み込まれているか、わかりやすい表現かなど、内容の品質を吟味したうえで作成されています。
一度クオリティの高い動画を作成すれば、それ以降は統一した教育品質を保てるようになります。
コスト削減・ペーパーレス化につながる

紙マニュアルを動画マニュアルへ変えることで、ペーパーレスとなり紙の消費やコストの削減になります。
社員の人数が多い企業程、コスト削減の効果は大きく表れるでしょう。20枚程度のマニュアルを500名の社員に配るだけでも、10,000枚の紙が消費されます。
自社でマニュアルを印刷しているなら、紙のほかにもインク代や製本するための人件費がかかっています。社員の人数分を製本するための時間と労力は、少ないとはいえないでしょう。
新人研修用のマニュアルなら、毎年新人が入ってくるたびに印刷と製本が必要です。動画マニュアルは動画を共有するだけでマニュアルの準備が整います。
ペーパーレス化してコストが削減できる点も動画マニュアルのメリットです。
動画マニュアル制作の基本的な流れ
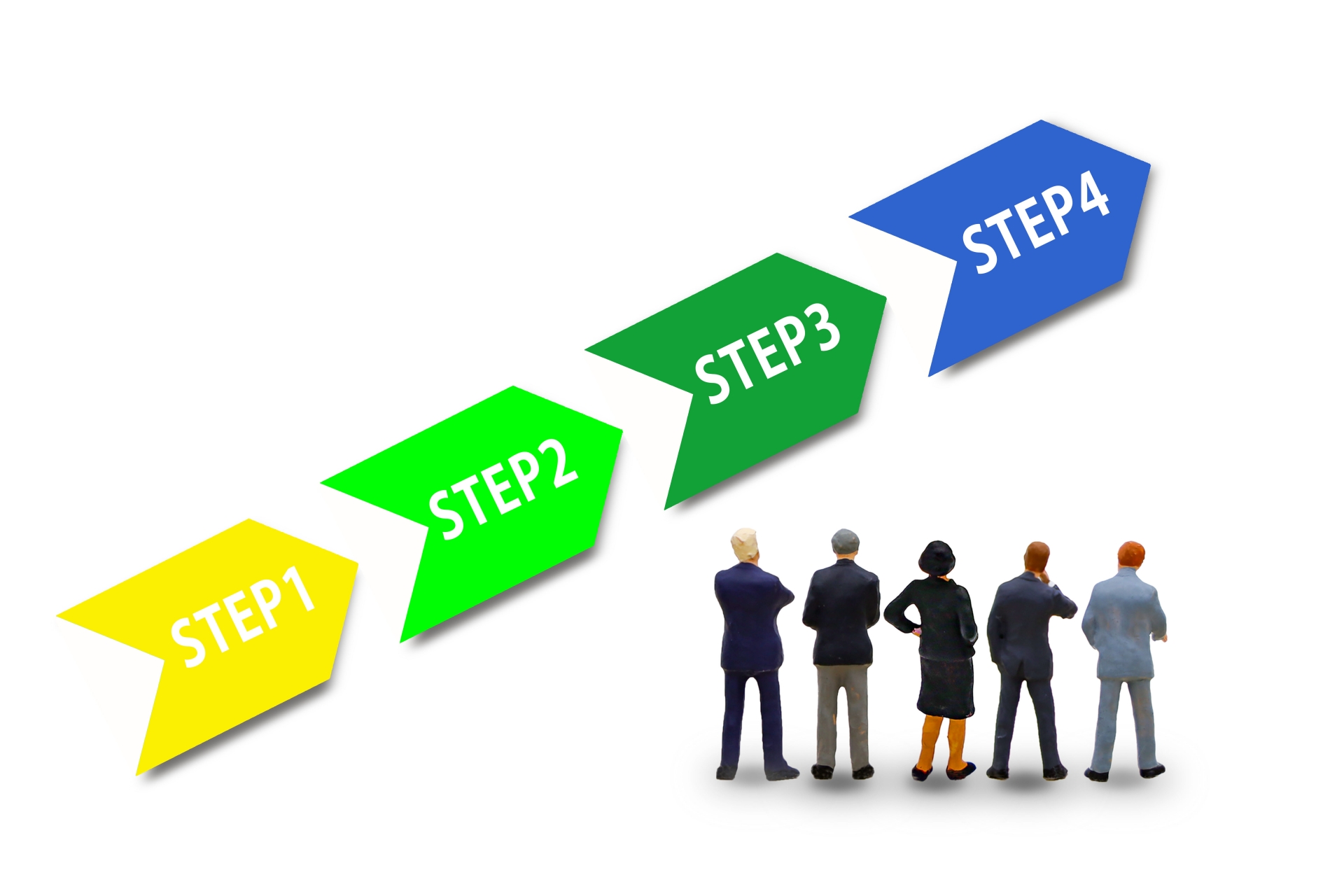
動画マニュアルは準備や綿密な計画なしに制作できるものではありません。
一つひとつステップを踏んで作業を進めていく必要があります。
制作のために欠かせない事前準備や作業工程は以下のとおりです。
- 目的とターゲットを設定する
- 構成案・台本を作成する
- 撮影・ナレーション録音を行う
- 編集・テロップや図解の挿入
ステップごとにどのような作業を行えばよいか詳しく解説します。
目的とターゲットを設定する
誰に向けての動画を作るのか、どのような目的の動画なのかを明確にするところから始めます。
ターゲットと目的がはっきりと定まっていないと、動画の方向性がぶれてしまい、誰のためにもならない動画となってしまいます。
また、目的を企業の根本的な理念や計画を伝えることに絞れば、経営理念や将来のビジョンを盛り込んだ動画にまとまります。
ターゲットと目的を決めれば動画の内容に統一性が出て、相手にしっかりと内容が伝わる意味のあるマニュアルとなります。
構成案・台本を作成する
目的とターゲットの設定が明確にできたら、構成案と台本を作成します。
構成案は全体の流れを組み立てるもので、どの内容をどの順番で動画にしていくかの骨組みとなるものです。
構成ができたら骨組みをもとに台本を作りましょう。
台本は動画の展開やナレーションなどを決めて文書に書き起こしたものです。
できた台本をもとにその後の撮影を進めるため、1シーンごとにできるだけ細かく描写を決めておきましょう。
撮影・ナレーション録音を行う

台本に沿ってシーンごとの撮影を進め、その後動画にあわせたナレーション録音を行います。
撮影した画像があまりにも悪いと見る方にストレスを与えるため、画質や画角を意識しましょう。
できるだけきれいな画質で撮影できるカメラを選ぶことも大切です。
撮影した動画が問題なく撮れているか、1シーンごとに確認をしながら進めていきます。
動画の撮影がすべて終わったら、動画の尺に合うようにナレーションを録音します。
聞き取りやすい発音やイントネーションで録れているか、すべての台詞をチェックしましょう。
編集・テロップや図解の挿入
撮影とナレーション録音が終わったら最後に編集を行います。撮影したシーンをつなぎあわせ、必要な場面にはテロップ・図解・BGMなどを入れていきます。
映像とナレーション・テロップなどが合っているかを確認しておきましょう。
見にくいところはないか、シーンの移り変わりが速すぎないかなど、最後に全体のできあがりをチェックして完了です。
わかりやすい動画マニュアルを作るためのポイント

動画マニュアルをわかりやすく作るにはいくつかのポイントがあります。
- 動画は1テーマごとに短くまとめる
- 作業シーンを具体的に伝える
- テロップや図解を効果的に活用する
上記の3つのポイントを押さえるだけで、動画が格段に理解しやすいものへと変わります。
具体的にどのようにすればよいかを解説します。
動画は1テーマごとに短くまとめる
1つの動画に取り入れるテーマは1つに絞り、なるべく短い時間でまとめていくのがポイントです。
1つの動画で複数のテーマを取り扱うと理解が追いつかず、長すぎる動画は重点を伝えられないからです。
複数のテーマを詰め込んだ長い動画は、結局何を伝えたいのかがわかりません。テーマごとにわけて動画を作成し、視聴者にとって理解しやすいものとなるよう心がけましょう。
たくさんのことを伝えたい思いが、裏目に出ないように注意しなければなりません。
作業シーンを具体的に伝える

動画の特性を活かして、実際の作業シーンを映像にして伝えるとわかりやすくなります。
例えば、調理手順を解説する動画があるとします。「にんじんを乱切りにする」と聞くとイメージが湧きにくいですが、実際に乱切りのシーンを見れば簡単にわかるでしょう。
「玉ねぎをあめ色に炒める」という言葉だけではわからなくても、映像で見れば理解が可能です。
料理をする作業シーンを動画にして見せることで理解がしやすくなり、映像のイメージが記憶に残ります。
業務手順やシステム操作など、さまざまな動画で同じ手法が使えます。
テロップや図解を効果的に活用する
動画マニュアルは映像とナレーションに加えて、テロップや図解を適度に入れるとさらにわかりやすい動画になります。
作業シーンにはナレーションと同時にテロップを入れるとよいでしょう。
見ている方にとって聞きなれない言葉があれば、ナレーションだけでは聞き逃してしまうかもしれません。
テロップを入れることで聞き逃しそうな言葉も目でとらえることができます。
また、数字や組織図などを解説するときは図解を入れるのが効果的です。
ナレーションやテロップで説明されるよりも、グラフやチャート図を見た方が一目瞭然で理解ができるからです。
テロップや図解を入れる際には、視聴者が見やすい大きさや色、表示スピードなどに気を付けましょう。
見にくかったり表示時間があまりにも短かったりすると、視聴者が目で捉えられず理解ができません。
テロップや図解の挿入はわかりやすい動画マニュアルを作るための大切な要素です。
動画マニュアルを自社制作する際の課題・注意点

自社で動画マニュアルを制作するには、解決しなければならない課題がいくつかあります。
以下の課題は多くの企業で制作の壁となる問題です。
- 撮影・編集には専門的な技術が求められる
- 社内リソース(人材・時間)が不足しやすい
- 動画の品質にばらつきが生じる恐れがある
それぞれの問題を詳しく解説します。
撮影・編集には専門的な技術が求められる
動画をわかりやすくクオリティの高いものへ仕上げるには、撮影や編集のスキルが必要です。動画制作に携わっている方でなければ、通常は持ちあわせていないスキルです。
少し学んだだけで身に付けられる技術ではないため、自社の制作担当者が習得するのは難しいでしょう。撮影と編集のスキルは動画制作において必須です。
自社でスキルの確保ができない場合は、動画制作会社への依頼をおすすめします。プロのスタッフが行うことで、間違いのない品質の動画に仕上がります。
Funusualは、BtoB企業向けの動画制作に精通した制作会社として、これまでに数多くの動画を手がけてきた経験があります。
IT・製造業・工業・建設業など、専門性の高い業界にも対応し、複雑な手順や業務内容を誰にでもわかりやすく伝える動画を企画・制作しています。
「自社で動画を作る時間もノウハウもない」「クオリティの高いマニュアル動画を外注したい」とお考えの方は、まずはお気軽にFunusualまでご相談ください。
社内リソース(人材・時間)が不足しやすい

社内が人手不足だったり社員に余裕がなかったりすると、動画制作に割ける時間は確保できないでしょう。
動画制作を一人で完結させるのは無理があるため、数人を制作担当者として割り当てる必要があります。
制作には長い期間が必要で、その間は担当者がほかの仕事をこなすのが難しくなります。
無理してほかの仕事と同時進行で行えば担当者に負担がかかり、担当者が仕事を抜けた分の穴埋めを周囲の社員が行わなければなりません。
人材と時間に余裕がなければ社員の負担が大きくなり、本来の業務もままならなくなるでしょう。社内リソースが不足することは自社制作を困難にする大きな壁となります。
動画の品質にばらつきが生じる恐れがある
自社制作を行うとどうしても動画の品質にばらつきが生じ、一定のクオリティのものは期待できません。制作のプロではない担当者が作るので仕方のないことです。
しかし、クオリティの低い動画マニュアルは伝えたいことが伝わらず、学習効果の低いものとなってしまいます。
制作の労力に見合っただけの成果が得られない可能性もあります。
人材と時間を割いても品質に期待できない点は自社制作の課題です。
動画マニュアル制作を外注するメリット

動画マニュアルの制作を自社制作にこだわる必要はありません。制作を外注すると次のメリットがあります。
- プロ品質で高クオリティな動画が完成する
- 制作期間が短縮され効率化できる
- 本業に集中し社内負担を大幅に軽減できる
自社制作を行う際に障害となる問題を、外注に出すことで解決できます。外注のメリットを詳しく解説します。
プロ品質で高クオリティな動画が完成する

外注に出せば、自社制作では叶えられない高クオリティの動画が仕上がります。
動画制作会社はプロ集団です。企画の段階から任せれば、制作手順の第一ステップであるターゲットと目的の設定もより細かく行ってくれます。
構成や台本もプロが作ったものは、視聴者にとって理解がしやすいものとなるでしょう。プロのナレーションは聞き取りやすく、不自然さや違和感のない音声としてスムーズに耳に入ります。
見る方に伝わりやすいことはもちろん、心に響く動画にしたいなど、プラスアルファの要望も叶えてくれます。
高クオリティな動画が完成して費用対効果が得られることは、外注の大きなメリットです。
制作期間が短縮され効率化できる

自社制作では膨大な時間を割いてすべての作業を行うことになりますが、外注すると制作期間は短く済みます。
動画が早く仕上がる分、動画マニュアルの導入も早くなり、教育担当者の負担が減るなどして業務が効率化されます。
自社制作では不慣れな担当者が制作を行うため、必要以上に時間がかかるでしょう。制作会社に任せれば制作期間の短縮が可能です。
本業に集中し、社内負担を大幅に軽減できる
制作を外注すれば社内の人材や時間を奪われることなく、本来の業務に集中できます。制作に割かれる時間は、制作会社との打ち合わせや要所ごとのやり取りのみです。
自社制作のように、制作担当者やその周囲の社員に負担がかかりません。社内負担を大幅に減らせる点は大きなメリットです。
「動画マニュアルを作りたいけれど、社内に人手も時間もない」「どう進めればいいかイメージが湧かない」そんなお悩みをお持ちの方は、まずはBtoB企業向け動画制作に特化したFunusualにご相談ください。
Funusualでは、企画の段階から丁寧にヒアリングを行い、目的や課題を明確にしたうえで、適切な動画構成をご提案いたします。
具体的な内容が決まっていない段階でもご相談OKです。プロの視点から、制作の必要性や効果も含めてアドバイスいたします。
「まずは話を聞いてみたい」「本当に動画制作が必要か判断したい」という方も、お気軽にお問い合わせください。
動画マニュアル制作会社の選び方・比較ポイント

動画制作を外注する際に、どのような基準で制作会社を選べばよいのか、選び方と比較ポイントを紹介します。以下の3つに注目して選んでください。
- 過去の制作実績や得意分野を確認する
- 見積り内容が明確でわかりやすいか
- 企画力・提案力の高さをチェックする
選び方を具体的に解説します。
過去の制作実績や得意分野を確認する
動画制作会社は多くありますが、会社により特徴や得意分野はさまざまです。会社のホームページを見ると、どのような動画に特化していてどのような実績があるのかがわかります。
自社の動画作成目的に合ったものが作れそうか、会社紹介などを見ながら確認していきます。過去に作った動画のサンプルが掲載されていれば、実際に再生して見てみましょう。
社内向けの動画マニュアルを作成するなら、企業向けの動画制作に特化した会社を選ぶのがおすすめです。
見積り内容が明確でわかりやすいか
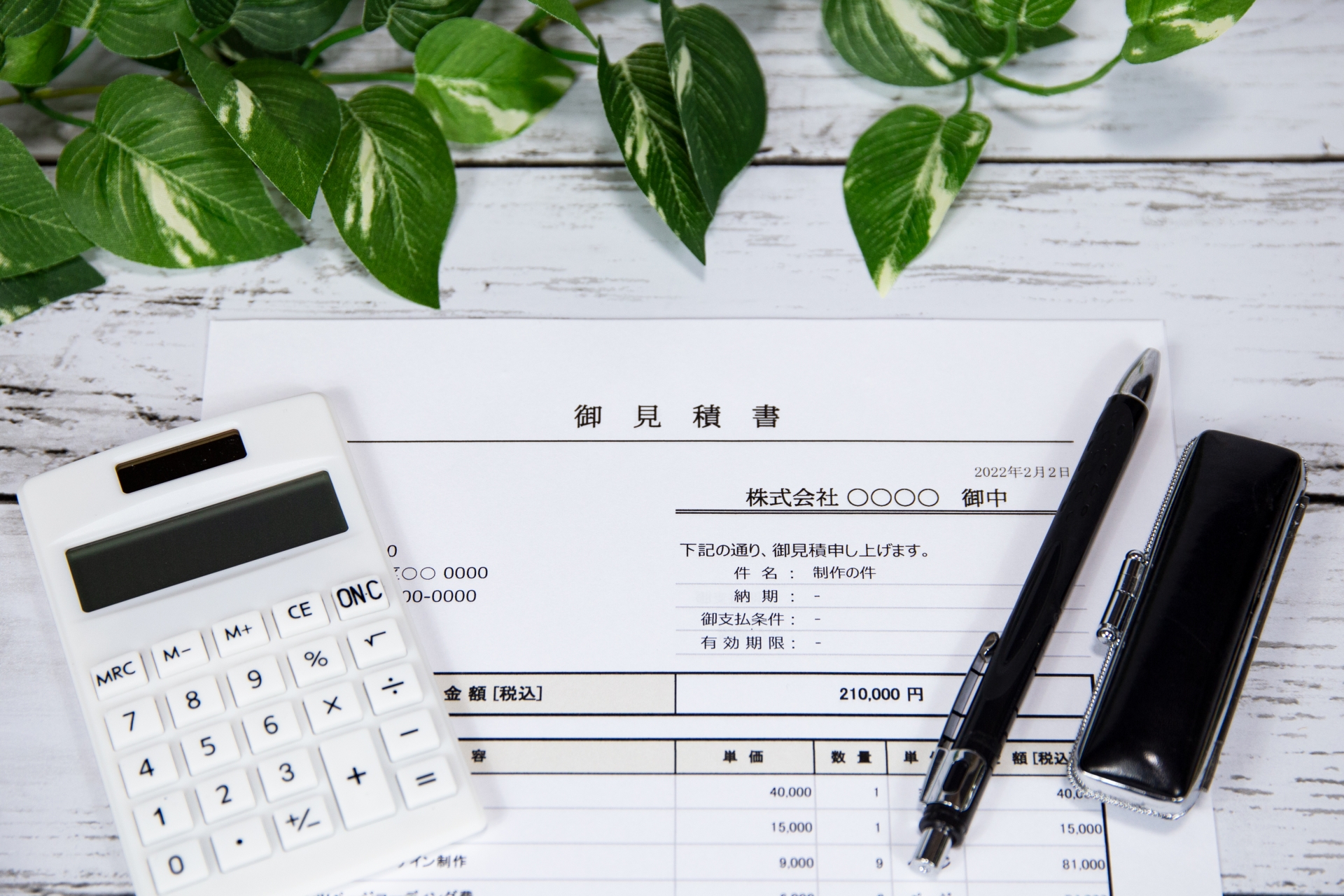
見積りがわかりやすいものになっているかも重要です。
実際に打ち合わせをすると、依頼者の希望をヒアリングして見積りを出してくれます。
よくわからない項目が記載されていたり、本当に必要かわからない項目があったりする場合は、明確な回答を求めましょう。
誰が見てもわかりやすい見積り書になっているかも、よい制作会社を選ぶポイントとなります。
企画力・提案力の高さをチェックする
こちらの要望や悩みに対して、どれだけの企画と提案ができるかも重要な決め手です。
制作会社に費用を払って制作を依頼するのは、費用対効果を期待してのことでしょう。
ただ要望したとおりの動画を作るだけではなく、プラスアルファの効果が得られれば外注に出すメリットは大きくなります。
契約前の打ち合わせで十分に話をして、相手の力量を見極めるようにしましょう。制作にコストをかけるなら、企画力と提案力のある制作会社を選ぶことが大切です。
動画マニュアルの効果を高めるためにプロへの依頼を検討しよう

動画マニュアルは紙マニュアルとは違い、学習者が理解しやすく繰り返し何度も見られるというメリットがあります。
社内教育に導入している企業も多く、これからは動画マニュアルが主流になっていく可能性も高いでしょう。
自社制作を行う選択肢もありますが、高いクオリティと費用対効果を求めるなら、プロの制作会社への依頼がおすすめです。
Funusualは、BtoB企業向けの動画に特化した制作会社です。
動画マニュアル業務内容や社内教育に直結する動画だからこそ、伝わる構成・分かりやすい表現・高いクオリティが重要です。
私たちは、企画の段階から丁寧にヒアリングを行い、現場の課題や目的に合わせて費用対効果の高い動画を企画・制作します。
「紙のマニュアルでは伝えきれない」「業務を標準化したい」「新人教育の効率を上げたい」そんなお悩みを、視覚的でわかりやすい動画マニュアルで解決しませんか?
まずはお気軽にご相談ください。目的と現場に寄り添った映像をご提案いたします。













