日常的に映像と動画の言葉に触れているものの、その違いが曖昧なままで、どちらを使うべきか判断に迷っている方もいるでしょう。
映像と動画は似ているようで異なり、目的や手段によって使い分けることで伝達効果が大きく変わります。
この記事では、映像と動画の違いを意味や特徴、制作面や活用場面などの多角的な視点から丁寧に解説します。
両者の違いが明確になり、今後の企画立案や制作依頼の判断に役立てられれば幸いです。
映像と動画の意味と特徴
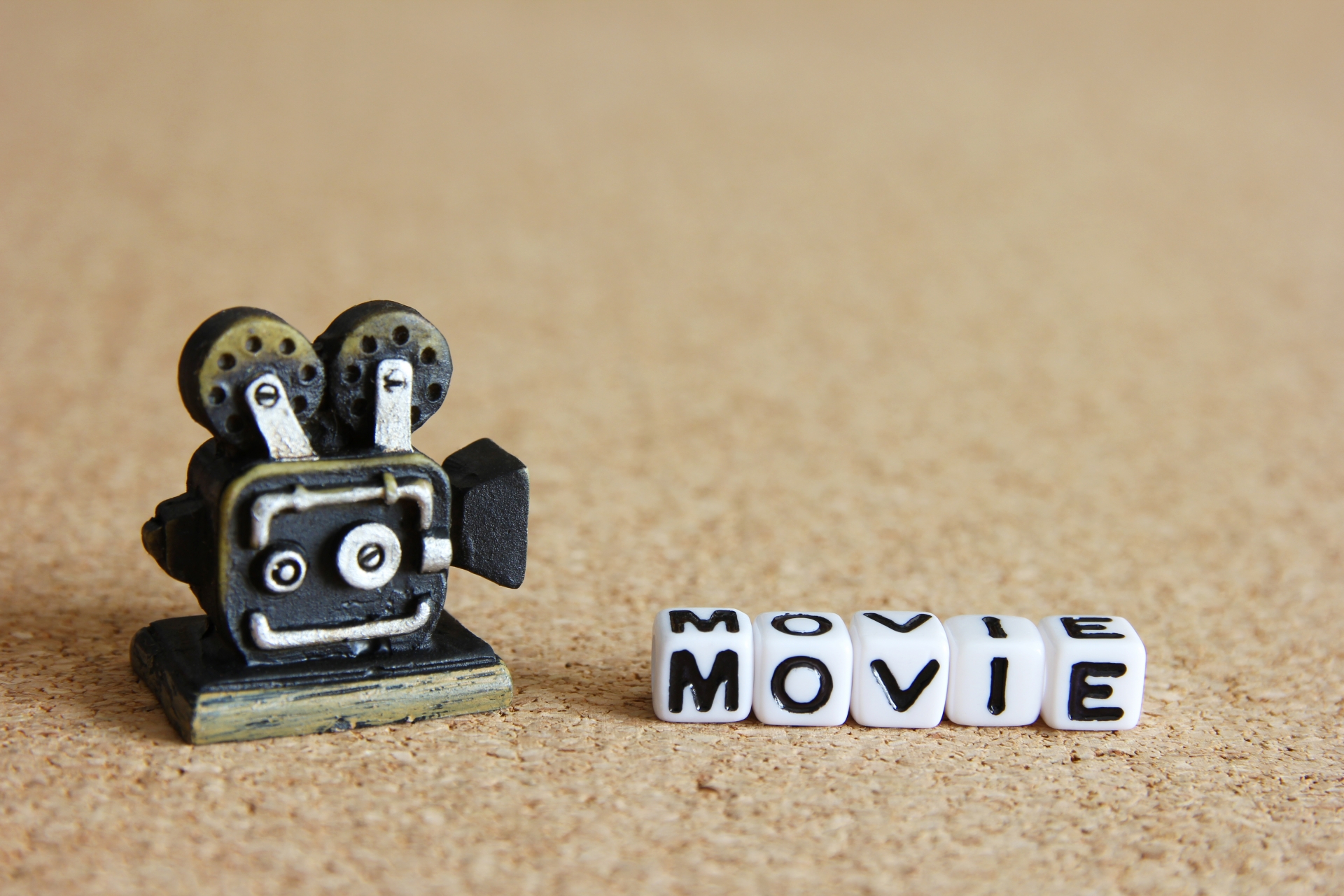
映像と動画はどちらも視覚コンテンツを指しており、両者の違いにあまり意識を向けていない方もいるでしょう。
実は、映像は芸術性や物語性が重視され、動画は情報伝達や短時間の訴求を目的とする傾向があります。
そのため、映像は作品、動画はデータとして取り扱われる場合がほとんどです。
例えば、式典で撮影されたものは動画となりますが、その動画を編集してDVDやCDに焼くことにより映像となります。
このように、同じ撮影されたものでも、映像と動画のように呼び方が異なります。
では、具体的に映像と動画について以下で詳しくみていきましょう。
映像
映像は、デジタル技術で生成された視覚的な表現全般を指しており、静止画と動画の両方を含んでいます。
そのため、映画のフィルムやテレビ放送だけではなく、デジタルカメラで撮影された写真も含まれます。また、芸術的・技術的な文脈で使われることがほとんどです。
特徴は、静止画や動画だけではなく、CGやアニメーションなどの広範な視覚コンテンツを含んでいることです。
また、映画やテレビ、芸術作品などのストーリー性や美的要素を重視する場合に使われます。
動画

動画は、連続する画像を時間に沿って再生する視覚コンテンツです。映像とは違い動くものだけに限定されており、デジタル形式で扱われることがほとんどです。
そのため、YouTubeやTikTok、オンライン講座などが動画に含まれます。また、日常的でカジュアルな場面に使われることがほとんどです。
特徴は、静止画と比べると一定時間でよりたくさんの情報を提供できる点です。また、インターネットやSNSでの共有やストリーミング配信に適した形式で提供されます。
近年では、スマートフォンの普及や通信環境の向上により、動画の視聴がより手軽になっています。
情報収集や娯楽の手段に用いられているため、今後もさらに動画の重要性は高まるでしょう。
映像と動画の違いを判断する基準

映像と動画の違いを判断する基準には、以下が挙げられます。
- IPT(Informative/Persuasive/Thematic)
- 媒体(映画・YouTube・CMなど)
これら2つによって判断できることを、事例を交えて解説します。
IPT
IPTとは、Informative Persuasive Thematicの略で、下記の3つにコンテンツの目的や性質を分類します。
- Informative(情報提供型):情報や知識の伝達
- Persuasive(説得力型):行動の促進やメッセージの伝達
- Thematic(テーマ型):感情やテーマの伝達
映像はThematicやInformativeな目的で利用される場合がほとんどで、ストーリー性や芸術性、深いメッセージ性を重視する傾向があります。
一方で、動画はPersuasiveやInformativeな目的で利用される場合が一般的で、短く気軽に消費されるコンテンツがほとんどです。
InformativeとPersuasive、Thematicに分けて映像と動画の具体例を見ていきましょう。
Informativeの映像では深い情報や専門性を提供する長尺のものが多く、動画では短く簡潔で実用的な情報が多い傾向です。
例えば、映像はテレビ放送のドキュメンタリー、動画は解説動画が挙げられます。
Persuasiveの映像ではストーリー性や高品質なビジュアルで深い印象を与えるものが多く、動画では短くインパクト重視で視聴者の行動を促すものが多い傾向です。
例えば、映像はプロモーション映像、動画はSNSのキャンペーンが挙げられます。
Thematicの映像は深いテーマや長編のストーリーが中心で、動画は短いながらも感情やメッセージを凝縮したものが中心です。
映像の例には映画が、動画の例にはYouTubeのショートフィルムが挙げられます。
このように、IPTで映像と動画の目的や違いを分類できます。
媒体

媒体とは、視覚コンテンツが配信されるプラットフォームや映画やYouTube、テレビやSNSなどの形式を指します。
媒体により、コンテンツの長さや視聴環境、ターゲット層が異なります。
映像は映画館やテレビ、美術館などのフォーマルな場面や長尺のコンテンツで使われるのが一般的です。
一方で、動画はYouTubeやSNSなどの短尺でカジュアルな視聴環境で配信されるものに使われることが多い傾向です。
そのため、インターネットやスマートフォンで視聴する方がほとんどでしょう。
明確な定義ではありませんが、媒体ごとでも映像と動画の区別を行えます。
映像と動画の制作面での違い

映像と動画の制作面での違いを、以下の4つの観点から説明します。
- メッセージ性
- 伝えられる情報量
- クオリティ
- 規模
詳しくみていきましょう。
メッセージ性
映像は深いメッセージ性を重視しており、視聴者に印象やテーマを伝えるため、制作する際は綿密なプランを作成して撮影や編集などが行われています。
一方で、動画は簡潔なメッセージが中心のため、制作する際は撮影のみ行ったり簡単な編集をして仕上げたりするのが一般的です。
そのため、映像は抽象的で芸術的なメッセージを伝えることが得意で、動画は具体的で即時的な訴求が得意です。
伝えられる情報量
映像はほとんどが長尺で、複雑なストーリーや多層的な情報を盛り込めるため、全体を通して伝えられる情報が多くあります。
動画は短尺な場合がほとんどのため、伝えられる情報量は少ないです。そのため、情報は簡潔に、要点を絞る必要があるでしょう。
一方で、一定時間で伝えられる情報量は、映像よりも動画の方が多い傾向です。なぜなら、動画は視聴者の求める情報を短時間で伝えきらなければならないからです。
クオリティ

映像は動画よりも大きな画面で見られることが多いため、プロが持つ高解像度の撮影機材が使用されています。
また、色彩補正やVFXなど細部までこだわり、高品質な仕上がりとなっています。
一方で、動画はスマートフォンや簡易カメラでも撮影や編集などの制作が可能です。また、一般の方が制作したものも多く、クオリティは幅広いです。
クオリティよりも、視聴者の求める情報を盛り込む必要があります。
そのため、映像は高クオリティが求められ、動画はクオリティに関係なく視聴者に受け入れやすいでしょう。
規模
映像は、大規模な場合がほとんどです。例えば、映画の場合は企画を行うだけでも数年かかる場合があります。
さらに、撮影や編集でも高度な技術やスキルが必要なため、1年以上に及ぶこともあります。
期間だけでなく、たくさんのスタッフや高額な予算、ロケやセットなど制作規模も大きいです。
一方で、動画は少人数でも制作できます。また、制作は企画から撮影、編集まで短期間で行われることが多い傾向です。
例えば、YouTube動画は企画から編集まで短ければ数日で制作できることもあります。
さらに、スマートフォンでの撮影や無料の編集ソフトの利用により、安価での制作も可能です。
一人でも制作できる動画とは異なり、映像は制作規模が大きくなります。
映像は、映画やテレビ番組、企業のプロモーションやドキュメンタリーに利用される場合が多いです。一方で、動画はSNSコンテンツや低予算のプロモーションに利用されます。
映像と動画の制作面での違いを理解して、作成を検討している方は、Funusualをご利用ください。
Funusualは、クライアント様のニーズに応じた戦略的な動画制作を行うBtoB動画エージェンシーで、BtoB業界の企業に向けた高品質な動画制作を提供しています。
動画制作の際は、単に視覚的に魅力的な動画を制作するだけではなく、クライアント様が抱える課題に寄り添って効果的な戦略に基づく動画を提供しています。
まずはヒアリングで動画の目的や期待効果、お客様の事業内容や製品の特徴をお話しください。
その後、業界の特色や競合他社のリサーチなどを行い、絵コンテや見積もりを通じてイメージとストーリーをご提案します。
映像や動画制作が気になる方は、まずは無料相談をご利用ください。
映像と動画の活用場面

自社の業務に映像と動画のどちらが適しているか知りたいと考えている方もいるのではないでしょうか?
ここでは、採用や営業、ブランド構築など映像に適した場面と動画に適した場面を分けて具体的に紹介します。
映像の活用が適しているシーン
映像の活用が適している採用や営業、ブランド構築のシーンをみてみましょう。
採用では、企業の文化や将来のビジョンなどを伝えるためのリクルートメント映像の制作に適しているでしょう。
なぜなら、高品質な映像の場合は求職者の感情に訴えやすく、企業への信頼感や憧れを持たせやすいからです。
営業では、大規模なプレゼンテーションや投資家向けの企業紹介映像に用いるとよいでしょう。
なぜなら、高品質な映像は視聴者の信頼性を高めたり強い印象を与えたりするのに効果的だからです。
作成する際は、製品やサービスの社会的影響やビジョンを強調する必要があります。
ブランド構築では、広告キャンペーンやホームページ素材に用いるとよいでしょう。
美しくストーリー性がある映像を制作することにより、ブランドのプレミアム感や独自性を強調できます。
動画の活用が適しているシーン

動画の活用が適している採用や営業、ブランド構築のシーンを紹介します。
採用では、求職者向けの職場紹介やイベント告知動画に動画を利用するとよいでしょう。
短くカジュアルな動画は拡散しやすいほか、気軽に企業の雰囲気を伝えられるため応募のハードルを下げられるからです。
営業では、製品デモやキャンペーン告知動画を作成し、視聴者に手軽に情報を伝えて購買意欲の促進につなげるとよいでしょう。
なぜなら、短尺でわかりやすい動画は、忙しい視聴者でもすぐに視聴できるからです。
ブランド構築では、SNSでのブランドエンゲージメント向上に利用するとよいでしょう。なぜなら、動画は頻繁に投稿可能なため、視聴者との継続的な接点を確保できるからです。
映像や動画活用の将来性

スマートフォンの普及や5G・AI・XRなどの技術の進化により、映像も動画も今後さらに重要になります。
VRやARの融合により、没入感のある体験を提供できるため、エンターテイメントや医療などさまざまな分野での革新が期待できるでしょう。
映像業界は、NetflixやAmazon Prime Videoなどの動画配信サービスの発達により、高品質な映像コンテンツへの需要を高めています。
また、高速大容量通信によって、高画質映像のストリーミング配信がよりスムーズになるでしょう。
さらに、AIによる動画編集やCG技術の進化により効率的で高品質な映像制作が可能になります。今後も、新たな技術の登場により、映像業界はさらに進化するでしょう。
一方動画市場は、SNSの普及により拡大の一途をたどっており、TikTokやYouTubeなど手軽なコンテンツが人気を集めています。
また、映像業界と同様に、技術の進化により多様化するでしょう。
映像や動画活用にはどちらも将来性があります。利用したいと考えている方は、Funusualまでご相談ください。
Funusualは、BtoB企業に特化した動画制作のノウハウを有しており、業界ごとのニーズに即した動画制作が得意です。
さらに、制作は企画から撮影や編集、修正対応まで一貫して対応しています。そのため、クライアント様にかかる負担は少なく、高品質な動画を提供できます。
まずは、無料相談をご利用ください。
動画制作のステップ

動画制作は、以下のステップで行われます。
- 企画と構成
- 撮影
- 編集
- 公開
各フェーズのポイントをみていきましょう。
企画と構成
企画と構成では、動画制作の目的やターゲットを決定し、ストーリーの構築を行います。ポイントは以下のとおりです。
- 動画制作の目的を明確化
- ターゲットの綿密な設定
- 掲載先の決定
- 動画撮影の準備
動画制作の目的には、ブランディングや販売促進、企業紹介などがあります。目的の明確化により、視聴者の行動決定を促すアクションが決まるでしょう。
ターゲットの綿密な設定は、動画のテイストや長さ、強調点などの決定に重要です。ターゲットに合わせた動画制作により、視聴されやすくなるでしょう。
掲載先の決定は、ターゲットを踏まえて行うとよいでしょう。
例えば、Facebookは幅広い年齢層が利用するのに対して、TikTokは若年層が主に利用しています。また、掲載先により視聴者に見られる動画の長さが異なる点にも注意しましょう。
動画撮影前の準備では、ストーリーの構成の作成はもちろん、動画撮影に必要な機材の準備を行いましょう。
綿密な準備を行わなければ、撮影に時間や余計なコストがかかる恐れがあります。
企画段階で、動画の内容をしっかりと検討しておきましょう。
撮影
動画撮影では、以下のポイントに注意しましょう。
- カメラの固定
- 1カットを短くする
- カメラワークの決定
カメラの固定は、手ぶれの防止や見やすい動画の撮影に必要です。
1カットを短くする理由は、視聴者が同じ映像が続くと飽きてしまうためです。さまざまな角度から撮影し動画に変化を持たせましょう。
カメラワークとは撮影技法のことです。カメラの固定のほか、手持ちで撮影し臨場感を出す技法やレンズの焦点を変化させるズームインなどがあります。
企画内容に合った撮影技法を用いましょう。
編集

編集では、撮影した素材の切り貼りやテロップや効果音、BGMなどを加えます。
撮影した素材の切り貼りでは、無駄な時間をカットして動画の間延びを防ぎましょう。特に、テンポを重視する場合は丁寧にカットすることが必要です。
テロップは、スマートフォンで見られることも考慮してなるべく大きな文字にしましょう。
また、文が長くなると読まれなかったり強調したい部分がわかりにくかったりすることがあるため、端的な短い文章にしましょう。
その他の効果音やBGMの追加は、動画にメリハリを持たせるために行われます。演出に合った効果の追加を行いましょう。
公開
公開は、YouTubeやSNSなどの動画プラットフォームで行います。公開の際は、タイトルや説明文に適切なキーワードを加えるSEO対策をしましょう。
公開後は、放置するのではなく、きちんと再生できるか確認を行うことも大切です。
動画制作に必要なスキル

動画制作に必要なスキルは、以下のとおりです。
- 企画構成スキル
- 撮影スキル
- 編集スキル
それぞれ詳しくみていきましょう。
企画構成スキル
個人やSNS向けの簡単なコンセプトやストーリーの制作なら、初心者レベルで構いません。
しかし、企業のプロモーションやCM、映画の制作の場合はプロ並みのスキルが求められます。
企画構成ではアイデア出しやストーリー制作のセンスが必要で、さらに撮影の段取りも行わなければいけません。複雑な動画制作なら、中級以上のスキルが求められるでしょう。
撮影スキル
スマートフォンや簡単なカメラでの撮影なら、初心者レベルで行えます。
しかし、カメラの露出やホワイトバランスなどの機能の利用や動きのある撮影、複雑な撮影を行う際は初心者レベルでは難しいでしょう。
さらに、大人数での大規模な撮影になると、撮影スキルに加えてチーム連携を必要とするプロレベルでのスキルが要求されます。
編集スキル
簡単な編集ソフトでのカット編集やBGM挿入、テロップ追加を行う場合は、初心者レベルで行えます。
しかし、複雑な編集ソフトを用いたい場合は、動画編集のスキルが求められるでしょう。動画編集ソフトを利用する技術のほか、構成力や効果追加のセンスなども問われます。
質の高い動画制作ならプロへの依頼がおすすめ

この記事では、映像と動画の違いを紹介しました。
記事をご覧の方のなかには、内製と外注のどちらがよいか決めきれない方や映像や動画の制作を失敗したくないと考えている方もいるでしょう。
プロへの依頼により、質の高い動画が短期間で完成するだけではなく、ブランドイメージや成果にも直結しやすいです。
映像や動画を制作したい方は、Funusualへご相談ください。
Funusualでは、さまざまなBtoB企業の会社紹介映像や製品紹介映像、ブランディング動画や採用動画などを手がけています。
制作には、クオリティを担保する以下のプロセスが含まれます。
- 詳細な企画コンテの作成から納品までのスケジュール管理
- ロケハン
- キャスティング
- 降板表作成
- 撮影と編集
- 修正対応
実写とアニメーション両方での制作に対応でき、企業の特色に合わせた適切な表現が提案可能です。品質を重視する企業に対して、信頼性の高いサービスを提供できます。
質の高い動画制作をお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。













