リモートワークや拠点の分散が進むなか、社内の情報共有は複雑さを増しています。文章や口頭説明だけでは、ニュアンスや重要度が十分に伝わらず、社員ごとに理解の差が生じやすいのが現状です。
こうした課題を解決する手段として、動画を活用した情報共有が注目されています。本記事では社内動画のメリット・配信方法・システムの選び方・費用感・活用事例まで詳しく解説します。
最後にはプロの制作会社に依頼する価値も伝えているので、読み終える頃には、社内動画に取り組む具体的なヒントが得られると感じるでしょう。
動画配信で社内の情報を共有するメリット
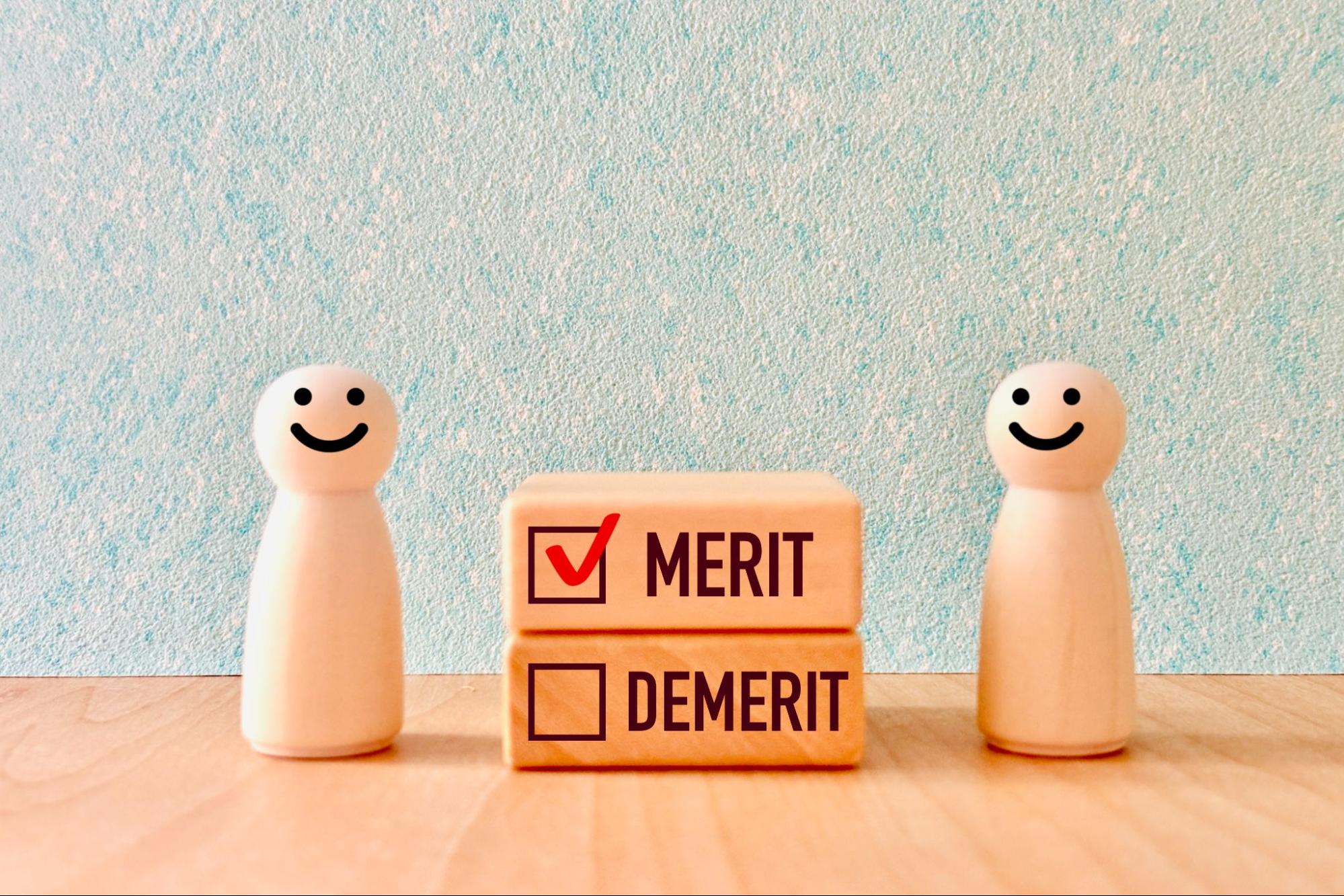
働き方の多様化に伴い、社員が同じ場所や時間に集まることが難しくなりました。
こうした状況で注目されるのが、動画を活用した情報共有です。映像は視覚と聴覚に訴えかけるため、より多くの情報を直感的に伝えられます。
ここでは、動画配信が持つ具体的なメリットを3つの視点からみていきます。
情報が伝わりやすい
テキストや口頭説明では表現しにくいニュアンスや手順も、動画なら一目で理解できます。
例えば、業務フローや新製品の仕組みを文章で説明するより、映像と音声を併用する方が社員の理解は格段に早くなります。
社内報に動画を取り入れることで、情報が視覚的に伝わるため誤解が減り、より正確に理解できる環境を整えることが可能です。
映像が視覚と聴覚の両方に働きかけることで、内容の把握や記憶の定着を助ける効果があるためです。
社員が時間と場所を選ばずに視聴できる

動画は必要なときに視聴できるため、社員が自分の都合に合わせて情報を得ることが可能です。拠点が複数ある企業やリモートワーク主体の組織でも、情報格差が生じにくくなります。
特に研修やマニュアル動画は、忙しいときでも後から見返せるため、社員が自分のペースで理解を深めることが可能です。
繰り返し視聴することで内容の定着度が高まり、教育コストの削減にも役立ちます。
時間や場所に縛られずに学習できることで、業務の効率化や情報共有の精度向上にもつながります。
一度動画を制作すれば繰り返し使える
文書資料や対面説明と違い、動画は一度制作すれば繰り返し活用可能です。
新人研修や業務マニュアルなど、毎回同じ説明が必要な情報を動画化することで、担当者の負担を減らし効率化が図れます。
加えて、視聴者の理解度に応じて何度でも再生できるため、習熟度の向上にもつながります。
法人向けプラットフォームを活用すれば、動画を社内資産として蓄積し、必要に応じて繰り返しの再利用が可能です。
こうした運用により、同じ内容を何度も制作する手間を省き、効率的な情報共有が可能になります。
動画配信の種類

社内動画の活用といっても、配信の方法にはいくつかの種類があります。大きく分けると、リアルタイムで配信するライブ型と、録画した動画を後から視聴できるオンデマンド型です。
どちらも社内コミュニケーションに活用できますが、向き不向きがあるため、用途に応じた選択が重要です。それぞれの特徴とメリットを見ていきましょう。
ライブ配信
ライブ配信は、リアルタイムで映像や音声を共有する仕組みです。経営方針説明会や全社ミーティングなど、その瞬間の空気感や臨場感を共有したい場合にぴったりです。
参加者はチャットや質疑応答機能を通じて双方向のコミュニケーションができるため、距離が離れた拠点でも一体感が出やすくなります。
ただし、インターネット回線や配信環境のトラブルがあった場合、即座に影響が出るリスクもあります。
そのため、ライブ配信は配信サポートやバックアップ体制が重要です。また、録画データをアーカイブ化すれば、リアルタイムで参加できなかった社員も後から内容を確認できます。
オンデマンド配信

オンデマンド配信は、事前に録画した動画を社員が好きなタイミングで視聴できる方式です。
研修動画やマニュアル、業務手順の説明など、繰り返し視聴して理解を深めたい情報に適しています。
また、視聴履歴や進捗を管理できるプラットフォームを活用すれば、学習状況の把握も容易です。
ライブ配信に比べると配信環境に左右されにくく、制作した動画を資産として長期的に活用可能です。
Funusualではライブ配信の企画や技術サポートから、オンデマンド動画の制作、運用まで一貫して対応しています。
社内動画の活用を検討しているものの、どの方法が自社に適しているのか迷っている場合でも、プロの視点から適切なプランを提案いたします。
自社の動画をもっと活用したい、印象に残る仕上がりにアップデートしたいと感じたら、まずはお気軽にご相談ください。
動画配信で社内の情報を共有する方法

動画を使って社内の情報を共有する際、どの配信手段を選ぶかは重要なポイントです。
コスト・セキュリティ・視聴環境・運用負荷などを考慮し、自社の状況に適切な方法を選ぶことが求められます。
ここでは代表的な配信方法の特徴と、それぞれに向いているケースを解説します。
YouTubeなどの無料プラットフォームを利用する
手軽に始められる方法が、YouTubeやVimeoなどの無料プラットフォームの活用です。限定公開機能を使えば、リンクを知っている方のみ視聴できるように設定できます。
導入コストがかからず、すぐに動画配信をスタートできるのが大きな魅力です。
ただし、社内限定を前提とした環境ではありますが、外部への漏えいリスクがゼロとはいえません。
また、視聴履歴の管理やアクセス制御など、法人向けに必要な機能は不足しています。
一般的な周知や啓発動画など、社外に公開しても問題ないコンテンツなら有効ですが、社内限定の機密情報を扱う場合は不向きです。
その際は、セキュリティ機能が充実した法人向け配信システムの活用を推奨します。
企業向けの動画配信システムを利用する

よりセキュアに配信したい場合は、法人向けの動画配信サービスがおすすめです。
ユーザーごとのアクセス権管理やログ取得、暗号化などの機能が標準搭載されており、機密性の高い情報でもセキュリティに配慮した共有システムとして活用できます。
また視聴履歴の把握や進捗確認、アンケート機能など、社内研修や人材育成に役立つ機能も豊富です。
サポート体制が整っているため、社内のITリソースが限られていても導入しやすく、配信環境の管理負荷を軽減しながらセキュリティに配慮した運用が可能です。
こうした仕組みにより、専門知識がなくても安定した動画配信が実現できます。
自社で配信環境を構築する
自社のオンプレミス環境やクラウド上に独自の配信システムを構築する方法もあります。すべて自社管理のため、セキュリティやカスタマイズの自由度が高いのが特徴です。
ただし、初期構築コストやメンテナンスの負担が大きく、専門知識を持つIT担当者が必要です。
大企業や情報セキュリティポリシーが厳しい組織では有効な選択肢ですが、運用負荷が高いため慎重に検討する必要があります。
導入前には運用体制や将来的な拡張性も含めた総合的な判断が求められます。
社内情報を動画で共有できる企業向け配信システムのメリット

YouTubeのような無料プラットフォームは手軽に始められますが、社内限定の機密性が高い情報共有には不向きです。そこで、企業では専用の動画配信システムを導入するケースが増えています。
ここでは、企業向け配信システムを導入する3つの大きなメリットを解説します。
セキュリティ対策ができる
法人向け動画配信システムはアクセス権管理や視聴ログの記録、DRM(デジタル著作権管理)、暗号化通信などの高度なセキュリティ機能を標準で備えています。
無料プラットフォームはリンクが漏れると視聴される恐れがありますが、専用システムなら認証が必要なため流出リスクを抑えられます。
特に個人情報保護法や社内情報管理規程の制限が厳しい業種では、セキュリティ面の強化が必須です。
情報漏洩リスクを考慮する場合、セキュリティ機能が充実した法人向け配信システムを選ぶ方が、リスクを抑えて運用することができます。
さらに、視聴履歴の管理やアクセス制御を徹底できることも、法人向けシステムの大きな利点です。
閉じた環境での使用に適している

法人向け動画配信システムは、社内ネットワーク内だけで配信することができます。
さらに社外アクセスの遮断やIPアドレス制限、SSO(シングルサインオン)など、閉じた環境を構築するための機能も充実しています。
例えば金融機関や医療機関など機密性の高い情報を扱う業種では、社外アクセスを一切許可せず、社内LAN環境のみで視聴できる仕組みが必要です。
こうした要件にも柔軟に対応できるのが、企業向けシステムの大きな強みでしょう。
動画は社員限定でしか視聴できない環境を作ることができるため、セキュリティ面に配慮した活用が可能です。
サポートが受けられる
法人向け配信システムは、導入から運用、トラブル対応まで専門スタッフのサポートを受けられる点もメリットです。
無料プラットフォームの場合、トラブルが発生しても基本的に自己解決が前提ですが、法人サービスでは配信サポートや運用代行オプションがあります。
そのため、社内リソースが少ない企業でも安定した運用が可能です。
さらに視聴データの分析レポートや運用改善の提案など、継続的なサポートを提供するサービスもあるため、動画活用の効果をより高めやすくなります。
社内での動画配信の活用事例

実際に動画配信を導入している企業は、どのように社内活用しているのでしょうか。
社内動画のメリットを理解しても、具体的な使い方がイメージできないと、導入の判断が難しい場合もあります。
ここでは、多くの企業が動画配信を活用している4つの代表的なシーンを紹介します。これらの事例を参考に、自社で取り入れやすい分野を検討してみましょう。
代表者から社員へのメッセージ
経営方針の説明や年度初めのキックオフなど、トップメッセージを動画で配信する企業は増えています。
文章だけでは伝わりにくい経営者の熱量や表情を、動画ならまるでその場にいるかのように届けられます。
特に拠点が分散している企業では、リアルタイムで全社員が集まることが難しいため、ライブ配信や録画配信で社長メッセージを共有するケースが一般的です。
動画を活用することで、メッセージの意図がより伝わりやすくなり、社員の理解度やモチベーション向上にもつながります。
さらに動画をアーカイブ化しておけば、後から何度でも視聴できるため、新入社員や異動者の情報共有にも役立ちます。
社内研修
新入社員研修やコンプライアンス研修、ITセキュリティ教育など、社内研修動画は代表的な活用シーンです。
動画なら、何度でも繰り返し視聴できるため、社員の理解度に応じて学習できます。
また、研修担当者が毎回同じ内容を説明する必要がなく、時間とコストの削減が可能です。
さらに法人向け配信システムを使えば、視聴履歴や理解度テストの結果を自動で記録できるため、受講管理が効率化されます。
こうした仕組みにより、研修内容の標準化や品質の向上を期待できます。
マニュアルの共有

業務手順やシステム操作方法など、文章や画像だけではわかりにくいマニュアルも、動画化すると理解度が飛躍的に高まります。
製造ラインの点検手順や新システムの操作方法を動画で解説すると、現場でスマートフォンから確認でき、作業ミスの防止に役立ちます。
また、新人教育や業務引き継ぎの際にも、動画マニュアルがあるとスムーズです。マニュアルを動画化すれば、問い合わせ件数の削減や社員の教育期間の短縮につながります。
さらに、視覚的な情報は記憶に残りやすいため、社員の習熟度向上にも効果的です。
社内イベントのライブ配信
全社イベントや表彰式、社員総会など、社内イベントをライブ配信する企業も増えています。リアルタイムでイベントの雰囲気を共有すれば、拠点間の一体感を高める効果があります。
また、イベントを録画してオンデマンド配信すれば、当日参加できなかった社員も後から視聴可能です。
ライブ配信とオンデマンドを併用すれば、視聴率の向上やイベントの価値向上に役立ちます。
さらに、動画として残すことで社内アーカイブとしても活用でき、次回のイベント企画や改善にも効果的です。
社内で配信する動画の制作は自社と外注どちらにするべき?

社内動画の制作を検討する際に、多くの担当者が迷うのが自社で制作するか、外注するかという選択です。
どちらが適しているかは、目的や求めるクオリティ、リソースの有無によって変わります。
自社制作のメリットは、コストを抑えられ、内容の変更や更新が柔軟にできる点です。
簡易的なマニュアル動画や、社内でのみ共有する補足的なコンテンツなら、スマートフォンと無料編集ソフトでも対応できます。
ただし、高品質な映像を継続的に作るには、専門的なスキルと時間が必要です。一方、外注は撮影から編集までプロの技術で高品質な動画を制作できるのが強みです。
社長メッセージや社外向けPR映像など、企業ブランドに直結する動画は外注の方が適しています。
またライブ配信をはじめトラブルリスクがあるシーンでも、外注なら運用サポートを受けられるため、安定した配信が可能です。ただし、一定の制作費がかかる点は考慮が必要です。
簡易的な社内向けコンテンツは自社制作、高品質や大規模配信が必要なコンテンツは外注と使い分けるのが効率的でしょう。
Funusualでは、社内で補えない部分をプロの技術でサポートし、目的に合わせた適切な制作方法をご提案します。
自社制作と外注のどちらが適しているか判断に迷う場合でも、ヒアリングを通じてぴったりなプランの設計が可能です。
自社の動画をもっと効果的に活用したい、印象に残る仕上がりにしたいと感じたら、まずは一度ご相談ください。
社内での動画共有にかかる費用
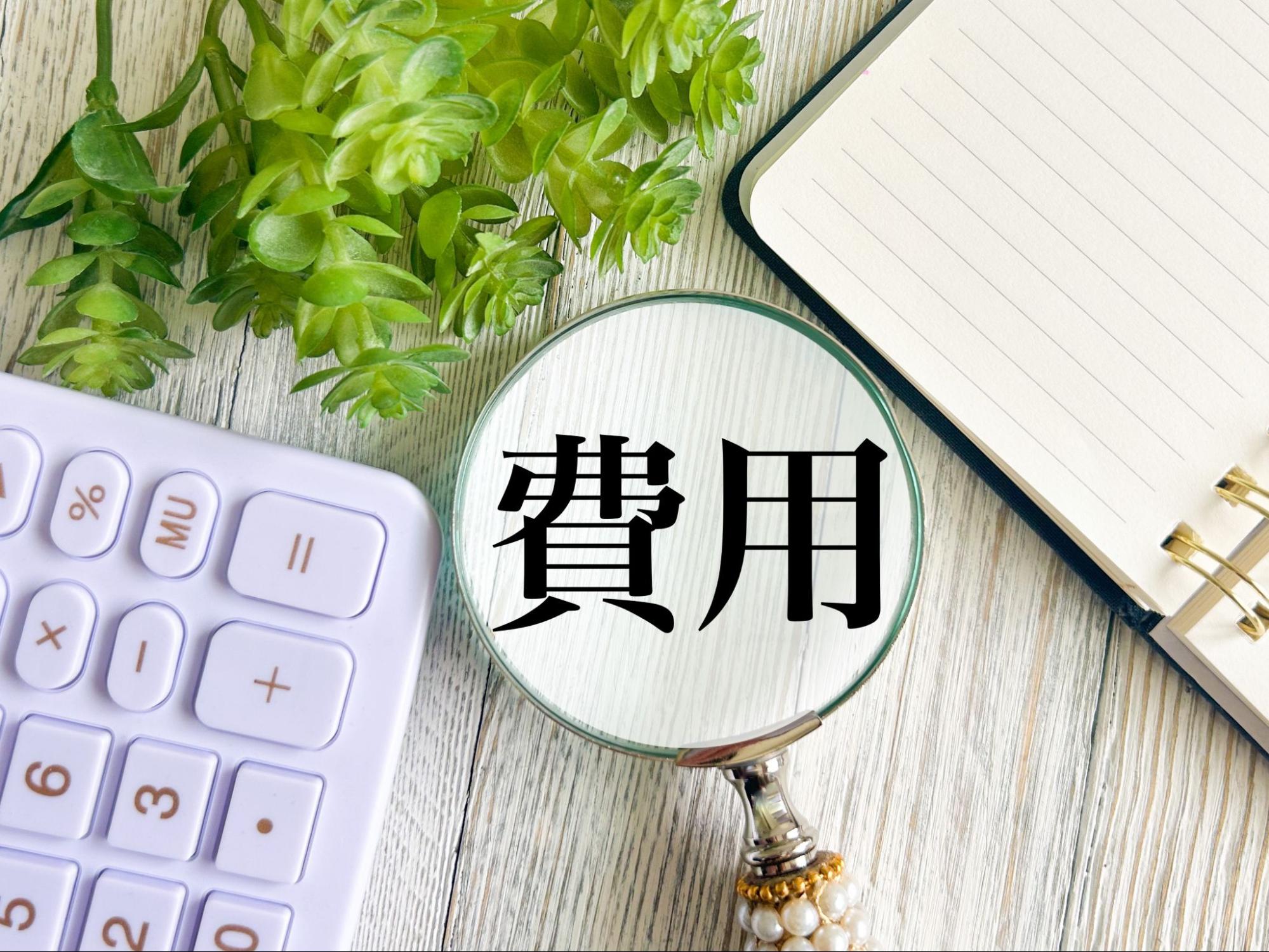
社内動画を活用する際の費用は、動画の制作費用と配信や運用にかかる費用の2つに大別されます。
どの程度の品質を求めるか、どの配信環境を選ぶかによって、全体のコストは大きく変わります。そのため、導入前に必要な予算を明確に把握することが重要です。
ここでは、それぞれの費用の目安を簡単に紹介します。
動画制作にかかる費用
動画制作の費用は、内容や目的、求める品質によって幅があります。
例えば簡単な業務マニュアルや研修の補助コンテンツであれば、社内で撮影し簡易的な編集をするだけで済むため、数万円程度で制作可能です。
一方、社長メッセージや企業ブランドを意識した動画は、より高い品質が求められます。
撮影機材や複数カメラの使用、ナレーションやテロップ、さらにはCG演出なども必要になるため数十万円以上かかるケースが一般的です。
さらに、長期的に運用する動画であれば、後から内容を更新しやすい構成にしておく必要があります。再編集が可能なデータ管理も考慮すると、予算に余裕を持った検討が求められます。
配信にかかる費用

配信のコストも選ぶプラットフォームによって変わります。
YouTubeやVimeoなど、無料の動画プラットフォームを利用すれば、配信そのものに追加費用はほとんどかかりません。
しかし社内限定での共有や視聴履歴の管理、アクセス制御などが必要な場合は、法人向けの動画配信システムの導入が推奨されます。
法人向けシステムはセキュリティ機能や視聴ログの管理が充実しており、リスクを抑えた運用が可能ですが、月額で数万円から数十万円程度の利用料が必要です。
また自社サーバーを構築する方法の場合は、初期投資や運用、メンテナンスにかかる費用が発生します。
情報の機密性や運用体制に応じて、どの方法が適切かを慎重に検討する必要があるでしょう。
社内で共有する動画の制作を考えているなら

社内動画の必要性を感じながらも、どこから始めればよいのか迷う担当者は少なくありません。
動画制作には企画や撮影、編集、そして配信など複数の工程が必要です。さらに、目的に合わせた構成や演出を考えることも求められます。
特に初めて動画制作を導入する場合や、限られたリソースで高品質な動画が必要な場合は、プロの制作会社に相談するのがおすすめです。
制作会社であれば、動画の目的整理から適切なフォーマットの提案・撮影・編集・納品後の配信サポートまで一貫して対応が可能です。
Funusualでは、企画段階からヒアリングを行い、企業ごとの目的やターゲットに合わせた構成や表現を提案しています。
さらに、配信環境や利用シーンにぴったりな動画フォーマットの調整や、運用面でのアドバイスも可能です。
まだどのような動画が必要か明確になっていない場合や、制作費用の目安を知りたいときでも気軽に相談できます。
失敗せずスムーズに社内動画を導入するためには、まずプロの視点を取り入れることが重要です。
どのような動画が自社にあっているか迷っている方は、ぜひご相談ください。













