動画広告を導入したいと思っても、制作にいくらかかるのかわからず不安を感じる広報担当者は少なくありません。
さらに配信や運用にどのような費用が発生するのか、全体像が見えないことも悩みの一因となっています。
実際、動画制作費と広告掲載費の区別が曖昧なまま予算を組むと、途中で計画が頓挫するリスクもあるのです。
そこで本記事では、動画広告の種類ごとの制作費用相場・コストに影響する要素・費用を抑えるポイントを整理します。
さらに媒体別の掲載料金や課金の仕組みについても、わかりやすく解説していきます。
最後まで読むことで、動画広告に必要なお金の全体像を把握でき、不安なく次の一歩を踏み出せるはずです。
動画広告とは

動画広告とは、動画コンテンツを活用して商品やサービス、企業の魅力を伝える広告手法のことを指します。
近年はインターネット環境の整備やスマートフォンの普及により、動画を使った情報発信が急速に拡大しました。
従来のテレビCMのように一方的に放映するだけでなく、WebサイトやSNS、動画配信プラットフォームなどでユーザーの行動や興味関心に応じて配信できるのが特徴です。
YouTubeやInstagramなど各媒体に合わせた配信が可能で、ターゲット層にピンポイントでリーチできます。
動画広告のメリットは、視覚と聴覚の両方に訴求できる高い表現力にあります。静止画やテキスト広告では伝わりにくいストーリー性や臨場感を演出できるため、ブランドイメージを強化するブランディング施策や、新製品の魅力を短時間で伝える販促施策に有効です。
また、クリック数や視聴完了率などのデータを取得できるため、配信後に効果を可視化しやすい点も企業にとって大きな利点といえます。
さらにBtoBの領域では、展示会や営業活動に代わる手段として注目が集まっています。
複雑な製品機能やサービスの価値を短時間で理解してもらうのに動画は効果的であり、Webセミナーや会社紹介映像と組み合わせることで、信頼感や専門性を訴求できるのです。
加えて、SNS広告として発信すれば、既存顧客だけでなく潜在顧客や採用候補者への認知拡大にもつながります。
つまり動画広告は単なる宣伝ではなく、認知・理解・信頼の獲得を同時に実現できる総合的なマーケティング手段です。全体像をつかむことで、どの場面で活用すべきかが見えてきます。
動画広告の種類別の制作費用相場

動画広告と一口にいっても、目的や用途によって種類が大きくわかれます。そして種類ごとに必要な制作工程や表現方法が異なるため、費用感にも差が出ます。
ここでは代表的な4種類の商品サービス動画・会社紹介動画・採用動画・インタビュー動画について、一般的な費用相場と特徴を整理しましょう。
自社の目的に合った動画を検討する際の参考にしてください。
商品サービス動画
もっとも需要が高いのが、自社の商品やサービスを紹介する動画です。
製品の特徴や利用シーンをわかりやすく伝えることを目的とし、展示会や営業活動・Webサイト・SNSなど幅広い場面で活用されます。
費用相場は30秒から1分程度の短尺であれば700,000〜1,500,000円程度が一般的です。CGやアニメーションを多用したり、複雑な機能を視覚的に説明したりする場合は2,000,000円を超えるケースも珍しくありません。
逆に、簡易的なモーショングラフィックスを中心に構成すれば、相場より安く制作できる場合もあります。動画の長さや表現手法の選び方で、コストは大きく変動するのが特徴です。
会社紹介動画
会社の理念や事業内容・強みを伝える会社紹介動画は、採用活動や営業資料・展示会での上映など、汎用性の高いコンテンツです。
費用相場は1,000,000〜2,000,000円程度が目安で、取材撮影やナレーション、社員インタビューを組み合わせる場合はさらにコストがかかります。
自社のブランディングを目的とするため、映像のクオリティやデザイン性を重視する傾向が強くあるようです。
また、実写とアニメーションを組み合わせて、よりわかりやすく構成するケースも多く見られます。
制作後は長期的に利用できるため、投資対効果を意識した制作がポイントになるのです。
採用動画
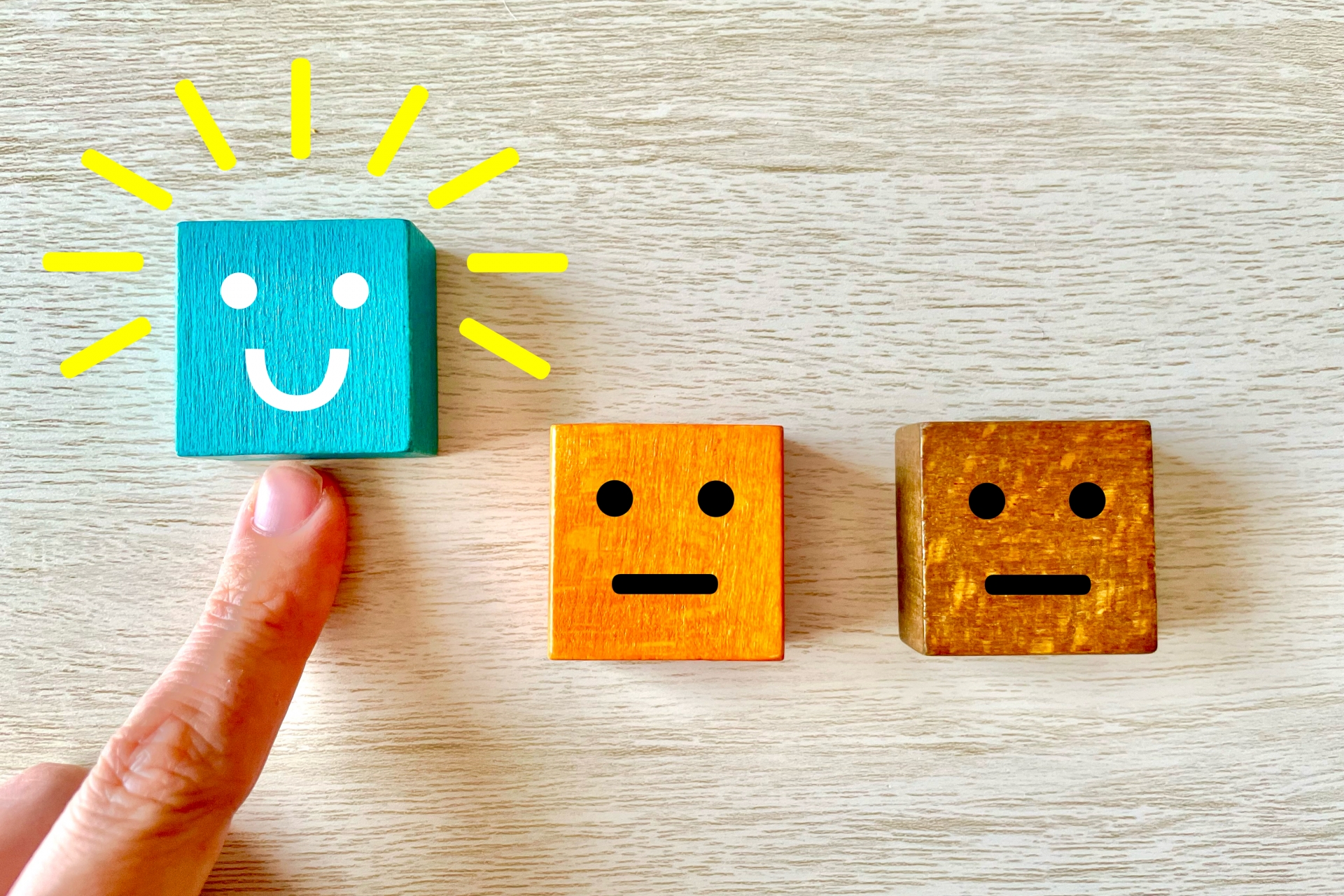
近年注目されているのが、学生や求職者に向けた採用動画です。仕事内容や職場環境、先輩社員の声を紹介することで、入社後のイメージを明確に伝えられます。
採用動画の費用相場は500,000〜2,000,000円程度です。シナリオを丁寧に作り込み、複数のロケーションで撮影する場合は2,000,000円以上に達することもあります。
一方で、短い尺でSNSにぴったりなライトな採用動画であれば、低コストで制作できるのです。
採用市場では動画の有無が候補者の志望度に直結することも多いため、費用だけでなく採用効果の高さを意識した投資が重要です。
インタビュー動画
経営者・社員・顧客へのヒアリングを映像化するインタビュー動画は、シンプルな構成で制作できるため、費用相場は100,000〜300,000円程度とほかの種類に比べて抑えられる傾向があります。
基本的には撮影と編集が中心で、複雑な演出が必要ない分、コストが軽減されやすいのです。
ただし、音声収録の環境や映像の仕上がり品質には注意が必要で、短めの尺でもプロの撮影・編集を依頼することで信頼感のある仕上がりになる点が大きなメリットです。
インタビュー動画は営業資料の補強やオウンドメディアでの掲載など、多様な活用方法があるため、費用対効果の高い選択肢といえるでしょう。
このように、動画広告の制作費用は種類ごとに大きく異なります。商品サービス動画は内容や尺によって1,000,000円を超えることも多く、会社紹介動画はブランディング重視で2,000,000円規模になるケースもある一方、インタビュー動画は低コストで導入可能です。
採用動画はその中間に位置し、SNS展開も見据えた企画によって費用感が変動します。重要なのは、目的と活用シーンに合わせて適切な種類を選ぶことです。
費用相場を把握しておけば、予算計画が立てやすくなり、自社にとってぴったりな投資を判断できるようになります。
動画広告の制作費用に影響する要素

動画広告の費用は一律ではなく、複数の要素によって大きく変動します。
同じ1本の動画でも、尺の長さや種類・編集の複雑さ・使用するスタジオの規模などによって見積もりが大きく異なることは珍しくありません。
ここでは、特に費用に直結しやすい4つの要素について詳しく解説します。
動画の長さ
わかりやすい要素が動画の長さです。動画が長ければ長いほど、企画や撮影、編集の工数が増えるため費用も高くなります。
例えば、15秒〜30秒程度の短尺動画は、シンプルな構成であれば10,000〜500,000円前後から制作可能です。
一方で、5分を超える長尺動画になると、2,000,000円以上かかるケースも多くなります。
さらに、長尺になればナレーション・テロップの追加・複数カットの組み合わせが必要になるため、編集工程も膨らみます。
ただし、長ければ効果が高いとは限りません。むしろBtoBマーケティングにおいては、短尺で要点を押さえた動画の方が視聴者に届きやすいケースも多いです。
目的に応じて必要な長さを見極めることが、コストと効果を両立させる鍵となります。
動画の種類
次に影響するのが動画の種類です。前章で触れたように、商品サービス動画・会社紹介動画・採用動画・インタビュー動画など、目的に応じて種類が異なりそれぞれ必要な工数が違います。
例えば、実写を中心とした会社紹介動画は、取材や複数ロケーションでの撮影が必要となるため費用が高くなりがちです。
一方、アニメーションやモーショングラフィックスを活用した説明動画は、撮影費が不要な分コストを抑えられるのです。
しかし、緻密なデザインやモーションを組み込む場合は、逆に高額になることもあります。
つまり種類によって、費用が増える要素と削減できる要素の両方が存在します。どの種類が自社の目的達成に効果的かを先に見極めることが、余計な出費を防ぐ第一歩といえるでしょう。
編集レベル

制作費用を左右する大きな要因が編集レベルです。単純にカットをつなぎ合わせるだけの編集であれば、安価に仕上げられます。
しかし、3DCGの追加・動きのあるアニメーションやテロップを駆使した演出などを組み込むと、編集にかかる工数が一気に増えます。
その結果、費用が数十万円単位で上乗せされることも珍しくありません。
特にBtoB企業の動画では、専門性や信頼感を視覚的に表現するために、編集の仕上がりが大きな差を生みます。
編集の質を落としすぎるとチープな印象を与えかねないため、必要な部分にはしっかり投資し、不要な演出は省くというメリハリのある判断が重要です。
スタジオの規模
見落とされがちですが、撮影を行うスタジオの規模も費用に直結します。小規模なスタジオで簡易的に撮影する場合は、費用を抑えての利用が可能です。
一方で、大規模なスタジオを貸し切り複数の照明設備や背景セットを組むとなると、1日あたり高額な費用がかかるケースもあります。
また、ドローン撮影や特殊機材を導入する場合は、さらにコストが増える点に注意が必要です。
ただし、必ずしも大規模スタジオが必要というわけではありません。商品紹介や社員インタビューのようにシンプルな構成であれば、小規模スタジオや自社オフィスでの撮影でも十分なケースがあります。
目的に合った規模を選ぶことで、費用を抑えられるのです。
動画広告の制作費用は、動画の長さ・種類・編集レベル・スタジオ規模といった複数の要素が組み合わさって決まります。
これらを理解せずに制作を進めると、想定外のコストが発生するリスクがあります。
しかし逆にいえば予算に影響する要素を事前に把握し、優先順位をつけて取捨選択すれば、無駄な出費を防ぎながら効果的な動画広告を実現できるということです。
費用感を正しく理解することが、戦略的な動画マーケティングの第一歩となります。
動画広告の制作費を抑えるコツ

動画広告を検討する際、多くの広報担当者が気にするのがどうすれば予算内で高品質な動画を作れるかという点です。
実際、工夫次第で大幅にコストを抑えることが可能になります。
まず効果的なのは、自社で対応できる部分を社内で完結させることです。
例えば出演する社員の手配や撮影場所の調整、ナレーション原稿の一次案作成などは、外部に依頼せずに自社で進められる場合があります。
制作会社に丸投げするよりも工数を減らせるため、見積もりが抑えられる可能性が高いです。
次に、既存の素材を有効活用する方法があります。過去に撮影した写真や映像、社内で使用している図解資料を再編集すれば、新たに撮影する必要がなくなります。
特にBtoB企業では、展示会や社内イベントの記録映像を編集して商品サービス動画や会社紹介動画に転用するケースが有効です。
さらに、複数本をまとめて制作するのもコスト削減につながります。
例えば採用動画と会社紹介動画を同じタイミングで撮影すれば、スタジオ費用や人件費を分散できるため、1本あたりの費用を抑えられます。
配信媒体や目的ごとに短尺バリエーションを作成するのも、効率的な運用につながる工夫です。
このように事前準備や素材の活用・まとめての発注を意識することで、無駄な費用を省きつつ効果的な動画広告を実現できるのです。
とはいえ、費用を抑えつつ効果を出すには、専門的な視点からの企画や適切な編集レベルの見極めが欠かせません。
BtoBに特化した動画制作のノウハウを持つFunusualなら、予算に合わせたぴったりなプランを提案できます。まずはお気軽にご相談ください。
制作費以外の動画広告に必要な費用

動画広告を検討する際、多くの担当者が意識するのは制作費ですが、実際にはそれ以外にも大きなコストがかかります。
特に広告の掲載費用と広告運用の代行費用は、予算計画を立てるうえで欠かせない項目です。
制作費だけを基準に見積もると、全体のコストが想定より大きく膨らみ、結果的に効果的な運用ができなくなるリスクがあります。ここでは、それぞれの費用について詳しく解説します。
広告の掲載費用
動画広告を配信するためには、媒体ごとに掲載費用が発生します。これは一般的に広告枠を確保する費用であり、掲載先によって金額が大きく異なるのです。
YouTube・Facebook・InstagramといったSNSや動画配信プラットフォームは、オークション形式で広告枠を決定する仕組みを採用しており、入札単価やターゲティング条件によって費用が変動します。
具体的には、1再生あたり数円から数十円の範囲で課金されるケースが多く、月額換算すると数十万円から数百万円規模になる場合もあるでしょう。
BtoB企業の場合はターゲットを業種や役職に絞り込むことが多いため、表示単価が高めになる傾向があります。
広告掲載費用を正確に見積もるには、目的・ターゲット・配信量を事前に設定することが重要です。
広告の運用代行費用

もう一つ見落とされやすいのが、広告運用の代行費用です。広告は配信を開始すれば終わりではなく、効果測定やクリエイティブの改善、ターゲティング条件の調整を継続的に行う必要があります。
これを社内で行うには専門的な知識とリソースが求められるため、多くの企業は広告代理店や制作会社に運用を委託しているのです。
運用代行費用は、一般的に広告費の20%前後が相場といわれています。例えば、月間1,000,000円の広告費を投下する場合、200,000円程度の運用代行費用が追加で発生するイメージです。
代行を依頼することで、クリック率やコンバージョン率の改善を図れるため、結果的には投資対効果を高めることにつながります。
特にBtoB領域では、ニッチなターゲットに効率的にリーチするために、専門的な運用ノウハウが不可欠です。
動画広告の費用を正しく把握するには、制作費用だけでなく、掲載費用と運用代行費用を含めた総額で見積もる必要があることを理解しておくことが大切です。
制作に十分な予算を割いても、掲載や運用を見落とせば思うような成果は得られません。逆に、運用まで見据えて計画を立てれば、効果を出しつつ無駄な支出を防ぐことができます。
つまり動画広告の成功は、制作と配信、そして運用を一体として考えるところから始まります。
動画広告の媒体別の掲載料金相場

動画広告を配信する際には、どの媒体を選ぶかによって費用が大きく変わります。
媒体ごとに料金体系や課金方法が異なるため、目的やターゲットに応じてぴったりな選択をすることが重要です。
ここでは、代表的な4つの媒体であるInstagram・YouTube・TikTok・タクシー広告について特徴と相場を整理します。
Instagramはビジュアル重視のSNSとして、特に若年層から30代まで幅広い利用者を抱えています。
BtoBの世界でも、採用活動やブランド認知に活用する企業が増えているのが特徴です。
広告の料金はクリック課金(CPC)で1クリックあたり40~100円程度、またはインプレッション課金(CPM)で1,000回表示あたり500〜1,000円程度が目安になります。
ターゲティング精度が高く、業界や職種での絞り込みも可能なため、ニッチな層にリーチしたい場合に有効です。
特に動画ストーリーズ広告は、短時間で視聴者にインパクトを与える点で人気です。
YouTube
動画プラットフォームであるYouTubeは、幅広い年齢層にリーチできる強力な媒体です。
特にBtoB企業にとっては、製品紹介やサービス説明のような長尺の動画広告を届けやすいのがメリットです。
料金体系はインストリーム広告で1再生あたり2〜25円前後が相場とされ、視聴者が30秒以上視聴した場合や動画をクリックした場合に課金されます。
これにより、興味のないユーザーへの無駄な課金が発生しにくい仕組みになっています。
TikTok

短尺動画の代表格であるTikTokは、エンタメ色の強いプラットフォームというイメージが先行していますが、近年ではBtoB領域でも注目を集めています。
特に若手人材の採用やブランドの親しみやすさを訴求する際に有効です。広告料金はクリック課金で1クリックあたり30〜100円程度、インプレッション課金で1,000回表示あたり100〜1,000円程度が一般的です。
さらにハッシュタグチャレンジやブランドエフェクトなど、TikTok特有の広告形式を利用する場合は、数百万円単位の大規模投資になることもあります。
ターゲット層と施策の相性を見極めることが肝心です。
タクシー広告
近年注目を浴びているのが、ビジネスパーソンに直接アプローチできるタクシー広告です。
都心部を中心にタクシー車内のモニターで配信され、経営層や意思決定者にリーチできるのが特徴といえるでしょう。
料金相場はエリアや期間によって異なりますが、車内の動画広告で月額およそ1台25,000~50,000円程度が目安です。
大規模な配信になると10,000,000円規模に達することもありますが、BtoBの高単価商材にとっては投資対効果が見込める媒体です。
ターゲットが限られる分、効率的にブランドの信頼性を訴求できるでしょう。
媒体ごとに料金相場と特徴は大きく異なります。Instagramはビジュアル訴求・YouTubeは幅広いリーチと長尺対応・TikTokは若年層への浸透・タクシー広告は経営層への直接アプローチに適しています。
つまり、自社の目的やターゲットを明確にし、適切な媒体を選ぶことで予算を適切化できるのです。
どの媒体を選ぶべきか悩むときは、業界特化のノウハウを持つ制作パートナーに相談するのが効率的です。
FunusualならBtoB企業の課題に合わせた媒体選定から動画制作、配信までを一貫して支援できます。費用対効果を高めるプランニングを求める方は、ぜひ一度ご相談ください。
動画広告における課金の仕組み

動画広告を出稿する際に避けて通れないのが課金方式の理解です。料金がどのように発生するかを把握していないと、予算を立てても実際のコストが想定以上に膨らんでしまうリスクがあります。
特に多くの媒体で採用されているのは、CPV・CPM・CPCの3つです。それぞれの仕組みと特徴を理解しておくことが、効率的な広告運用の第一歩となります。
CPV
CPV(Cost Per View)は、動画が1回視聴されるごとに費用が発生する課金方式です。
YouTubeのインストリーム広告が代表例で、ユーザーが30秒以上視聴した場合や動画をクリックして行動を起こした場合に課金されます。
相場は1再生あたり4〜10円程度といわれ、興味を持ったユーザーに対してのみ費用が発生する点が特徴です。
無関心なユーザーがすぐにスキップした場合は課金されないため、費用対効果を測定しやすく、動画広告を初めて試す企業にも向いています。
ただし、短尺動画や冒頭の数秒で印象を与えられないと視聴されにくいため、強い導入部分の設計が成果に直結します。
CPM

CPM(Cost Per Mille)は、広告が1,000回表示されるごとに費用が発生する課金方式です。
SNSやディスプレイ広告でよく採用されており、認知度向上やブランドイメージの浸透に向いています。
相場は1,000回表示あたり500〜3,000円程度が一般的です。課金は表示された回数に基づくため、視聴完了率に関わらず料金が発生します。
そのため、必ずしも多くの方に最後まで視聴されるとは限りません。しかし、大規模に露出を確保できるので、新サービスの認知拡大や展示会前の告知といった目的に効果的です。
成果の測定指標としてはクリック数や再生完了率を組み合わせ、投資対効果を確認する必要があります。
CPC
CPC(Cost Per Click)は、広告がクリックされた回数に応じて費用が発生する課金方式です。
主にWeb広告やSNS広告で採用されており、直接的な行動喚起を目的とする場合に有効です。
相場は1クリックあたり30〜100円程度で、業種や競合状況によって変動します。クリックされなければ課金されないため、費用対効果をコントロールしやすいのがメリットです。
BtoB領域では、資料請求やセミナー申し込みといった具体的なコンバージョンにつなげる施策と相性がよいといえます。
CPVは視聴ベース・CPMは表示ベース・CPCはクリックベースで課金される方式です。それぞれ目的に応じた使い分けが重要で、認知拡大にはCPM・興味喚起にはCPV・具体的な行動につなげたい場合はCPCが適しています。
課金の仕組みを理解すれば、予算設計がより現実的になり、無駄なコストを抑えながら効果的な配信が可能になります。
動画広告は費用感だけでなく、どの課金方式を選ぶかによって成果が大きく変わる点を意識し、媒体や目的に応じてぴったりなプランニングを行うことが成功への近道です。
予算内の費用で質の高い動画広告を制作するなら

ここまで解説してきたように、動画広告には制作費・掲載費・運用費など複数のコストが発生し、動画の種類や課金方式や媒体によって費用感も大きく異なります。
情報を整理すれば全体像を把握できますが、いざ自社で制作しようとすると限られた予算で本当に成果を出せるのかと不安を感じる方も少なくありません。
実際、費用を抑える工夫は可能ですが、戦略性を欠いた動画は視聴されても成果につながらないリスクがあります。
BtoBの動画広告は消費者向けと比べて専門性や信頼性が求められるため、単なる映像表現ではなく、事業や製品の強みを正しく伝える企画力が欠かせません。
ここで重要になるのが、専門的な知見を持つ制作パートナーの存在です。
Funusualなら、BtoBに特化した動画制作の豊富な経験とノウハウをもとに、クライアント様の課題に寄り添ったぴったりなプランを提案できます。
IT・製造業・建設業・工業など各業界での成功事例を踏まえ、戦略的な絵コンテ作成から撮影・編集・運用までワンストップで対応可能です。
BtoB企業にとって、動画広告は今や競合との差別化を図るための重要な武器です。制作費用を投資として効果をより大きく引き出すためには、経験豊富なプロと組むことがより適切な方法といえます。
予算に不安があっても、戦略的な動画制作で費用対効果を高めることは可能です。
BtoB特化の専門ノウハウを持つFunusualにご相談いただければ、御社の課題に合わせたぴったりな動画広告を予算内で実現できます。まずはお気軽にお問い合わせください。













