チュートリアル動画を充実させ、顧客満足度の向上や業務効率化につながる事例は少なくありません。
製品の使い方や活用方法を動画で解説すれば、従来の取扱説明書よりも視聴者に伝わりやすく、より理解してもらいやすくなります。
一度制作したチュートリアル動画には多くの活用方法があり、マーケティングやカスタマーサポートの負担軽減も可能です。
本記事では、チュートリアル動画の活用方法や制作の流れ、効果的で効率的な制作時のポイントを解説します。
チュートリアル動画の導入を検討している方の、参考になれば幸いです。
チュートリアル動画とはどのようなものか
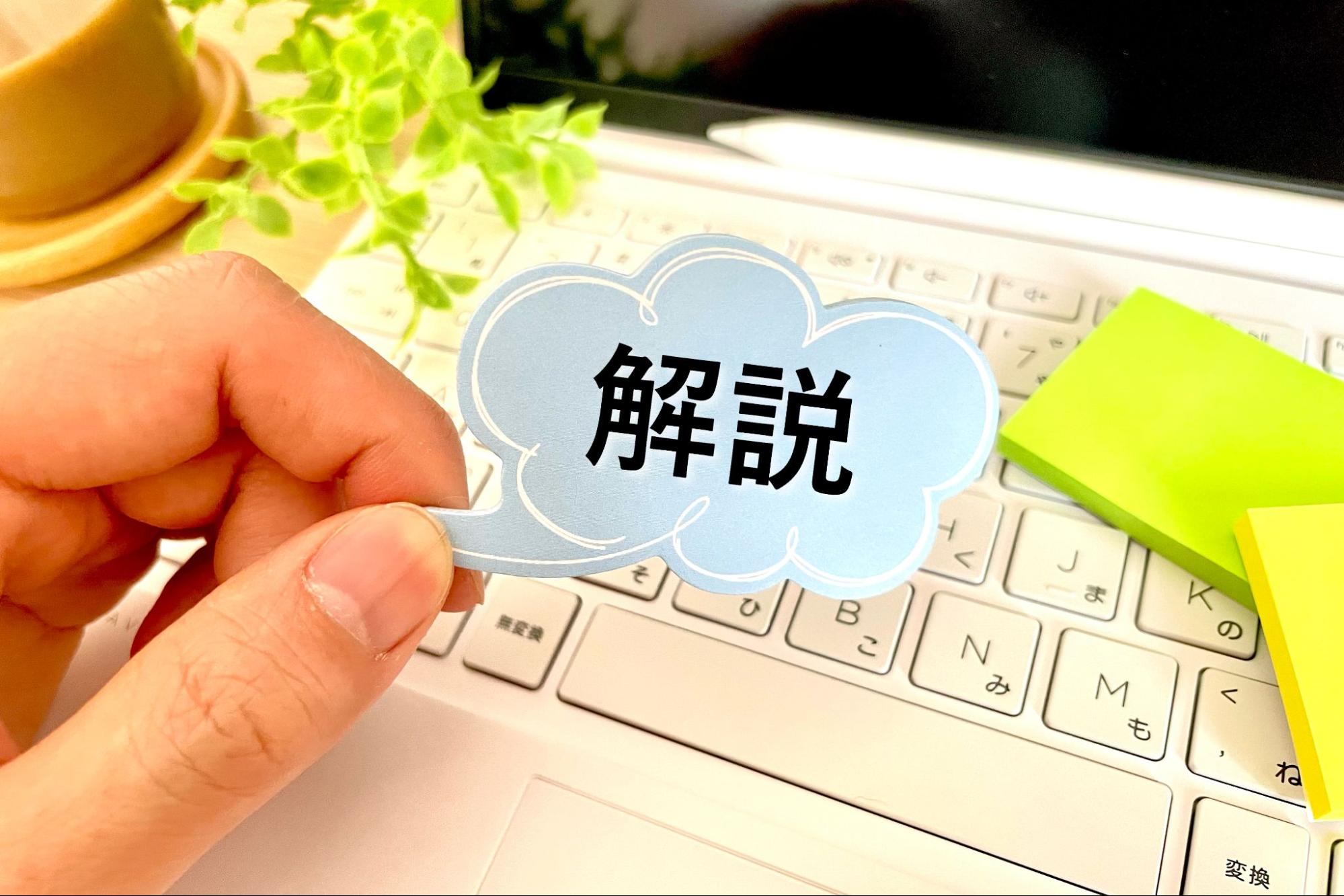
チュートリアル動画とは、製品やサービスの使い方を、ユーザーにわかりやすく解説することを目的とした動画です。
従来の文字ベースの取扱説明書を補完・代替する目的で制作され、一般公開されるものだけでなく、社内資料として使われるものまでさまざまです。
チュートリアルとは、特定の製品の使い方やスキルを指導することを意味します。
似た言葉としてマニュアルがありますが、マニュアルは製品の仕様なども含めて全般的に説明するものです。
これに対し、チュートリアルは初心者向けの実践ガイドとしての役割が主になります。
自社製品のチュートリアルを動画化すれば、製品の使い方をより理解しやすくなるでしょう。
顧客の利便性向上や、社内教育の省力化のために、チュートリアル動画を導入する企業は増加しています。
チュートリアル動画を社内で制作することも可能ですが、十分なクオリティを確保するのは容易ではありません。
撮影機材や編集ソフトの費用を考慮すると、動画制作会社に外注する方がコストを抑えられます。
Funusualは、BtoB企業向け動画制作に特化したプロフェッショナル集団として、視覚的にわかりやすく、ブランドイメージにマッチした動画の制作を得意としています。
無形サービスや専門性の高い製品など、「説明が難しい」「イメージしづらい」といった内容であっても、構成力・表現力・編集技術に優れたチームが、理想の動画をかたちにします。
「ユーザーにしっかり使い方を理解してもらいたい」「自社のトーンを保ちながら分かりやすいチュートリアル動画を作りたい」といったご要望にも柔軟に対応可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
チュートリアル動画の活用シーン

チュートリアル動画はさまざまな場面で活用でき、一度制作すれば繰り返し利用可能です。製品の利便性向上や業務の効率化に貢献します。
チュートリアル動画の主な活用方法を、次の2つのシーンから解説します。
- 製品マニュアル
- 社内研修
製品マニュアル
チュートリアル動画の一般的な活用シーンは、顧客に向けた製品マニュアルです。
自社の製品を購入した顧客に、製品の基本的な使い方や活用方法をわかりやすく解説することを目的として制作します。
文字や画像だけの取扱説明書に比べて、動画を用いて説明すれば、より理解しやすくなるでしょう。
また、動画は製品が動く様子を撮影できるため、実際の動作と照らし合わせて確認できます。
ソフトウェアやアプリケーションも、操作画面を録画することで、マウスの動きや画面遷移がわかりやすくなります。
社内研修

チュートリアル動画は、従業員向けの研修にも活用できます。新商品の操作方法や特徴を解説し、研修の効率化や標準化を図れます。
自社商品を顧客に販売する営業社員に、商品の使い方や強みを説明するチュートリアル動画を見てもらえば、営業の現場で大いに役立つでしょう。
チュートリアル動画が充実していれば、商品研修の時間も削減できます。
また、社内システムの使用方法などもチュートリアル動画にすることで、対応が必要な問い合わせの減少が見込めるのも大きなメリットです。
全員に同じ内容の動画を見てもらうことで、研修内容の属人化(担当者の能力に依存してしまうこと)を防げます。
チュートリアル動画の制作の流れ

チュートリアル動画の制作手順を解説します。必要な流れを把握し、効率的に進めましょう。
チュートリアル動画制作の流れは、主に以下の3つの手順となります。
- 商品やサービスの利用手順を整理する
- 伝えたいポイントを明確にする
- 撮影・編集を行う
それぞれの内容を解説します。
商品やサービスの利用手順を整理する
チュートリアルを制作するには、まず対象となる商品やサービスの利用手順を整理します。
商品の機能ごとに利用手順を整理して、どのような順番で説明すればわかりやすいかを検討しましょう。
商品の開発目的を振り返り、この商品はどのような課題を解決するためのものなのかを考えれば、説明の順番も整理しやすくなります。
まず課題を提示し、その解決方法として商品の使い方を説明するのが基本です。
説明すべき内容を整理して、動画の構成も同じように作成しましょう。
伝えたいポイントを明確にする
チュートリアル動画は、一つの動画につき一つのテーマで制作するのが基本です。
一つの動画にいくつものテーマを盛り込むと、視聴者にとっては重要なポイントがわからず、内容が伝わりにくくなってしまいます。
動画で伝えたい重要なポイントを明確にし、そのポイントを伝えるために順序よく説明することを意識しましょう。
伝えたいポイントは、動画のオープニング・本編・まとめの3つのセクションで、繰り返し強調しましょう。
撮影・編集を行う

商品の利用手順を整理し、伝えたいポイントを明確にして動画の構成が決まったら、実際に撮影と編集を行います。
形のある商品の場合は、実物を使っているシーンを撮影し、適切にナレーションやテロップで解説する必要があります。ソフトウェアやアプリなど、画面上で使用するものは、PCやスマートフォンの画面を録画して解説する方法がよいでしょう。
撮影した動画は、テンポよく編集し、必要に応じてテロップや画面効果を挿入します。撮影・編集には専門的なスキルが必要なため、社内に人材がいなければ外注を検討するとよいでしょう。
Funusualは、BtoB企業に特化した動画制作チームとして、製品の使い方やサービスの導入方法などをわかりやすく伝えるチュートリアル動画の制作を得意としています。
「無形サービスでイメージが難しい」「専門性が高く説明が複雑」といった内容も、視覚的に整理された構成とプロの編集技術で「伝わる動画」に仕上げるノウハウがあります。
また、ご予算に応じて柔軟に対応可能です。「予算内でどこまで実現できるのか知りたい」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
チュートリアル動画制作のコツ

チュートリアル動画をわかりやすく実用的にするには、いくつかのポイントがあります。
チュートリアル動画の内容がわかりにくいと、かえって視聴者を混乱させてしまい、クレームや問い合わせ対応の増加につながってしまいます。
視聴者がチュートリアル動画だけで理解できるようにするために、制作の際は以下のポイントを意識しましょう。
- 実際に操作しながら説明する
- トラブルの対処法を解説する
- テロップ・ナレーションを適切に入れる
それぞれの内容を解説します。
実際に操作しながら説明する
文字や画像に比べて、動画の強みは動きを表現できることです。実際に製品が動く様子や、画面上での動きを撮影し、動きに合わせて説明するようにしましょう。
細かい操作が必要な製品は、手元をアップで撮影すると視聴者に伝わりやすくなります。
正常に動いている様子を動画で確認できれば、視聴者はどのような動きが正しいのかをすぐに理解できるでしょう。
PC画面を録画する場合も、画面の遷移を飛ばさずに録画することが重要です。
画面のどのボタンをタップして、どの画面に移行するのかを視聴者が確認できるようにしましょう。
製品の仕様が変わって画面が変更された場合は、速やかにチュートリアル動画も撮り直す必要があります。
トラブルの対処法を解説する
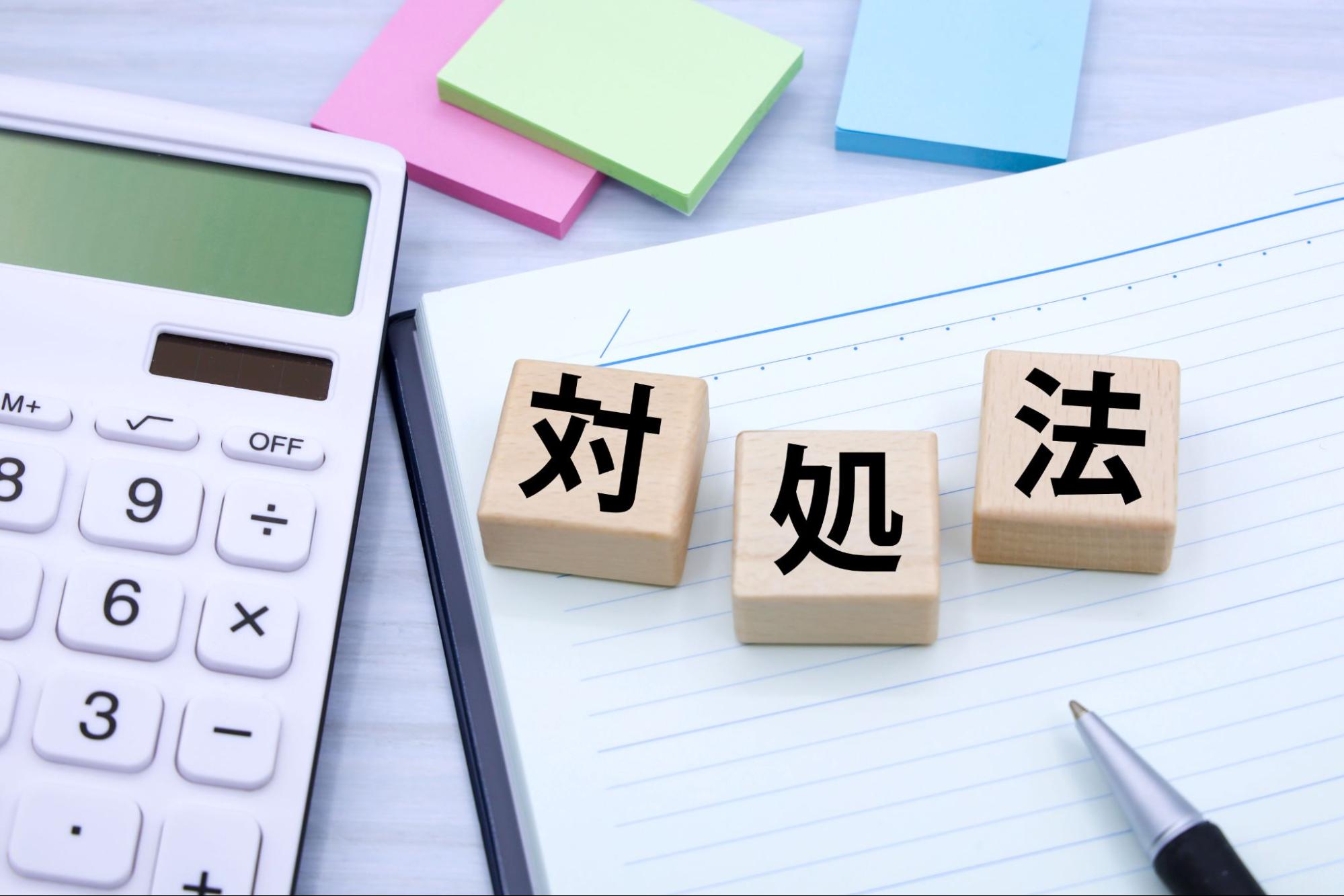
チュートリアル動画の内容として、重要なのがトラブルの対処法です。
想定されるトラブルの対処法をチュートリアル動画で説明しておけば、ユーザー自身でトラブルの解決ができ、製品の満足度向上にもつながります。
チュートリアル動画でトラブルを解決できれば、問い合わせ対応の負担が軽減され、業務効率も向上します。
テロップ・ナレーションを適切に入れる
チュートリアル動画では、動きによる説明を補完するテロップ・ナレーションの活用が不可欠です。
ナレーションだけでなく、ナレーションの字幕をつけることで、より内容を理解しやすくなります。
また、チュートリアル動画を見ている視聴者は、音を出せない環境にいることも少なくありません。
チュートリアル動画は、音声なしでも内容を理解できるように構成しましょう。
ナレーションを挿入する場合は、話すスピードや明瞭な発音を意識しましょう。聞き取りにくい声は視聴者に不快感を与え、動画の内容を理解しにくくなります。
参考になるチュートリアル動画の事例
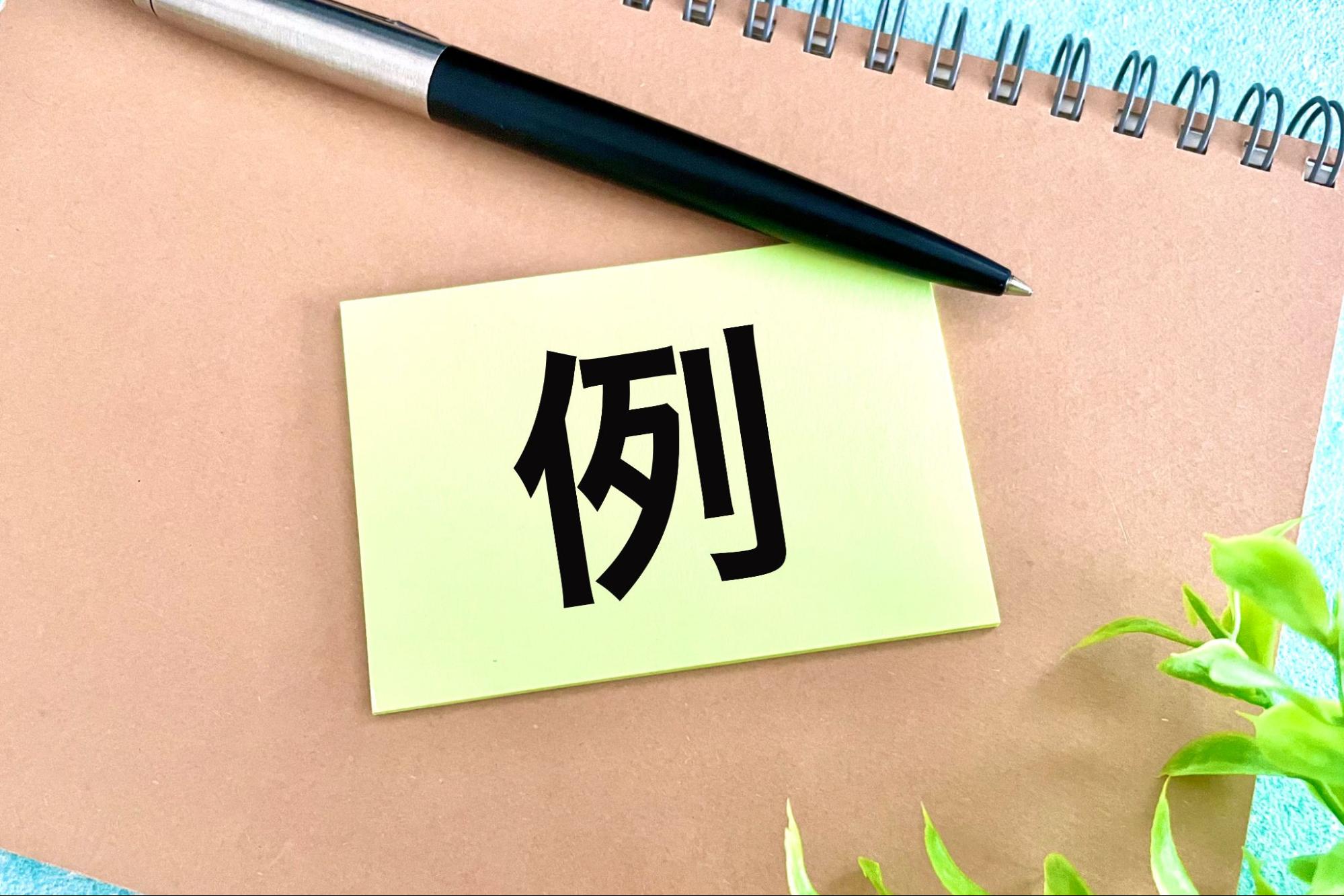
チュートリアル動画の参考事例として、実際に活用されている動画を紹介します。自社サービスに適した形式を考える参考にしてください。
Uber Eats
引用元:www.youtube.com/@UberEats
Uber Eats加盟店に向けたチュートリアル動画は、実写映像を使った事例として参考になります。
飲食店がデリバリーサービスを利用する際の詳しい手順を、実写映像で直感的に理解できます。
既存の加盟店はもちろん、加盟を検討している飲食店も、オペレーションを具体的にイメージしやすい動画です。
システムを利用するためのタブレット画面を録画するだけでなく、ロケーション撮影を行っているため、チュートリアル動画の制作にも多くの予算をかけていることがわかります。
Money Forward
引用元:www.youtube.com/@Moneyforward
Money Forwardの事例は、PCで操作するソフトウェアのチュートリアル動画として参考になります。
従業員向けに、システムの利用方法を手順ごとに解説しています。BGMのみで字幕による説明のため、音声なしでも視聴できます。
会計ソフトの操作画面を見せながら、効果的にテロップやアニメーションを挿入し、単調にならない工夫がされています。
一つひとつの作業を丁寧に説明しており、視聴者が動画を見ながら操作を進めやすい構成です。
アニメーションのみを用いた動画であるため、撮影やナレーションのコストはかかりません。
チュートリアル動画のメリット・デメリット

チュートリアル動画を導入するか検討する際は、メリット・デメリットを洗い出して整理しましょう。
動画の制作には手間や費用がかかるため、検討が不十分だと期待した程の効果を得られない場合もあります。
動画の特性を理解すると、メリットを最大限に活かせるでしょう。チュートリアル動画には、主に以下のようなメリット・デメリットがあります。
- 視聴者の理解を促しやすい
- 学習環境の自由度が高い
- ユーザーがつまずくポイントを分析できる
- カスタマーサポートの業務効率化につながる
- マーケティング効果が期待できる
- 閲覧環境が必須となる
- 情報更新するときの手間がかかる
それぞれの内容を解説します。
視聴者の理解を促しやすい
動画は、文字や画像のみの説明書に比べて、視聴者の理解を促しやすいのが特徴です。
アメリカ国立訓練研究所が提唱したラーニングピラミッドでは、学習方法別の学習定着率は、以下のようになっています。
- 講義:5%
- 読書:10%
- 動画視聴:20%
- デモンストレーション:30%
- グループ討論:50%
- 実践体験:75%
- 他人に教える:90%
視覚と聴覚に同時にアプローチする動画は学習定着率のうち20%となっており、チュートリアル動画はデモンストレーションの要素も含んでいます。
さらに、チュートリアル動画を見ながら自分でも操作してみれば実践体験となり、高い学習定着率を期待できるでしょう。
学習環境の自由度が高い

従業員向けのチュートリアル動画は、研修時間外に視聴するケースも少なくありません。
業務時間中に研修の時間を設けなくても、業務の合間でチュートリアル動画を見て作業をすすめられれば、業務効率化につながります。
顧客にとっても、自分の都合のよいタイミングでチュートリアル動画を視聴でき、問題解決にかかる時間が短くなります。
ユーザーがつまずくポイントを分析できる
動画は視聴者の動向が分析できるため、再生数やリピート数が多い場面を分析すれば、ユーザーがどの部分をわかりにくいと感じているのかも見て取れます。
このようなデータは、製品の品質向上に活用できるでしょう。
ユーザーや従業員からの問い合わせ内容をもとにチュートリアル動画を追加していけば、満足度向上にもつながります。
カスタマーサポートの業務効率化につながる

顧客がいつでも視聴できるチュートリアル動画を用意しておけば、カスタマーサポートへの問い合わせを大幅に減らせます。
カスタマーセンターにかかるコストを削減し、業務を効率化できるでしょう。
また、顧客にとっても、カスタマーサポートに問い合わせるのは面倒に感じる方が少なくありません。
わかりやすいチュートリアル動画が用意されている方が、顧客満足度の向上につながります。
マーケティング効果が期待できる
製品のチュートリアル動画があることは、潜在顧客の購入意欲を高める施策にもなります。
製品の購入を検討していても、使い方が難しそうで、使いこなせるか不安に感じている方は少なくありません。
わかりやすいチュートリアル動画があることがわかれば、潜在顧客の不安を解消できるでしょう。
また、チュートリアル動画によって実際の活用シーンがイメージしやすくなり、購買意欲を高められます。
閲覧環境が必須となる

チュートリアル動画のデメリットは、動画を視聴できる環境が必須となることです。
PCやスマートフォンなどのデバイスと、動画視聴に耐えうる十分な通信速度がそろっていなければ、快適な動画視聴はできません。
特に店頭で販売する商品の場合、顧客が動画を視聴できるかどうかわからない場合があります。
特に、動画視聴に慣れていない方には不便に感じられることもあります。
情報更新するときの手間がかかる
動画は一度公開すると内容変更ができないため、再編集して新しい動画に差し替える必要があります。
製品の仕様やルールが変わると、動画の差し替えが必要になります。
変更の可能性がある場合は、撮影素材を適切に管理し、再編集できるよう準備しましょう。動画制作会社に外注すれば、素材の管理や再編集もスムーズに任せられます。
チュートリアル動画制作は内製か外注か

チュートリアル動画の制作は、自社で内製する方法と、動画制作会社に外注する方法があります。
どちらにもメリット・デメリットがあるため、自社にとって適切な方法を慎重に検討しましょう。
チュートリアル動画を内製する場合と外注する場合の、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
内製はコスト面で有利だが品質面が未知数
自社内でチュートリアル動画を制作できれば、制作会社に外注する費用はかかりません。
現代ではスマートフォンのカメラとアプリを使用すれば、ほとんど費用をかけずに動画の制作も可能です。
コスト面で有利になるものの、品質面で満足いくクオリティを確保できるかは未知数です。
わかりにくいチュートリアル動画では、視聴者の不満を増大させ、信頼の低下につながる可能性もあります。
また、動画制作の経験が少ない場合、想像以上に手間がかかってほかの業務を圧迫するケースも少なくありません。
動画制作にどこまでのリソースを割けるかや、十分なクオリティを確保できるのかを慎重に検討しましょう。
外注はコストがかかるが品質は保証できる

動画制作会社に外注する場合、外注費用はかかるものの、品質はプロのクオリティが保証されるのがメリットです。
チュートリアルの目的は、わかりやすさと利便性の向上が第一であるため、コストを許容できるなら外注した方が目的達成につながるでしょう。
チュートリアル動画の制作費用は、動画の長さや制作方法によって変動します。
一般的に、撮影が必要ないアニメーション動画は制作費が安く、ロケーション撮影やナレーションの手配が加わると費用が高くなります。
予算に応じてどのような動画が制作できるのか、まずは見積もりを依頼しましょう。
チュートリアル動画を外注する際は、担当の動画制作会社が製品に精通している方が打ち合わせがスムーズにすすみます。
動画制作会社を選ぶ際は、企業向けのチュートリアル動画制作の実績が豊富な会社を選ぶとよいでしょう。
わかりやすいチュートリアル動画を制作したいならプロに任せよう

チュートリアル動画の概要や、制作のポイントを解説してきました。
複雑で多機能な製品である程、わかりやすいチュートリアル動画は不可欠です。
チュートリアル動画が充実していることで、潜在顧客の購買意欲を高め、従業員の業務効率化につながるでしょう。
一方で、動画制作には手間がかかり、経験が少ないとイメージどおりのクオリティを確保するのが難しくなります。
内製が難しい場合は、動画制作会社に依頼した方が、結果的にリソースの節約になるでしょう。
動画制作会社を選ぶ際には、エンタメ系動画ではなく、企業向け動画の制作を得意とする会社を選ぶことがポイントです。
BtoB企業向けに特化した動画制作チームFunusualでは、IT・製造業・工業・建設業など専門性の高い企業のチュートリアル動画も制作可能です。
チュートリアル動画は、使い方の理解や製品・サービスの活用促進に直結する重要なコンテンツです。
だからこそ、視聴者が迷わず理解できる「わかりやすさ」と「伝え方の設計」が欠かせません。
Funusualでは、業界に精通したプランナーと経験豊富なクリエイターが、複雑な内容も視覚的に整理し、見やすく効果的な動画に仕上げます。
「難しい内容を伝えたい」「社内マニュアルとしても使いたい」「ユーザー向けにわかりやすくしたい」など、さまざまなニーズに対応可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。Funusualが、視聴者に「伝わる」チュートリアル動画を制作いたします。













