ショート動画では、短時間で強い印象を与えられるため、近年のマーケティング分野で存在感を強めつつある状況です。
特にBtoB領域では、忙しいビジネスパーソンが効率的に情報を得たいというニーズが高まっており、ターゲットの悩みや課題を的確に伝える手段として活用されています。
本記事ではショート動画の戦略や特徴、成功のポイントを踏まえつつ、各プラットフォームに合わせた適切な活用法を解説しています。
ショート動画とは

ショート動画とは、おおむね15〜60秒ほどの尺です。
Shorts、Instagram ReelsやTikTokなどのプラットフォームで広く利用されており、近年では企業のマーケティング施策にも組み込まれるケースが増加しています。
従来の長尺動画と比べて、ショート動画は一瞬で視聴者の注意を引きつけることが求められます。
情報量よりも瞬発力が重視され、ファーストインプレッションの強さやテンポのよさが成果を左右するといっても過言ではありません。
特にモバイルユーザーにとっては、スキマ時間で気軽に視聴できる点が大きな利点であり、SNS上での拡散性の高さも特徴です。
ショート動画マーケティングが注目される理由

企業が情報発信に取り組むうえで、コンテンツの届け方は年々変化しています。
特にスマートフォン中心の社会においては、瞬時に伝わる内容でなければユーザーの関心を引き留めることが難しくなってきました。
こうした環境下で注目されるのが、ショート動画を活用したマーケティングです。
また視聴者の見たい意欲を自然に引き出す構成がしやすいため、強引な訴求ではなくスムーズな情報浸透が可能です。
制作負担も低く、複数の用途に展開しやすい点も多くの企業にとって魅力といえるでしょう。それぞれの要素がなぜ活用すべき武器となりえるのか解説していきます。
エンゲージメントが促進されやすいため
ショート動画はその短さと構造によって、視聴者の反応が自然に引き出されやすい特徴を持っています。
特に企業のマーケティングにおいて、コメントやいいね、シェアといったエンゲージメントが重要視される場面で有効です。
まず視聴完了率の高さがエンゲージメント向上に直結します。全編視聴されることで、伝えたいメッセージへの共感や印象付けも強まるでしょう。
またSNSプラットフォームはショート動画を優先的にフィード表示に組み込む設計で、自然な視聴を促します。
このように視聴者が参加しやすい場が設計されていることで、企業アカウントのエンゲージメント指標も高まるのです。
ユーザー行動が変化しているため
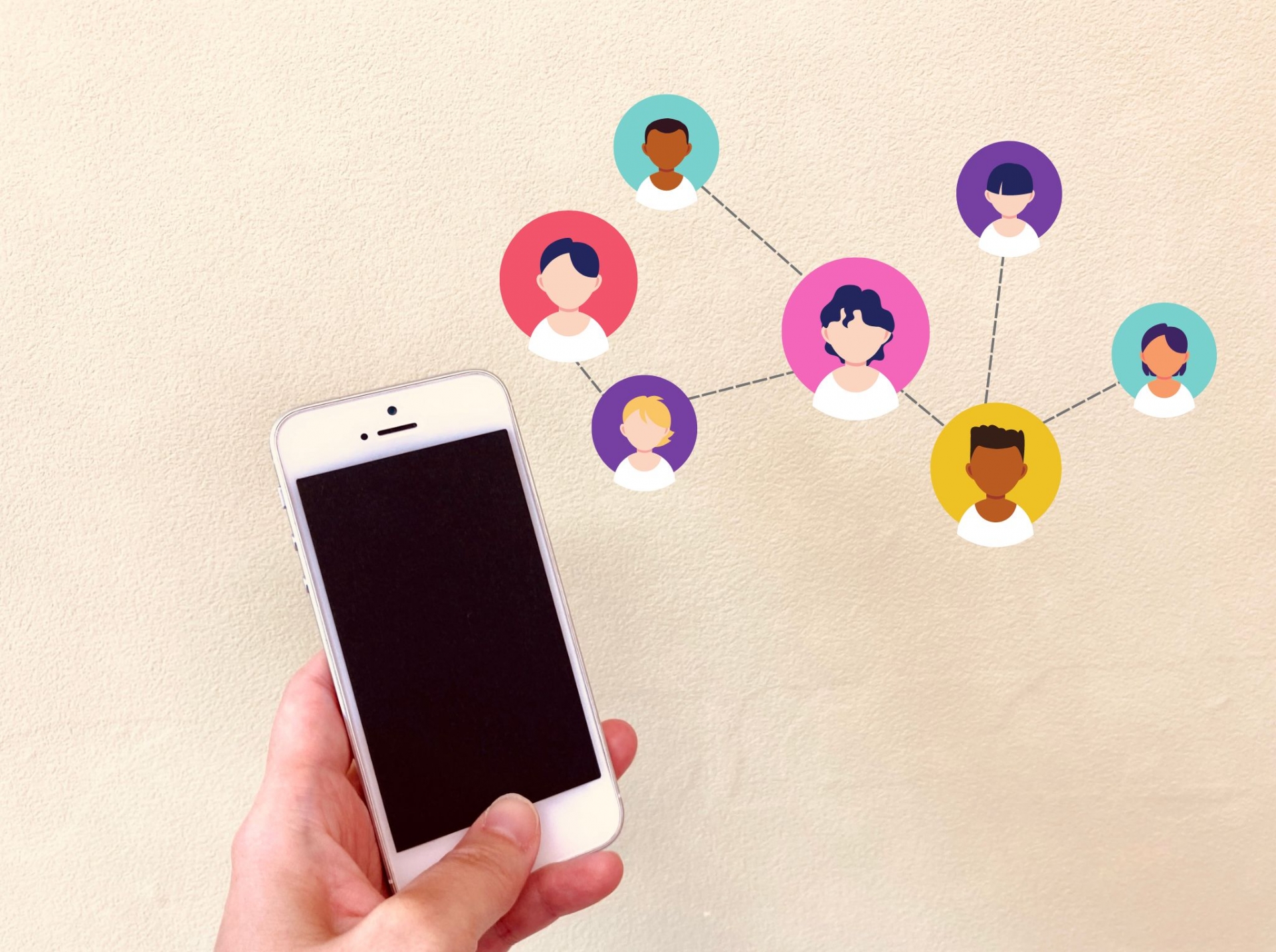
近年、スマートフォンの普及によってユーザーは短時間で多くのコンテンツを視聴し、瞬時に判断する傾向が強まりました。
こうした変化は、マーケティングにおいても重要なポイントです。具体的には長文や複雑な説明よりも、簡潔で視覚的に理解しやすいコンテンツが好まれています。
ショート動画はこのニーズに合致し、移動時間やスキマ時間などの短いインターバルでも視聴されやすい傾向です。
さらに、ユーザーの能動的な情報探索から受動的な情報接触へと行動様式が変わり、アルゴリズムによる動画推奨が増えたことも背景にあるといえるでしょう。
短時間で情報を伝えられるため
現代のビジネスシーンでは、受け手の時間が限られていることが多く、効率的に情報を届ける手法が求められています。
ショート動画は数秒から数十秒程度で要点を伝えられるため、忙しいユーザーでも気軽に視聴しやすいのが特徴です。
テキストや長尺動画に比べて、視覚と聴覚を同時に刺激できるため、内容の理解と記憶に効果的です。
特にマーケティングでは、専門的な内容を短くまとめることで意思決定者や担当者の関心を引きやすくなります。
動画制作の専門家であるFunusualは、クライアントの目的や課題に合わせた最適な長さの動画を提案し、効率的な情報伝達を実現します。
忙しい視聴者にも響く、短時間で訴求力のある動画を制作したい方は、まずは一度Funusualまでご相談ください。
視覚的な訴求力が高いため

ショート動画は視覚と聴覚を同時に使うため、感情やメッセージが直感的に伝わりやすい特性があります。
このため、商品やサービスの価値を具体的かつ印象的に表現でき、ユーザーの関心を引きやすいのが特徴です。
専門的な内容や技術的なポイントを短くまとめて伝えることで、信頼感の醸成やブランドの専門性を効果的に訴求できます。
また動きや音による表現は、静止画やテキストだけでは伝わりにくいニュアンスや情熱を伝える手段としてとても有効です。
そのため視覚的な説得力や影響力が高まり、購買や問い合わせなどの行動喚起につながりやすいといわれています。
ショート動画市場の動向

ここ数年で、ショート動画は個人の発信手段にとどまらず、企業マーケティングにおいても急速に存在感を高めています。
YouTube ShortsやInstagram Reels、TikTokのような縦型動画プラットフォームの成長は、その流れを加速させました。
企業もユーザーとの接点として本格的に活用し始めています。こうした動きの背景には、ユーザーの視聴習慣の変化と、それに対応した企業側のマーケティング戦略の転換があります。
では具体的にどのような需要があり、どのような将来性が見込まれているのでしょうか。詳しく解説していきます。
ショート動画の需要
ショート動画市場が拡大し続けている背景には、ユーザーの視聴環境と行動習慣の変化が大きく関係しています。
例えばサイバーエージェントの調査によると、スマートフォン向けの縦型動画広告の需要は2023年から急増し続け2024年には前年比171.1%の伸びを示し、市場規模は900億円までに達しました。
これはユーザーが短尺動画を積極的に受け入れている証拠でもあります。さらにBtoB市場でもショート動画の需要は高まっています。
Hub Spotのデータによると、マーケティング担当者のうち約33%がショート動画が高いROIを生んだと回答しており、従来の長尺コンテンツよりも短尺方式の評価が高まっていることが明らかです。
このようにユーザー側の視聴習慣の変化、広告投資の増加などの要素が重なり合い、ショート動画の需要を後押ししています。
ショート動画の将来性

ショート動画は今や一過性のブームではなく、市場全体の成長を支える重要なコンテンツ形式として定着しています。
特にモバイル環境下でのユーザー行動の変化と、企業のマーケティング戦略の進化が相まって、今後ともさらなる普及が見込まれるでしょう。
mordorintelligenceの調査では、世界的な市場規模が2024年の19.9億ドルから2029年には31.7億ドルに達し、年平均成長率は9.8%と見込まれています。
こうしたデータから、ショート動画は今後とも成長ドライバーとしての地位を強化し、企業にとってますます戦略的なコンテンツとなることが明らかです。
ショート動画のメリットとデメリット
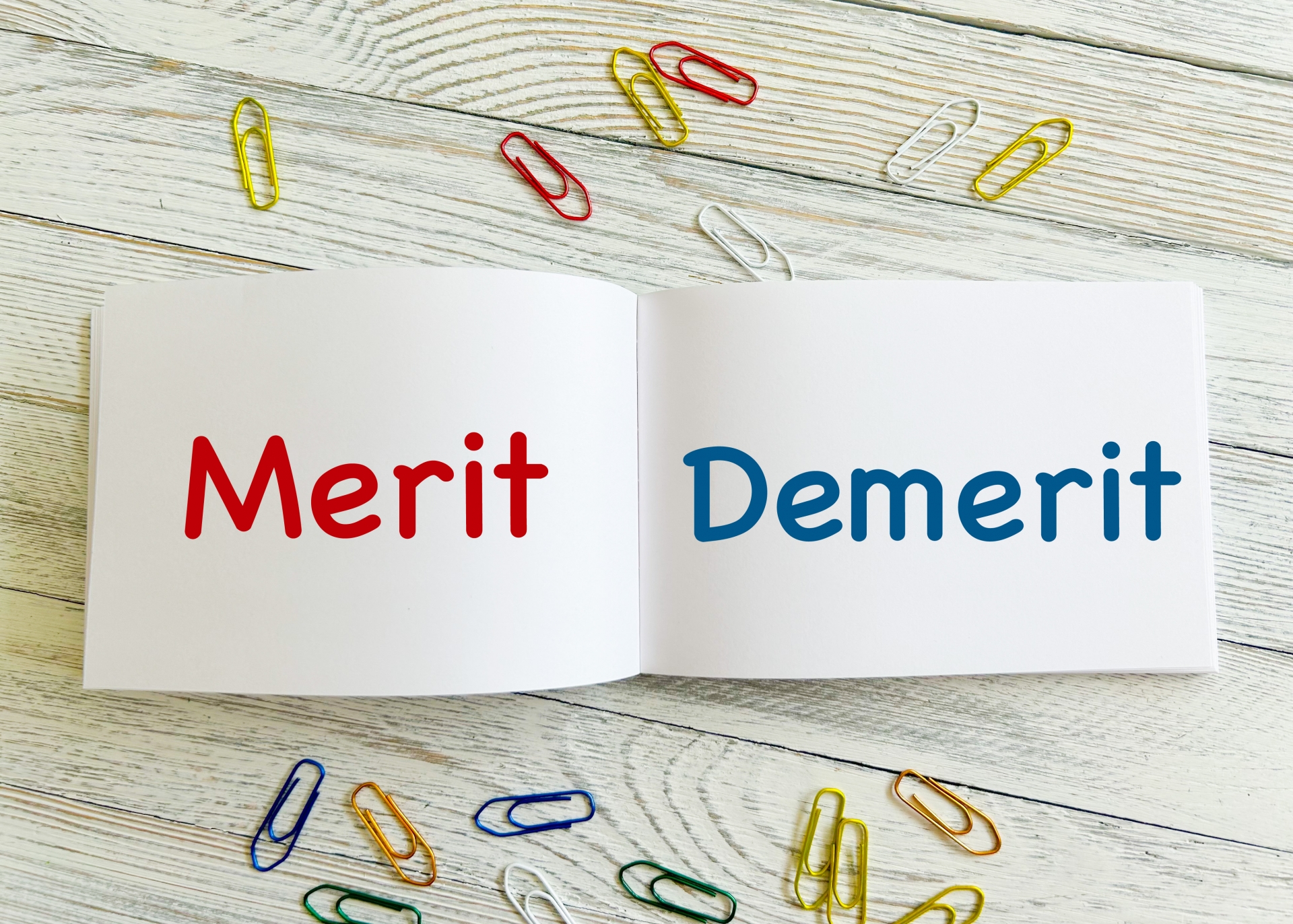
ショート動画は、その手軽さや高い拡散力によってマーケティングにおいても注目を集めるようになりました。
特に情報の伝達スピードが求められる現代において、短時間で視聴者の興味を引きつけられる点は大きな利点です。
またSNSとの相性がよく、視聴データの収集やABテストにも適しています。一方で、短尺ゆえに情報量が制限されやすいため、伝えたい要点を明確に整理することが必要です。
活用次第では大きな効果を見込める一方、注意すべき点も存在します。それぞれを整理しながら解説していきます。
メリット
ショート動画は、マーケティングにおいても多くの企業にオファーされつつあります。この理由の一つが、低コストでの政策や運用が可能な点です。
近年では、スマートフォン1台で撮影から編集、投稿まで完結できるツールが整っており特別な機材を必要としないケースも増えてきています。
またアプリ内の編集機能が充実しており、初めて動画を活用する企業にとっても導入のハードルが下がっています。
さらに短尺動画はそのまま複数のプラットフォームに展開しやすく、再利用できるため制作コストに対するリーチ効率がとても高いのが特徴です。
一つの動画コンテンツで複数のチャンネルにアプローチできることは、運用面での大きなメリットになります。
加えて動画の内容がわかりやすければ、ユーザーの購買行動や資料請求など、実際のコンバージョンにも直結するでしょう。
このように制作のしやすさと拡張性、成果への結びつきやすさといった要素が重なり、ショート動画はマーケティングにおいて有効な選択肢となっています。
デメリット

ショート動画は多くのメリットを持つ一方で、マーケティングにおいては慎重に扱うべき側面もあります。
しかし、適切な対策を施すことで、十分にその価値を引き出すことが可能です。まず視聴者とのミスマッチです。
ショート動画は若年層への訴求に向く傾向がありますが、ターゲット層がシニアや専門職中心の場合、期待した成果が得にくくなる可能性があります。
この点はターゲットを明確に定め、配信先プラットフォームの選定を慎重に行うことで緩和できます。
次に深い内容や複雑なメッセージを伝えにくいという構造的制約です。ショート動画だけでは商品やサービスの全体像を伝えきれないケースも見られます。
この場合は、シリーズ方式や長尺コンテンツへの誘導設定を行うことで補完が可能です。これらのデメリットはしっかりと戦略、設定を行えば、逆に強みとして活用できる余地が十分にあります。
Funusualはターゲットや目的に応じたプラットフォーム選定や企画設計、誘導設計にまで踏み込んだ支援を提供します。
マーケティングに適したショート動画制作を希望の際は、ぜひFunusualへご相談ください。
ショート動画マーケティング戦略を成功させるためのポイント

ショート動画は拡散力や訴求力に優れた手法ですが、単に投稿するだけでは期待した効果を得るのは難しくなっています。
ただ再生数を伸ばすのではなく、いかにターゲット企業との接点を築き、ビジネス成果に結びつけるかが鍵になります。
そこで重要になるのが、誰に向けてどのようなメッセージを、どのようなタイミングで届けるか細かく設定することです。
具体的にはユーザーの明確化や動画開始直後の印象づけ、検索性の確保や資格要素の工夫などいくつかの要素が関係しています。それぞれのポイントについて具体的に解説していきます。
ターゲットの明確化
ショート動画をマーケティングに活用するうえで、ターゲットを明確に設定することは始めの一歩です。
具体的なペルソナを設定すれば、内容やトーンの方向性が定まり視聴者にとって響く動画に仕上がります。
SNSのプラットフォーム特性にも狙う業種や課題、関心内容を絞ることで、成果につながりやすくなるでしょう。
実際、精密に定義されたターゲットを前提に構成された動画が、視聴率やエンゲージメントにも顕著な成果を示しているという報告も見られます。
開始数秒で惹きつける工夫
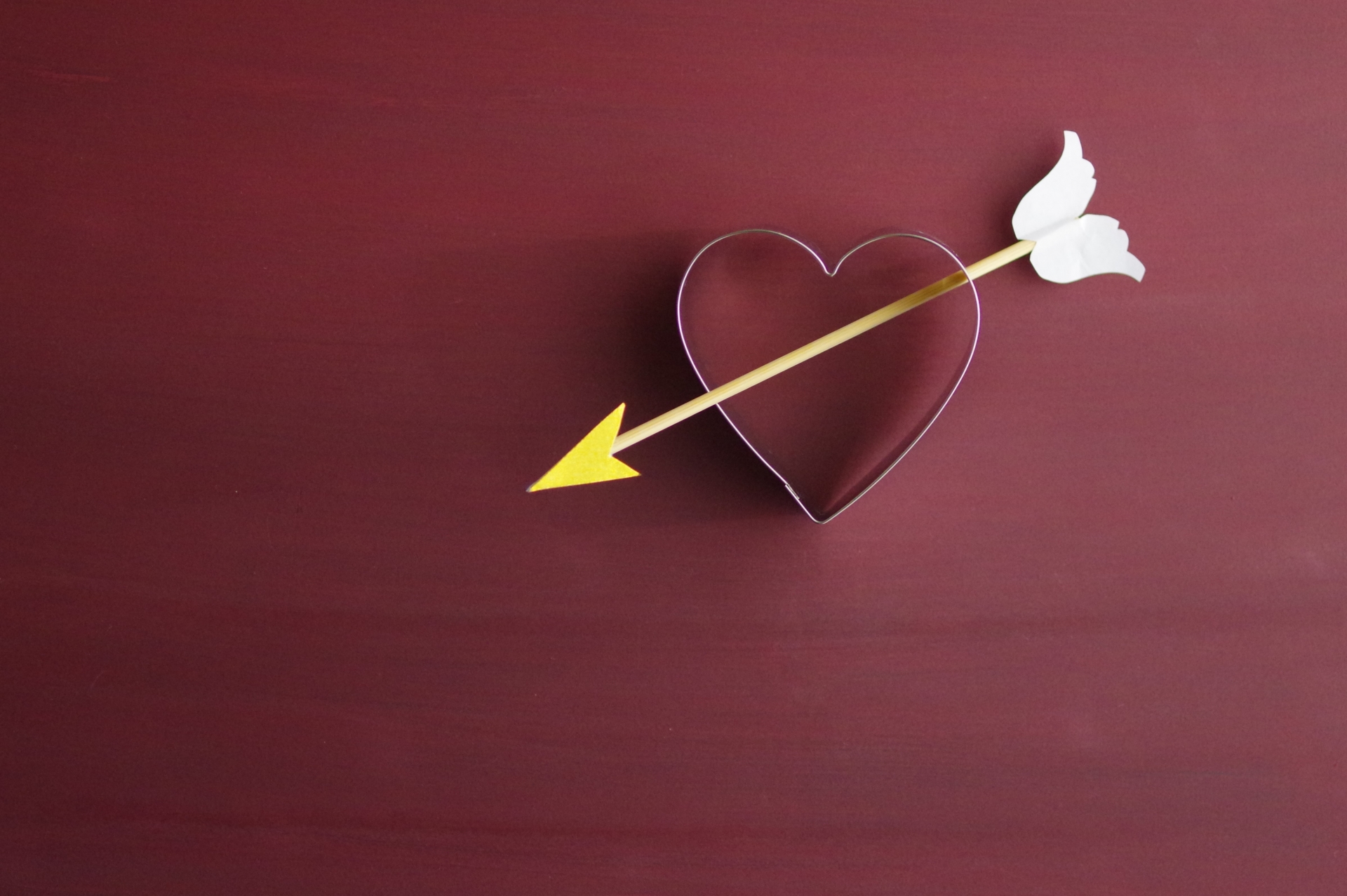
ショート動画において、再生開始のインパクトが視聴継続率を大きく左右します。
ユーザーは、始めの1〜3秒でこの動画が見る価値があるのかを判断するため、冒頭に明確な問いかけや驚き要素を設けることが鍵です。
具体的には、ターゲットに直接呼びかけるテキストや意外性のある映像カット、印象深いBGMで視覚聴覚の注意をつかむ手法が効果的です。
またアニメーションや素早いカット切替を前半に集中させると、動画のリズムがよくなり、離脱率を下げられます。
それにより、ユーザーは続きが気になる流れとなり、最後まで視聴される確率が高まります。
トレンド活用
ショート動画の効果をできるだけ大きくしたいなら、現在話題になっている音楽やハッシュタグ、時事ネタなどを取り入れることが有効です。
短尺動画は投稿から結果がわかりやすいため、流行に合わせた企画を素早く検証し、改善することで再生数やエンゲージメントの向上につながりやすい特徴があります。
例えば人気の楽曲や定番のテンプレートを使うと、視聴者の心理的ハードルは下がりやすく、アルゴリズムの優先表示を受けやすくなります。
こうした施策を通じて、トレンドと自社メッセージを組み合わせながら伝えることで、視聴者への関心を引いたうえでブランドや商品への理解へつなげやすくなるでしょう。
SEO対策

ショート動画でもSEO対策は欠かせない要素です。動画そのものと、その周辺のメタ情報をしっかり整えておくことで、Google検索やプラットフォーム内検索で露出が高まり潜在的な視聴者への接点が増えます。
具体的にはキーワード選定やタイトル、説明文やタグ、サムネイルの設計が基本です。
タイトルにはターゲットの検索しそうな語句を自然に盛り込み、説明文に本質的な内容や補足情報を含めておくことで、アルゴリズム評価とユーザー理解の両面に有利になります。
ショート動画のクリック率や検索流入を意識しつつ、長期的にはナーチャリングにつながる誘導設計も意識すると、より高い成果が期待できるでしょう。
魅力的なサムネイルとキャプションの作成
ショート動画において、どのように中身が優れていても視聴者がクリックしなければ意味がありません。
ここで重要なのが、再生前に目を引くサムネイルと再生中に理解を助けるキャプション設定です。
サムネイルには高解像度画像と明確なメッセージを組み込み、色や構図で視線を引きつけることが効果的です。
キャプションの設計は動画視聴を促進するとともに、音声なしでも内容が伝わる補助線として機能します。
特に重要なキーワードや導入部分にテキストを配置することで、視聴者の理解が促進され再生完了率やクリック率の向上に寄与するでしょう。
Funusualでは、プラットフォームに合わせた適切なサムネイルデザインや、効果を狙ったキャプション設計も含めた制作をご支援しています。
成果につながるショート動画をお求めの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
投稿のタイミングと頻度の適正化

ショート動画の効果を高めるには、いつ投稿するのか、どれくらいの頻度で投稿するのかが重要です。
単なる配信のタイミングではなく、視聴者の生活リズムに合わせて接点を増やし、アルゴリズムに好まれる状態を作りこむという戦略です。
投稿のタイミングは、ユーザーがスマートフォンで動画を閲覧しやすい時間が選ばれやすく、YouTube Shortsでも視聴率の高い結果が報告されています。
また投稿頻度については、企業アカウントでは毎週1〜2本が品質と継続性のバランスが保てる目安とされています。
一方、頻繁に更新できる体制が整っている場合は、週に5本以上の投稿でアルゴリズムの露出機会を増やす戦略も有効です。
ただしクオリティの維持が前提でなければ、逆効果となる可能性もあります。
これらを踏まえて視聴者の活動ピークに合わせたタイミング設定と、無理のないペースでの継続的配信により、ショート動画は確かな成果につながります。
プラットフォーム別のショート動画戦略

ショート動画を活用する際は、配信するプラットフォームごとの特性を踏まえた戦略が欠かせません。
ユーザー層やアルゴリズム、利用目的が異なるため同じ動画でも反応は大きく変わります。
例えばある媒体ではエンタメ性が重視され、別の媒体では情報性やブランド訴求が評価されることもあります。
こうした違いを理解し、適切な見せ方を選ぶことが、成果につながる鍵です。それぞれに適したアプローチをご紹介します。
TikTok
TikTokは、フォロワー数に関係なく、動画が広く拡散されやすい特性を持つため、企業アカウントでも短期間で大きなリーチを得やすいプラットフォームといえます。
特にエンタメ性の高いコンテンツやトレンドを取り入れた投稿が歓迎されやすく、企業でも導入事例や社内紹介などを通じて若年層に親しみを持ってもらうことが可能です。
ブランドの印象をやわらかく伝える手法としても有効で、短尺動画との相性もとてもよいです。
YouTube Shorts

YouTube Shortsは60秒以内の縦型動画を投稿できる機能で、短時間で多くの視聴者にリーチできるのが特徴です。
YouTubeの圧倒的なユーザー数を活かし、BtoB分野でも専門知識や製品の魅力を手軽に伝える手段として注目されています。
ショート動画から長尺の解説動画やウェビナーへつなげる導線を設計することで、マーケティング効果を高めることができます。
Instagram Reels
Instagram Reelsは視覚的な表現力に優れたショート動画機能で、ブランドの世界観やトレンド観を伝えるのに適しています。
特に感度の高いユーザーが多く、ビジュアルや音楽、テンポの工夫によって企業アカウントでも自然に認知拡大を図れます。
ハッシュタグやリール専門タブの活用により、フォロワー以外の潜在層への露出も期待できるため、ブランディングと集客の両面で効果を発揮するでしょう。
ショート動画マーケティング戦略の成功事例

ショート動画マーケティング戦略の成功事例としては、プラットフォームごとに生かした投稿やトレンドの活用によって、視聴者の関心を引きつけて成果を上げた例が多くみられます。
こうした成功事例から、効果的な動画戦略のポイントが明確になり、今後のマーケティングに活かせるヒントが得られるでしょう。
効果的なショート動画で魅力を伝えたいなら

効果的なショート動画で魅力を伝えるには、ターゲットのニーズを明確にとらえ、短い時間でインパクトのある内容を届けることが重要です。
映像の質やメッセージの明確さを意識し、視聴者の関心を引き続ける工夫が求められます。こうしたポイントを押さえることで、商品やサービスの魅力を効果的に伝えられます。
効果的なショート動画作成をご希望の方は、ぜひFunusualにご相談ください。
Funusualでは、再生数やコンバージョンを意識したショート動画の制作を強みとしています。
TikTokやYouTube Shortsなど各プラットフォームの特性を熟知し、視聴者の目を引くサムネイル設計、数秒で惹きつける構成、ブランドイメージに合ったキャプション作成まで、一貫してサポート可能です。
これまでに大手企業からスタートアップまで、幅広い業種の動画マーケティングを支援しており、動画を活用したプロモーション施策で売上や認知拡大につなげた実績も多数あります。
「自社に合ったショート動画の活用方法がわからない」「短期間で効果的な動画を制作したい」とお考えの方は、まずは一度、Funusualにご相談ください。
目的に合わせて適切なご提案をいたします。













