YouTubeショート動画は、最長3分の短尺で視聴者の関心を引き、拡散力を発揮できる新しい動画フォーマットです。
近年では、企業の広報やマーケティング活動においても重要度が増しており、ブランド認知から購買促進まで幅広い効果をもたらす手段として注目されています。
しかし、ただ投稿するだけでは成果を得るのは難しく、映像編集の工夫・適切な投稿時間の選定・クリックされやすいタイトル設計といった工夫が大きく左右するでしょう。
この記事では、まずYouTubeショート動画の基礎知識やほかのSNSとの違いを整理したうえで、メリットとデメリットを解説します。
また、バズを狙うための映像編集のコツ・投稿時間の見極め方・効果的なタイトルの作り方を一緒に紹介するので、実践に活かしてバズるYouTubeショート動画を作っていきましょう。
YouTubeショート動画の基礎知識と概要

YouTubeショートは、2020年にテスト提供が始まって以降、急速に利用者を拡大している縦型の短尺動画フォーマットです。
スマートフォンに適切化されたUIと、アルゴリズムによるおすすめ表示機能により、視聴者は次々と動画を楽しめます。
その結果、ユーザーの滞在時間が伸び、クリエイターや企業にとって新たな集客チャネルとなりました。長尺動画より制作が容易で、短い時間で強い印象を残せる点が特徴です。
ここでは、YouTubeショート動画の特徴や人気の理由、ほかのSNSとの違いを説明します。
YouTubeショート動画の特徴
YouTubeショートは、最長3分という制限があることで、内容を凝縮しテンポよく伝える必要があります。縦型フルスクリーンで表示されるため、視聴者の集中を得やすく、離脱率を下げやすい形式です。
また、通常のYouTube動画と同じようにチャンネル内に蓄積され、検索や関連動画からの流入も期待できます。
この仕組みによる長期的な集客につながる点がTikTokなどとは異なる強みといえるでしょう。
YouTubeのショート動画が人気な理由

TikTokやInstagramリールと比べると、YouTubeショートは検索されやすい、公開後も再生され続けるといった特徴があります。
TikTokはトレンドの拡散力が高く、Instagramは利用者同士の共感やつながりを深めやすいのが持ち味です。一方でYouTubeショートは、公開後も検索や関連動画から視聴され続ける点が特徴です。
さらにGoogle検索に表示される可能性もあり、SEOの観点でも有利に働きます。
短期的な拡散を狙うならTikTok、長期的に動画を残して集客につなげたいならYouTubeショートといったように目的に合わせて選ぶことが重要です。
ほかのSNSショート動画との違い
TikTokやInstagramリールと比較すると、YouTubeショートは検索性と蓄積性に強みがあります。
TikTokはトレンド拡散力に優れ、Instagramはコミュニティ内での共感形成が得意です。
一方で、YouTubeショートは公開後も検索や関連動画から視聴が続きやすく、中長期的に再生回数を伸ばせる特徴があります。
また、Google検索結果に表示される可能性があり、SEO観点からも有利です。
この違いを理解することで、自社が求める目的に合った媒体選定が可能になります。
YouTubeショート動画のメリットとデメリット

YouTubeショートは企業のマーケティング活動において大きな可能性を秘めていますが、同時に注意すべきリスクも存在します。
ここでは代表的なメリットとデメリットを整理し、自社で活用する際の判断材料にしましょう。
メリット
YouTubeショートを活用するメリットは以下のとおりです。
- 拡散力の高さ
- 低コストで制作可能
- 購買行動につなげやすい導線設計
- 海外ユーザーへのリーチ
まず、大きな特徴は拡散力の高さです。短い時間で視聴できるため完了率が高く、アルゴリズムに評価されやすい傾向があります。
おすすめ欄や関連動画に表示されやすくなり、短期間で数万〜数百万回の再生を獲得するケースも珍しくありません。
次に、低コストで制作可能な点です。スマートフォン撮影と簡易編集だけでも十分に成果を出せる場合が多く、長尺動画よりも初期投資を抑えやすいという利点があります。
また、購買行動につなげやすい導線設計が可能な点も強みです。
ショートで関心を引いた後、詳細な情報を長尺動画や公式サイトで補完することで、マーケティングファネル全体で効果的に活用できます。
さらに、YouTubeショートはグローバルに利用されているため、海外ユーザーへのリーチも可能です。
言語の壁を越えて拡散されやすいのは、短尺動画ならではの魅力です。YouTubeのアナリティクス機能を活用すれば、視聴者の年齢層や地域、再生維持率などの詳細なデータを取得できます。
これにより、次の動画制作や広告戦略に活かせる具体的なインサイトを得られる点も大きな強みです。
拡散だけでなく、PDCAを回しながら改善を重ねられるため、マーケティング施策全体の質を高められます。
その結果、低コストかつ高効率でブランド認知や売上アップにつなげることが期待できます。
デメリット
YouTubeショートを活用するメリットがある一方で、ショート動画ならではの課題もあります。デメリットは以下のとおりです。
- 情報量の制約
- 炎上リスク
- 継続的な運用負担
まず、情報量の制約です。3分以内で伝えられる内容は限られるため、複雑なサービス説明や専門的な情報提供には向きません。
次に、炎上リスクです。短時間で強いインパクトを狙うため、誤解を招く表現や過度な演出がネガティブな反応につながる可能性があります。
特に企業アカウントでは、ちょっとした演出がブランドイメージに影響することもあるため、発信する内容は慎重に考えましょう。
最後に、継続的な運用負担が挙げられます。アルゴリズムの性質上、定期的に動画を投稿しないと再生数が安定しません。
運用チームの体制や時間の確保が必要であり、片手間の取り組みでは成果が出にくい点も認識しておく必要があります。
YouTubeショート動画をバズらせる映像編集のコツ

YouTubeショート動画をバズらせるには、次の3つの編集ポイントを意識すると効果的です。
- 動画冒頭で視聴者の興味を惹いて最後まで見たいと思わせる構成にする
- 繰り返し視聴したくなる動画構成にする
- トレンドを入れる
それぞれのポイントを具体例とともに解説します。自社の動画に合いそうな編集があれば、積極的に取り入れてみましょう。
動画冒頭で視聴者の興味を惹き最後まで見たいと思える映像にする
冒頭の3秒は、視聴者がこの動画を見るか、スキップするかを決める重要な瞬間です。
強いビジュアルやキャッチコピー、疑問を投げかける構成を入れることで離脱を防ぎ、最後まで見たいと思わせる流れを作ります。
例えば「知っているようで意外と知らない〇〇の秘密」といったフレーズを冒頭に置けば、続きが気になって視聴が継続しやすくなります。
何度も繰り返し視聴したくなる動画にする
バズる動画は、一度見ただけで終わらず「もう一度見たい」と思わせる要素を持っています。テンポのよい編集やリズム感のあるBGM、最後に軽いオチを入れるなどの工夫が有効です。
また、ループ再生を意識した構成もポイントです。動画の終わりと始まりを自然につなげると、ユーザーが無意識に繰り返し再生することがあり、結果的に再生回数が伸びやすくなるでしょう。
トレンドを入れる
YouTubeショートは、トレンドや時流を取り入れることで拡散力が高まります。
流行のBGMや話題のハッシュタグを組み合わせると、アルゴリズムに取り上げられやすくなる傾向があります。
流行をただ真似するだけではなく、自社の商品やサービスに結びつける工夫が大切です。例えば人気の楽曲を使いながら、自社ブランドを印象づける演出を加えると、独自性が出て拡散も期待できます。
タイムリーな話題を取り込みながらも、自社ならではのストーリーを加えることで、ファン化やリピーター獲得にもつながるでしょう。
編集の工夫を取り入れることで再生数や拡散力は大きく変わります。しかし、自社での取り組みだけでは限界を感じる場面もあるでしょう。
自社編集では再生数が伸びない、限界を感じているときは、Funusualにご相談ください。
これまで大手企業の動画を数多く成功に導いてきたディレクターが、御社の課題を分析し、適切な編集手法とバズにつながる具体策をご提案します。
YouTubeショート動画がバズりやすい時間帯

YouTubeショートは2023年以降、60秒から拡張され、最長3分以内の動画を投稿できるようになりました。
これにより、従来の短い一発ネタ型だけでなく、ストーリー性を持たせた動画・商品紹介・チュートリアル形式の活用も可能になっています。
しかし、いくら内容を工夫しても投稿する時間を誤ると視聴回数は伸びにくくなります。
バズを狙うためには、時間帯を意識した戦略的な投稿が欠かせません。特にショート動画は初動の勢いが重要であり、再生数の立ち上がり次第でアルゴリズムに評価されるかどうかが決まります。
ここでは、バズる時間の重要性や見極め方を解説します。
バズる時間を見極める重要性
視聴者は常に同じ時間にYouTubeを利用しているわけではありません。ターゲット層がもっともアクティブな時間帯に投稿することで、再生直後にインプレッションが伸び、アルゴリズムに評価されやすくなります。
投稿直後の再生数が急速に増えると人気が出る動画と判断され、さらにおすすめに表示される確率が上がるのです。
反対に視聴者が少ない時間に投稿してしまうと、初動で伸び悩み、バズの可能性を逃すリスクがあります。
バズる時間の見極め方

具体的に狙うべき時間帯はターゲット層によって異なります。学生や若年層は平日の放課後(16〜19時)や夜(20〜23時)が活発です。
社会人は昼休み(12〜13時)、帰宅後の夜(19〜22時)が利用のピークといえるでしょう。休日は午前中〜午後にかけて広い時間帯で利用が増える傾向があります。
また、YouTube Studioのアナリティクスで視聴者がオンラインの時間を確認すれば、自社チャンネルに適した投稿タイミングが把握できます。
アルゴリズムは、最初にどれだけ再生されるかを重視するため、いくつかの時間帯で何度も投稿を試してみてください。
特に反応がよいタイミングをつかめれば、視聴回数を伸ばしやすくなるでしょう。
バズりやすいタイトル作成のコツ

YouTubeショートは映像のクオリティだけでなく、タイトルの工夫によって大きく成果が変わります。タイトルはクリック率だけでなく、視聴回数や拡散力も大きく左右する要素です。
特に最長3分になったショートでは、内容が一目でわかるタイトルを設定することが、最後まで見てもらうきっかけにつながります。
ここでは、バズるタイトルをつけるための考え方を解説します。
バズるタイトルをつける重要性

YouTubeのアルゴリズムはクリック率をとても重視しています。いくら内容がよくても、タイトルに魅力がなければ再生されることはありません。一方で、関心を強く引くタイトルは再生回数を大きく押し上げます。
特にショート動画は次々と流れる環境で視聴されるため、瞬時に興味を惹くタイトルが必要です。
タイトルを適切に設計すれば、動画冒頭の数秒と相まって初動の再生数を伸ばし、バズの可能性を高められます。
バズるタイトルをつけるコツ
効果的なタイトルを作るには、次の3つを意識するとよいでしょう。
- 具体性
- 意外性
- 感情に響く言葉
具体性を出すために、数字などの客観的な指標を入れましょう。売上が伸びる方法よりも売上を30%伸ばす方法とした方が、視聴者に行動を促しやすくなります。
一般的な常識を覆す表現を入れることで「本当にそうなの?」と関心を引きます。例えば実は逆効果なダイエット法3選とすれば、意外性で関心を集められるでしょう。
また、驚く・失敗しない・最速で、など感情を揺さぶるフレーズを使うのもクリック率を高めるうえで効果的です。
タイトルは、動画を見てもらえるかどうかを決める大切な要素です。しかし、上記のコツを踏まえて実際にタイトルを考えるとなると、意外と時間がかかって手が止まることもあるでしょう。
「魅力的なタイトルが思いつかない」「クリック率を上げたい」とお悩みなら、Funusualにお任せください。
過去の成功データとマーケティングの知見をもとに、視聴者が思わずクリックしたくなるタイトルを御社専用に設計し、再生数と成果を大きく伸ばすサポートをします。
YouTubeショート動画がバズる前兆
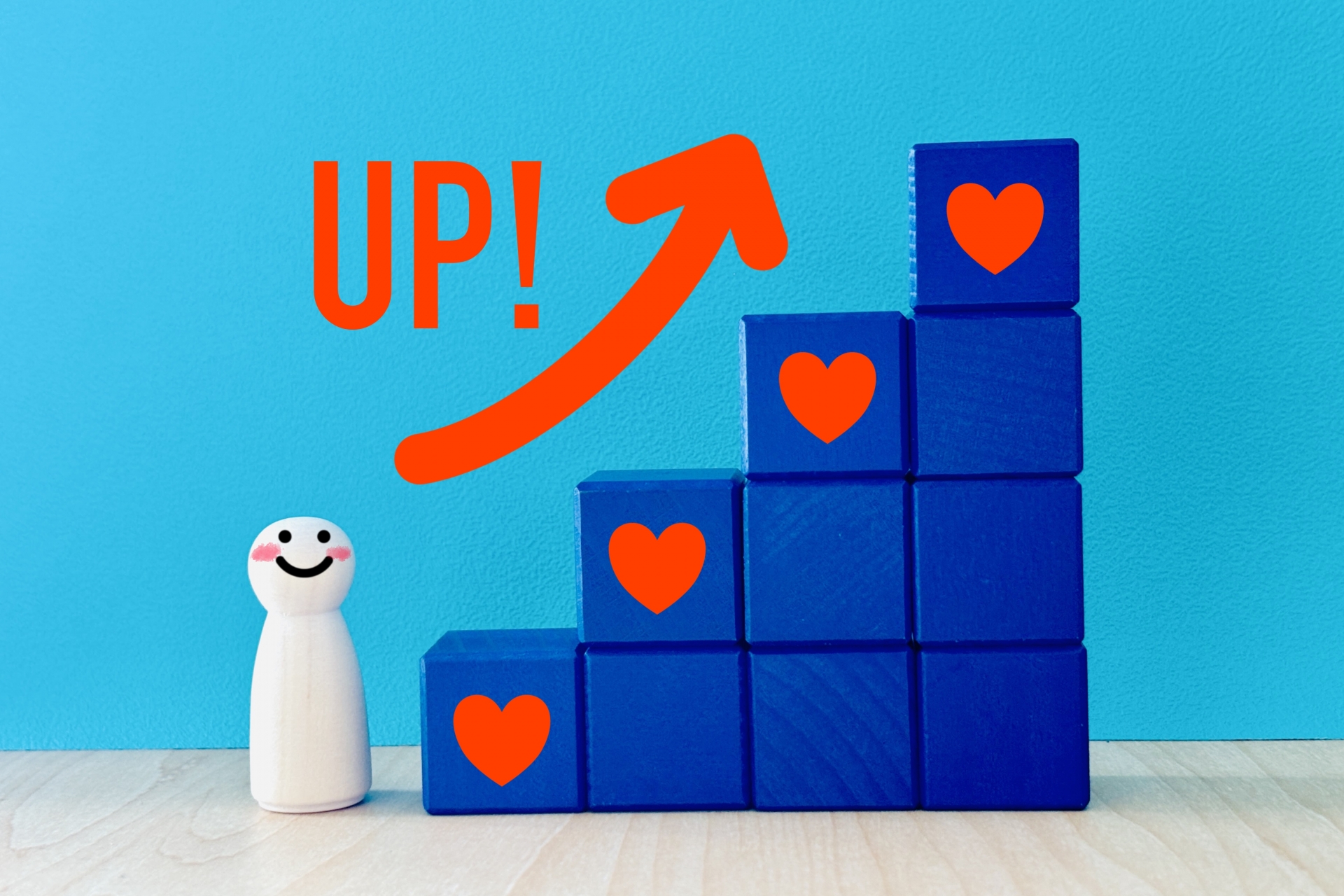
動画を公開した直後から「これは伸びそうだ」と感じる瞬間があります。YouTubeショートでは特に、初動の数時間から数日のデータが重要です。
再生数・エンゲージメント・チャンネル登録者数の変化を観察することで、バズる可能性を早い段階で見極められます。
ここでは、具体的な前兆を3つ紹介します。
視聴者のいいねやコメントが増える
動画に対するいいねやコメントは、視聴者が積極的に反応している証拠です。
特にコメント数が急に増える場合は、動画が共感や驚きを呼び起こしている可能性が高く、アルゴリズムからもプラス評価を受けやすくなります。
また、コメント欄が活発になるとほかのユーザーも参加しやすくなり、二次的な拡散効果が期待できます。
単なる再生回数だけでなく、こうしたリアクションを伴う伸び方はバズの大きな前兆です。
投稿直後の視聴回数が伸びる

公開直後に再生数が急増するのは、アルゴリズムが動画をおすすめに載せ始めたサインです。YouTubeは投稿後の視聴維持率やクリック率を見て、一定基準を超えるとさらに多くのユーザーに表示します。
特にショート動画はフロー型コンテンツとしての性質が強く、初動の勢いが命です。
最初の数時間で伸び始める動画は、その後も加速度的に再生が広がりやすい傾向にあります。
チャンネル登録者数の変化
ショート動画をきっかけに登録者が急増する場合は、コンテンツがターゲット層に強く刺さっている証拠です。おもしろいで終わるのではなく、また見たいと思わせている点が評価できます。
登録者の増加は今後の視聴回数の増加にもつながるため、長期的にチャンネルを育てるうえでも重要です。
特に短期間で登録者が目に見えて増えた場合は、動画がバズる直前の状態ととらえてよいでしょう。
バズるYouTubeショート動画の制作方法

YouTubeショート動画を制作する際には、自社で制作するか外部に依頼するかの2つの選択肢があります。
どちらにもメリットとデメリットがあり、自社の体制や目的に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。
ここでは、それぞれの方法の特徴を整理します。
自社で制作する
自社で制作する大きなメリットは、コストを抑えられる点です。
スマートフォンと無料アプリを使えば、低予算で動画を作れます。また、自社の社員が企画から編集までを行うため、ブランドのトーンや社内の細かな要望を直接反映させやすいというのも利点です。
一方で、品質や継続性の確保が課題となります。専門的な編集スキルが不足している場合、仕上がりが見劣りしてしまい、ブランドイメージを損なうリスクがあります。
また、日常業務と並行して動画制作を行うと、投稿を続けるのが難しくなるケースも少なくありません。
外部へ依頼する

制作会社やフリーランスに依頼するメリットは、高いクオリティと安定した制作体制を確保できることです。
プロの映像編集者やマーケティングの知見を持つ外部パートナーであれば、新しいトレンドを踏まえた動画を効率的に制作できます。
さらに、撮影・編集・効果測定まで一貫して任せられるため、担当者は企画や戦略立案に集中できるでしょう。
一方で、コストがかかる点や外部依存のリスクは避けられません。
制作費は依頼内容によって数十万円〜数百万円と幅があり、予算確保が必要です。また、依頼先によっては仕上がりや対応にばらつきが出ることもあります。
外注する場合は、一定の品質を保って納品できる業者かどうかを確認しましょう。
バズるYouTubeショート動画を制作したいなら

以前は60秒以内という制限がありましたが、現在は3分まで投稿が可能です。簡単な紹介だけでなく、商品の特徴や利用シーンを伝える動画にも活用しやすくなりました。
そのため、自社サービスの魅力をしっかり伝えたい企業にも適しているといえるでしょう。
Funusualでは、戦略づくりから制作・配信・効果の検証までトータルで支援し、貴社のYouTubeショート動画をバズへと導くお手伝いをいたします。
さらに、ショート動画単体だけでなく、長尺動画やWebサイトへの誘導を組み合わせたクロスメディア戦略も設計可能です。
売上や問い合わせにつながる成果を実現できます。
特に最近のYouTubeショートは3分以内の投稿が可能になっているため、商品紹介やサービス解説を盛り込みたい企業にとっては大きなチャンスといえるでしょう。
「自社のショート動画をもっと多くの方に見てもらいたい」「バズを狙って売上につなげたい」と考える方は、ぜひ一度Funusualにご相談ください。













