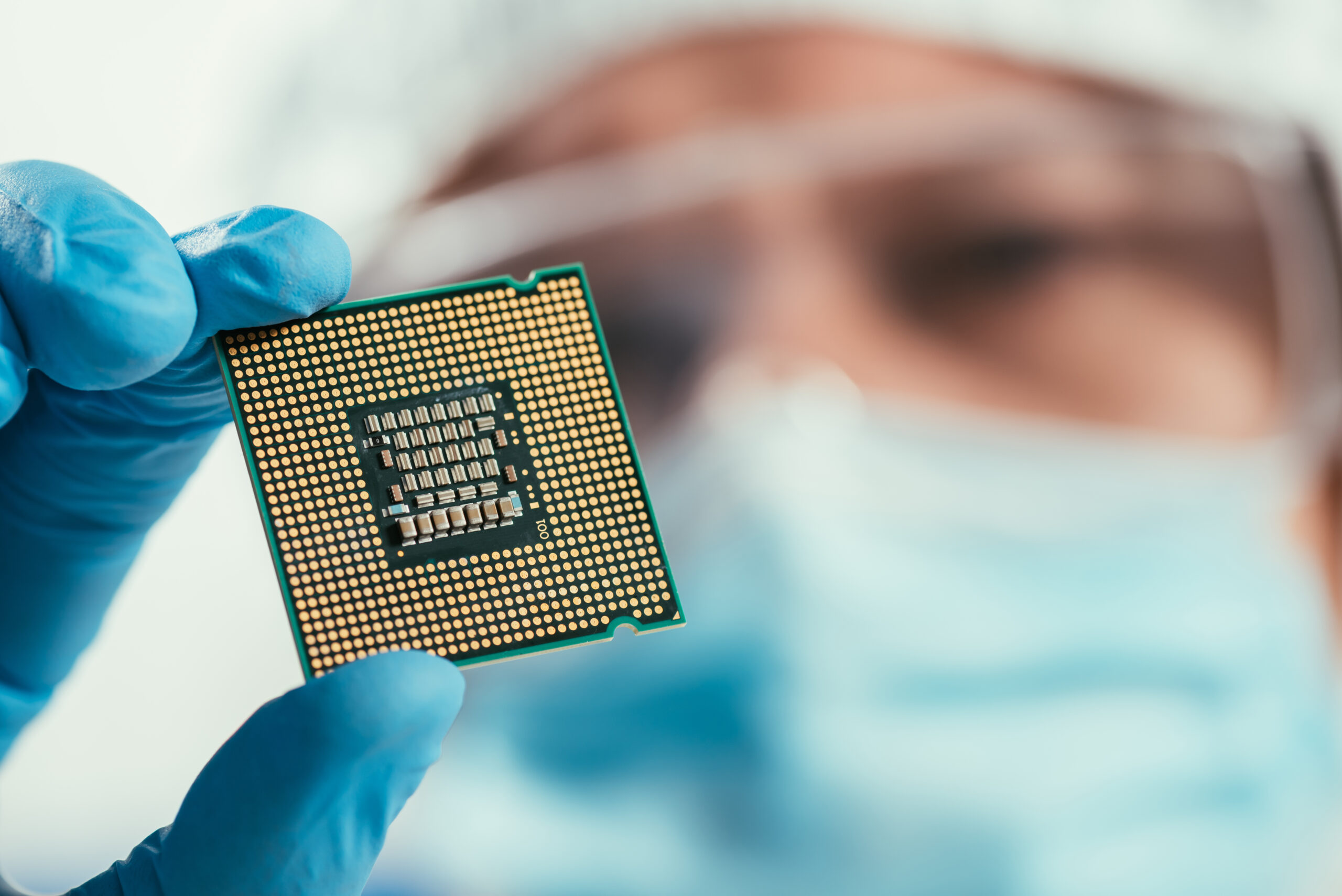BtoB企業特化型ハイクオリティ動画制作。会社紹介映像、展示会プロモーション、社員総会・イベント映像、営業ツール、採用ブランディング等。
お客様のビジネスモデルを深く理解し、高品質なPR映像制作を伴走型で行います。動画を作ったその先まで丁寧にコンサルティングサポート。
はじめに
【AIの頭脳】半導体関連動画事例集
- キオクシア株式会社
- シンフォニアテクノロジー株式会社
- ルネサスエレクトロニクス株式会社
AIの成長とともに、その心臓を担う半導体需要も飛躍的に高まっています。
ChatGPTなどの生成AIは大量のデータを同時に高速処理するため、性能に特化した半導体を使う必要があります。半導体の微細化に伴い、周囲を取り巻く環境も大きく変化してきている中で、企業もその対応に追われている日々です。
かつては世界をけん引していた日本の半導体企業も、現在では世界のTOP10圏外となってしまっていますが、日々加速する競争の中でどのような進化を遂げるかが重要となってくるでしょう。
今回は半導体だけでなく、半導体製造を支える企業の動画も含めて見ていこうと思います。
それではいってみましょう!
1. キオクシア株式会社
キオクシア株式会社は、日本の東京都港区芝浦に本社を置き、主にNAND型フラッシュメモリを製造する半導体メーカーです。社名の「キオクシア」は、日本語の「記憶」と、ギリシャ語で「価値」を意味する「axia(アクシア)」を組み合わせたものです。
2017年の半導体メーカー売上ランキングでは市場シェア世界第8位でした。
注目すべきポイント
実写人物による解説と、アニメーションやCGなどのインフォグラフィックスを駆使したものを組み合わせた動画となっており、世界向けに英語での解説も入ったものとなっています。
特に注目すべきはインフォグラフィックスの部分です。簡素なものから詳細を入れてカラフルにするなど、それぞれの解説に合わせた工夫が凝らされています。
AIやAR技術の発展とともに、データ量と複雑さが相当量なものとなり、それを効率的に保存し、高速にアクセスできるフラッシュメモリの需要はますます高まっています。
また従来のままで開発を続けた場合、大量の消費電力を伴うことになってしまうので、それは環境問題とも直結してきます。
技術の革新が電子環境だけでなく、人間の生活そのものも変えてしまう。加速度的に変化していく中で私たちは生きていると痛感しますね。
2.シンフォニアテクノロジー株式会社
シンフォニアテクノロジー株式会社は、発電機、電動機、搬送機器、航空宇宙、電磁クラッチ・ブレーキ、産業用大型車両、トーイングトラクター、プリンターをはじめとする電気機器などの生産を行う電機メーカーです。
元は神戸製鋼所系列で、2009年に現在の社名へと変更をしています。
半導体製造装置に材料を供給するインタフェース部分のロードポートでは世界トップシェアを握っています。
注目すべきポイント
動画は会社紹介となっており、パート分けして事業説明を行っています。
各部門の導入ではCGやアニメーションもうまく使われていますね。
メインの事業説明では、実際の製造過程などで実写を利用しています。また製造過程だけでなく、実生活のどの部分で使われているかも表現されています。
半導体という細かい部品の製造のためには、寸分の狂いもなく大量の製造を求められるため、製造機械においても正確性や速度といった高度な技術が求められます。
現代ではいたるところで機械をつくるために機械が使われていますが、これらは元を辿れば緻密に計算を重ね、熱意を持った開発によって作られたものです。
技術を支えるのもまた技術、ということですね。
3. ルネサスエレクトロニクス株式会社
ルネサスエレクトロニクス株式会社は、東京都江東区豊洲に本社を置く半導体メーカーです。三菱電機および日立製作所から分社化していたルネサス テクノロジと、NECから分社化していたNECエレクトロニクスの経営統合によって、2010年4月に設立されました。
社名の『Renesas』は、あらゆるシステムに組み込まれることで世の中の先進化を実現していく真の半導体のメーカー(「Renaissance Semiconductor for Advanced Solutions」)を標榜して名付けられたものです。
注目すべきポイント
実際のオンボーディングの様子を動画したものとなっています。
参加している新入社員側と、開催している会社側、表裏の双方から構成されています。
途中にインタビュー場面を組み込むことでそれぞれの「生」の声を伝えることができます。何を意図したもので、それをどう感じるか。通じ合うことで会社は成長していきます。
製造業の課程の多くは機械が担っていますが、開発や販売においては人間の力も必要です。人間の力を引き出すためには個人ではなく、力を集めることが重要であり、それを可能にするのがコミュニケーションです。1人ではできないことでも、多くの人間が助け合えば大きなことができるようになる。技術のスタートは、やはり人の力、です。