物件の内覧は不動産取引の大切なステップですが、日程調整や現地訪問には時間と労力がかかります。この課題を解決するのが、不動産内覧動画です。
顧客が現地に足を運ぶ前に、文章や写真では伝えきれない、リアルな雰囲気を体感できる強力な営業ツールといえます。
本記事では、不動産内覧動画の効果や撮影方法と配信方法、成功のポイントまで詳しく解説します。動画導入を検討している不動産業者の方は、ぜひ参考にしてください。
不動産内覧動画とは

不動産内覧動画とは、実際に現地を訪れなくても物件の内部や周辺環境の様子を映像で確認できる動画コンテンツのことです。
室内の間取りと設備から採光や風通し、さらには周辺地域の雰囲気まで、視覚と音声でわかりやすく伝えることができます。
従来の写真中心の物件紹介では、部屋の広さや動線、実際の空気感を把握するのは難しいものでした。しかし内覧動画を活用すれば、まるで物件内を歩いているかのような臨場感のある映像で、リアルな空間イメージを顧客に届けることが可能です。
さらに物件の紹介にとどまらず、最寄り駅からのアクセスや周辺の施設や街並みなども映像で伝えることで、実際の暮らしをよりリアルに想像してもらえるようになります。
このように内覧動画は、現地に行かずともリアルな体験を提供できる、顧客と不動産会社の双方にとって大きなメリットを持つツールです。
特に近年はスマートフォンの普及により、いつでもどこでも物件の様子をチェックできるようになりました。
内見動画を検討材料とするニーズも高まっています。遠方の顧客や多忙な層にもアプローチしやすく、成約につながる可能性を広げてくれるでしょう。
不動産内覧動画を作るべき理由

内見動画を作るのは手間がかかりそうだし、本当に効果があるのか分からないと感じていませんか。内覧動画はただの映像ではなく、営業活動を効率化し、成約率を上げるための大事なツールです。
ここでは内覧動画を導入するべき、具体的な理由を4つに分けてご紹介します。
物件の魅力を伝えられる
不動産内覧動画の強みは、物件の魅力を実際に住む視点で具体的に伝えられる点にあります。
写真や文字情報だけでは見落としがちな部屋の広さや動線、自然光の入り具合や外の眺めといった空間の体感を、動画であれば直感的に伝えることが可能です。
例えば、玄関からリビングへの動線や収納スペースの使い勝手など、細かな部分までリアルに映し出すことで、視聴者は物件での暮らしを具体的に想像しやすくなります。
動画内でスタッフがナビゲーションする形式を採用すれば、この部屋は寝室や趣味の部屋としても使えますといった提案ができることも魅力です。
興味を持ってもらいやすい
物件に対して興味を持ってもらうためには、いかにはじめの数秒で惹きつけられるかがポイントです。
静止画だけの掲載では、見る側がすぐに離脱してしまうこともあります。
しかし、動画は動きや音声、字幕といった要素を組み合わせることが可能です。そのため視聴者の注意を引きつけ、物件に対する興味と関心を高められます。
また動画内でスタッフが登場して物件の特徴を明るく解説すれば、視聴者に親近感を与え、信頼感向上にもつながります。
内覧のコストを抑えられる

不動産業者にとって、内覧のアポイント調整や案内は大きな業務負担です。動画内覧により、本当に興味を持った顧客だけが実際の内覧に来るようになれば、業務効率が大幅に向上します。
また複数物件を検討している顧客も、動画で事前に候補を絞れるため、内覧回数が減少し時間と交通費の節約になります。
現地に足を運べない方にも見てもらえる
遠方に住んでいる方や、多忙で内覧の時間が取れない方でも、動画なら物件の様子を確認することが可能です。
特に転勤や移住を検討している顧客にとって、事前に物件の雰囲気を確認できることは大きなメリットです。
またコロナ禍以降、非接触での物件紹介の需要も高まっており、そうしたニーズにも対応できます。
不動産内覧動画撮影の流れ

興味はあるけれど、どうやって撮ればよいのか分からない、そんな不安を抱えている方も少なくないでしょう。
内覧動画の効果を引き出すには、計画的な撮影と丁寧な編集が不可欠です。しかし一度流れを把握してしまえば、誰でもスムーズに動画制作に取り組めます。
初めての方でも迷わず進められるように、動画撮影の具体的な流れを4つのステップに分けてご紹介します。
準備から編集までの手順をしっかり押さえて、自信をもって内覧動画を作成できるようにしましょう。
撮影内容を決める
動画撮影を始める前に、何をどのように撮るのかを明確にしておくことが大切です。
あらかじめ構成や撮影の流れを考えておくことで、撮影当日に迷うことなくスムーズに進めることができます。
基本的にアピールしたいポイントを決めておきましょう。
以下のような項目を押さえておくと、物件の魅力がしっかり伝わる動画になります。
物件ごとの特徴や売りにしたいポイントがあれば、そこを重点的に撮影できるように、事前に計画を立てることは必須です。
- 物件の外観と周辺環境(最寄駅からの道のりや街並みなど)
- エントランスや共用部分(オートロック、宅配ボックスなど)
- 各部屋の様子(間取り、広さ、収納の有無)
- キッチン・バスルーム・トイレなどの水回り
- 窓からの景色や自然光の入り方
- バルコニーや駐車場などの付帯設備
さらに動画のスタイルも事前に決めておく必要があります。動画の内容を考える際には、以下の点も決めておくと撮影がスムーズです。
- ナレーションはその場で話すか、後から録音するか?
- 映像にスタッフや人の姿を映すかどうか?
- 動画はどのシーンから始めるか
ナレーションを後で録音する場合は、現場で音声を気にせず撮影できます。また人を映さない方針であれば、ドアの開閉時など工夫が必要です。
このように動画の構成とスタイルを先に決めておくことで、無駄のない撮影が可能になります。
撮影に必要な機材を用意する

撮影に必要な基本的な機材は以下のとおりです。
- カメラ(スマートフォンでも高画質なものであれば問題ありません)
- 三脚(手ブレを防止するため)
- ワイドレンズ(狭い室内でも広く撮影できます)
- LEDライト(暗い部屋用)
- マイク(説明を入れる場合)
予算や撮影のクオリティに応じて、必要な機材を揃えましょう。初心者であれば、まずはスマートフォンと三脚、ポータブルLEDライトからスタートするのがおすすめです。
手ブレや明るさに気を付けて撮影する
物件紹介動画の品質を大きく左右するのが手ブレと明るさです。
どれだけよい内容を撮影していても、映像がブレているあるいは映像が暗いと視聴者に伝わりづらく、印象も悪くなってしまいます。
見やすく魅力的な映像を撮るためには、下記のポイントに注意しましょう。
撮影前には、室内をなるべく明るくすることが基本です。昼間であれば自然光を取り入れるためにカーテンを開け、すべての照明を点けておきましょう。
また手ブレを抑えるためには、以下の工夫が効果的です。
- 三脚やジンバルを使う
- カメラは両手でしっかり持ち、脇を締めて安定させる
- カメラを動かすときは体ごと移動する
- 手ブレ補正機能を利用する
できるだけ三脚を使い、固定した状態で撮影するのが理想です。歩きながら撮影する際は、ジンバル(スタビライザー)を使用するとスムーズな映像になります。
手持ちの場合でも、両手でしっかり持ち、脇を締めて体の中心でカメラを構えるとブレを抑えやすくなります。
腕だけで動かすとブレやすいため、カメラを移動させたいときは体全体で移動することを意識しましょう。
編集作業

物件動画の撮影が終わったら、次に大切なのが編集作業です。撮影した映像は、編集ソフトを使って不要な部分をカットし、テロップを入れて完成させます。
初心者向けには以下のような編集ソフトがおすすめです。
- iMovie(Mac向け・無料)
- Windows フォト(Windows向け・無料)
- Adobe Premiere Rush(有料だが使いやすい)
- Filmora(有料だが機能が充実)
撮ったままの映像をそのまま使うのではなく、編集によってより伝わりやすく、魅力的な動画に仕上げることができます。
編集の良し悪しによって、視聴者が最後まで動画を見てくれるかどうかが大きく変わります。
編集するときは、下記のポイントを押さえましょう。
- 動画は3分以内にまとめる
- テロップや字幕を活用して、わかりやすさをプラス
- BGM・ナレーションで雰囲気づくり
- メリハリのある構成で最後まで飽きさせない
不動産内覧動画は、自分で作ることができます。ただし物件の魅力をしっかり伝え、視聴者の印象に残すには、構成や見せ方の工夫が欠かせません。
撮影の手ブレや明るさの調整、音声のクリアさに注意が必要で、編集には思った以上に手間がかかります。動画制作に費やす時間がないなら、プロの力を借りるのも一つの方法です。
Funusualは、物件やブランドの魅力を的確に伝える高品質な映像表現に強みを持っています。
360度カメラやドローンを活用したダイナミックな撮影、ユーザーの検索意図を捉えたSEOに強いタイトル設計、SNSやWeb集客との連携まで、反響を生むためのノウハウをフル活用したご提案が可能です。
「もっと質の高い動画を作りたい」「ブランド価値の向上にもつなげたい」そんな方は、まずはお気軽に無料相談をご活用ください。
不動産内覧動画の配信方法

せっかく時間と労力をかけて制作した内覧動画も、届け方を間違えてしまうと効果は半減してしまいます。
内覧動画の配信にはいくつかの方法があり、それぞれ特長やメリットがあるため、ここからはそれぞれの配信方法の特徴や活用シーンについて詳しく解説します。
自社の営業スタイルや物件のターゲットに合った配信方法を見つけ、動画の効果を高めましょう。
アプリを利用したリアルタイム配信
ZoomやLINE、FaceTimeなどのビデオ通話アプリを使って、営業担当者が物件内を案内しながらリアルタイムで配信する方法です。
顧客からの質問にその場で答えられるため、コミュニケーションを取りながら物件を紹介できるメリットがあります。
リアルタイム配信では、下記のことに注意しましょう。
- 事前に通信環境を確認しておく
- 顧客が見たい場所などの要望を聞きながら進める
- 予備バッテリーを用意しておく
- 音声が聞き取りやすいように話す
YouTubeなどでの録画配信

撮影・編集した動画をYouTubeやInstagram、TikTokなどの動画サイトにアップロードし、顧客に視聴してもらう方法です。
動画を作成するには、時間と手間がかかりますが、一度アップロードすれば多くの顧客に見てもらえるメリットがあります。
たくさんの情報を伝えられる一方、すぐに質問に答えられないというデメリットもあります。
また動画配信では、以下のことを工夫するとよいでしょう。
- SEO対策として適切なタイトルや説明文をつける
- サムネイルは物件の魅力が伝わるものにする
- 物件情報や問い合わせ先を動画説明欄に記載する
自社サイトやホームページで配信
自社のホームページや物件紹介ページに動画を埋め込む方法です。
自社のホームページや物件紹介ページに内覧動画を載せることで、写真だけでは伝わりにくい物件の雰囲気まで見せることができます。
動画があることで、お客様は物件について事前に詳しく知ることができ、検討を進めやすくなります。
配信する際には、次のような点に気をつけましょう。
- 動画の読み込みが遅くならないように、画質は適度に調整する
- スマートフォンで見ても問題ないように、画面サイズや表示方法に配慮する
- ページ内で目に付きやすい場所に動画を配置する
- すぐに問い合わせできるよう、動画の近くにボタンを設置する
こうした工夫を取り入れることで、動画を見るお客様にとって便利でわかりやすいページになります。また営業担当者の負担も軽くなるため、ほかのお客様への対応にも余裕が生まれます。
動画をうまく使えば、物件の魅力をしっかり伝えながら、成約までの流れを自然に導けるようになるでしょう。
不動産内覧動画を成功させるポイント

動画を作ったものの、効果が感じられず、見てもらえているか不安と感じる方は少なくありません。動画制作は始めやすくなった一方で、しっかりと成果につなげるにはコツが必要です。
見やすさとわかりやすさ、最後まで飽きずに視聴してもらう工夫、この3つを意識するだけで動画の印象は大きく変わります。
ここでは、視聴者にしっかり届く内覧動画に仕上げるためのポイントを具体的に解説します。少しの工夫で、動画の印象も効果も帰ることが可能です。
動と静を組み合わせて見やすくする

不動産内覧動画では、常にカメラを動かしてしまうと、視聴者が疲れてしまうことがあります。
そこで重要なのが動きと静止のバランスです。テンポ良く映像を見せつつ、要所ではしっかり止めることで、落ち着いて情報を伝えることができます。
映像にメリハリをつけることも大切です。アップと引きの画角を切り替え、途中で静止画を挿入すると、飽きずに最後まで見てもらいやすくなります。
さらに今どの部屋を紹介しているかが分かるように、間取り図を差し込むのも効果的です。
動画制作では、あくまで視聴者の見やすさを第一に考えることがポイントです。
どれだけ映像がきれいでも、見続けられなければ魅力は伝わりません。伝えたい内容が多すぎる場合は、メッセージをひとつに絞ることで、情報が整理され伝わりやすくなります。
テロップを入れてわかりやすくする
賃貸物件の魅力をしっかり伝えるには、映像だけに頼らず、テロップや字幕をうまく活用することが大切です。
適度に字幕を挿入することで、視聴者の理解が深まり、伝えたいポイントをより明確に示すことができます。
映像にナレーションを加えている場合でも、話している内容をそのまま字幕にすることで、視聴者が内容をよりしっかりと受け取れるようになります。
特に、音声を出せない環境で視聴しているユーザーにも配慮できる点は大きなメリットです。
さらに部屋の広さや収納スペースの容量、設備の特徴など、数字や具体的な情報はテロップで表示すると分かりやすくなります。
視覚的に補足することで、映像では拾いきれない細かい情報まで伝えることが可能です。
ただ字幕を入れるだけでなく、表示するタイミングや言葉選びにも気を配ることで、より伝わる動画に仕上がります。視聴者にとって見やすく、理解しやすいコンテンツを目指していきましょう。
時間が長すぎないように編集する
不動産の内覧動画は、視聴者の集中力を意識してコンパクトに仕上げることが大切です。理想の長さは3〜5分程度です。
必要な情報をしっかり伝えつつも、見やすい長さに収めることで、最後まで視聴してもらえる確率が高まります。
特に冒頭30秒は、視聴者の印象を左右するので重要です。物件の魅力的な部分や注目ポイントを最初に見せることで、続きを見たいと思わせる導線がつくれます。
動画の中にあれもこれもと詰め込むと、どうしても尺が伸びてしまいがちです。情報はしっかり取捨選択し、余分なシーンは思い切ってカットしましょう。スッキリとまとまった動画は、視聴者にとっても理解しやすくなります。
動画が長くなってしまう場合は、チャプターを分けるなどの工夫を加えると、見たい部分だけを効率よくチェックできるようになります。これにより、視聴者のストレスを軽減しつつ、必要な情報を届けることが可能です。
また場面ごとのテンポを意識することもポイントです。各シーンの時間を短めに設定し、テンポよく映像が切り替わることで、飽きずに見てもらえる動画に仕上がります。
不動産内覧動画を制作するときの注意点
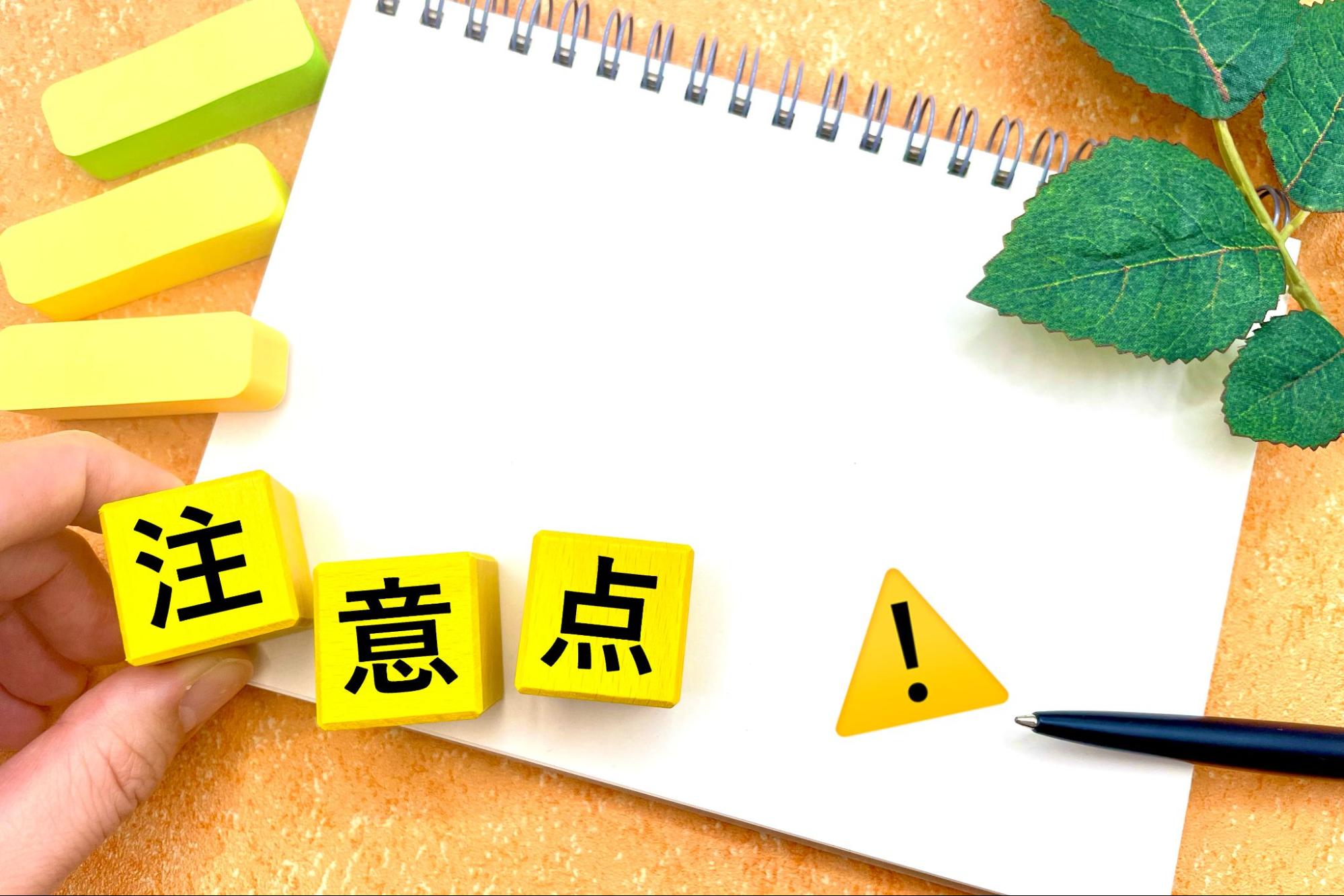
不動産内覧動画を作る際には、ただ魅力的な映像を撮ればよいというわけではありません。法律や業界のルールを理解し、適切に対応することがトラブルを防ぐうえで欠かせないポイントになります。
特に気をつけたいのが「おとり広告」や「誇大表示」といった表示ルール違反です。知らず知らずのうちに法律を逸脱してしまうと、後から指摘や罰則を受けるリスクもあるため、注意が必要です。
不動産業界で内覧動画を安全に活用していくために押さえておくべき法律や規約をわかりやすく紹介します。正しい知識をもって制作に臨めば、心配なく動画を運用していけるはずです。
おとり広告にならないように気を付ける
不動産内覧動画を制作するうえで、まず注意したいのがおとり広告に該当しないようにすることです。
おとり広告とは、実際には取引できない物件を宣伝して消費者の関心を集める、不当表示の一種とされています。
例えばすでに契約済みの物件をそのまま掲載し続けてることや、実際よりも魅力的に見せすぎることで、意図せずおとり広告になる可能性もあります。
これは悪意がなくても、削除の遅れや確認不足によって発生してしまうケースもあるため、日頃から丁寧な運用が必須です。
特にSNSに掲載した動画や画像は、紙媒体と同様に広告とみなされる点にも注意が必要です。
投稿の期限があいまいになりやすく、削除を忘れることで存在しない物件を紹介していると判断されるリスクも否定できません。
また動画編集の段階でも気をつけましょう。実際の広さ以上に見えるレンズを使うことはもちろん存在しない設備を映すことや、周辺環境のマイナス面をあえて避けて撮影すると、誇張表現になります。これは視聴者に誤解を与える原因となります。
内覧動画は、実物とできる限り近い印象で見せることが大切です。正確な情報提供を心がけることで、信頼を損なわずに集客へつなげることができるでしょう。
宅地建物取引業法を意識する

不動産業に携わるうえで重要なのが、宅地建物取引業法(宅建業法)の理解と遵守です。
この法律は、取引の透明性を確保し、購入者や借主の利益を守るために定められています。不動産広告における表現も、その対象として明確に規制されています。
まず知っておきたいのが、誇大広告の禁止です。物件の立地や広さ、価格などを実際以上に良く見せる表現は認められていません。
事実と異なる内容で興味を引こうとする行為は、信頼を損なう大きなリスクにつながります。
次に注意したいのが、広告開始時期の制限です。特に新築物件においては、建築確認や開発許可の申請が通っていない段階での広告は禁止されています。
設計の変更などが発生した際に、誤った情報が消費者に伝わる恐れがあるため、慎重な対応が求められます。
また取引態様の明示も義務付けられている項目のひとつです。自己取引か代理か、媒介かを明記することで、視聴者が安心して物件を検討できるようになります。
動画を使った広告でも宅建業法の対象であることを忘れてはいけません。動画内には、宅建業者名や免許番号、物件の所在地・面積・価格などの基本情報を正しく表示する必要があります。
建築年数や構造といった重要事項も、誤解を生まないように丁寧に説明しましょう。
これらのルールを守らなかった場合、指示処分や業務停止、最悪の場合は免許取り消しという厳しい処分を受ける可能性もあります。
動画制作においても法令を意識することが、信頼される不動産業者としての第一歩です。
公正競争規約もチェックする

公正競争規約とは、各業界が自ら定めた広告に関する自主的なルールのことです。不動産業界でもこの規約が存在しており、高額な取引が発生することの多い分野だけに、他業種と比べて特に厳格な内容となっています。
法的な拘束力こそありませんが、規約違反が発覚すれば罰則や罰金の対象になることもあります。トラブルを防ぐためにも、事前にルールを把握しておくことが重要です。
例えば「徒歩〇分」の表記には明確な基準があります。この表示は、物件から最寄り駅やバス停までの距離を80メートル=1分で換算して算出します。
信号や坂道など現実の移動環境も加味して、実際の感覚に近い時間を記載するようにしましょう。表記と体感がかけ離れていると、虚偽広告とみなされることもあります。
また文字サイズや色にも規定があります。広告の文字は基本的に7ポイント以上で表示する必要があり、視認性の高い色を使って、誰が見ても分かりやすいようにすることが求められているのです。文字が小さすぎることや、色が背景と同化してしまうようでは、情報が正しく伝わりません。
使ってはいけない表現も明確に定められています。例えば「最高」「完ぺき」「絶対に得」など、過度に期待を持たせる言葉は使用禁止です。これらの言葉は誤解を招きやすく、トラブルのもとになる恐れがあります。
このように、不動産広告は法律に加えて業界独自のルールに基づいて運用されています。適切な情報提供を心がけ、ユーザーが安心感を持って物件を検討できる環境を整えることが、信頼される広告運用の基本です。
不動産の内覧動画は、ただ見栄えのよい映像を作ればよいというわけではありません。
おとり広告のリスクや、宅建業法・公正競争規約への理解が求められるため、法令を意識した適切な情報発信が重要です。
これらのルールをすべて自社で把握し、遵守しながら動画を制作するのは簡単なことではありません。特に初めて動画に取り組む方にとっては、不安もあるでしょう。
Funusualでは、不動産業界特有のルールや広告表現を熟知し、安心感を持って公開できる内覧動画を一から丁寧に制作いたします。
法令に配慮した原稿作成や正確な情報表現はもちろん、視覚的な美しさと信頼性を両立させた映像編集が可能です。
「動画を使って集客したい」「ブランドイメージも大切にしたい」そんなお悩みをお持ちの方は、まずは無料相談からお気軽にご連絡ください。
不動産内覧動画の事例

実際に成功している不動産内覧動画の事例を紹介します。ぜひ今後の動画作成の参考にしてください。
YouTubeチャンネル「Gハウスのルームツアーチャンネル」
引用元:www.youtube.com/@Ghouse-osaka
大阪の高性能住宅を建てる大阪のビルダーであるGハウスが手がけたオシャレで高性能な住宅を、実際の建築事例をもとにご紹介するYouTubeチャンネルです。
経験豊富なスタッフが、間取りやデザインと性能や、住み心地などをルームツアー形式で分かりやすく解説しています。ご家族の構成やライフスタイルに合わせた世界に一つだけの住まいを多数取り上げているのが特徴です。
大阪市内ならではの狭小住宅や3階建てからビルドインガレージ付き住宅、ホテルライクな高級邸宅や二世帯住宅など、多彩な事例を紹介しており、オーナー様のこだわりが詰まった住まいを通じて、どんな暮らしができるのかがリアルに伝わる内容になっています。
このチャンネルでは、見た目のデザインだけでなく、断熱性・気密性など住まいの性能面もしっかりと解説しているのが特徴で、デザインと性能の両立がもたらす豊かな暮らし、その可能性を知ることができます。
YouTubeチャンネル「あなたの理想不動産」
引用元:www.youtube.com/@_anariso_
主に東京都内の物件を紹介する人気チャンネルで、登録者は49万人以上です。不動産会社に勤務する営業マンが紹介物件の短所もかくさず、上司の愚痴も混ぜながら物件を紹介していきます。
LINE誘導のQRコードが表示されており、個人チャンネルでありながら企業の営業活動と連動していることがわかります。
さらに運営元の株式会社ZENTENは物件検索サイトも立ち上げ、LINEによる問い合わせ対応や引越し費用プレゼントキャンペーンなど、動画×SNS×顧客接点を活かした戦略を展開しているのが特徴です。
従来の不動産ポータルサイトに不満を持つZ世代に対し、視覚情報で直感的に物件を選べる新たなスタイルを提示しており、不動産業界の次世代モデルといえます。
センスある不動産内覧動画を制作したいなら

不動産内覧動画は、自社でスマートフォンや家庭用カメラを使って制作することも可能です。しかし見やすさと伝わりやすさ、さらに印象に残るかといった観点で、素人制作には限界があるのも事実でしょう。
照明の当て方やカメラアングル、テロップやBGMの工夫に動画タイトルの付け方など、どれも物件の魅力を引き出すためには欠かせない要素です。
実際にやってみると想像以上に手間も時間もかかります。加えてスマートフォン動画ではどうしても仕上がりに素人感が残ってしまい、せっかくの物件価値を十分に伝えきれないこともあります。
Funusualは、業界に精通したプロフェッショナルチームが企画から撮影・編集・公開までを一貫してサポートしています。
360度カメラやドローンなどの機材を駆使し、物件のスケール感や雰囲気を最大限に引き出す映像を制作します。
「動画のクオリティを上げたい」「もっと反響が欲しい」「自社制作が難しくて困っている」そんなお悩みをお持ちの方も、まずは無料相談からお気軽にご連絡ください。
Funusualが、成果に直結する不動産内覧動画で、集客力を一段と高めるお手伝いをいたします。













