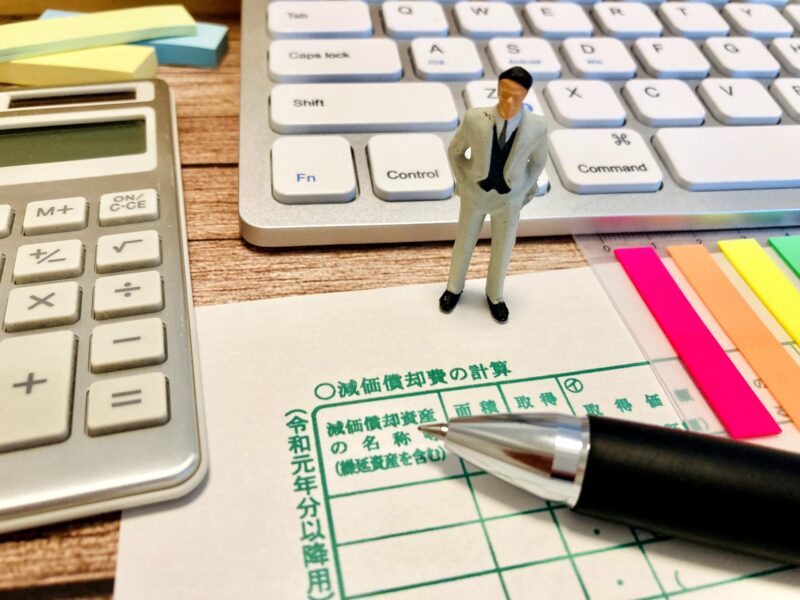PR動画を制作したいが、「費用は経費として処理できるの?」「資産計上は可能?」と迷う方もいるのではないでしょうか。広告費として処理されることが多い動画費用ですが、実は内容や目的によっては資産として計上できるケースもあります。
本記事では、PR動画の資産計上の可否や勘定科目の選び方、仕訳や会計処理のポイントをわかりやすく解説します。経理や上層部との調整に不安を感じている広報担当者の方にも、参考になる情報です。
PR動画の費用処理に関して判断に迷ったときの道しるべとして、ぜひご活用ください。
PR動画は資産計上できる?

「PR動画は広告なんだから、広告宣伝費として経費処理するしかないのでは?」と考えている方もいるかもしれません。
実際、ほとんどの動画制作費は広告費として一時費用に分類されます。しかし、一定の条件を満たす場合には、資産としての計上も可能です。
資産計上とは、将来的に価値を生み出す支出を資産として扱い、複数年にわたって償却していく会計処理のことです。
例えば、自社のブランド価値を長期的に高めることを目的としたPR動画や、継続的に営業資料として活用されるケースもあります。
こうした場合は、広告費ではなく、繰延資産や無形固定資産として計上できる可能性があるようです。
国税庁の見解でも、企業が制作するPR用映画フィルムなどが固定資産として扱える場合があると示されています。
つまり、制作費用の内容や使用期間によって、会計処理の考え方が変わります。
すべてのPR動画が広告費として処理されるとは限りません。この点を理解することが、正しい会計処理を行うための第一歩です。
動画制作における勘定科目の考え方

PR動画の費用を正しく会計処理するためには、まずその勘定科目をどう設定するかを明確にしておく必要があります。
科目の選定を誤ると、税務調査の対象になる可能性があるほか、社内での予算管理にも悪影響を及ぼすおそれがあります。
ここでは動画の目的と判断基準に分けて詳しく見ていきましょう。
特徴や目的
勘定科目の選定では、動画を制作した目的が重要です。例えば、消費者へのブランド訴求や商品認知を高めることを主眼としたPR動画であれば、広告宣伝費として処理されることが一般的です。
一方で企業の採用活動や営業支援で長期にわたって使用されるような動画の場合には、単なる広告費ではなく、繰延資産や無形固定資産として認識される場合もあります。
さらに業務用の教育動画やマニュアルとしての用途であれば、企業内部の資産としての性格が強くなり、仕訳にも注意が必要です。
このように単に動画だから広告費と一括りにするのではなく、その動画が何のために制作されたのかの目的の明確化が、正しい勘定科目選定の第一歩となります。
選ぶ基準

勘定科目を選定する際は、使用目的に加えて、いくつかの視点を踏まえて判断する必要があります。
まず着目すべきは、その動画がどれくらいの期間にわたって使用されるのかです。例えば、1年未満の短期使用を前提とした動画は、費用として一括処理するのが妥当です。
一方で、1年以上にわたって継続的に使用される場合は、資産計上の対象となることがあります。
また、動画制作にかかる金額も判断材料の一つです。特に100,000円未満の小規模な動画であれば、消耗品費として処理されることが多く、資産として管理する必要は薄くなります。
しかし500,000円や1,000,000円規模の制作費となる場合、その内容や目的によっては、固定資産や繰延資産としての取り扱いが適切です。
加えて動画にプログラミングやカスタマイズ性が含まれている場合、会計上はソフトウェアとして扱われ、無形固定資産の一種として管理される可能性もあります。
このように、使用期間や金額、機能性など複数の観点から総合的な判断が大切です。
PR動画の制作費用の仕分け

PR動画を制作する際には、さまざまな工程に対してコストが発生します。
それぞれの費用を一括して広告宣伝費で処理するのではなく、発生した項目ごとに分けた仕訳が、適切な会計処理には不可欠です。
このセクションでは、動画制作の代表的な費用項目に関して、その仕訳方法と勘定科目の考え方を解説します。
動画制作費用と撮影費
動画の企画や構成、撮影にかかる費用は、通常広告宣伝費に分類されます。
ただし、これが自社内での活用や社内向けの研修用動画であれば、広告ではなく業務用資産として扱う必要が出てきます。
特に撮影に外部業者を利用した場合は、外注費や業務委託費としての処理が適切です。
さらに、こうした動画が長期的に使用される予定であれば、会計処理のうえでは繰延資産として資産計上されるケースも考えられます。
機材費
撮影に使用するカメラや照明機材などを新たに購入した場合、それは備品として有形固定資産に該当する可能性があります。
購入額が100,000円以上であり、かつ1年以上使用する場合には、減価償却資産として処理する必要があります。
一方で、短期間かつ少額のレンタル機材費などは、地代家賃や消耗品費としての処理が一般的です。
このように、機材に関する費用は、金額や使用期間によって会計処理が異なります。
そのため、単に動画制作の一環として一括処理するのではなく、仕訳の段階で明確に区分しておくことが望ましいです。
編集ソフト代

動画編集のためにソフトウェアを購入した場合、その金額や使用方法によって勘定科目が異なります。
一般的には購入価格が100,000円未満であれば消耗品費として扱われ、100,000円以上で1年以上使用する場合は、ソフトウェアとして無形固定資産に計上されるのが一般的です。
また、月額利用のサブスクリプション型サービスを利用している場合は、通信費や支払手数料として処理されることもあります。
ソフトの種類や契約形態に応じて勘定科目を変える必要があるため、会計処理の柔軟さが求められる項目です。
PR動画の仕訳には費用項目ごとの内容や金額、使用目的を見極めて、適切な勘定科目の選定も重要です。
とはいえ、会計処理のルールをすべて自社だけで対応するのは難しいと感じる方も少なくないのではないでしょうか。
Funusualでは、動画の活用目的や会計処理まで見据えた提案を行っており、広報担当者と経理担当者の両方に納得していただける動画制作支援を心がけています。
制作費用の適正化や減価償却の観点も踏まえ、企業の資産価値を高める動画活用を実現します。
さらに、社内稟議や予算承認がスムーズに進むよう、コスト面と活用効果を明確にしたご提案も可能です。
長期的に使える動画を資産として計上したい方、会計処理と連携した動画制作を進めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
目的ごとの勘定科目の違い

同じPR動画であっても、その使用目的によって会計上の勘定科目は大きく異なることがあります。
このセクションでは、代表的な目的別に分類し、それぞれの会計処理の考え方を整理します。
商品やサービスのPR
一般消費者や取引先に向けて、商品やサービスの認知向上や購入促進を目的に制作された動画は、多くの場合広告宣伝費として会計処理されます。
これは不特定多数に向けた情報発信であり、販促費用と見なされるためです。
例えば、SNS広告用の動画やYouTubeチャンネルに掲載するPR映像などがこれに該当します。
このような動画は明確に広告活動と結びついており、資産計上の対象とはならず、費用としてその期に一括で計上されるのが原則です。
広告収入
PR動画を使って自社の広告収入をえることを目的としている場合、その動画は単なる販促物ではなく、自社の収益を生み出す資産としての性質を持つ可能性があります。
例えば、YouTubeで配信した動画から広告収入を得ている場合、その動画は売上に直接結びつく媒体です。
このようなケースでは、無形固定資産として資産計上する選択肢も検討されます。
このように、広告収入を目的とした動画制作は、動画が果たすビジネス上の役割によって扱いが変わります。
単なる広告宣伝費ではなく、将来的な収益源として評価されるケースもあるでしょう。
制作費用
動画の制作費用そのものも、目的や活用方法によって処理の仕方が大きく異なります。外部に委託して制作したPR動画でも、その目的によって処理方法は異なります。
広告目的なら広告宣伝費、業務用資料なら繰延資産や無形固定資産として扱うのが一般的です。
また制作費に含まれる項目は企画費やディレクション費、編集費、ナレーション費など多岐にわたります。
そのため、それぞれを明細にしておくことが、後々の会計処理や税務調査への備えにもつながります。
PR動画の会計処理のポイント

PR動画の制作に関わる会計処理は、広告費として一括処理するだけでは済まないケースもあります。
特に近年では動画の資産性が問われる場面も増えており、勘定科目の選定だけでなく、会計処理の基本概念を理解しておくことが重要です。
このセクションでは、動画費用がどのような資産として扱われるのか、どのような条件で処理方法がわかれるのかを解説します。
無形固定資産のソフトウェア
ソフトウェアとは通常、プログラミングなどが施された無形資産を指します。
そのため、PR動画自体にプログラミング的な機能やシステムとしての再利用性が含まれていない場合には、この科目には該当しないと考えるのが一般的です。
動画制作でこの勘定科目を使うのは、よりソフトウェア的な性質を持つケースに限られます。
例えば、カスタマイズ可能な動画テンプレートやインタラクティブ機能を備えたWebシステム型動画などが該当します。
こうした機材に関しても、資産としての扱いが適切かどうかを検討する必要があるでしょう。
有形固定資産

撮影に使用したカメラや照明、収録ブースなどを新たに購入した場合、これらは有形固定資産として扱うのが一般的です。
特に購入価格が100,000円以上で、使用期間が1年以上に及ぶものは、減価償却資産として管理する必要があります。
動画制作自体は無形ですが、それに付随する物理的な資産が関与している場合、その会計処理も忘れてはならないポイントです。
繰延資産
PR動画が長期間にわたって使用される予定であり、その内容が企業のブランド構築や営業活動に長期的な効果をもたらすと見なされる場合があります。
このようなケースでは、繰延資産としての会計処理が可能です。
繰延資産とは、本来は発生時に費用計上されるべき支出を、将来の複数期間にわたって配分して償却する会計手法です。
繰延資産に該当するには将来の収益に貢献する支出であること、発生時期と収益が対応していないこと、金額が明確であることなどの条件を満たす必要があります。
動画を長く使い続ける予定がある場合には、税理士などの専門家と相談のうえ、繰延資産処理を検討する価値があります。
PR動画の制作費用での注意点

PR動画の費用処理は項目ごとに分類し、目的を明確にしたうえで仕訳が基本ですが、実際の業務では細かい判断に迷う場面も少なくありません。
特に少額費用の取り扱いや、税務調査での証拠管理や専門家への確認など、各観点で注意が必要です。
このセクションでは、実務上の落とし穴になりやすいポイントを整理します。
100,000円未満のソフトは消耗品費
動画編集やサムネイル制作に使用するソフトウェアの費用が100,000円未満の場合、その支出は資産計上の対象にはなりません。
一般的には、消耗品費として費用処理されます。これは会計基準で100,000円未満の物品、ソフトは耐用年数や資産性の観点から消耗品扱いになるルールに基づいています。
もし、これを誤って資産計上してしまうと、帳簿上の資産額が実態より多くなってしまうため注意が必要です。
会計処理に役立つツールの導入も検討
PR動画の制作にはさまざまな業者や工程が関わり、請求書や契約書も複雑化しがちです。
会計処理をスムーズに行うためには、クラウド会計ツールや経費精算システムなどを導入しておくと、証憑管理や科目仕分けが明確になります。
特に複数部署が関与する場合には業務フローを標準化し、科目の選定ルールを明文化しておくことで、経理部門との連携もスムーズになります。
ツールの活用で、属人的な判断ミスを減らす効果も期待できるでしょう。
不明点は必ず税理士や会計士を通す

動画費用の処理には、金額の大きさや目的によって会計処理が微妙に変わるため、迷った場合は必ず税理士や公認会計士への相談が重要です。
特に資産計上とするか費用処理とするかの判断は、税務調査で重視されるポイントの一つです。
自己判断で処理を進めてしまうと、後からの修正や課税リスクに発展する可能性があります。
プロの意見を取り入れながら処理を進めることで、法令順守と実務の円滑な遂行が両立可能です。正確な処理のためにも、専門家と連携して進めていきましょう。
PR動画の費用処理は仕訳を誤れば税務リスクにつながる一方で、的確な処理ができれば、企業の信頼性や財務管理の精度向上にもつながります。
Funusualでは、会計処理の視点も意識したBtoB向け動画制作を得意としています。動画の目的や活用期間を踏まえたうえで、仕訳しやすい構成や運用しやすい仕様をご提案が可能です。
動画を作るなら会計処理まで安心感を持って任せたい方、広報と経理どちらの視点にも対応してくれる会社に依頼したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
PR動画の制作費用を経費にするために必要なこと

PR動画の制作費を広告宣伝費などの経費として正しく処理するには、単に支払いを済ませるだけでは不十分です。
経費として計上するためには、支出の記録や分類、計上時期の判断を的確に行う必要があります。
このセクションでは、制作費用を正しく経費処理するための基本的なステップを紹介します。
費用発生状況を把握する
まず大切なのは、PR動画制作に関連するすべての費用の発生状況の正確な把握です。
企画や撮影、編集やナレーションなど費用が発生するタイミングや取引先が異なるため、各工程での支出内容と時期を明確に記録しておくことが重要です。
特に複数の外注先が関与する場合には、請求書と納品物の照合も徹底する必要があります。
適切な勘定科目に振り替える
費用の内容を把握した後は、それぞれの項目に適した勘定科目へ振り分けます。
広告を目的とした動画であれば広告宣伝費、社内資料であれば業務委託費や消耗品費などが該当する場合もあります。
目的ごとに勘定科目を使い分けることは、会計処理の透明性を高めるうえで重要です。また、税務調査に備えるうえでも有効な対応でしょう。
費用の発生時に正しい科目で記帳されていないと、後からの修正や確認作業に手間がかかるため、経理部門との連携も欠かせません。
費用の計上時期を判断する

最後に重要なのが、費用の発生時点と計上時期を一致させることです。
例えば動画制作の契約を年末に結び、納品が翌期になる場合には、その費用をどちらの会計年度に含めるかを正しく判断しなければなりません。
制作の進行状況によっては、前払費用や未払金として処理する必要がある場合もあります。
また請求書や納品書だけでなく契約書の内容や納品実態をもとにして、費用の帰属期間の合理的な判断が、経費処理の正確性を保つポイントです。
PR動画のわかりやすい仕分けで資産計上を明確にしたいなら

ここまでご紹介してきたように、PR動画の制作費用は広告費として経費処理すればよいとは限りません。
目的や内容、金額、活用期間などに応じて適切な判断が求められます。
実際には広告宣伝費として処理すべき動画もあれば、繰延資産や有形固定資産、あるいは無形固定資産として処理すべきケースもあります。
しかしこうした判断には会計知識だけでなく、動画の内容や使用意図、さらに企業の会計方針まで理解していなければなりません。
広報担当者やマーケティング部門が単独で判断するには限界があるのも事実です。だからこそ、動画制作と会計処理の両方に精通した専門家への相談が、適切な選択肢です。
PR動画の仕訳に不安がある場合は、経験豊富な動画制作会社や税理士と連携し、自社にとって妥当な処理方法を導き出しましょう。
Funusualでは、動画の表現力と会計処理のしやすさを両立したPR動画制作をお手伝いしています。
BtoB企業様の目的や課題に寄り添いブランディングや採用、営業支援など多様なシーンで活用できる動画を企画、制作しています。
制作工程ごとの費用明細を丁寧に整理し、経理部門との円滑な連携を可能にする体制です。
PR動画を通じて企業の魅力を伝えたい、仕訳に不安がなく動画制作を進めたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。貴社の目的に沿った動画プランをご提案いたします。