新入社員のオンボーディングに、動画を活用する事例が増えています。
新入社員の早期離職を防止し、戦力化までの時間を短縮するために、効果的なオンボーディングは極めて重要です。
一方で、オンボーディング担当の人手不足に悩む企業も多く、動画を活用した省力化が求められています。
本記事では、オンボーディング動画の活用シーンや制作方法など、動画の導入前に知っておくべきポイントを解説します。
オンボーディング動画の導入を検討している方の参考になれば幸いです。
オンボーディング動画とはどのようなものか

オンボーディング動画とは、新入社員に対する研修などで用いられる動画です。
オンボーディングとは、船や飛行機に乗り込むことを意味するon boardに由来し、新しい乗組員を迎えるための施策全般を指しています。
オンボーディングは新入社員の離職防止や定着促進、また即戦力化を目的として行われ、新卒社員だけでなく中途採用も対象となります。
企業は採用に多くのコストを割いており、せっかく入社した社員が早期離職してしまうことは、大きな損失です。
また、即戦力となることを期待した中途採用の社員が、新しい業務に馴染めないケースも少なくありません。
企業の理念や事業内容を理解し、円滑に仕事に加わるためにもオンボーディングは不可欠で、そのために動画を活用する企業は少なくありません。
近年では、ほとんどの労働者が日常的にスマートフォンで動画を視聴しており、オンボーディングにも動画は積極的に活用されています。
Funusualでは、丁寧なヒアリングを通じて、企業ごとの文化や導入背景に合わせた動画を企画・制作しています。
「どのような構成が効果的かわからない」「限られた予算で高品質な動画を作りたい」といったお悩みにも、プロの視点で適切なご提案が可能です。
オンボーディング動画の導入をご検討中の方は、まずはお気軽にFunusualにご相談ください。
オンボーディング動画の活用方法

オンボーディング動画には、目的や活用シーンに応じたさまざまな種類があります。
それぞれのテーマごとに専用の動画が作られ、新入社員のオンボーディングに活用されています。
オンボーディングの具体的な活用シーンは、主に次の3つです。
- 業務マニュアル
- 実務の知識・スキル習得
- 会社の理念・文化の伝達
それぞれの内容を解説します。
業務マニュアル
毎日行う業務を円滑に進めるために、各企業には業務マニュアルが不可欠です。
従来は文字ベースの業務マニュアルがほとんどでしたが、これを補完・代替する目的で動画マニュアルを導入する企業が増えています。
動画を活用すると、文字だけでは理解しづらい工程を視覚的に把握でき、従業員の理解が深まります。
また、わからない部分を繰り返し何度も再生すれば、記憶の定着効果も高くなるでしょう。
一度制作した動画マニュアルは、新入社員が入るたびに何度も使えるため、新人研修の省力化にもつながります。
実務の知識・スキル習得

業務上必要な知識やスキルの習得のためにも、動画マニュアルが役立ちます。
習得したいスキルの内容にあわせて、作業する手元をアップで撮影した動画や、PC画面を録画した動画マニュアルが一般的です。
従業員は、習得したいスキルに応じて動画マニュアルを選び、好きなタイミングで何度も視聴できます。
動画マニュアルを見ながら自分でも実際に作業を進めることで、スキルをより早く習得できるでしょう。
動画マニュアルは何度でも再利用できるため、マニュアル集自体が企業の大きな財産になっていきます。
会社の理念・文化の伝達
新入社員に会社の理念や文化を理解してもらうためにも、オンボーディング動画は活用されています。
代表メッセージや会社沿革をストーリー仕立てでドラマチックに演出すれば、新入社員に会社への誇りを持ってもらえるでしょう。
先輩社員のインタビューを交え、数年後の理想像を描けるよう工夫することで、仕事へのモチベーション向上につなげられます。
このような動画は、オンボーディングだけでなく採用活動にも転用可能です。
オンボーディング動画の事例

ここでは、実際に活用されているオンボーディングの事例を紹介します。
動画の目的や予算にあわせてさまざまなタイプの動画がありますので、自社のオンボーディングにどのような動画が適しているかイメージしてみましょう。
アパレルショップの従業員向け動画
全国にファッションビルを展開する企業の、アパレルショップ従業員に向けたオンボーディング動画は、従業員の意識向上を促す動画として参考になります。
店舗のブログやSNSなど、Webを通じた潜在顧客へのアプローチの重要性を説明する内容です。
単に業務の内容を説明するだけでなく、それがどのように店舗の利益や従業員のやりがいにつながっていくかを強調しており、従業員のモチベーションアップを促しています。
動画は全編アニメーションで構成されており、撮影が必要ないため、制作費用は抑えられているでしょう。
大手メーカーの新入社員向け動画
知名度の高い大手電子機器メーカーでは、新入社員に向けたオンボーディング動画で社員のモチベーションを高めています。
数多くのイノベーションを生み出してきた世界的企業としての誇りを強調し、映画のようなドラマチックな演出が印象的です。
社員のモチベーションを高め、会社への誇りや愛社精神を醸成することが目的です。担当者が壇上でしゃべるだけのプレゼンテーションに比べて、新入社員の感情を揺さぶる効果は極めて高いでしょう。
ダイナミックなCG演出だけでなく、複数の俳優を起用しており、制作費用はかなり高くなっていると考えられます。
オンボーディング動画のメリット

オンボーディング動画を導入する前に、そのメリットを正しく理解することが重要です。
メリットを理解したうえで、明確な目的を持って動画を企画することが重要です。オンボーディング動画の主なメリットを、以下の4つの点から解説します。
- 社内研修の品質を標準化できる
- 場所・時間を選ばず学習できる
- わからない点を繰り返し確認できる
- 教育担当者の負担減につながる
社内研修の品質を標準化できる
従来は担当者の経験や能力に依存していたオンボーディングを、動画を用いることで標準化できます。
新人研修の担当者が離職したり、別の部署に異動したりして、研修の品質を保てなくなってしまうケースは少なくありません。
また、担当者によって研修の質が異なると、新入社員の満足度低下にもつながります。オンボーディング動画なら、誰が受講しても同じ内容で研修を受けられます。
研修の属人化を予防し、業務の効率化が可能です。
場所・時間を選ばず学習できる
オンボーディング動画を視聴してもらう環境は、研修中だけとは限りません。新入社員に動画を送信し、都合のよいタイミングで見ておいてもらうこともできます。
業務の空き時間でオンボーディング動画を視聴してもらえば、担当者によるオフラインの研修も効率的に進められるでしょう。
業務マニュアルなどの動画であれば、通勤時間や休憩時間をスキルアップに活用できます。
わからない点を繰り返し確認できる

動画のメリットは、見たい箇所を何度も繰り返して再生できることです。一度見ただけでは理解しにくい部分も、何度も繰り返し確認すれば理解を深められるでしょう。
特に動画マニュアルでは、社員がスキルを習得するまで何度も視聴できることが大きなメリットになります。
先輩社員に質問しなくても、動画マニュアルを繰り返し見て確認できれば学習の効率化につながるでしょう。
教育担当者の負担減につながる
オンボーディング施策を動画化することで、教育担当者の負担も大幅に軽減できます。
従来は研修で一つ一つ説明していたことが、動画を視聴してもらうだけで済めばリソースの削減につながるでしょう。
動画マニュアルを活用してもらえば、新入社員から質問を受ける機会も削減され、教育担当者はより応用的な指導に注力できます。
一度作成した動画は何度も再利用できるため、頻繁に中途採用を実施している企業では、特にオンボーディング動画のメリットは大きいでしょう。
オンボーディング動画のデメリット
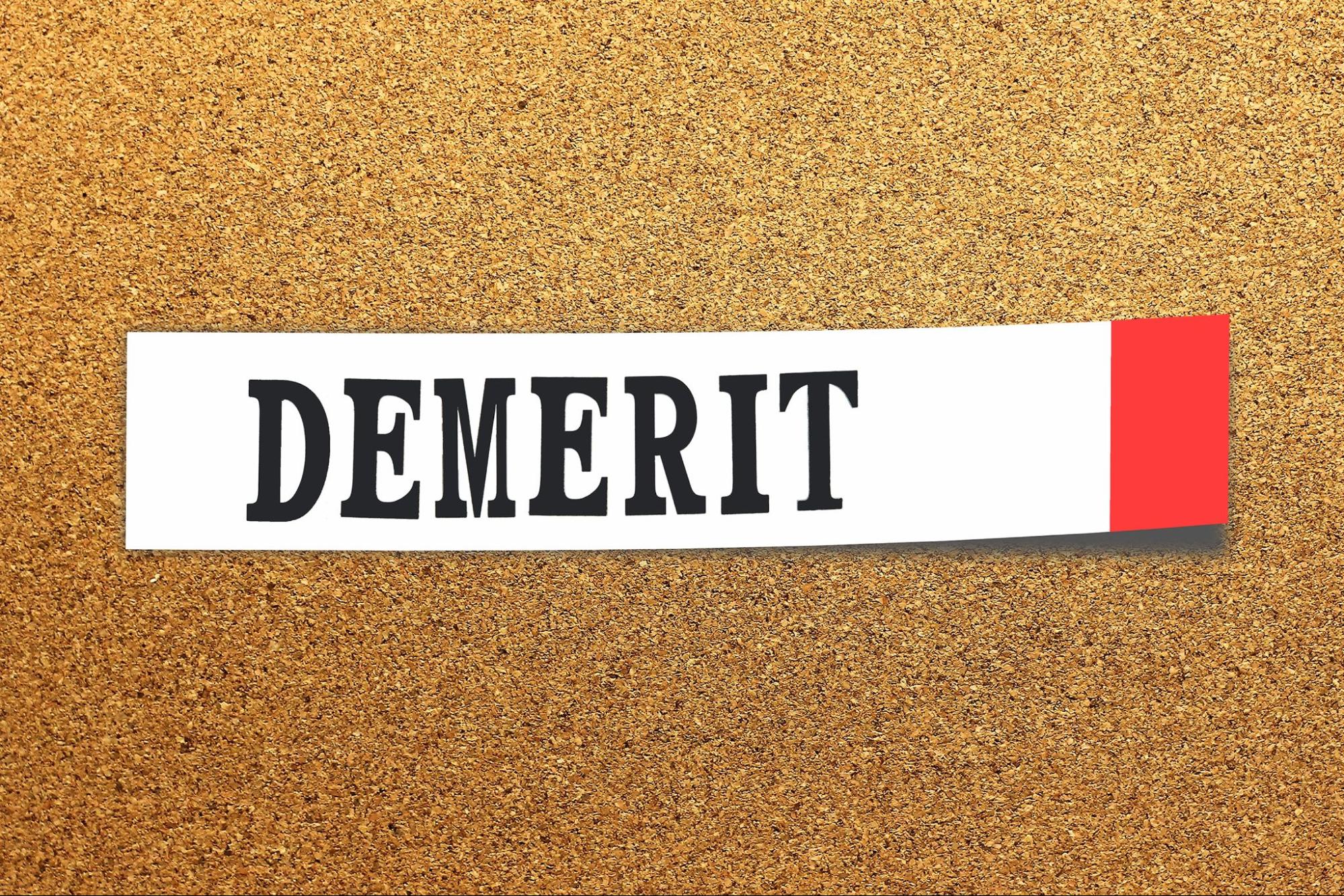
オンボーディング動画の導入には、注意すべきデメリットもあります。動画制作を検討する際には、デメリットの部分も慎重に検討しましょう。
オンボーディング動画のデメリットは、主に次の3つです。
- 編集から撮影まで手間がかかる
- わかりやすい内容にするのは難しい
- 簡単に更新・改善できない
それぞれの内容を解説します。
編集から撮影まで手間がかかる
オンボーディング動画に限らず、動画制作には膨大な手間がかかります。特に動画制作の経験が少ない場合には、試行錯誤しながらの作業になるので、必要な時間が予測できません。
動画の企画・撮影・編集は未経験の方には難しく、十分なクオリティの動画を作るのは困難です。
撮影機材や編集ソフトがない場合には、購入やレンタルで調達する手間もかかります。
動画制作にどこまでリソースを割けるかは、慎重に検討しましょう。
わかりやすい内容にするのは難しい
動画はスマートフォンでいつでも視聴できますが、新入社員にとってわかりやすい内容にするのは簡単ではありません。
動画の構成や演出が効果的でないと、視聴者が集中力を保てず、内容が印象に残らなくなってしまいます。
低クオリティの動画では、かえって会社に不信感を抱く可能性があります。
低品質なオンボーディング動画では、結局先輩社員への質問が増え、教育担当者の負担を削減できません。
簡単に更新・改善できない

動画は、一度作ったら改変ができないため、内容に変更があった場合には再編集して差し替えが必要です。
撮影データや編集データを管理して常に再編集ができる状態にしておく必要がありますが、効率よく再編集するにもスキルが不可欠になります。
また、担当社員が離職してしまい、再編集ができなくなるケースも少なくありません。
社内に動画制作の専門部署がない場合でも、制作会社に外注することでスムーズかつ効率的に導入動画を作成できます。
Funusualは、BtoB企業向け動画に特化したプロフェッショナルチームとして、これまで多くのBtoB企業様の動画を手がけてきました。
構成設計から撮影・編集・納品までをワンストップで対応し、企業のカルチャーや業務内容をわかりやすく伝える高品質な動画をご提供します。
「社内教育の効率化を図りたい」「印象に残るオンボーディング動画を作りたい」とお考えの方は、ぜひお気軽にFunusualへご相談ください。
オンボーディング動画の制作のポイント

より高品質なオンボーディング動画を制作するために、意識すべきポイントを解説します。
わかりやすく印象的な動画にするには、漠然と撮影するのではなく、企画段階から明確な戦略を持っておきましょう。
オンボーディング動画を効果的に制作するために、特に重要なポイントは次の7つです。
- 明確な学習目標を設定する
- 従業員にあわせた内容設計をする
- 適度な長さを決める
- わかりやすい構成を組み立てる
- 制作手法を適切に選ぶ
- 効果測定方法を決める
- 定期的な更新計画を立てる
それぞれの内容を解説します。
明確な学習目標を設定する
オンボーディング施策全般で重要になるのが、明確な目標の設定です。株式会社STANDSの調査によれば、企業がオンボーディングにおける課題としてトップに上げているのが、完了定義が不明確であることでした。
オンボーディングで何を習得すればよいのかゴールを設定し、新入社員と教育担当者で共有することが大切です。
オンボーディング動画を制作する際にも、この動画でどのような学習をするのか、何のスキルを習得してほしいのかを明確にしましょう。
また、新入社員とも細かく学習目標のすり合わせを行い、その都度成果の確認をしていくことが重要です。
従業員にあわせた内容設計をする

オンボーディング動画の内容は、対象とする従業員に合わせて設計しなければいけません。
例えば、新卒採用社員と中途のキャリア採用社員では、ベースとなる経験などが大きく異なります。
対象となる従業員の年齢・経験・業務などを勘案し、それぞれに適切な内容の動画を設計しましょう。
新卒社員向けにはビジネスマナーや基礎知識の説明が必要ですが、キャリア採用社員向けならある程度の知識経験がある前提で、より高度な説明が必要です。
適度な長さを決める
動画の尺が長すぎると、視聴者の集中力が続かず、内容が伝わらなくなってしまいます。
マニュアル動画の適切な長さは5~10分といわれており、この時間内に収めることを原則としましょう。
動画のテーマはできるだけ細分化し、一つの動画に対して一つのテーマに絞ることが重要です。
一つの動画にいくつものテーマを盛り込むと、内容がブレてしまい重要なことが伝わりません。
複数のテーマで動画が必要な場合は複数の動画に分けた方が、見たいテーマを探しやすく利便性が高まります。
わかりやすい構成を組み立てる
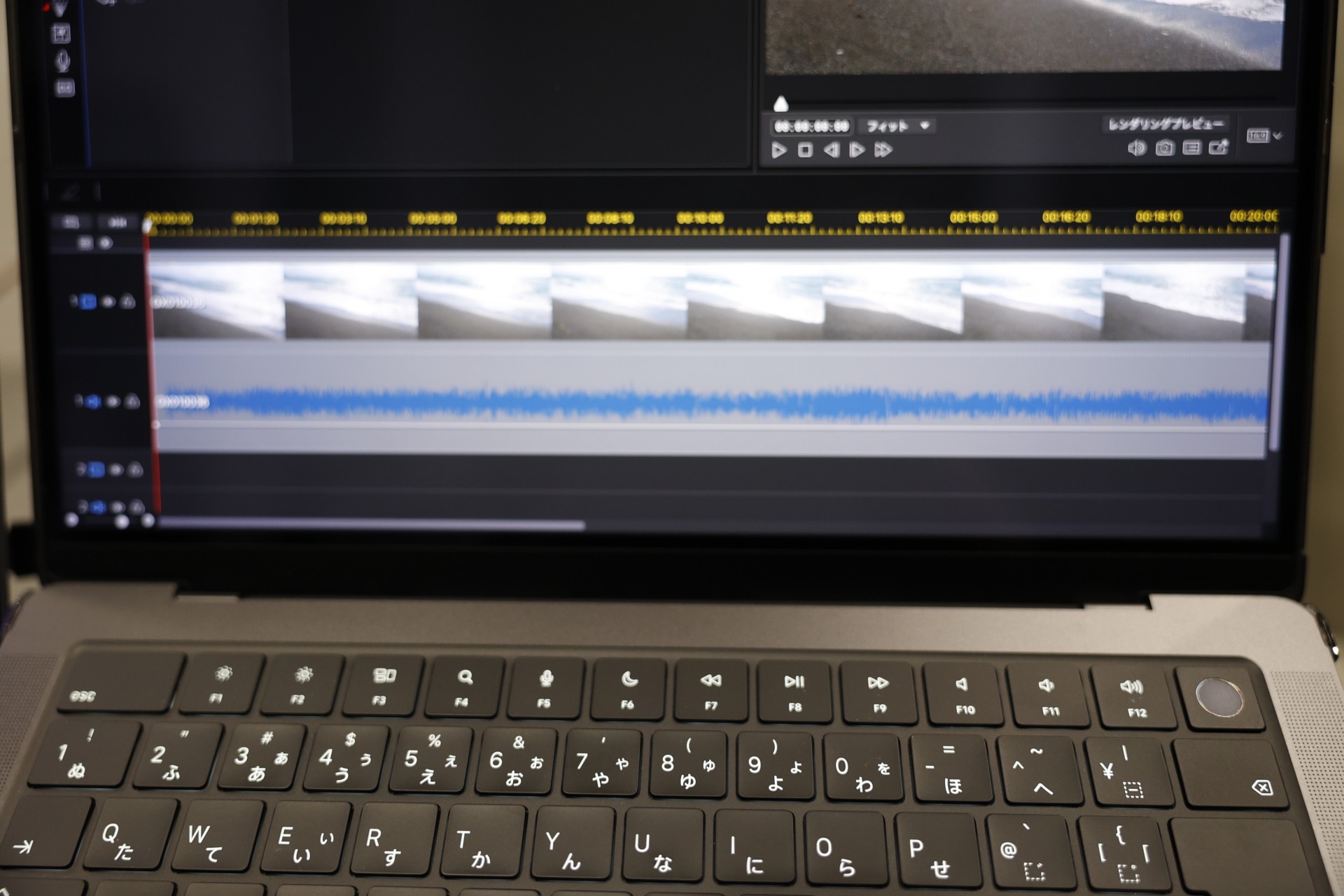
動画の構成は、単調な説明だけでなく、明確にセクションを分けた方が理解しやすくなります。
オンボーディング動画では、オープニング・本編・まとめの3セクションで構成されることが一般的です。
オープニングでは動画のテーマや学習目標を簡潔に説明し、本編で詳しい説明を行います。
最後にまとめとして動画の内容を復習し、重要な部分を繰り返して記憶の定着を促しましょう。
制作手法を適切に選ぶ
動画の制作方法は、主にアニメーション・PC画面録画・スタジオ撮影・ロケーション撮影などがあります。
オンボーディング動画のテーマにあわせて、適切な制作方法を選択しましょう。
目に見えない無形サービスの説明などは、アニメーション動画が適しており、制作費用も安くなります。
撮影には手間や機材が必要ですが、実際の業務シーンを見ながら説明した方が、伝わりやすいことも多いでしょう。
どの制作方法であっても、クオリティの高い動画を作るには経験とスキルが必要になるため、人材がいない場合は動画制作に依頼するのがおすすめです。
効果測定方法を決める

オンボーディング施策では、目標設定と同時に、その効果測定方法も決めておくことが重要です。
効果測定方法をはじめに決めておくことで、オンボーディング施策が適切に進んでいるかを判断できます。
動画を活用しながらオンボーディングを進めつつ、随時効果測定を行いましょう。
こまめに確認の時間を設けることで、ついていけていない従業員の脱落を予防できます。
オンボーディングの効果が上がっていない場合には、動画の内容を見直して改善していきましょう。
定期的な更新計画を立てる
オンボーディング動画を制作したら、定期的に内容を見直して更新していくことも重要です。
実際にオンボーディングを受けた社員や、オンボーディングを担当した社員からのフィードバックをもとに、動画を再編集してブラッシュアップしていきます。
また、業務マニュアルやルールが更新された際には、オンボーディング動画も速やかに対応させなければいけません。
このような動画の再編集を円滑にするには、編集データや撮影データを効率的に管理しておく必要があります。
動画制作専門の部署がない場合には、制作会社に外注した方がリソースの節約になるでしょう。
オンボーディング動画は内製か外注か

オンボーディング動画は、自社で内製する場合と、動画制作会社に外注する場合があります。どちらにもメリット・デメリットがあり、自社にとって適切な方法を選択しましょう。
内製する場合には、自社内で動画制作の経験がある人材がいることが条件となります。
ただし、動画制作の経験があっても、オンボーディング動画の企画から編集までを経験しているとは限りません。
内製できれば制作コストは大幅に節約できますが、優先すべきゴールはわかりやすく利便性の高い動画を作ることです。
クオリティの高いオンボーディング動画を作りたい場合には、経験豊富な制作会社に外注する方が無難でしょう。
外注費用はかかりますが、社内で試行錯誤するよりも結果的に時間対効果が高くなることがほとんどです。
動画の制作費用は、動画の長さや制作方法によって大きく異なります。
一般的には撮影の必要ないアニメーション動画の方が安く済み、ロケーション撮影やタレントの手配をする場合にはその分の費用が上乗せされます。
プロの技術で効果的なオンボーディング動画を作ろう

オンボーディング動画のメリットや、制作のポイントを解説してきました。
近年では新入社員の早期離職や、採用側とのミスマッチが問題になっており、オンボーディングの重要性が広く認識されています。
その一方で、人手不足によってオンボーディングに割ける人的リソースは多くありません。
そのため、動画をはじめとしたオンボーディングの省人化施策が、ますます重要になってきています。
わかりやすく印象的に残りやすいオンボーディング動画を制作するには、豊富な経験とスキルが必要になるため、専門の動画制作会社に外注した方が無難です。
BtoB企業向け動画に特化した制作チームであるFunusualは、言葉で伝えづらいイメージを具現化する力を重視し、視覚的にわかりやすく、印象に残る動画を制作しています。
オンボーディング動画では、企業文化・業務フロー・職場の空気感など、文字や資料だけでは伝わりにくい情報を、効果的に映像で表現することが可能です。
新人社員の早期理解・定着につながる動画コンテンツを、企画から撮影・編集・納品までワンストップで提供いたします。
「初めて動画をつくる」「うまく伝えられるか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。













