企業の広報担当者のなかには、自社商品やサービスを効率よく紹介するために、解説動画を活用したい方もいるのではないでしょうか。
解説動画はマニュアルなどの複雑な情報をわかりやすく伝えるために、多くの企業で活用されています。この記事では、広報活動における解説動画の制作方法や注意点について解説します。
解説動画制作のメリットやデメリット、活用したいツールについても紹介しているため、解説動画制作に悩んでいる方にもおすすめです。
解説動画とは

解説動画は、自社商品やサービスの利用方法を、視聴者にわかりやすく解説するのが目的の動画です。
文章マニュアルを補足する目的で制作され、一般公開だけでなく社内資料など幅広く活用できます。
文章や静止画では伝わりづらい情報でも、映像と音声を組み合わせることで、直感的に理解できます。
自社商品やサービスを動画で解説することによって、活用方法をより理解しやすくなるでしょう。
解説動画は情報を整理して、視覚的に訴求できるため、視聴者の理解が深まるのが特徴です。
視聴者の利便性の向上や社内教育の人的リソース削減のために、解説動画を導入する企業は増加しています。
動画を制作することで、商品説明や社内教育に何度も利用できるため、担当者の負担軽減につながります。
解説動画は、情報を伝えるだけではなく、理解を深めてもらうのに効果的です。
視聴者や目的に合わせた内容にすることで、視覚と聴覚に訴求して、効率的に情報を伝えられます。
解説動画の種類

解説動画はターゲット層や目的によって、内容だけではなく種類も異なります。
訴求したい情報を伝えるためには、正しい種類の動画を提供することが重要です。
ここでは、4種類の解説動画について説明します。
文字解説動画
映像内に字幕を挿入して、内容を解説する動画です。製品紹介や教育、広告などに効果的です。
映像と音声だけでは、視聴者が目的や内容を正確に理解できない場合がありますが、字幕やテロップによって伝えたい内容が明確に伝わります。
字幕やテロップの挿入は作業工程が少ないため、動画制作初心者にもおすすめです。字幕やテロップによって、音が出せない周辺環境でも、解説を視覚的にとらえることができます。
インタビュー型動画

テレビのショップ番組のように、商品やサービスを紹介する動画です。インタビュー形式で紹介するのが特徴であり、マーケティングやプロモーションに効果的です。
インタビュアーと商品やサービスを紹介する人物によって、視聴者が持つ疑問や懸念点について、インタビュアーによる質疑応答で進行します。
視聴者の関心事を中心に話が進むため、自然と関心を引き、商品やサービスの魅力を効果的に伝えられます。
アニメーション型動画
静止画に動きを加えた映像表現であり、イラストやグラフィックで構成された動画です。
文章だけでは伝えにくい内容でも、音声や動きによってわかりやすく伝えられます。
1分間の動画は、Webページ3,600ページ相当の情報を伝えることができるともいわれており、短時間で多くの情報を伝えられるのが特徴です。
アニメーションによって、視聴者に訴求できる情報を変えやすいため、社内研修や採用業務など幅広く活用できます。
インフォグラフィック型動画
映像にイラストやグラフを挿入して、商品やサービスを解説する動画です。
文章だけでは伝わりづらい内容でも、グラフやチャートのような視覚的情報を組み合わせることでイメージが湧きやすくなり、視聴者の理解度を深められます。
教育や研修だけではなく、営業成績や経済状況などデータを活用する動画に効果的です。
複雑な情報を直感的に理解しやすいため、科学的な情報に精通していない方に専門知識に関する情報を伝えやすくなります。
Funusualは、視聴者に必要な情報を正確に伝えることができ、印象に残る魅力的な解説動画を制作可能です。クライアント様の要望に合わせて、目的に合わせた映像を提供いたします。
動画制作で必要なアドバイスなど、すべてサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
解説動画の制作方法
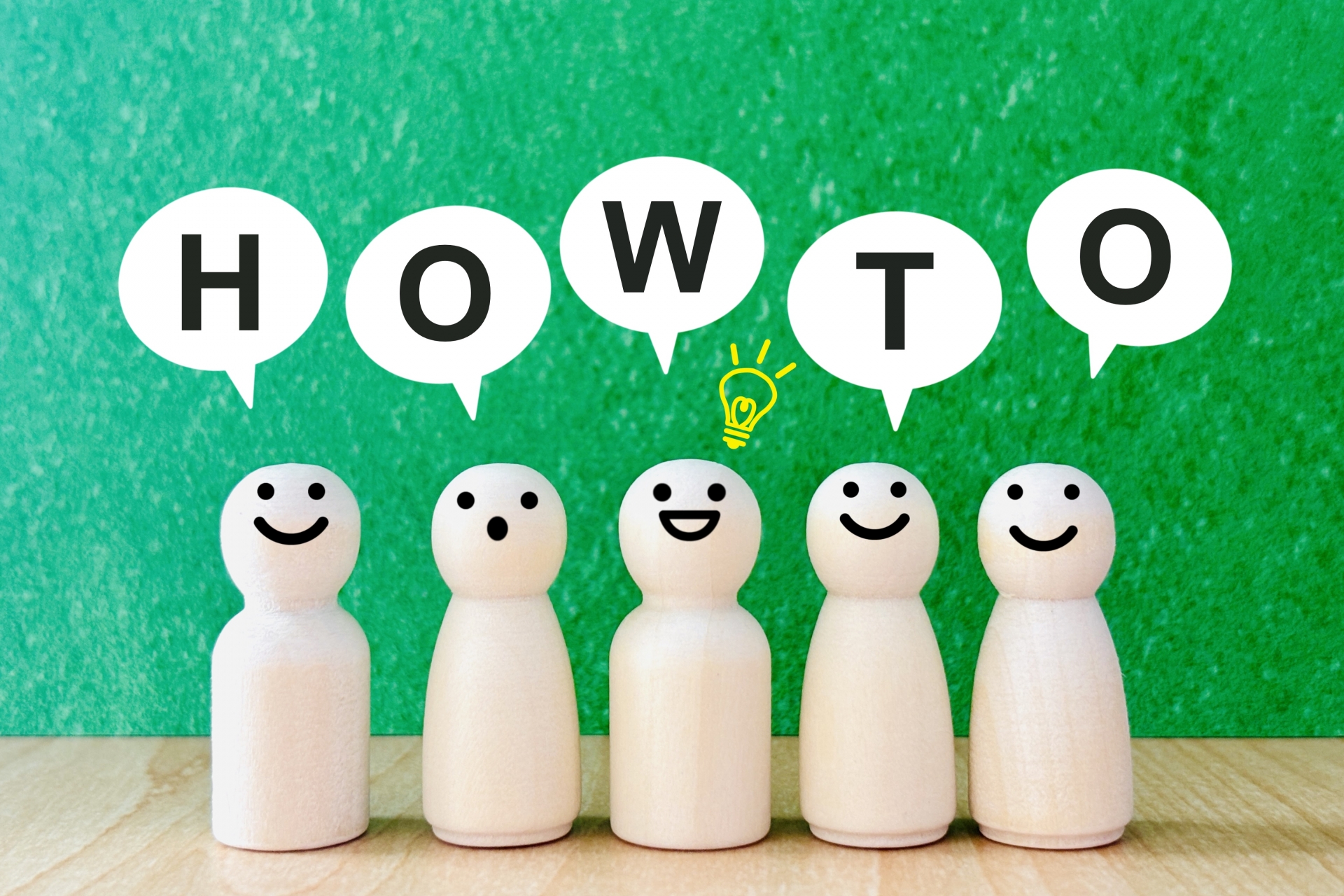
実際に解説動画を制作するうえで、具体的な方法を知りたい方もいるでしょう。解説動画は種類が異なる場合でも、基本的には5つの手順で制作することになります。
- 企画の立案
- 構成の検討
- 撮影
- 編集作業
- 公開
はじめに、企画を立案して、目的とターゲットを決めておくことが重要です。解説動画を制作する理由を明確にすることで、必要な情報が明らかになり、効率的に情報収集ができます。
目的やターゲットが定まっていなければ、動画の方向性がわかりづらくなり、内容が伝わりにくくなるリスクがあります。
構成案を作成して、訴求する情報を整理して、説明の手順を確認することが必要です。
構成案を作成するうえで、さまざまな情報を集約するのではなく、テーマを絞って制作しましょう。
情報が多岐にわたっている場合、テーマに分けて構成を作ることで、視聴者が理解しやすい内容の動画となります。
撮影段階では、事前に台本と絵コンテを作成しておきましょう。台本によって、動画の流れを把握することができ、絵コンテは動画撮影時のカメラアングルや画角を決めるのに重要です。
撮影した素材をもとに編集作業をすることで、視聴者に情報が伝わりやすくなります。編集は情報訴求力に大きく影響するため、苦手な方はプロに任せるのがおすすめです。
解説動画が完成したら、目的やターゲットに合わせたプラットフォームを選定して、動画を公開しましょう。
解説動画が効果を発揮する場面

解説動画はさまざまな場面で活用でき、一度制作することで何度でも利用可能です。
動画を活用することで、情報共有が容易になり、利便性や業務効率の向上につながります。
ここでは、解説動画が効果を発揮する4つの場面について説明します。
購入者向けの操作説明
解説動画は、購入者向けの操作説明として活用されるのが一般的です。自社製品を購入した顧客に対して、基本的な使用方法や注意点を効率よく説明するために制作します。
文章や静止画だけの説明より、映像として動きを交えることで、理解が深められます。動画であれば、製品の動きを確認しながら、実際の動きと照らし合わせられるのが特徴です。
実際の動きと照らし合わせることで、効率よく製品の操作方法を習得できるでしょう。
商談での商品やサービス紹介
商談で自社商品やサービスを紹介する際、解説動画を活用することによって、利用方法や使用感をイメージしてもらいやすくなります。
視聴者の購買意欲を引き上げるために、商品やサービスを使った際のイメージが重要です。
視覚的な情報訴求は、直接的なイメージにつながります。解説動画を社内で共有することで、異なる担当者でも同じクオリティで魅力を伝えることができます。
商談での商品やサービス紹介が画一化されるようになるため、社内全体の営業力の底上げにつながり、顧客から信頼されやすくなるでしょう。
社員用の研修動画

解説動画は、社員用の研修動画にも活用できます。自社製品の操作方法や特徴を解説することで、研修の効率化だけでなく、社員の標準化を図るのに効果的です。
営業社員が、自社製品の操作方法や特徴を理解することで、説明時の説得力が増します。研修目的の解説動画の充実によって、研修に割く時間は削減可能です。
解説動画を活用すれば、研修内容の属人化を防ぎ、標準化を図れます。
マーケティングや広告動画
解説動画は短時間で多くの情報を伝えられるため、マーケティングや広告動画にも活用できます。動画と音声を組み合わせることで、複雑な情報を効率よく伝えられます。
視覚的に情報訴求できる動画は、効率的に情報を伝えられるのが特徴です。マーケティングや広告は、効率よく情報を伝えることが重要です。
動画の動きによって、視聴者にインパクトを与えることができ、効率よく情報訴求できます。映像や音声だけではなく、テロップを組み合わせることで、視聴者に寄り添った動画が作れます。
Funusualは、訴求力と業務効率化の両立を目指した動画制作のご提案が可能です。
企画から公開まで一貫して対応するため、初めて動画制作を行う企業様でも安心感を持って取り組める体制を整えています。
研修や広告など、目的に応じた適切なプランをご案内可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
解説動画の制作で気を付けたいこと

解説動画を効果的に活用するには、いくつかの注意点を踏まえて制作することが大切です。
動画制作において、編集作業で工夫する必要があります。
ここでは、解説動画制作での5つの注意点について説明します。
内容は適切な長さにする
動画の内容を適切な長さにして、視聴者に離脱されないようにすることが重要です。
スマートフォンの普及とともに、スマートフォンでの動画視聴が増加しているため、短い動画ほど離脱されにくいです。
長尺の動画は飽きられやすく、途中で離脱されやすいため、情報を伝えきれないことがあります。複数の要素を盛り込む場合、短尺動画を複数制作する方が視聴されやすくなります。
スマートフォンが主流になっている現代社会において、解説動画は適切な長さにして、隙間時間での視聴を意識しましょう。
飽きさせない工夫をする
視聴者の離脱を防いで、訴求したい情報を伝えるためには、飽きさせない工夫をすることが重要です。飽きさせない工夫として、動画開始5秒間の演出が挙げられます。
冒頭の演出が視聴者の興味を引き付けるポイントであり、インパクトのある映像や印象に残りやすい音楽、胸を打つようなメッセージを取り入れましょう。自社製品やサービスの紹介であれば、独創的な映像や意外性のある演出によって、興味を抱きやすくなります。
印象的な冒頭演出によって、続きが気になる期待感を生み出すことが可能です。期待感が膨らむことで、継続的な動画視聴につながり、情報をより伝えやすくなります。
視聴環境を考慮に入れる

動画を視聴するうえで、どの媒体からでも視聴できるように考慮することが重要です。
視聴する媒体はスマートフォンやパソコンが一般的であり、どの媒体でも視聴できるように動画制作する必要があります。
SNSの普及により、スマートフォンでの動画視聴が増加しているため、小さな画面でも視聴できるように考慮しましょう。
デバイスを傾ける必要がないような縦長の動画にしたり、テロップのフォントサイズや商品画像などを活用したりする必要があります。
視聴環境を考慮して、スマートフォンでも視聴しやすく工夫することで、情報を伝えやすくなります。
テーマを絞って簡潔に伝える
解説動画を制作するうえで、テーマを絞って簡潔に情報を伝えることが重要です。
動画のテーマが明確になっていなければ、方向性が定まらず、効率的な情報訴求が難しくなります。
解説動画のジャンルは多岐にわたっているため、ジャンルに合った要素を盛り込む必要があります。
ジャンルに合った要素を盛り込むことで、視聴者が内容をイメージしやすいようにして、情報を正確に伝えることが重要です。
テーマを絞って簡潔に伝えることで、視聴者の情報理解に向けて、より効果的な動画を制作できます。
視聴者に知識のレベルを合わせる

解説動画を制作する際、情報訴求するターゲット層を考慮して、知識のレベルを合わせるようにしましょう。
知識のレベルを合わせることで、伝えたい内容を意識することができ、視聴者目線で動画制作できます。
視聴者の年齢層や性別、興味関心などを考慮して動画の内容や構成を決めるのがおすすめです。
初心者向けの解説動画の場合、専門用語を使わないようにして、説明を丁寧にする必要があります。
ビジネスシーンで活用するのであれば、長尺にならないように、簡潔に伝わる内容にすることも必要です。
視聴者の知識レベルに合わせることで、動画の方向性が明確になり、効率的に制作を進められます。
解説動画を作るメリットとデメリット

解説動画の制作を検討するうえで、メリットとデメリットを把握しておくことが重要です。
動画制作には労力やコストがかかるため、検討が不十分な場合、満足のいく効果が得られない可能性があります。
ここでは、解説動画の制作における2つのメリットと2つのデメリットについて説明します。
メリット:ネット環境があれば視聴可能
解説動画はネット環境さえあれば、場所を問わず視聴できる点がメリットです。
制作した動画をホームページやSNSにアップロードしておくことで、スマートフォンやパソコンなどで、視聴者の好きなタイミングで手軽に視聴可能です。
紙媒体は持ち運ぶ必要があるため、紛失のリスクや手元にないこともあります。解説動画はネット環境があれば、どこでも視聴できるため、持ち運び不要で紛失するリスクがなくなります。
メリット:音声なしでも理解できる
解説動画はテロップを挿入することで、音声がなくても内容を理解できます。視聴者が音声を出せない環境で動画を視聴する場合、映像だけで内容を理解しやすくなります。
テロップは音声がない環境での説明だけではなく、強調部分や補足部分の情報も視覚的に得られるため、内容を深く理解できるのが特徴です。
テロップを多用すると、映像が見えづらくなるので、伝えたい情報に活用するようにしましょう。
デメリット:コストに左右されやすい

解説動画は撮影機材や人件費が必要となるため、コストが高くなりやすい点がデメリットです。
制作する動画の種類や撮影環境によって費用は異なりますが、初期コストは紙媒体よりも高額になることがほとんどです。
動画制作に不慣れな場合、編集作業に労力がかかりやすく、費用対効果が合わない可能性があります。
自社で制作するよりも、外注した方が安くなることもあるので、事前に確認しておくようにしましょう。
デメリット:動画が利用者に見られない可能性もある
動画視聴には、安定した通信環境が必要であり、環境によっては再生されない可能性があります。
通信速度や容量に制限がある場合、スムーズに動画を視聴できないため、必要な情報が伝わりづらいです。
また、デジタルに疎い方にとって、動画視聴の操作を困難に感じることがあります。解説動画は、必ずしも誰でも容易に視聴できるわけではないことを理解しておきましょう。
解説動画の制作に活用したいツール

解説動画を広報活動に導入するうえで、自社制作を検討している方もいるでしょう。動画を自社制作する場合、動画制作ツールを活用することで、効率的に制作できます。
自社で解説動画を制作するのであれば、活用したいツールは3つあります。
- Adobe Premiere Pro
- Filmora11
- PowerDirector365
Adobe Premiere Proは高度な動画編集ソフトであり、動画制作会社が手掛けるような動画を制作できます。
動画制作に必要なすべての編集作業機能を備えており、AIによる自動編集や字幕生成機能が特徴です。
Filmora11は直感的な操作がしやすく、初心者でも高品質な動画制作ができます。高機能で初心者でも扱いやすいので、動画制作初心者にもおすすめです。
PowerDirector365はAIによる動画編集ツールであり、初心者から上級者まで幅広く活用できます。複雑な編集作業を自動で行うことができ、効率的な動画制作が可能です。
魅力の伝わる解説動画を制作したいなら

ここまで、広報活動における解説動画の制作方法や注意点について解説してきました。
自社商品やサービスを効率的に紹介するためには、広報活動に解説動画を導入する必要があり、視聴者に情報を伝えやすくできることを理解できたかと思います。
必要な情報を発信できる解説動画は自社でも制作できますが、魅力の伝わる動画制作は、プロの動画制作会社に依頼するのがおすすめです。
BtoB領域では解説動画によって企業の商品やサービス内容、ブランドイメージを正確に伝える必要があります。
映像制作は視聴者目線で設計されていなければ、凝った映像でも離脱してしまい、必要な情報が伝わらないこともあるでしょう。
Funusualは、BtoB領域の専門用語や業界慣習にも精通しているため、企業課題やニーズを深く分析できます。
見た目だけの演出に頼るのではなく、視聴者の心に響くような表現力も備えています。
視聴者の印象に残り、魅力的な解説動画を制作したいのであれば、私たちにご依頼ください。
「視聴者に訴求できる解説動画を活用するにはどうしたらよいか」「魅力的な解説動画を自社でも作ってみたい」そんな悩みをお持ちの方もお気軽にご相談ください。
視聴者に必要な情報を深く理解してもらうために、魅力ある解説動画を一緒に作りましょう。













