近年のクラウドファンディングでは、動画を活用してプロジェクトを成功に導いた事例も少なくありません。動画は視覚と聴覚に訴え、プロジェクトの理念や熱量を効果的に伝えられます。
一方で、動画制作には多くの手間がかかり、期待したほどの効果を上げられないケースもあるのが現実です。
本記事では、クラウドファンディングの種類に合わせた動画制作のポイントや、クラウドファンディングの成功事例を解説します。
支援者の心を掴み、惹きつけるポイントも解説しますので、クラウドファンディング動画の活用を検討中の方の参考になれば幸いです。
クラウドファンディング動画の種類

クラウドファンディング動画は、プロジェクトの魅力を視聴者に伝え、資金を募る手段として活用されています。
クラウドファンディングには、その形態によって複数の種類があり、動画もクラウドファンディングの種類に応じて作り方を工夫が必要です。
クラウドファンディングの種類では、以下の3つが代表的です。
- 寄付型クラウドファンディング
- 購入型クラウドファンディング
- 投資型クラウドファンディング
それぞれの内容と、動画の特徴を解説します。
寄付型クラウドファンディング
寄付型クラウドファンディングとは、支援者がクラウドファンディングの仕組みを通じて起案者にお金を寄付する仕組みです。
起案者は、集まった資金で行った活動内容や収支を報告しますが、金銭的・物品的なリターンは一切発生しません。
災害復興や教育・地域振興など、社会貢献性の高い事業で行われ、事業理念に共感した人々から寄付を募る形式です。
寄付型クラウドファンディングの動画では、その事業が社会にどのように貢献するのかをしっかり伝え、真面目で誠実な雰囲気の動画にするのが望ましいでしょう。
また、寄付型クラウドファンディングは寄付金控除の対象となることも、必ず動画内でアナウンスしましょう。
支援者へのリターンがなく、事業理念への共感だけで出資を募るため、どれだけ社会的価値を伝えられるかが動画のポイントとなります。
購入型クラウドファンディング

購入型クラウドファンディングとは、支援者への商品購入を約束して、商品開発のための資金を募る仕組みです。
今までになかった商品で、多くの需要が見込めるアイデアがある場合には、事業化のための資本金をクラウドファンディングで調達する事例が増えています。
購入型クラウドファンディングの動画では、開発したい商品の魅力や開発ストーリーを伝え、視聴者に欲しいと感じてもらえる内容を意識しましょう。
視聴者が潜在的に抱えている悩みに共感し、その悩みを解決できる新商品であることをアピールできれば、同じ悩みを抱える方が出資してくれる可能性が高くなります。
商品の内容に合わせて、動画の雰囲気は明るく親しみやすいものや、真面目で誠実なものなどを使い分けることも重要です。
投資型クラウドファンディング

投資型クラウドファンディングとは、支援者が事業の成果から配当や金利を受け取れる仕組みです。
投資の種類や、未公開株の提供・融資・ファンド型融資などの種類があり、事業の利益の一部を支援者に還元します。
購入型と違い、支援者が求める商品ではなく、成功が見込める事業であることが重要になります。
投資型クラウドファンディングの動画では、その事業にどのような強みがあり、なぜ成功が見込めるのかを論理的に説明しなければいけません。
インフォグラフィックなどを活用して、事業内容と成長見込みをプレゼンテーションしましょう。
事業の成功可能性に説得力があれば、資産を運用したい投資家からの支援を受けられる可能性が高くなります。
Funusualは、BtoB企業を中心に多数の動画制作経験があるプロフェッショナルチームです。
支援者の心を動かすストーリー設計とビジュアル表現で、クラウドファンディング動画の魅力を最大限に引き出します。
「限られた予算の中で、効果的な動画を作りたい」「初めてでどう進めていいか分からない」そんなお悩みにも、企画から撮影・編集・納品までワンストップで対応します。
まずはお気軽にご相談ください。
クラウドファンディングで動画を活用するメリット

クラウドファンディングで資金を募るなら、できるだけ多くの方に事業の存在を知ってもらわなければいけません。
自分のクラウドファンディング事業で動画を活用するにあたって、動画にどのようなメリットがあるかを理解しておきましょう。
動画のメリットを理解したうえで、動画を有効活用する戦略を立案していきます。
クラウドファンディング動画のメリットは、主に以下の4つです。
- 短い時間でたくさんの情報を伝えられる
- プロジェクト内容が伝わりやすい
- 日本国内だけでなく世界に発信できる
- SNSでの拡散が期待できる
それぞれの内容を解説します。
短い時間でたくさんの情報を伝えられる

動画は、文字や画像に比べて、短時間でたくさんの情報を伝えられるのがメリットです。
アメリカの調査会社の研究によると、1分間の動画は、Webページ3,600ページ分の情報を伝える効果があります。
3,600ページ分のテキストを読んでもらうのは極めて難しいですが、動画であれば1分間で伝えられます。
クラウドファンディングを募る際には、事業の内容や出資者へのリターンを理解してもらう必要があるため、動画でわかりやすく伝えられるメリットは大きいでしょう。
プロジェクト内容が伝わりやすい
アメリカの心理学者アルバート・メラビアンが提唱した法則によると、人間の情報伝達は以下のような割合となっています。
- 視覚情報:55%
- 聴覚情報:38%
- 文字情報:7%
人間の情報伝達の93%は視覚と聴覚によるものとされており、動画はクラウドファンディングの内容を効果的に伝えるツールです。
また、インフォグラフィックや字幕などでテキスト情報を加えることもでき、短時間でプロジェクトの魅力を知ってもらいやすくなります。
文字だけでイメージしづらい無形サービスであっても、動画なら具現化して伝えやすくなるのもメリットです。
日本国内だけでなく世界に発信できる

現代では、SNSの発達により日本国外にも動画はシェアされやすくなっています。
クラウドファンディング動画がSNSで拡散されれば、日本国外からも支援者を集められる可能性があります。
日本語がわからない人にも、動画だけでプロジェクト内容が理解できる構成であれば、海外から支援を受けることは十分可能です。
社会貢献性の高い寄付型クラウドファンディングや、金銭的リターンを得られる投資型クラウドファンディングでは、日本国外からの出資も視野に入れておきましょう。
SNSでの拡散が期待できる

動画を活用するメリットのひとつは、SNSで拡散されやすいことです。
文字や画像だけの投稿に比べて、動画はSNSで拡散されやすく、内容が魅力的なら次々にシェアされていきます。
SNSで動画の視聴者が増えれば、支援者が増加する可能性も高まるでしょう。
多くの方に共感される悩みを解決できる新商品のアイデアは、購入型クラウドファンディング動画をSNSで拡散させれば、目標額を大幅に上回る支援金を獲得できる可能性もあります。
SNSで拡散される動画構成は、経験豊富なディレクターに相談しながら、戦略的に作っていくことが重要です。
クラウドファンディングで動画を活用するデメリット

クラウドファンディング動画には多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットも存在します。
動画を活用するかどうかを判断する際には、デメリットを理解し、適切な対策を講じることが重要です。
クラウドファンディング動画のデメリットは、主に以下の2つです。
- 動画の制作に時間とコストがかかる
- 支援者数は動画のクオリティに左右される
それぞれの内容を解説します。
動画の制作に時間とコストがかかる
現代では、スマートフォンのカメラとアプリを活用すれば、動画制作は誰でもできます。
しかし、動画制作の経験が少ない方がいきなり取り組む場合、十分なクオリティの動画を制作するには膨大な時間とコストが必要です。
動画制作に時間を取られて、ほかの業務に支障をきたすケースも少なくありません。
動画制作にかけられる人的リソースを考慮し、それに見合うメリットがあるかを慎重に判断しましょう。
支援者数は動画のクオリティに左右される

動画は多くの方にプロジェクトの存在を知ってもらうために有効ですが、実際に支援者の増加につながるかは別問題です。
動画のクオリティが低い場合、プロジェクト自体の信頼低下にもつながってしまい、支援者は獲得できないでしょう。
特に投資型では、プロレベルのハイクオリティな動画でないと、プロジェクトの成功可能性に説得力がありません。
購入型や寄付型でも、視聴者にプロジェクトの価値が十分に伝わらなければ、支援者の増加にはつながらないでしょう。
クラウドファンディング動画を制作するのであれば、十分なクオリティを確保する必要があり、低品質の動画はかえってプロジェクトの印象を損ねることがあるため慎重に判断しましょう。
手間と時間をかけずに、クオリティの高い動画を制作したいとお考えの方は、Funusual」にぜひご相談ください。
Funusualでは、ヒアリングを通じて目的やターゲットを明確にし、最小限のやり取りで最大限の成果が出る動画をお届けすることが可能です。
経験豊富なプロデューサー・ディレクター陣が丁寧にリードし、スムーズな制作進行をサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
クラウドファンディング動画の制作ポイント

クラウドファンディング動画を制作する際に、意識すべきポイントを解説します。
動画は漠然と作るのではなく、明確な戦略を持って制作しないと、期待した効果を発揮できません。
動画制作には少なからず手間やコストがかかるため、無駄にしないように以下のポイントを意識しましょう。
- ターゲットを明確にする
- 主催者が出演して熱量を伝える
- 最後まで見たいと思わせるオープニングにする
- 動画の尺が長くなりすぎないようにする
- 効果的な字幕や音楽を使用する
- プロジェクトについての経緯を説明する
- リターンについて説明する
それぞれの内容を解説します。
ターゲットを明確にする
クラウドファンディングを成功させるためには、どのような人を支援者として想定するのかを明確にすることが重要です。
年齢・性別・職業・居住地・趣味嗜好などを具体的に書き出し、ターゲットのペルソナを設定します。
具体的に設定された一人のターゲットに向けたメッセージを、動画に込めるイメージで制作するのがポイントです。
幅広いターゲットに向けたメッセージの方が伝わりやすいと思われがちですが、ターゲットが幅広いとメッセージがぼやけてしまい、誰にも伝わらないメッセージになってしまうケースは少なくありません。
主催者が出演して熱量を伝える
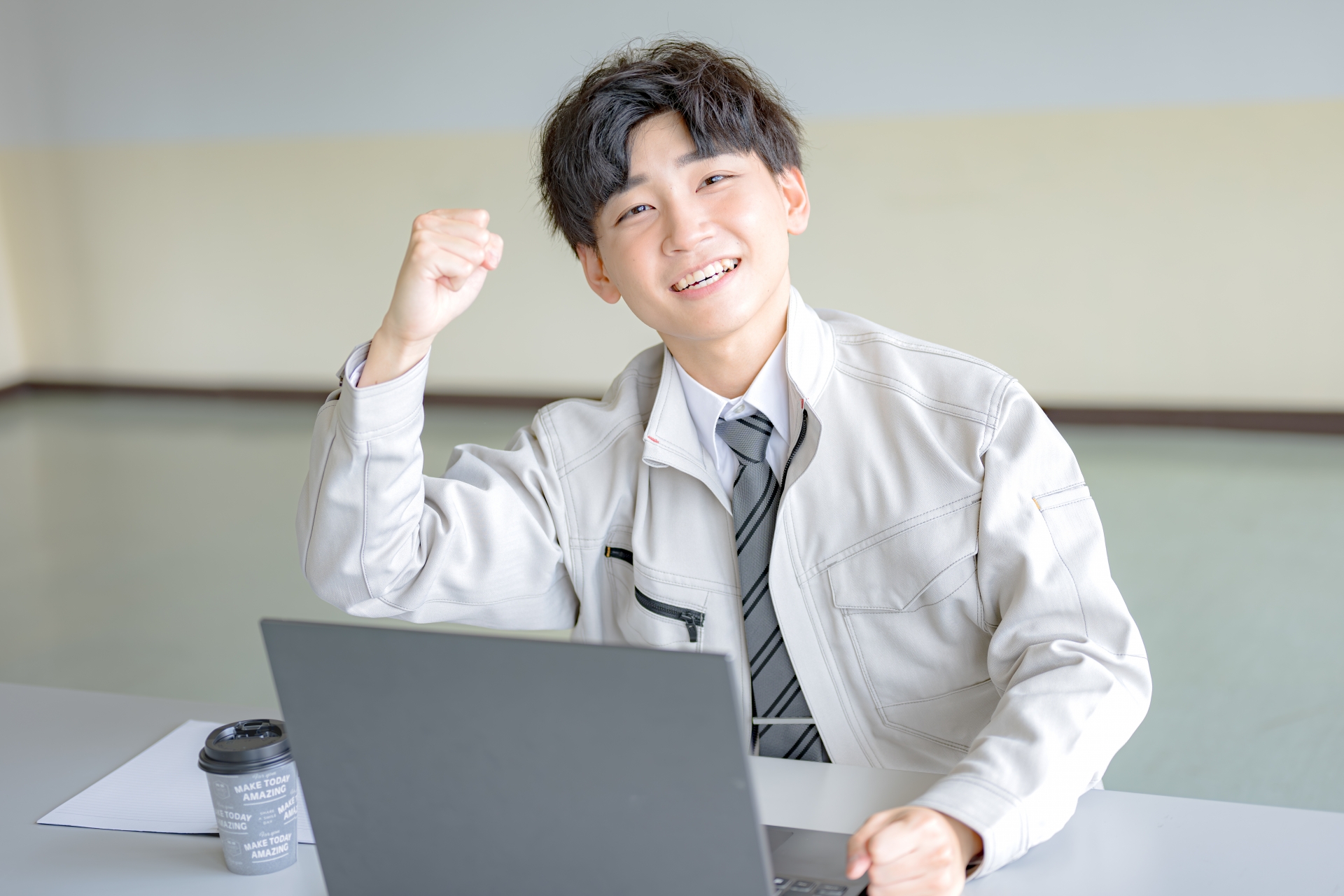
クラウドファンディングは、プロジェクトの理念や将来性に共感してもらうことが不可欠であるため、主催者自らが伝えるメッセージが極めて重要です。
特に寄付型クラウドファンディングでは、主催者が理念を熱く語ることが不可欠です。主催者の表情や身振り手振りも合わせてメッセージを伝えることで、視聴者の共感を得やすくなります。
投資型クラウドファンディングでも、事業の将来性を信じてもらうために、主催者自らのメッセージは重要となるでしょう。
最後まで見たいと思わせるオープニングにする
動画制作では、オープニングの5秒間が極めて重要といわれています。
現代のスマートフォンユーザーは日常的に多くの動画を流し見しており、興味がない動画は次々にスキップしてしまいます。
スキップされずに動画を見てもらうためには、オープニングの5秒間でどれだけ視聴者の関心を引くかが重要です。
視聴者の興味を惹くためのオープニング施策を、フックといいます。フックでどのような工夫ができるかは、経験豊富なディレクターに相談するのがおすすめです。
動画の尺が長くなりすぎないようにする
長すぎる動画は途中でスキップされる可能性が高くなるため、動画の長さは1~2分程度におさめるのが適切です。
一つの動画につき一つのメッセージとするのが基本で、一つの動画にいくつものメッセージを盛り込むと、結局何が伝えたいのかわからなくなってしまいます。
ただ一つだけのメッセージを熱量を持って伝えることを意識し、短く簡潔にまとめるのがポイントです。
効果的な字幕や音楽を使用する

動画は視覚と聴覚に同時にアプローチできるのがメリットであるため、このメリットをフルに活かした構成を意識しましょう。
主催者メッセージやインタビューの部分では、音声に加えて字幕をつけることで、よりメッセージが伝わりやすくなります。
文字を動画に合わせて動かしていくタイポグラフィなどの演出を用いれば、動きのないスライドよりも視聴者の目を惹きやすくなります。
BGMや効果音を利用して、伝えたい雰囲気を演出する工夫も重要なポイントです。
プロジェクトについての経緯を説明する
プロジェクトや商品の魅力を伝える際に、視聴者の感情を揺さぶる重要な要素がストーリーです。
人は商品ではなくストーリーを買うといわれるように、プロジェクトの発案から発展までの経緯を伝えることで、視聴者の共感を得られます。
プロジェクトが支援者にもたらすメリットだけでなく、プロジェクトの理念に共感してもらわなければ、クラウドファンディングは成功しません。
クラウドファンディングをはじめるまでのストーリーを劇的に演出できれば、感情を揺さぶれて支援者になってくれる方も増えるでしょう。
リターンについて説明する

寄付型クラウドファンディングを除いて、クラウドファンディング支援者には何らかのリターンがあることがほとんとです。
特に投資型クラウドファンディングでは、リターン目当てで出資する方も少なくないため、具体的なリターンの説明は必ず盛り込みましょう。
寄付型クラウドファンディングであっても、寄付金控除の対象となることなどはアナウンスが必要です。
クラウドファンディング動画の事例

ここでは、実際にクラウドファンディング動画を活用してプロジェクトを成功させた事例を紹介します。
引用元:www.youtube.com/@AMBER-vh5wb
こちらは、アウトドアメーカーのMakuakeが企画したテント型サウナの購入型クラウドファンディングです。
動画では、アウトドア愛好家が好みそうな美しい自然の風景をフックとし、どこでも簡単に設営できるテント型サウナの使用イメージを伝えています。
あえてナレーションを使用せずに、字幕だけのメッセージとなっていますが、BGMと合わせて自然のイメージを邪魔しない工夫がポイントです。
自然の風景を美しく見せるために、プロの撮影技術や機材を使用しているのも重要で、動画の企画段階から綿密な戦略が練られています。
このプロジェクトは、500,000円の目標額に対し、257人の支援者から17,050,350円の資金調達に成功しています。
クラウドファンディングの動画制作方法

クラウドファンディングの動画制作方法には、自身で制作するか動画制作会社に依頼するかの2つの選択肢があります。
それぞれのメリット・デメリットを解説します。
自身で制作する
動画を自身で制作すれば、人件費や撮影費はかからず、費用を大幅に抑えられるのがメリットです。
撮影データも自社内で管理すれば、動画の再編集や使い回しも容易に行えるでしょう。
しかし、動画制作の経験が少ないと、理想的な高クオリティな動画を作るには多くの時間がかかります。
動画のクオリティが低いと、プロジェクト自体の信頼性を損ねてしまうため、十分なクオリティの動画を作れるのかは慎重に検討しましょう。
動画制作会社に依頼する
動画制作会社に依頼すれば、手間をかけずに質の高い動画を制作してもらえるのがメリットです。
動画制作の経験が少ない場合は、プロの動画制作会社に依頼する方が無難でしょう。
ただし、外注には費用がかかるため、予算を慎重に検討する必要があります。
クラウドファンディングの動画制作にかかる費用

クラウドファンディング動画の制作にかかる費用は、制作方法や動画の内容によって大きく異なります。
自身で動画制作を行う場合、手持ちのスマートフォンのカメラとアプリを利用すれば、ほぼ費用をかけずに動画制作も可能です。
撮影機材や動画編集ソフトを購入する場合でも、100,000円(税込)以内で制作できるでしょう。
動画制作会社に依頼する場合は、1本あたり50,000〜300,000円(税込)の予算がかかります。
撮影の不要なアニメーション動画であれば費用は安くなり、スタジオや屋外での撮影が必要になれば費用は高くなります。
撮影した素材は複数の動画で活用できるため、異なるパターンを制作して、ABテスト(2つのパターンを比較してよいほうを選ぶテストのこと)も可能です。
応援したくなるクラウドファンディング動画を制作したいなら

クラウドファンディング動画の種類や、制作ポイントをまとめて解説してきました。
クラウドファンディングでは、共感した支援者を集めるため、プロジェクトの理念を熱意をもって伝えることが重要です。
そのためにも動画は有効なツールとなり、拡散されれば多くの方の目に止まるでしょう。
一方で、信頼される高クオリティな動画を制作するには膨大な手間がかかるため、動画制作にリソースを割けるかも重要なポイントです。
動画制作会社に依頼すれば、手間をかけずに、経験豊富なスタッフと動画の戦略を相談できるメリットもあります。
プロのサポートにより、支援者の心により響く動画の制作が可能になります。
クラウドファンディング動画の制作は、Funusualにお任せください!
Funusualは、企業向けに特化した動画制作チームとして、これまで数多くのプロジェクトに携わってきました。
クラウドファンディング動画では、支援者の心を動かすストーリー性や共感を呼ぶ映像演出が重要ですが、Funusualならプロの視点で的確なご提案が可能です。
企画構成から撮影・編集・納品までワンストップで対応し、短期間で高品質な動画を実現します。
「クラウドファンディングを成功させたい」「伝わる動画を作りたい」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。













