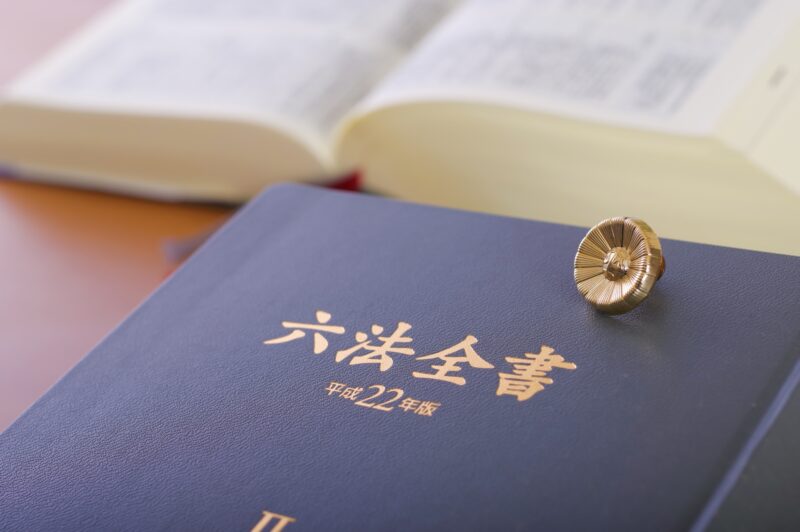企業のマーケティングやブランディングにおいて、動画配信は必要不可欠な手段となっています。しかし、その手軽さの裏で、著作権や肖像権などの法律が複雑に関わっていることをご存知でしょうか。
動画配信に関わる法律への理解が曖昧なままコンテンツを公開していると、炎上や訴訟に発展し、企業の信頼やブランドに大きな影響を与えかねません。
本記事では、企業が動画配信を行ううえで押さえておきたい法律の基本を、実際に起こりうるケースを交えながらわかりやすく解説します。
リスクを回避しながら動画活用を進めるために、ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。
動画配信に係る法律とは

動画配信には、映像に登場する人物や背景だけでなく、セリフや商品ロゴなどあらゆる要素に法的な権利が絡んでいます。
例えば人物には肖像権、会話の音声や映り込んだ個人情報にはプライバシー権、BGMや挿入画像には著作権が関係してきます。
さらに、撮影した場所や登場する商品に企業ロゴが含まれている場合などには、商標権やパブリシティ権が問題になるケースも少なくありません。
これらの法律はそれぞれ独立しているわけではなく、一つの動画コンテンツに対して、複数の法律が同時に関わってくることがほとんどです。
しかもそれらの権利は多くの場合、明確な線引きがしづらく、判断を誤ると意図せず違反行為に該当してしまうこともあります。
「知らずに使ってしまった」では済まされず、炎上や訴訟に発展するケースも実際に存在します。
ただし、関係する法律を無理にすべて暗記したり、専門家レベルの知識を習得したりする必要はありません。
まずはどのような種類の法律が動画配信に関係するのか、その全体像を理解し、どういったケースで問題になりやすいかを知るようにしましょう。
各権利の意味と注意点を正しく把握すれば、リスクを未然に防ぎながら動画配信を行うことが可能です。
動画配信をする前に覚えるべき法律
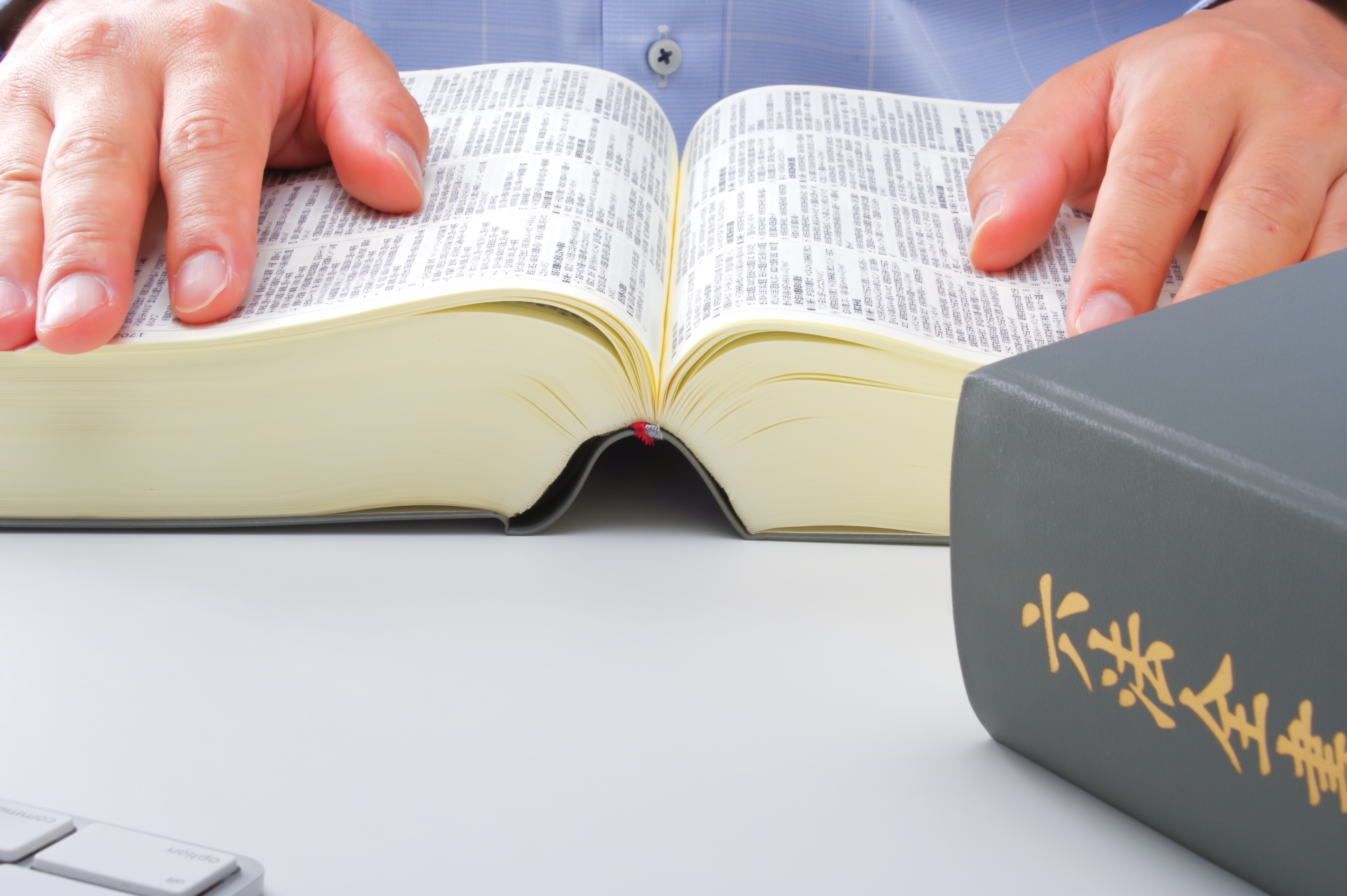
動画配信に取り組む際に、法的リスクの判断が曖昧なままだと、思わぬトラブルや炎上を招く可能性があります。
ここでは、特に企業の動画制作で注意すべき3つの基本的な法律の概要と、動画配信で問題になりやすい具体例を挙げながら解説します。
著作権法
著作権法は、創作物や著作物を保護する法律です。動画に含まれる映像・音楽・写真・イラスト・セリフ・ナレーションなど、他人が制作したあらゆる素材には著作権が発生します。
これらの無断使用は、著作権の侵害に該当します。例えば、下記のケースでは注意が必要です。
- テレビ番組や映画の一部を切り取って配信する
- 商用利用が許可されていないBGMを挿入する
- 他者のYouTube動画やSNS画像を素材として流用する
- 有名なアニメキャラクターのイラストやグッズを使用する
たとえ悪意がなくても、無断で使用すれば著作権侵害とみなされる可能性があります。原則として、使いたいなら許諾を得る必要があることを覚えておきましょう。
肖像権
肖像権は、自分の顔や姿を無断で撮影されたり、それを公表されたりしないように主張できる権利です。
動画内に登場する人物が誰であっても、その撮影・配信には原則として同意が必要です。例えば、下記のようなケースは問題になる可能性があります。
- 街頭インタビューやイベント撮影で通行人が無許可で映っている
- 社内紹介動画に社員が登場するが出演同意を取っていない
- 撮影中に映り込んだ第三者が明確に識別できる状態で配信している
上記以外でも許諾なく有名人の写真を使用し、あたかもその人物が商品を推奨しているかのような印象を与えることも、パブリシティ権の侵害です。
たとえ数秒であっても、本人が不快に感じる範囲で顔や体が映っていた場合、訴えられるリスクがあります。
許諾を得ることが難しい通行人などが映り込む場合は、個人が特定できないように顔にぼかしやモザイク処理を施したり、後ろ姿で撮影したりなどの配慮が不可欠です。
プライバシー権

個人の私生活に関する情報を無断で公開されないための権利です。具体的には下記の個人を特定しうる情報が該当します。
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- 顔写真
- 勤務先
- 家族構成
撮影場所から個人宅の住所が特定できてしまったり、動画内に映り込んだ社内のパソコンから顧客情報や社員の個人情報が見えてしまったりすると、プライバシーの侵害と判断される可能性があります。
配信前に内容を丁寧にチェックし、個人情報が含まれていないかの確認が大切です。万が一映り込んでしまった場合は、ぼかしやモザイクなどを使って適切に隠しましょう。
動画配信時の法律に関するポイント

著作権法や肖像権、プライバシー権など法律の概要は理解できても、「実際の現場では何に注意すればよいのか?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、担当者が判断に迷いがちな3つの場面を取り上げ、具体的な注意点を解説します。
背景に映る著作物・人物の無断使用に注意
撮影時、思いがけず映り込んでしまったポスター・商品ロゴ・雑誌・絵画・アート作品などには、すべて著作権が関わる可能性があります。
これが著作権法第三十条の二で定められている付随対象著作物の利用です。
例えばインタビューの背景に有名アーティストの作品が写っていた場合、その作品の権利者に無許可であれば、たとえ偶然の映り込みでも著作権侵害とされることがあります。
また、公共の場での撮影中に第三者が明確に映り込んでしまった場合も、肖像権の侵害にあたる可能性があるため注意が必要です。
企業のPR動画の撮影で、街中ロケやイベントの様子をそのまま配信するケースでは、映り込みリスクを事前に想定しておきましょう。
BGM・効果音など音楽使用のルール

BGMや効果音など、音楽素材を動画に使用する際には、著作権と利用許諾の確認が欠かせません。
フリー素材の音楽でも、商用利用が禁止されているものや、クレジット表記が義務付けられているものが存在します。
音楽の使用には誰が権利を持っていて、どの範囲まで使用が許可されているのかを確認しなければなりません。
例えば、CDを購入して得られるのは、私的に楽曲を聴く権利に限られます。その音源をコピーして動画のBGMに使う行為や、動画をインターネットで公開する行為には、別途権利者の許諾が必要です。
音楽使用の可否に関しては、JASRACやNexToneなどの管理団体に問い合わせるか、ライセンス明記された商用可能な素材サイトを利用しましょう。
ライブ配信時の肖像権・著作権の扱い
編集による後処理ができないライブ配信は、一瞬の映り込みがそのまま公開されてしまうため、収録動画以上に細心の注意が求められます。
例えば、下記のシーンでは注意しましょう。
- 背景で流れている音楽がそのまま拾われてしまう
- 通行人や来場者が映り込んでしまう
- 資料スライドに他者の画像や文章を無断で使用していた
事前に配信場所を確認し、映り込む可能性のあるものをリストアップしておきましょう。出演者や来場者に対しては、同意書や注意文を用意すれば、トラブルの未然防止につながります。
ライブ配信を録画してアーカイブ化する場合は、事前に使用素材の著作権処理を済ませておく必要があります。
配信中は見逃されても、後日の視聴により違反が発覚するケースもあるため注意が必要です。
知っておきたい配信での侵害行為にあたるもの

法律の知識があっても、実際の現場では知らず知らずのうちに権利侵害のラインを越えてしまうことがあります。
著作権侵害は意図的なものでなくても成立するケースがあるため、判断が難しく、特にグレーゾーンの扱いには注意が必要です。
ここでは、動画配信でありがちな著作権トラブルを5つのケースに分けて紹介します。
著作者の表記のみで無断使用する行為
作者名やサイト名は表記すれば使用できると誤解されがちです。クレジット表記は、著作物の利用を許可するライセンスの代わりにはなりません。
著作者の名前を明記しても、許可を得ていなければ原則として無断使用にあたります。
例えば、YouTube動画で使用したイラスト素材にクレジット表記をしていても、著作者の許諾がなければ法的には著作権侵害と見なされるリスクがあります。
他者が使用していた著作物を無断で転用する行為
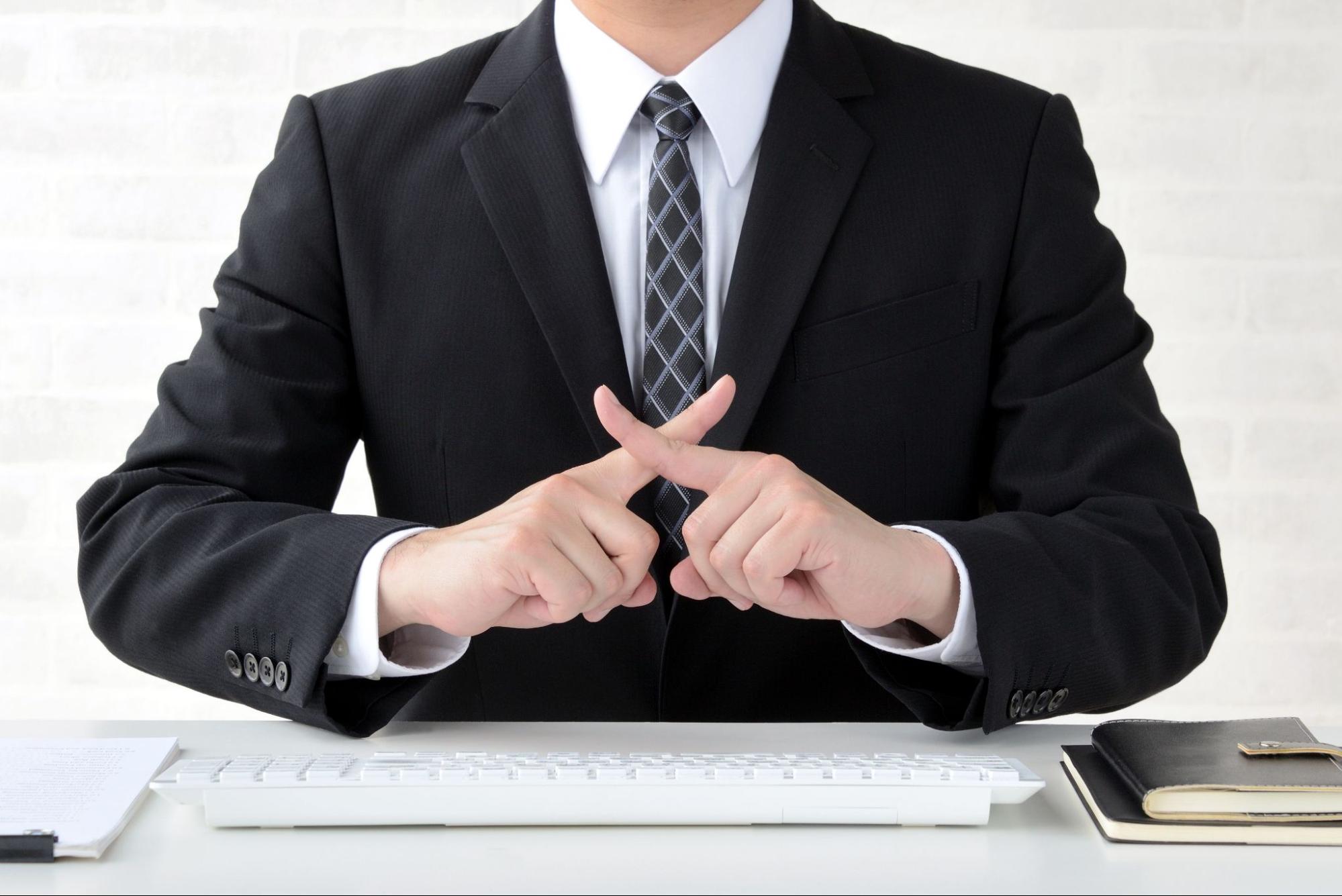
「ほかの会社も使っていたから大丈夫」と判断するのは危険です。その企業や個人は、正規にライセンス料を支払っている可能性があります。
あるいは、そのチャンネルやサイト自体が、気付かれていないだけで違法な可能性も十分にあります。
特に企業アカウントでの再利用は営利目的とみなされやすく、個人よりも厳しくチェックされる点に注意が必要です。
意図せず著作物を使用した場合でも許諾を得ていない行為
著作権侵害は、利用者の意図ではなく、権利者の許諾なく著作物を利用したかどうかの客観的な事実に基づいて判断されます。
そのため、「気付かず使っていた」と申し開きをしても、法的な免責理由にはなりません。
動画を公開する前には、意図しない映り込みがないか、使用した素材の権利はクリアになっているかを複数人で入念にチェックする体制が不可欠です。
短時間であっても無断で著作物を利用する行為
「ほんの数秒しか使っていないから問題ない」と思われがちですが、著作権には秒数の明確な基準はありません。
例えば楽曲のサビ部分を5秒だけBGMに使ったり、テレビ番組の一場面を10秒だけ切り抜いて使用したりする行為でも、著作権者が使用を不許可とすれば権利侵害とみなされます。
商用動画の場合、視聴数や広告収益など金銭的利益が絡むため、数秒の無断使用でもトラブルになる可能性が十分にあります。
使用する際は量ではなく、許可を得ているかで判断するようにしましょう。
著作者からの指摘や訴訟がないことを根拠に使用を継続する行為
これまで問題が起きなかったからといって、今後も大丈夫とは限りません。著作権侵害は、権利者が気付いた時点で警告・請求される可能性があります。
たとえ1年以上公開していても、突然、削除依頼や損害賠償の通知が届くケースも珍しくありません。
発覚が遅れるほど損害賠償額が増加し、複数の動画に対して修正や削除が必要となるなど、企業への影響は深刻化します。
問題が表面化する前に、自主的に権利関係を確認しておきましょう。
動画制作で著作権を侵害した場合の処罰

「バレなければ問題ない」と軽く考えてしまいがちですが、著作権侵害は重大な違法行為です。実際に処罰の対象となるケースも多く、民事裁判や刑事裁判へ発展するリスクもあります。
ここでは、動画制作で著作権を侵害した場合にどのような責任が生じるのかを具体的に解説します。
民事裁判
著作権を侵害された著作者が、損害賠償や差止め請求を行うのが民事裁判です。
例えば無断でBGMを動画に使用し、YouTubeで広告収益を得ていた場合に著作者はその収益分の損害賠償を請求できます。
加えて、動画の公開停止や削除を求められることもあります。民事裁判では「知らなかった」では免責されません。過失でも責任を問われるため、著作物を扱う以上は、事前に許諾を得るなどの対応が必要です。
刑事裁判

著作権侵害が故意かつ悪質と判断された場合には、刑事事件として立件されることがあります。
刑法上の処罰対象となると、著作権法第119条により、10年以下の懲役または10,000,000円以下の罰金(またはその両方)が科される可能性があります。
実際に、他人の動画や音源を繰り返し無断で転載していた投稿者が逮捕されたケースもあるため、十分な注意が必要です。
また、刑事事件になると前科がつくおそれもあり、社会的信用の失墜や就職・転職活動への影響は避けられません。
動画配信は個人でも気軽にできる時代ですが、それだけに知らずにやってしまうリスクが高く、慎重な対応が求められます。
著作権への配慮は、もはや動画制作で欠かせない基本事項です。しかし、どこまで使ってよいのかの判断は専門知識が求められる場面も多く、現場の担当者だけで対応するのは難しいケースもあります。
万が一トラブルになれば、金銭的な損害だけでなく、企業の信用やブランドイメージにも深刻な影響を及ぼしかねません。
このようなリスクを未然に防ぐには、企画段階から法令遵守を前提に制作を進めることが不可欠です。
Funusualでは、著作権や使用許諾の可否を制作前に確認し、必要な許諾の取得や素材選定の段階から無料でアドバイスを行っています。
コンプライアンスを守りながら成果につながる動画を作りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
動画配信で気を付けたい注意点

動画配信はコンテンツ制作の自由度が高い一方で、著作権や契約に関する見落としがトラブルの火種になることもあります。
誰の権利が関わっているのか、どこまで利用できるのかを曖昧にしたまま配信を進めてしまうと、後から権利者からのクレームや損害賠償に発展するケースも少なくありません。
ここでは、動画制作の現場で特に注意すべきポイントを紹介します。
制作した動画の著作権の帰属を明確にする
動画制作を外部に依頼する場合、著作権の帰属先を契約書で明確にしておきましょう。
そうしないと、後々「この動画はうちのものだから自由に使わないでほしい」と制作者側から主張される恐れがあります。
例えば、企業がPR動画を制作しても、契約上の取り決めが曖昧だったことで自由に再編集や広告利用ができなくなる可能性もあります。
著作権の譲渡や利用許諾の範囲を事前に明記しましょう。
動画の二次利用の条件を事前に決定する
一度制作した動画を再編集して別の用途で使いたくなる場面は少なくありません。しかし、初回の利用目的に限定された契約内容になっていた場合、勝手な二次利用は契約違反です。
例えば、社内研修用に作成した映像を営業用に流用しようとして、出演者から指摘されるトラブルも考えられます。
媒体や期間、地域など利用範囲を事前に明確に定めておくことが重要です。
音楽・画像などの使用許諾を取得する

動画内でBGMや画像素材を使用する際は、それぞれの権利者から使用許可を得る必要があります。
YouTube動画では自動で検出され、無許可の素材を使うと公開停止や広告収益の無効化が行われるケースも少なくありません。
無料素材サイトでも商用不可やクレジット表記必須などの条件付きが多く、条件を見落とすと違反になる可能性があります。
利用前にはライセンス内容を確認し、必要に応じて明示された方法でクレジットを記載しましょう。
出演者・タレントの使用に関する契約確認
動画に登場する人物がいる場合、その肖像をどこまで利用できるかも確認しておくべきです。
撮影当初は了承していても、後から「SNSには出したくない」と撤回されることもあります。
特にインフルエンサーやタレントを起用する場合は、使用期間・使用媒体・編集の可否など、詳細を契約書に落とし込みましょう。
書面で同意を得ておくことがトラブル防止につながります。
ロイヤリティフリー素材の誤解に注意
ロイヤリティフリー素材とは一度購入すれば、定められた利用範囲内であれば追加料金なしで何度も利用できる素材のことです。
ロイヤリティフリー素材は、すべての用途に自由に使えるわけではありません。一部商用利用NGや再配布不可などの条件が付いていることも多く、利用範囲を超えて使用すると権利侵害になる可能性があります。
例えば、テンプレート素材を使ってクライアント向けに制作したことで、再販行為とみなされて問題になる可能性もあるため注意が必要です。
素材サイトごとに利用規約は異なるため、都度確認しましょう。
このように、ロイヤリティフリー素材であっても、使用方法によっては著作権侵害に該当するリスクがあります。
動画や広告などの制作物で素材を活用するには、法律面のチェックも欠かせません。しかし、すべての規約や条件を細かく確認し、適切に使い分けるのはとても手間がかかる作業です。
そのようなときは、著作権に強いプロに相談しましょう。
Funusualは映像制作のプロとして、企画や構成はもちろん、使用素材の権利チェックや表現に関するリスク管理まで一貫して対応しています。
相談は無料なため、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
配信の録画・再投稿が違法と判断されるケース

ライブ配信やオンデマンド配信などのコンテンツを録画・再投稿する行為は、一見すると手軽に思えるかもしれませんが、著作権法の観点から重大なリスクを伴います。
特に下記の行為は、著作権侵害として違法と判断される可能性が高くなります。
- 視聴用に公開されているコンテンツを自分のSNSやYouTubeに再アップする
- 有料配信を録画して第三者に共有する
- 無断で録画した講演会や音楽ライブをそのままSNSに投稿する
また、配信プラットフォーム自体の利用規約にも違反するため、アカウント停止や損害賠償請求などの事態に発展するケースもあるでしょう。
たとえ録画・再投稿の目的が善意の拡散であっても、許可を得ていなければ法的責任を問われるおそれがあります。
再利用を想定している場合は、録画・再利用が許可されている素材かどうかの確認が重要です。
また、配信に関する運用ポリシーを社内で整備し、録画・再投稿の可否を明確にしておくことが重要です。
法律を守りながら動画配信ができる制作会社を選ぶなら

動画配信を行うにあたり、「法的に問題がないか心配」と感じる方は少なくありません。
特に著作権や肖像権、使用許諾など動画制作に関わる法的課題は見落としやすく、一度のミスで配信停止や訴訟につながるリスクもあります。
そこで重要になるのが、コンプライアンスに強い制作会社の存在です。
FunusualはIT・製造業・建設業・工業のほか、金融・不動産などのBtoB業界に特化した動画制作ノウハウを有しています。
各業界の特性を理解したうえで、戦略性と法令順守の両立を前提にした動画制作支援が可能です。
また、大手企業の制作実績も豊富で、実写からアニメーションまで柔軟に対応できる点も強みです。
法令順守を前提に、成果につながる動画を制作したいなら、まずはFunusualにご相談ください。