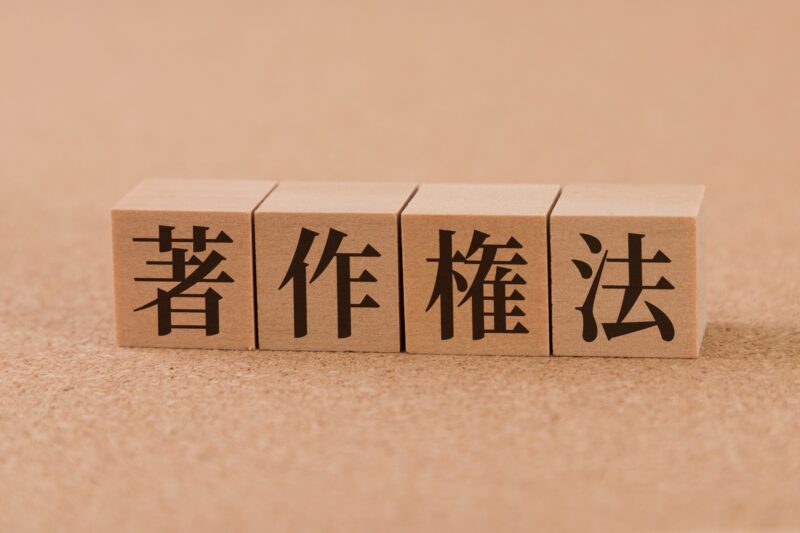企業の動画制作において、音楽や画像・キャラクターなどの素材を自由に使ってよいのか不安に感じることはありませんか。
著作権や肖像権に関する知識不足が原因で、知らないうちに法的リスクを抱えてしまう可能性があります。
この記事では動画制作における著作権の許容範囲や基礎知識・肖像権との違い・安全な素材選びの方法について詳しく解説します。
法的トラブルを避けながら、不安なく動画制作を進めるための実践的な知識を身につけましょう。
動画における著作権の許容範囲とは

動画制作において、どこまでの範囲で他人の著作物を使用できるのかは、多くの企業担当者が抱える疑問でしょう。
著作権の許容範囲を正しく理解することが、法的リスクを回避する第一歩となります。
法務省の資料によると、著作権は作品を作った時点で自動的に発生し、創作者に権利が付与されます。
このため他人の著作物を利用するには、原則として著作権者の了解を得ることが必要です。
動画制作における許容範囲は主に私的使用目的の制限、引用の条件、著作権フリー素材の活用という要素によって決まります。
動画をインターネット上に公開する場合は私的使用に該当しません。
近年人気の実況動画では、ゲーム会社の利用規約確認・朗読動画では文学作品の著作権者許諾・してみた系の動画では既存作品参考時の模倣程度に注意が必要です。
重要なのは、無料で入手できる素材であっても、必ずしも自由に使えるわけではないという点です。
利用条件を事前に確認し、制作会社やクリエイターとの契約で権利関係を明確にすることが安全な動画制作につながります。
著作権に配慮した動画制作でお困りの際は、専門知識を持つプロにお任せください。
Funusualでは法務知識を踏まえた動画制作のサポートを行っており、権利関係の確認から安全な素材選定、効果的な動画公開まで一貫して対応可能です。
過去には、著作権リスクを回避しながら企業の動画施策を成功に導いた実績も多数あります。
まずは無料相談で、御社の動画制作における著作権リスクを一緒に確認し、適切な解決策をご提案いたします。
著作権とは

動画制作に携わる企業担当者にとって、著作権の正確な理解は法的リスクを避けるための必須知識といえるでしょう。
文化庁の情報によると、著作権は創作者の権利を保護するための重要な制度として位置づけられています。
著作物
著作権法では、著作物を思想または感情を創作的に表現したものであり、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するものと定義しています。
動画制作に関わる主な著作物には音楽(楽曲・歌詞)や映像作品・写真・イラスト・絵画・文章・脚本・コンピュータ・プログラムなどがあります。
注意すべきは、何らかの個性が表現されているものであれば著作物に該当する可能性が高く、クオリティの高低は関係ないという点です。
一方で、東京タワーの高さ=333mといった単なるデータや、他人の作品の模倣品は著作物には該当しません。
著作者
著作者とは、著作物を創作した人を指します。動画制作においては、複数の著作者が関わることが一般的です。
動画に関わる著作者としては脚本家(脚本の著作者)や作曲家・作詞家(音楽の著作者)・カメラマン(映像の著作者)・イラストレーター(グラフィックの著作者)などが挙げられます。
文化庁の資料によると、著作物が創作された時点では著作者(創作者)と著作権者(著作権を持つ人)は同一です。
著作権が譲渡されたり相続されたりすると、著作者と著作権者は異なることになります。
著作隣接権

著作隣接権は、著作物の創作者ではないが、著作物の伝達に重要な役割を果たす実演家や録音・録画・放送事業者に与えられる権利です。
動画制作で関わる著作隣接権者には俳優や歌手・演奏家(実演家の権利)・レコード製作者(レコード製作者の権利)・放送事業者(放送事業者の権利)があります。
これらの権利も著作権と同様に保護されるため、動画で使用する際は適切な許諾が必要です。
著作者人格権
著作者人格権は、著作者が精神的に傷つけられないための権利で、創作者としての感情を守るためのものです。この権利は譲渡したり相続したりすることはできません。
著作者人格権には公表権や氏名表示権・同一性保持権の3つがあります。
公表権は無断で著作物を公表されない権利で、動画で他人の未公表作品を使用する場合は、必ず事前に許可を得る必要があります。
氏名表示権は自分の著作物を他人に使用させるときに名前の表示を求める権利で、動画のクレジット表示などで重要です。
同一性保持権は著作物を無断で改変されない権利で、音楽をカットしたり、画像を加工したりする場合は注意が必要です。
動画制作においては、これらの権利への配慮も含めた契約書の作成や、適切なクレジット表示が重要となります。
動画での著作権がある素材

動画制作では多様な素材を組み合わせるため、それぞれの素材に著作権があることを理解し、適切な許諾を得ることが重要です。
総務省の資料によると、作者や脚本家・制作会社・演者・演奏者・歌手・作曲家・作詞家など、著作物には多くの権利者が関わっています。
効果音やBGM
音楽関連の素材は、動画制作で著作権問題が発生しやすい分野の一つです。
楽曲の著作権構造としては、作詞者の権利(歌詞)や作曲者の権利(メロディー)・編曲者の権利(アレンジ)・実演家の権利(歌手・演奏家)・レコード製作者の権利があります。
文化庁の資料によると、音楽の場合は作曲した人と作詞した人・歌った人・伴奏した人・録音した人など多くの人々が関係するため、全員の了解を得ることが実際には困難な場合が多いとされています。
効果音についても、創作性があるものは著作物対象です。無料の効果音であっても、利用条件を確認せずに使用すると著作権侵害となる可能性があります。
キャラクター
キャラクターは、その表現に創作性が認められる場合、著作物として保護されます。
キャラクター使用時には、既存の有名キャラクターの無断使用は著作権侵害となり、類似したキャラクターの作成も侵害となる可能性があることに注意が必要です。
また、パロディーや二次創作も原則として著作権者の許諾が必要となります。
総務省の事例によるとテレビ番組や映画・ライブ映像・音楽・書籍・キャラクターなど、世の中は誰かの著作物であふれており、それらを許可なく公開やアップロードすれば権利侵害になります。
画像

写真やイラストなどの画像素材も、重要な著作物の一つです。写真の著作権については、撮影者に著作権が帰属し、被写体の肖像権も別途考慮が必要です。
ストックフォトサイトの素材でも利用条件の確認が必須となります。
イラスト・絵画の著作権については創作者に著作権が帰属し、模倣やトレースも著作権侵害となる可能性があり、デザインの一部使用でも許諾が必要な場合があります。
海外コンテンツ
海外で制作されたコンテンツについても、日本国内での使用には注意が必要です。国際的な著作権保護については、ベルヌ条約により多くの国で相互に著作権が保護されています。
海外の著作物を日本で使用する場合も、原則として著作権者の許諾が必要です。
海外フリー素材についても、海外のフリー素材サイトでも利用条件はさまざまでCreative Commonsライセンスなど、国際的なライセンス形態についても理解しておくことが重要です。
動画制作においては、これらすべての素材について事前に権利関係を確認し、適切な許諾を得ることが法的リスクの回避につながります。
著作権を侵害すると起こること

著作権侵害は単なる民事上の問題ではなく、深刻な法的・経済的リスクを伴う行為です。
総務省の資料によると、違法だと知りながら動画などの著作物をダウンロードした場合も、個人で楽しむ範囲でも違法として処罰される可能性があります。
プラットフォームでのリスク:動画削除・収益停止など
動画配信プラットフォームでは、著作権侵害に対して厳格な対応が取られます。
動画削除のリスクとしては、著作権者からの申し立てにより即座に削除される可能性があり、削除された動画の復旧は困難で制作費用が無駄になることです。
アカウント停止・収益化停止については、総務省の事例によると動画サイトの運営側から警告を受けても投稿を続けた結果、著作権法違反容疑で逮捕された事例があります。
プラットフォーム側の対応としては、一定回数の警告でアカウント停止や収益化機能の停止・新規アカウント作成の制限などです。
企業ブランドへの影響として、著作権侵害による動画削除は、企業の信頼性に深刻な影響を与える可能性があります。
法的リスク:損害賠償・刑事罰などの可能性

著作権侵害は民事責任だけでなく、刑事責任も問われる重大な法的リスクです。
民事責任については、経済産業省特許庁の資料によると著作権侵害により差止めや損害賠償・不当利得の返還・信用回復措置などの責任を負う可能性があります。
刑事責任については、著作権侵害に対する刑事罰は個人の場合10年以下の懲役または10,000,000円以下の罰金(またはその両方)、法人の場合3億円以下の罰金となっています。
違法ダウンロードについても、2021年1月からの法改正により2年以下の懲役または2,000,000円以下の罰金の対象です。
これらのリスクを避けるためには、動画制作の企画段階から著作権に配慮した制作体制を構築することが不可欠です。
法的トラブルを未然に防ぎ、不安なく動画制作を進めたい企業様は、著作権対応に精通した専門会社にご相談ください。
Funusualな確かな権利処理で、企業ブランドを守りながら効果的な動画をお作りいたします。
著作権と肖像権の違い

動画制作において、著作権と肖像権はまったく異なる権利であり、それぞれに適切な対応が必要です。
総務省の資料によると、これらの権利を混同することで、思わぬ法的トラブルに発展する可能性があります。
著作権は創作的な表現を保護する権利で、作品を作った時点で自動的に発生し、譲渡や相続が可能で保護期間は原則として著作者の死後70年です。
肖像権は勝手に写真に撮られたり、撮られた写真を勝手に公開されない権利で、誰にでも認められる基本的な権利です。譲渡や相続はできず、有名人にはパブリシティ権も併存します。
近年問題となっている著作権侵害の例として、ファスト映画(映画の内容を短時間にまとめた動画)やテレビ番組の無断転載です。
これらは映画会社や放送局の著作権を侵害する行為として、厳しく取り締まられています
動画制作時に注意したい著作権と肖像権のポイント

動画制作プロジェクトでは、企画段階から権利関係を整理し、適切な契約や許諾を得ることが重要です。
文化庁の資料によると、動画には写真・絵画・音楽・脚本・俳優の演技などさまざまな部品が使われるため、全員の了解を得ることが必要とされています。
著作権の帰属を契約で明確にする
動画制作では複数のクリエイターが関わるため、事前の契約で著作権の帰属を明確化することが不可欠です。
制作委託契約での重要ポイントとして文化庁の著作権契約書作成支援システムでは、映像作品の制作を依頼する際の著作権契約書として、著作権の譲渡範囲の明確化や著作者人格権の不行使特約・二次利用の権利関係・クレジット表示の方法を重視しています。
注意すべき契約条項として、著作権法では譲渡人の保護規定です。単に著作権を譲渡すると契約しただけでは、二次的著作物の創作権および利用権は権利者に留保されたものと推定されます。
そのため、すべての著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)を譲渡するなどの明確な文言が必要です。
第三者の著作物が映らないように注意する

撮影現場では、意図しない著作物の写り込みが著作権侵害となるリスクがあります。
注意すべき著作物は街中の広告やポスターや店舗のBGM・テレビ画面に映る番組・本や雑誌の表紙・アート作品や建築物などがあります。
対策方法としては事前のロケハン時に著作物の確認や撮影許可の取得・写り込みを避ける撮影アングルの検討・必要に応じて著作権者への許諾申請などが効果的です。
動画の二次利用は事前に確認する
制作した動画をさまざまな用途で活用する場合、二次利用権の事前整理が重要です。
二次利用で考慮すべき要素には使用素材の利用許諾範囲や出演者との契約内容・音楽著作権の利用範囲・配信プラットフォームの利用規約などがあります。
JASRACなどとの関係については、音楽を使用する場合、JASRACなどの音楽著作権管理団体への手続きが必要です。利用形態に応じた適切な手続きを行いましょう。
音楽を使う場合は許可を得る

動画制作における音楽利用は、複雑な権利処理が必要な分野の一つです。
必要な許諾としては音楽著作権(JASRAC・NexToneなどへの手続き)や原盤権(レコード会社への許諾)・実演家の権利(歌手・演奏家への許諾)があります。
商用利用での注意点として企業の宣伝動画やWebサイトで使用する場合、営利目的の利用として扱われ、より厳格な許諾が必要です。
社員であっても肖像権がある
企業内での動画制作において見落としがちなのが、社員の肖像権です。
総務省の資料によると、肖像権はアーティストやタレントに限らず、誰にでも認められます。
社員出演時の注意点としては事前の同意取得や利用目的の明確化・利用範囲の説明・退職後の取り扱いなどがあります。
同意書の重要性については、個人情報保護委員会の見解では、写真に写っている本人から事前に同意を得ることが重要です。社内利用であっても適切な手続きを踏むことが重要になります。
タレント起用するなら書面で契約を交わす
外部タレントを起用する場合、書面による詳細な契約が必要です。
契約で定める事項には肖像の利用範囲や期間・二次利用の可否・クレジット表示の方法・契約解除時の取り扱いなどがあります。
タレントが事務所に所属している場合は、事務所との使用許諾の交渉と契約が必要になり、動画の著作権を制作会社か自社で管理するのかも事前に決めておくことが重要です。
パブリシティ権への配慮として有名人の場合は、肖像権に加えてパブリシティ権(商業的価値)も考慮することが必要です。適切な対価を支払い、利用範囲を明確にした契約を締結しましょう。
著作権に配慮した動画素材の選び方

動画制作において、著作権をクリアした安全性が高く素材選びは、法的リスクを回避するための基本です。
総務省の資料によるとフリー素材のように二次利用や私的利用が許可されているものでも、利用の条件を確認し、ルールにしたがって使う必要があります。
公式ライブラリ・フリー素材の活用
政府・公的機関の素材活用については、政府広報オンラインなど、多くの政府機関が利用しやすいライセンス形態でコンテンツを提供しています。
これらの素材は安全性が高い状態で利用できますが、利用条件の確認は必須です。
フリー素材サイトの選び方として、信頼できるフリー素材サイトの特徴には運営者情報が明確・利用規約が詳細に記載・著作権者の許諾状況が明示・商用利用の可否が明確といった点があります。
注意すべきポイントとして、無料で使える曲や画像でも利用の条件をしっかり読み、ルールに従った使い方をしなければなりません。
主な確認事項は商用利用の可否やクレジット表示の要否・改変の可否・利用期間や地域の制限などがあります。
Creative Commonsライセンスは国際的に認められているライセンス形態で、表示(BY)では作者名の表示・継承(SA)では同じライセンスでの公開・非営利(NC)では営利目的での利用禁止・改変禁止(ND)では改変・翻案の禁止という組み合わせがあります。
パブリックドメイン素材の利用
パブリックドメインとは、著作権の保護期間が終了し、誰でも自由に利用できる状態になった著作物です。
パブリックドメインの判断基準としては、著作者の死後70年経過(一般的な場合)や法人著作物は公表後70年経過・著作権者が権利を放棄した場合などです。
利用時の注意点として、パブリックドメインであっても翻訳や編集版は別途著作権が発生する可能性があります。肖像権は別途考慮が必要で、商標権との関係や海外での権利状況の違いなどに注意が必要です。
確認方法としては、文化庁の著作権データベースや国立国会図書館の資料・専門機関への確認などがあります。
動画制作においては、これらの安全性の高い素材を積極的に活用することで、著作権リスクを大幅に軽減できます。ただし、どのような素材であっても、利用前の権利確認は欠かせません。
著作権対応を含む動画制作は専門会社への依頼がおすすめ

動画制作における著作権処理は、専門的な知識と経験が必要な複雑な分野です。動画制作では多くの権利者が関わるため、適切な権利処理を行うことが重要とされています。
自社対応のリスクとして、権利関係の見落としによる法的リスク・不適切な契約による後々のトラブル・時間とコストの増大・専門知識不足による判断ミスなどがあります。
専門会社に依頼するメリットとして、プロの動画制作会社は多様な業界での制作経験を通じて蓄積された著作権処理のノウハウを持っており、事前の権利調査や適切な許諾取得・契約書の作成と管理・二次利用への対応が可能です。
Funusualの強みとして、BtoB動画制作の専門家としてクライアントの課題に寄り添った制作・豊富な経験・業界特化のノウハウ・法的配慮を徹底した制作体制という包括的なサポートを提供しています。
動画制作における著作権対応は単なる法的義務ではなく、企業ブランドを守る重要な投資です。専門会社との連携により、法的リスクを回避しながら、効果的な動画マーケティングを実現しましょう。
著作権を含む動画制作のあらゆる課題を解決したい企業様は、豊富な経験と専門知識を持つFunusualにお任せください。お客様のビジネス成功をサポートする動画制作をご提供いたします。