近年、ストップモーション動画での広告が注目を集めています。特徴的で印象に残りやすいため、SNSなどでの拡散も期待できます。
自社でのストップモーションを活用した動画制作を検討しているが、自作はできるのだろうか?外注したら費用はどれくらいかかるだろうか?という不安をお持ちではないでしょうか。
この記事では、ストップモーション動画の特徴や効果について解説し、自作する場合の流れや準備するものなどを紹介しています。
自作する際の注意点や外注する場合の費用、活用事例も解説しているので、ぜひ制作の参考にしていただければ幸いです。
ストップモーション動画の特徴

ストップモーション動画は、コマ撮り動画ともいいます。静止画をつなげて動画にするため、CGなどの技術がなくてもインパクトのある映像を制作できます。
例えば、ジャンプをして跳んでいるところだけをつなげれば、宙に浮いているような映像になるでしょう。
映像はコマをつなげることで特徴的な動きとなり、印象に残りやすくなります。また、本来動かないものを動かして見せられる点も魅力のひとつです。
例えば、人形のポーズを少しずつ変えて一枚ずつ静止画を撮影していき、つなげれば人形が動いているように見えます。
そのため、アニメーションの制作にもよく用いられています。また、広告などで活用すれば印象に残りやすく、注目もされやすいでしょう。
ストップモーション動画の効果

ストップモーション動画の効果は、視聴者の興味を引きやすい点にあります。
ストップモーションで作られたインパクトがある動画や、独特な動きで再現される世界観は、印象に残りやすく幅広い年齢層に気に入ってもらえるでしょう。
ここでは、ストップモーション動画の効果について、以下の項目に沿って詳しく解説します。
自社のオリジナリティを伝えられる
ストップモーション動画の効果はオリジナリティを伝えられることです。コマ撮りを活用すれば、本来は動かせないものも動かして見せられるため制作者のオリジナリティを表現しやすくなります。
自社の商品やサービスなど、訴求したいものをオリジナルキャラクターにしたりメインに使ったりすれば、注目度も高まるでしょう。
インパクトがあるため記憶に残りやすい
ストップモーション動画はインパクトがあるため、記憶に残りやすくなります。独特な動きの世界観や現実では実現できないような動きを再現でき、ついつい見てしまう方も少なくありません。
独特な動きとは、カクカクとした動きになることです。コマ撮りをつなげているため、通常の映像とは違う動きになり、印象的に映ります。
また、現実では実現できないような動きとは、空を飛んでいるように見えたり人形などが勝手に動いているように見えたりする映像です。
幅広い年代に視聴してもらえる

ストップモーション動画は幅広い年代に視聴してもらえます。人形や紙粘土などを使用して作られるアニメーションも多いため子ども受けがよいでしょう。
また、1900年代前半のアニメはストップモーションの技術を用いて制作されることがよくありました。そのため、大人の方にとっては懐かしさを感じる映像になります。
ストップモーション動画の作り方
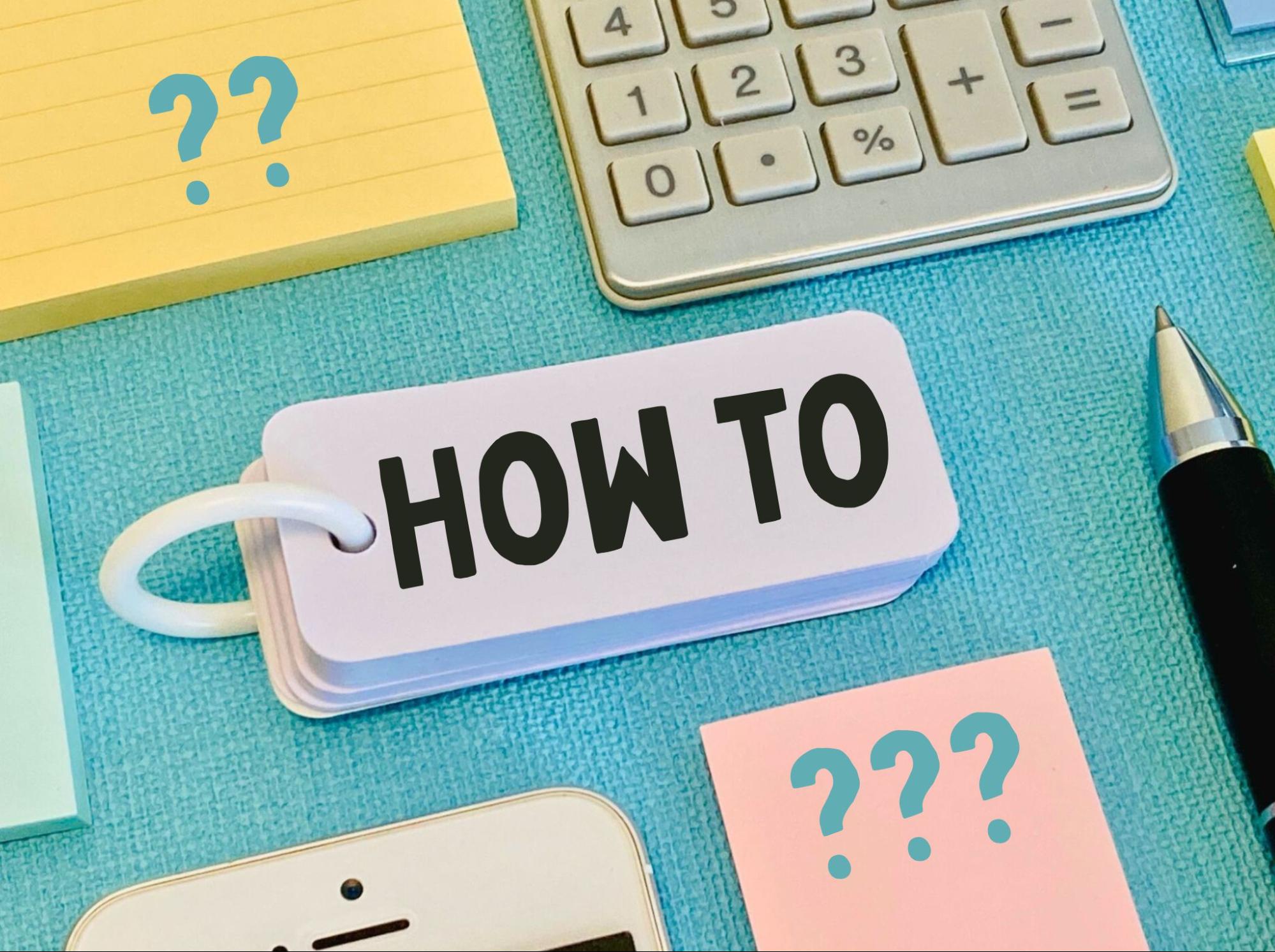
ストップモーション動画の制作は、特別な技術を必要とせず誰でも挑戦できる反面、静止画をいくつもつなげて動いているように再現しないといけないため根気のいる作業となります。
制作の際は、順序立てて進めていかなければなりません。撮影をするまでには、始めにストーリーを決めておきます。
次に、ストーリーに沿った環境を作ったり撮影機材を準備したりして撮影開始です。
ここでは、具体的にどのように制作するのか以下の項目に沿って解説します。
ストーリーを決める
ストップモーション動画制作を進めていくうえで、ストーリー決めは重要です。まずは、ターゲットや目的を明確にしておけばストーリーも決めやすくなります。
誰に向けて何を伝えたいのかという軸を持っておくとよいでしょう。この軸に沿ってストーリーを膨らませていきます。
また、ストーリーを決める時点で映像制作に必要な写真枚数を把握しておくと、撮影もすすめやすくなります。
必要な写真枚数は、1秒あたりに使用するコマ数を決めておくとよいでしょう。
場所や機材など撮影環境を準備する

ストーリーが決まれば、次は撮影環境の準備です。被写体の動きを少しずつ変えて、ブレずにコマ撮りするにはカメラの固定が大切です。
三脚で固定し同じ位置や角度で、ズレないように撮影します。
また、撮影の場所も大切です。屋外で撮影する場合は、時間経過や天候により日光の量が変動するため注意が必要です。
長時間撮影となれば、光量の変化が影響し、映像の始めと終わりで雰囲気の違うものになりかねません。
そのため、できれば室内やスタジオなどの安定した光量を得られる場所が適しています。
このような場所や機材の準備が自分たちでは難しい場合は、プロへ相談するのも一つの方法です。
動画制作のプロであれば、撮影機材が揃っていたりスタジオを持っていたりします。また、動画制作のノウハウを活かしたアドバイスをもらえることも期待できます。
動画制作のプロへの相談は、ぜひFunusualにお気軽にお問い合わせください。
Funusualでは、豊富な動画制作の経験を持っており、クライアント様の希望に寄り添って動画制作を行っています。
MOUNTAINというプロフェッショナル動画クリエーターを集結したプラットフォームの運営も行なっており、プロ動画クリエーターとの連携で企業の求める動画制作に適した制作チームを編成します。
そのため、幅広い業界のニーズにも対応可能です。気になる方は、ぜひ一度相談してみてください。
撮影と編集を行う
準備が整えば、次は撮影をして編集をします。始めに決めたストーリーの構図に沿って写真を撮ります。
進める際は、写真を見返しながら被写体の位置にズレはないかの確認が大切です。
写真が揃えば、次は編集です。始めに決めた1秒間あたりのコマ数に応じて、動画編集ソフトなどを使用してつないでいきます。
必要に応じてBGMや字幕を入れると、さらに印象的になることもあります。
ストップモーション動画を自作するときに必要なもの

ストップモーション動画を制作する際に必要なものは、撮影機材と撮影する被写体になる素材、そして編集に使用する動画編集ソフトです。
どれも、ストップモーション動画の制作には欠かせません。ここでは、それぞれどのようなものが必要になるのか紹介します。
三脚
三脚はカメラを固定するために必要不可欠です。ブレないように安定させるためにも、足の太いものがおすすめです。
本格的に撮影をしたい場合は、カメラの角度を細かく調整できる雲台付きの三脚などもあります。
しかし、いきなり本格的に始めるのは不安がある方もいるのではないでしょうか。とりあえず試しに撮ってみたい場合は、カメラが固定できる三脚を準備します。固定ができていれば映像はブレにくくなります。
カメラ

カメラはできれば、一眼レフカメラでの撮影がおすすめです。なぜなら、カメラの露光やホワイトバランスの調整が可能なためです。
露光は、写真の明るさを調整できます。また、ホワイトバランスは白い色が白く映るように写真の色味を調整することです。
白色をはっきりさせるだけでなく、写真全体の色合いを調整することもできます。これらが調整できることで、制作したい動画にあわせて写真の雰囲気を変えられます。
さらに、一眼レフカメラはレンズの変更も可能です。撮りたい内容にあわせてレンズを変更すればよりクオリティの高い動画となるでしょう。
ほかにも、カメラを選ぶ際はバッテリーを直接充電しながら使えるものがおすすめです。ストップモーションは長時間の撮影になる傾向があります。
充電しながら撮影ができれば、バッテリー切れなどで中断することなく続けられるため、撮影はスムーズに進みやすくなります。
ライト
ライトは、写真の明るさや被写体の写りを安定させるために必要な機材です。光量が安定していなければ、途中で映像が曇ったり影が入ったりしてしまい統一感のない動画になってしまいます。
外部からの光の影響などを受けにくいように光量の調整ができるライトがあるとよいでしょう。また、ライトも固定をしたり高い位置からライトを当てたりしたい場合は、ライトスタンドの準備も必要です。
撮影素材

撮影素材にはさまざまなものがあります。ストップモーション動画で使用されやすい素材は、主に以下のとおりです。
- 紙
- 人形
- クレイ(粘土)
- 黒板
紙は、折り紙や小さく切ったチラシなど身近なものから使用できます。
例えば、折り紙であれば折る工程を一つひとつ撮影し、つなげれば折り紙が勝手にできあがっていくような映像を作れます。
小さく切ったチラシも、集めて形を作る様子を一つひとつ、つなげれば切ったチラシが勝手に集まってくるように見える不思議な感覚になる映像となるでしょう。
人形は、ストップモーションを活用したアニメーション作品でよく使用されます。ポーズを少しずつ変えて撮影した映像は、まるで人形が勝手に動いているようにみえます。
クレイも人形同様に、アニメーション作品などでよく使用される素材です。クレイの場合は、クレイ自体の形を変えられるため、人形よりも自由度の高い動きが作れます。
黒板やホワイトボードなどを使用した場合は、文字や絵が描かれていく様子をコマ撮りで撮影します。
芸術的な文字や絵が描かれていく様子は、ついつい見いてしまう方も少なくありません。
このほかにも、人間自体が被写体となり、少しずつポーズを変えながら撮影する方法もあります。
人間を被写体にした場合は、1秒に使用するコマ数を少なくすれば、逆に人間が操り人形のように見えることもあります。
動画編集ソフト
動画編集ソフトは、撮影した写真をつなげるために必要です。また、動画編集ソフトによっては、さまざまな機能があります。
プロ仕様の動画編集ソフトでは、カメラとパソコンをつなげて、パソコンで撮影の設定をしたりデータをすぐに編集したりと撮影しながら編集できる動画編集ソフトもあります。
とりあえず、編集をしてみたいという場合は、無料版を使ってみるのもよいでしょう。動画編集ソフトのなかには、無料で使用できる動画編集ソフトもあるので試しに編集してみることも可能です。
ストップモーション動画を作るときの注意点

ストップモーション動画を制作する際は、コマ数や動画のつながりに注意が必要です。これらの点を無視すればチグハグな映像になったり思ったようにつながらなかったりします。
チグハグな映像にならないためにも、ストップモーション動画では手間をかける必要があります。手間をかけただけ、クオリティの高い映像が作れるでしょう。
ここでは、具体的にどのようなことに注意をすればよいか解説します。
適切なコマ数を設定する
ストップモーション動画を作る際の注意点は、適切なコマ数を設定することです。一般的には、1秒あたり5枚が目安とされています。
その目安を基準に、制作したい動画のイメージに合わせて調整が必要です。ストップモーション動画では、コマ数が映像の滑らかさに影響します。
滑らかな映像にしたい場合は、1秒あたりに使用する枚数は12〜24枚必要です。24枚に近いほど映像は滑らかになりますが、ストップモーションの特徴的な動きは出づらくなります。
そのため、誰に何を伝えるのかという目的をもとに、どのような映像を制作したいのかイメージをしっかり固めておくとよいでしょう。
被写体の高さを揃える
ストップモーション動画を制作する際は、被写体の高さを揃えることも大切です。写真一枚一枚の、被写体の高さを揃えなかった場合、動画がきれいにつながりません。
被写体の位置がズレれば、背景もつながらずチグハグな映像となってしまいます。
被写体の位置や高さがズレないためには、はじめの位置を把握しておく必要があります。定規で測っておいたり映像に映らない範囲にマークをつけたりする工夫が必要です。
手間がかかる
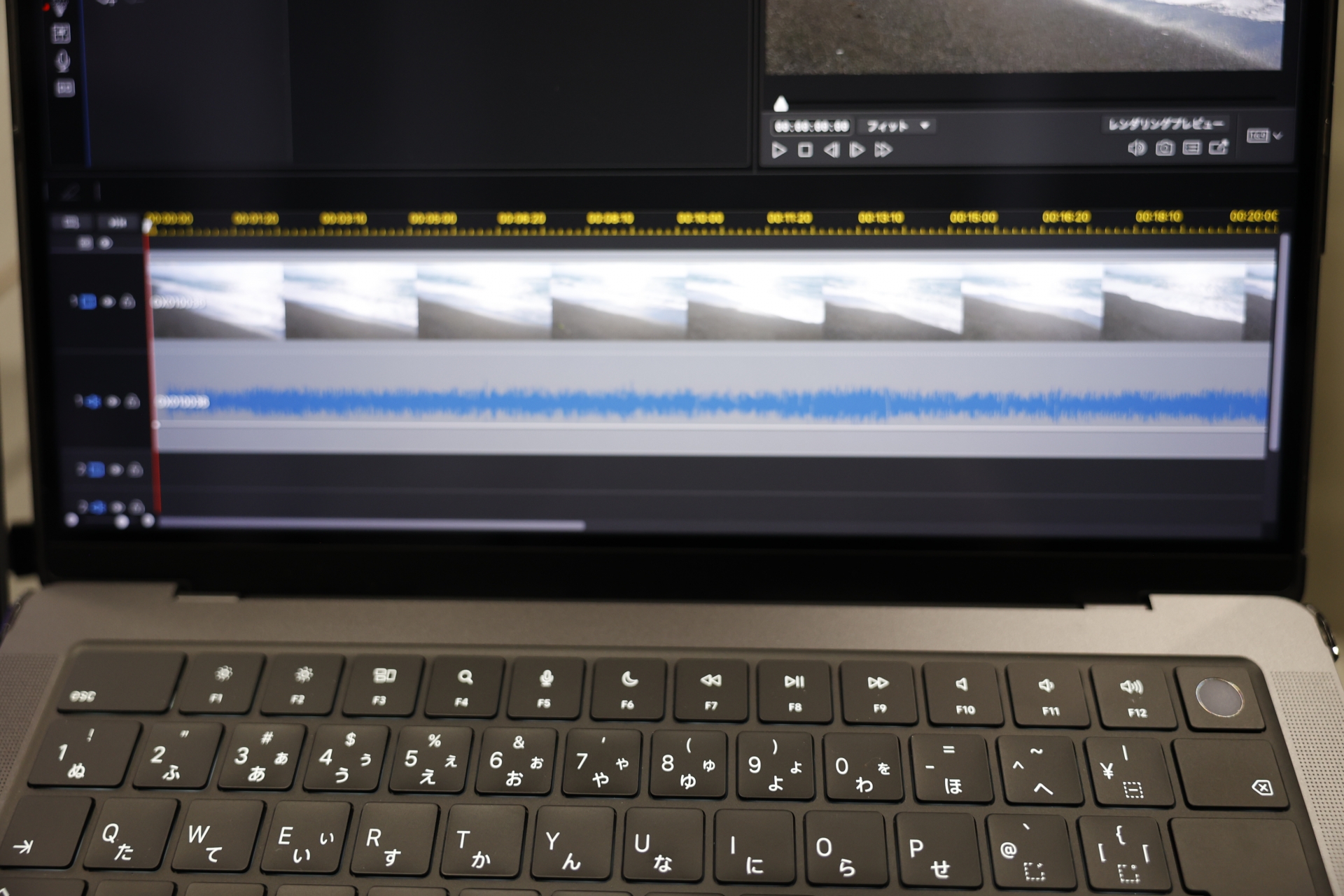
ストップモーション動画を制作する際は、手間がかかることを承知のうえで取り組むとよいでしょう。
例えば、コマ数を1秒あたり5枚に設定した場合でも10秒の映像を作るだけで50枚の写真が必要です。さらに、その50枚の映像がズレないように細心の注意をしなければなりません。
これを滑らかな映像で作りたい場合は、さらにコマ数が増え、手間もかかります。このように自作で制作する際は、多くの時間と労力を使います。
自作での制作に苦戦するようであればプロに相談してみませんか。
Funusualでは、豊富な経験と専門的な動画制作ノウハウをもとにクライアント様のニーズに寄り添った動画制作をします。
動画制作は、動画の企画から事前準備、撮影や編集だけでなく修正対応までワンストップです。
まずはヒアリングでクライアント様の目的や期待効果、事業内容や製品の特徴を把握し無料で絵コンテやストーリーの提案をします。
プロへの依頼に不安がある方も、まずは無料相談で課題の整理から始められます。動画制作でお悩みの際は、ぜひ相談ください。
ストップモーション動画制作を外部へ依頼したときの作り方と費用相場

ストップモーション動画制作を外部に依頼した際の流れは、以下のとおりです。
- 企画(打ち合わせ)
- シナリオ作成
- 撮影準備
- 撮影
- 編集
まず、どのような動画にしたいのか打ち合わせを行い、企画を立てます。そのため、打ち合わせ前に企業の方針を固めておくと打ち合わせも円滑に進むでしょう。
そして、企画に沿ってシナリオを作成し、絵コンテを作成します。
絵コンテが必要な理由は、制作の流れがわかりやすく表現でき、制作チームで共有しやすくなるためです。
シナリオが完成すれば、撮影準備をします。動画制作に必要な機材や撮影場所の準備、被写体となる撮影素材を揃えます。
準備が整えば撮影を行い、撮れた写真を編集でつなげて完成です。プロの動画クリエイターの技術によりクオリティの高い動画制作が期待できます。
この打ち合わせから編集までの費用相場は約200,000〜500,000円です。しかし、この費用は動画の内容によって変動することもあります。
ストップモーション動画の活用事例

ここでは実際に、ストップモーション動画を用いたアニメーションの動画広告で、注目を集めた企業の事例を紹介します。
これから紹介する事例の企業はそれぞれ別ジャンルのものですが、自社製品をどのようにストップモーションで活用するのか参考にできるのではないでしょうか。
タカラトミー
タカラトミーは自社製品のおもちゃを使用し、ストップモーション動画でアニメを制作しています。
YouTubeなどで放映されており、おもちゃが動いて展開するシンプルなストーリーは小さなお子さんでも理解しやすい内容です。
このように、通常は動かないおもちゃもストップモーションを活用すると、おもちゃが意思を持って動いているように見えます。
また、おもちゃが動く様子を見て遊び方を知ることもできます。そのため、子ども達の購買意欲の促進にもつながるでしょう。
ゼスプリ・インターナショナル・ジャパン
ゼスプリ・インターナショナル・ジャパンは、ゼスプリで販売するキウイのキャラクターを使用したストップモーション動画によるアニメーションのCMが有名です。
シリーズ化しているCMソングは、ヘルシーは楽しむものというメッセージが込められており、歌詞の内容に共感し涙する方もいるそうです。
このように、ストップモーション動画では自社製品に関するオリジナルキャラクターを用いたアニメーション制作もできます。
親しみやすい内容でありつつも、ついつい見入ってしまう映像はみる方の心をつかむでしょう。
インパクトのあるストップモーション動画を作りたいなら

ストップモーション動画を制作するには、まず目的やターゲットを明確にしストーリーを設定することが大切です。ストーリーに沿って機材や素材の準備をし、撮影をします。
撮影では、コマ数を決めておき、ズレのないように被写体の高さをあわせながら撮影しなければなりません。そのため、手間がかかることは念頭においておきましょう。
通常の業務に加え、企画・撮影・編集など行うことを考えると、多くのリソースを必要とします。自社での制作は難しいかもしれないと悩まれている方はFunusualへご相談ください。
Funusualは、各業界の企業の特性にあわせてアプローチが可能です。これまでの経験で培ってきたノウハウを用いて高品質な動画制作をします。
実写やアニメーションどちらも制作可能です。企業の特色にあわせ、適切な表現を提案します。まずは、ヒアリングで今のお悩みをお聞かせください。
クライアント様の事業内容や商材の特徴を丁寧に把握し、具体的な動画のイメージを提案します。













