SNSや動画配信プラットフォームに分散型メディアを構築して動画を投稿する動きが注目を集めています。
自然な拡散が期待できて集客のコストを抑えられる手法です。
ターゲットに合わせたコンテンツを投稿すると自社のよい宣伝になるでしょう。今回は分散型メディアの特徴や注目を集める理由のほか、動画活用のメリットやデメリット、制作のコツを紹介します。
従来の手法とは異なるマーケティング手法に興味がある経営者やマーケティング担当者はぜひ最後までご一読ください。
分散型メディアとは
 分散型メディアは自社のWebサイトやオウンドメディアとは一線を画す媒体です。
分散型メディアは自社のWebサイトやオウンドメディアとは一線を画す媒体です。
コンテンツを直接SNSや動画配信プラットフォームに投稿するため、情報の即時性や拡散性が期待できます。はじめに分散型メディアの定義や将来性を明確に理解しましょう。
分散型メディアとは何か
分散型メディアはリンク先のホームページがなく、SNSのアカウントや動画チャンネル上で完結するコンテンツです。
基本的にはフォロー中のユーザーに向けて動画を配信して、定期的に投稿を繰り返します。
また分散型の言葉のとおり、複数のチャネルを併用する特徴があります。
TwitterやInstagram・TikTok・YouTube・Podcastという風に組み合わせてマーケティングを展開するパターンが一般的です。
分散型メディアを構築する企業は、必ずしも自社のWebサイトを保有する必要がありません。
配信や問い合わせ対応、効果測定はすべてSNSのアカウントや動画配信チャンネル上で完結します。
分散型メディアの将来性
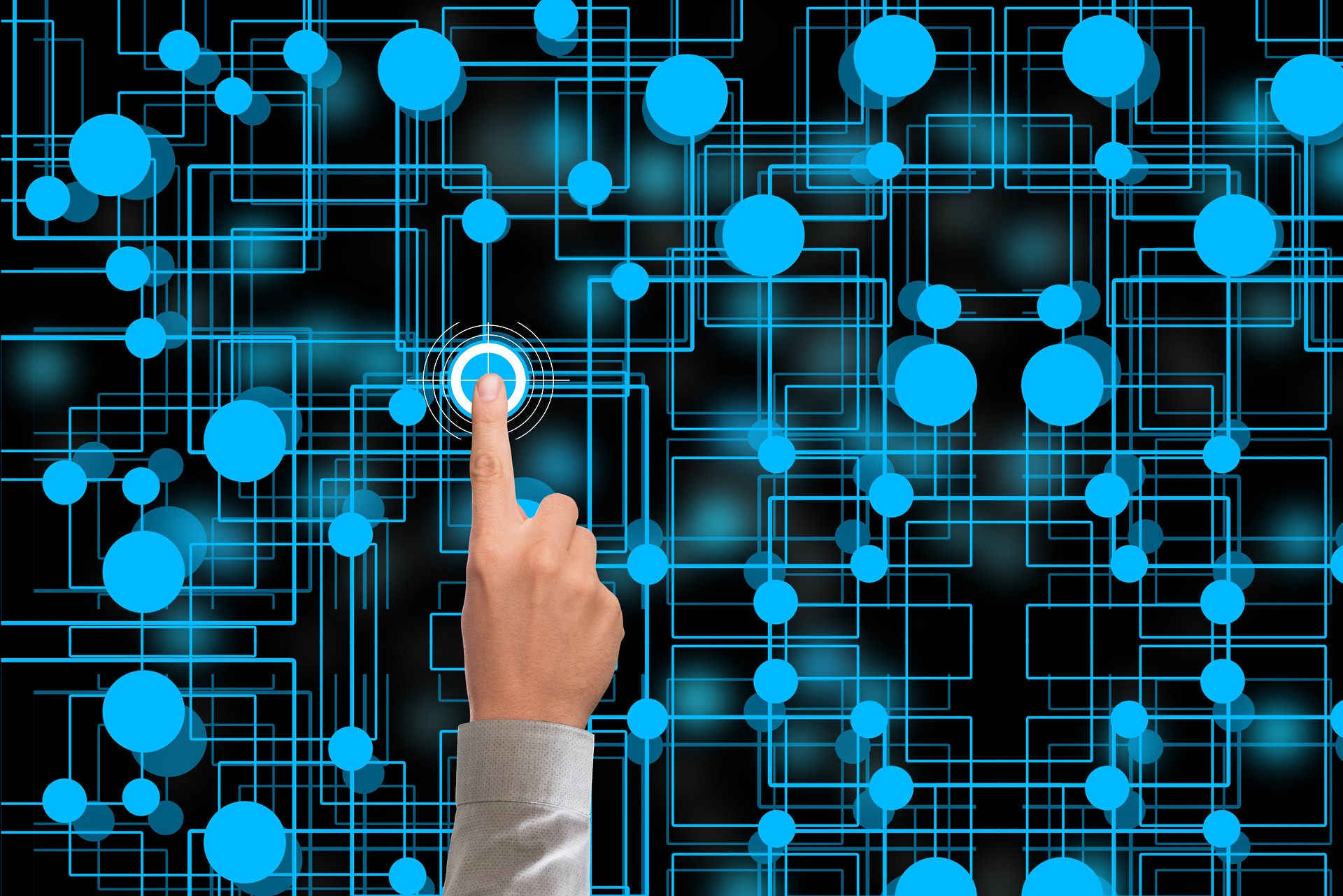 分散型メディアは将来性が高いデジタルマーケティングの手法です。世界中のソーシャルメディアの利用者数は2023年の49億人から2028年には60億5,000万人に上昇すると推定されています。
分散型メディアは将来性が高いデジタルマーケティングの手法です。世界中のソーシャルメディアの利用者数は2023年の49億人から2028年には60億5,000万人に上昇すると推定されています。
特に動画コンテンツの視聴やライブコマースの用途におけるニーズの増加が顕著です。
仮想空間でアバターを活用してコミュニケーションを図るメタバースSNSも、若者を中心に普及する見通しが立っています。
同時に今後は、多種多様化するSNSの融合や統合の動きが加速化する可能性が高いでしょう。分散型メディアはこれらの予測とマッチする将来性がある手法といえます。
今後は自社サイトを構築せずSNS完結型の販売促進活動に取り組む企業が増えると予想できます。
分散型メディアが注目されている理由
 分散型メディアに対して企業や求職者、消費者からの注目が集まり始めています。
分散型メディアに対して企業や求職者、消費者からの注目が集まり始めています。
スマートフォンやタブレットの普及に伴い、動画コンテンツの視聴者数や閲覧時間が長くなったためです。
また拡散力の高さやユーザーとのタッチポイントの多さも要因の一つです。
企業の視点に立つと、自社サイトの立ち上げやブログ投稿の積み重ねの必要がなく、手軽に実施できる手法といえます。
販促用のランディングページやホームページを作らなくても、既存のSNSアカウントでマーケティングを完結できるにこしたことはありません。
バズる投稿や動画を作ることで、自社サイトを充実させるよりも手軽に認知度やイメージを向上できます。
分散型メディアで動画を活用するメリット
 分散型メディアにテキストや画像ではなく動画を活用する利点は大きく、各所から注目を集めています。
分散型メディアにテキストや画像ではなく動画を活用する利点は大きく、各所から注目を集めています。
撮影や編集に手間がかかり通常の記事の投稿より工数がかさんだとしても、制作する意義があるコンテンツです。
分散型メディアを活用したマーケティングに動画を使用するメリットを紹介します。
コストを抑えられる
アカウントの開設が無料で可能なプラットフォームが多く、コストを抑えられる手法です。
自社サイトやオウンドメディアの構築とは異なり、サーバーの手配やドメインの調達に伴う費用がかかりません。
初期費用以外にも定期的な更新料が伴います。また従量課金型のクラウドサーバーを活用すればコストを抑えることは可能ですが、ゼロにはできません。
このように分散型メディアは費用面の負担が小さく、誰でも始めやすい手法です。
予算に限りがある中小企業はぜひアカウントの開設を検討しましょう。
SNS利用者が増加しており拡散が期待できる
前述のとおりソーシャルメディアの利用者数は将来的に増加に向かう見通しが立っています。ユーザーが多い環境で勝負した方が集客や販売促進によい効果を生むのは当然です。
また分散型メディアの利点は、拡散によりフォロワー以外にも自社のコンテンツを届けられることです。
「シェアしたい」と自然な感情を想起させる良質な動画を投稿すれば、企業名やブランドの名称が一気に浸透するでしょう。
動画本来の訴求力の高さや情報量を活かして短めの尺のコンテンツを作ることが、拡散を増やすポイントです。
分散型メディアで動画を活用するデメリット
 分散型メディアはこれからの時代に即した手法の反面、決して万能とはいえません。各プラットフォームの制約や効果的なコンテンツの作り方を意識する必要があります。
分散型メディアはこれからの時代に即した手法の反面、決して万能とはいえません。各プラットフォームの制約や効果的なコンテンツの作り方を意識する必要があります。
分散型メディアで動画を活用するデメリットは次のとおりです。
制作にあたって制限がある
制作した動画は、各プラットフォームが推奨する縦横比やファイルサイズに合わせる必要があります。
また分散型メディアの運用を成功に導くためには、複数媒体に展開する戦略が求められます。
エンコードやファイルの圧縮に手間どり、スケジュールどおりに投稿できなくなる可能性も否定できません。
さらに各プラットフォームによって異なるハッシュタグの使い方に対する理解も必要です。
社内にSNS運用のノウハウがある人材がいないと、マーケティングの推進が難しくなる傾向があります。
動画が拡散されないと集客につながらない
 分散型メディアの成功を分かつポイントは拡散数です。せっかく動画を公開してもシェアの数が少ないと効果は半減します。
分散型メディアの成功を分かつポイントは拡散数です。せっかく動画を公開してもシェアの数が少ないと効果は半減します。
もともと数千〜数万人規模のフォロワーがいるならフォロワーに情報が届けばよいかもしれません。
しかし多くの場合、認知度の向上や新商品の宣伝のために、極力多くのユーザーに投稿を見てほしいと考えます。
コストをかけずに閲覧数が増える拡散は、企業にとって積極的に狙いたい戦略です。しかし広まりやすさは裏を返せば悪評が伝達する範囲の大きさやスピードの速さを意味します。
節度を保って、悪ふざけだととらわれない倫理的に問題がないコンテンツ作りが求められます。
ターゲットに合わせてコンテンツを制作する必要がある
ターゲットの年代や性別、属性を意識して、興味をもたれるコンテンツを制作しなくてはいけません。
50代の男性向けにトレンドのファッションや美容ネタを発信してもよいリアクションは期待できません。
ターゲットとマッチしない動画は拡散が期待できず、費用対効果が悪い結果に終わる可能性が高いでしょう。
また分散型メディアは、各プラットフォームの利用者層を意識したチャネルの選定が重要です。
Instagramは10代や20代の女性、Twitterは30〜40代、Facebookは40〜50代というように主要な属性は年代ごとに異なります。
自社やブランド、商材のターゲットと合致するSNSを利用することで、多数の拡散を引き起こせるでしょう。
分散型メディアで使用する動画制作時のポイント
 分散型メディアを成功に導くには、ユーザーの印象アップに直結する動画の制作方法を知らなくてはいけません。具体的なポイントは次のとおりです。
分散型メディアを成功に導くには、ユーザーの印象アップに直結する動画の制作方法を知らなくてはいけません。具体的なポイントは次のとおりです。
- 動画の目的とターゲットを明確にする
- 細かくフィードバックして需要にコミットする
- 動画の更新頻度を高める
- 広告ではなく情報を提供する
- 開始数秒の短い瞬間で視聴者の興味を惹きつける
以下にそれぞれの注意点を具体的に記載します。
動画の目的とターゲットを明確にする
分散型メディアに動画を活用する目的とターゲットを明確にします。
テキストや画像より情報量が多く、エフェクトやテロップを駆使したリッチな訴求が可能な動画は、若年層を中心に視聴数が伸びています。
マーケティングにおける動画の有益性は明らかです。さらに一歩踏み込んで、認知度の向上や新商品の販売促進というように施策の目的をより具体的に決めるとよいでしょう。
コンテンツの企画や構成の軸を絞りやすく、より正確なマーケティングの推進につながります。
またフォーマットやSNSの選定に影響するターゲットの明確化も重要です。
細かくフィードバックを行い需要にコミットしていく
 何度もPDCAサイクルを回して、少しずつコンテンツを改善する取り組みが重要です。いきなりユーザーのニーズにはまる動画を投稿して、拡散が多発するケースは決して多くありません。
何度もPDCAサイクルを回して、少しずつコンテンツを改善する取り組みが重要です。いきなりユーザーのニーズにはまる動画を投稿して、拡散が多発するケースは決して多くありません。
一定のクオリティを満たすコンテンツを投稿後、適宜反応をみて改善を施す方針が効果的です。
分散型メディアに重要な指標はPV(ページビュー)ではなく、コンテンツの閲覧数を表すCV(コンテンツビュー)です。
SNSやプラットフォームごとに、特定の投稿や動画のインプレッション数(表示回数)を計測します。定期的に数値を解析し、目標に未達な場合は策を施して改善を待ちます。
動画の投稿頻度を高める
分散型メディアの成否を左右するポイントは投稿の質よりも量です。短い動画を早いテンポで公開する意識をもち、継続的に取り組みましょう。
更新頻度の上昇はリアクション率には大きな影響を与えない反面、リーチ率やインプレッション数の増加に直結します。
分散型メディアは、複数の媒体を使って認知度を高める際に効果的です。毎日または1週間に数回以上の頻度で、小刻みにコンテンツの投稿を続けた方が目的の達成に近づきます。
動画の尺は30秒〜1分程度の短さでも問題ありません。早いスパンで新たな投稿を生み出し、ユーザーとの接触機会を増やしましょう。
視聴者へ広告ではなく情報を提供する
 購入を目的とした広告色の強いコンテンツはユーザーに敬遠される傾向があります。視聴者が見たいと感じる有益かつおもしろい動画を公開する意識が求められます。
購入を目的とした広告色の強いコンテンツはユーザーに敬遠される傾向があります。視聴者が見たいと感じる有益かつおもしろい動画を公開する意識が求められます。
「前から知りたかった」もしくは「役に立ったから見てよかった」と喜ばれる投稿を目指しましょう。
よくある成功例は食品メーカーが自社の商品を用いたレシピを公開したり、化粧品メーカーが男性用コスメに特化した動画を制作したりするパターンです。
ターゲットに向けて気になるテーマのコンテンツを届けることは、良好なアクションの想起につながります。
自社起点だと特徴や魅力をアピールする押しつけがましい動画になりやすいことに注意が必要です。
開始数秒で視聴者に興味を持ってもらえるようにする
分散型メディアに投稿する動画は、最初の数秒で視聴者の興味を惹きつける工夫が求められます。
人間の第一印象と同様に出会った瞬間のタイミングが重要です。
現代人はインターネットの利用が一般化し、日々ブログやSNSを通じて多種多様なコンテンツにさらされています。
時間がなく忙しい方が少なくないため、ファーストインプレッションで見たいと感じさせないと離脱を引き起こします。
タイトルにはキャッチーなフレーズを入れ、映えるシーンを冒頭に位置づけましょう。また分散型メディアに投稿される動画は短尺のパターンが多いため、スピード感が重要な要素です。
開始数秒で視聴者の興味を惹きつけることに成功すれば、最後まで視聴を継続する可能性が高くなります。
分散型メディアに投稿するコンテンツのコンテンツビューを向上させるためには、企画力と編集力が必要です。
動画制作に不慣れな方が、ユーザーの注意を引く優れた動画を作ることは難しいでしょう。
悩みを抱える方は、Funusualへのお問い合わせをご検討ください。私たちは高い具現化力を備えた専門動画エージェンシーです。
お客様の事業や商材の魅力や特徴が伝わるショート動画の提供が可能です。少しでも気になる方は次のリンクより無料相談をお申し込みください。
分散型動画メディアの制作方法と費用相場
 分散型メディアの制作方法は自社もしくは外部の制作会社の活用のいずれかです。それぞれの制作方法と費用相場を次のとおり紹介します。
分散型メディアの制作方法は自社もしくは外部の制作会社の活用のいずれかです。それぞれの制作方法と費用相場を次のとおり紹介します。
自社で制作する
企画から撮影、編集、公開後の効果測定にいたる一連の活動を自社内で完結する手法です。
マーケティング部門が先導してSNSの選定や動画の絵コンテの作成、スケジュールの調整を担うケースが一般的です。
自社制作の場合は基本的にコストを安価に抑えられるメリットがあります。
ただし作業の増加による残業代の発生や社内にSNS運用や動画編集のノウハウをもつ人材がいないときは追加の採用コストが伴うことに注意が必要です。
またいくらコストを抑えられるとはいえ、編集ソフトや撮影機材の購入、もしくはレンタル費用は発生します。
人材の調達に要するコストが発生しないと仮定したときの費用相場は約100,000円です。
長期的にコンテンツを作り続ける場合、人件費や撮影の負担が大きくなる可能性があります。
外部へ依頼する
 動画制作会社やフリーランスに制作を依頼する方法です。制作やスケジュールの調整を外部に一任できるうえにクオリティやスピードの観点でも優位性があります。
動画制作会社やフリーランスに制作を依頼する方法です。制作やスケジュールの調整を外部に一任できるうえにクオリティやスピードの観点でも優位性があります。
SNSの運用を専門会社に任せる場合の相場は月額100,000〜500,000円です。
またショート動画の企画から編集までフルパッケージの対応を求める場合の相場は50,000〜70,000円といえます。
一本単位で30秒〜1分程度のショート動画の制作を依頼する際の目安は5,000〜20,000円です。
外部に依頼するメリットは自社の要望を満たすクオリティの高い納品物の提供が期待できることです。
分散型メディアに魅力がないコンテンツの投稿を続けても、著しい効果は期待できません。
Funusualは動画クリエイターのプロフェッショナルが集うプラットフォームMOUNTAINを運営しています。
撮影ディレクターやドローンカメラマン、3DCGクリエイターをはじめ、さまざまな得意分野をもつ人材が在籍中です。
案件ごとに適切なプロフェッショナルを抜擢した制作チームを結成することが叶う環境です。
分散型メディアの展開に重要なプラットフォームの特徴およびターゲットの興味のポイントを押さえたコンテンツを制作できます。
少しでも興味がある方はぜひ次のリンクより今すぐお申し込みください。
分散型動画メディアの成功事例
 従来のようにWebサイトに記事を投稿してSNSとリンクさせるオウンドメディア戦略を実施してきた企業にとって、分散型メディアの構築は簡単ではありません。
従来のようにWebサイトに記事を投稿してSNSとリンクさせるオウンドメディア戦略を実施してきた企業にとって、分散型メディアの構築は簡単ではありません。
すでに成功したパターンを確認して参考になる箇所は学ぶことが大切です。
ここではTasty Japanとエブリー、C Channelの分散型メディアの活用事例を紹介します。
Tasty JapanのTasty ブレンド
Tasty Japanは自社のオリジナルコーヒーのTastyブレンドの公式SNSを運用しています。
動画にはコーヒーを淹れるシーンが撮影され、映像を通しておいしさが伝わる感情を想起させるコンテンツです。
ツイートには140字以内のキャッチーなフレーズで商品の魅力や特徴を伝える文言が記載されています。
末尾に購入ページへのリンクを掲載することで、動画の視聴から購入まで完結する導線が確保されています。
分散型メディアとはいえ、ホームページやECサイトと連携してはいけないとは限りません。
宣伝する商品の購入ページに遷移する導線はブログ記事とは異なるため、設置しても問題ありません。
株式会社エブリーのDELISH KITCHEN
株式会社エブリーはFacebookやTwitter、Instagramにまたがる分散型メディアのDELISH KITCHENを運営しています。
プラットフォームごとの特性を活かして訴求方法やコンテンツの見せ方を変えていることが特徴です。
全体の尺に加えてコンテンツの構成によって視聴維持率が異なる因果関係を発見したようです。
食材を映すタイミングを変えたり、単調な調理シーンはカットしたりなどの工夫を施して数値の改善に成功しました。
プラットフォームの特徴を踏まえて動画の内容を変える重要性を感じさせる参考事例です。
C Channel株式会社のC CHANNEL
C CHANNELは20代の女性をターゲットに据えて料理や記念日など幅広いコンテンツを投稿する分散型メディアです。
スマートフォンの閲覧が多いと予測をして、縦長動画を中心に配信しています。
Instagramではgirlやfood、nailなどテーマに応じて複数のアカウントを運営中です。
2015年4月の立ち上げ以来継続的にコンテンツを投稿して、Facebookのいいね数は530万、Instagramの各アカウントのフォロワー数は10万人超えの成果を挙げました。
分散型動画メディアの活用を成功させたいなら
 分散型動画メディアは、自社サイトを持たずともSNSや動画配信プラットフォームを活用して情報発信ができる、新時代のマーケティング手法です。
分散型動画メディアは、自社サイトを持たずともSNSや動画配信プラットフォームを活用して情報発信ができる、新時代のマーケティング手法です。
しかし、動画コンテンツの特性を理解せずに発信を続けてもユーザーの関心を集められず、十分な成果にはつながりません。
特に「どのSNSに・どのような動画を・どのような構成で投稿するか」といった判断が曖昧なままでは、拡散や集客には結びつきにくいのが実情です。
そこで企画から構成、撮影・編集、そして配信・運用までを一貫して担うFunusualのような動画制作会社の力が求められます。
Funusualでは、プラットフォームごとの特徴やユーザーの視聴傾向を的確にとらえたショート動画を提案・制作し、企業の認知向上や商品訴求に貢献しています。
分散型動画メディアを本格的に活用したいとお考えの方は、ぜひ以下のリンクからご相談ください。
目的やご予算に応じた適切な動画活用をご提案いたします。













