自社の動画制作をするのであれば、成果につなげられる動画を作りたいと考えるでしょう。動画制作で、構成は成果につながるか否かを分ける重要な要素です。
なぜなら、構成が曖昧だと伝えたいメッセージが視聴者に届かず、期待した成果が得られない可能性が高まります。時間やコストが無駄になってしまう可能性もあるのです。
本記事では、動画制作をするにあたって重要となる構成の考え方から具体的な作り方までを徹底解説します。
効果的な成果を導くための動画制作に役立てていただければ幸いです。
企業の動画制作における構成の重要性

動画制作の構成は、動画の成果を大きく左右する重要な役割を果たしています。
伝えたいメッセージが視聴者に正確に届き、最後まで視聴してもらえるかは、構成段階で決まるといっても過言ではありません。
例えば構成を曖昧にしたまま制作を進めると、内容の軸がぶれてしまい、結局何を伝えたいのかが不明瞭な動画になりがちです。
一方で明確な構成に沿って作られた動画は、一貫したメッセージで視聴者の興味を惹きつけ、最後まで飽きさせずに視聴を促すことができるでしょう。
内容に一貫性があるため、視聴者が理解しやすい導線作りが可能です。
また構成があると撮影の順序や動画の内容が明確になり、撮影や編集段階で手戻りが少なく、修正作業が減りスムーズに制作できます。
さらに、再撮影や再編集のリスクを低減し、予算超過を防げます。
企業向け動画では、商品の認知拡大や採用強化、ブランディングなどの目的があるでしょう。その目的を達成するには、視聴者に適切な順序で情報を届ける構成が不可欠です。
冒頭から視聴者を惹きつけ、離脱を防いで最後まで視聴を促す構成は、動画が目的とする行動へとつながる確率を格段に高めます。
高価な機材や美しい映像を使っても、構成が曖昧であれば期待する成果は得られません。動画制作の第一歩は、この構成の重要性の理解から始まります。
企業が動画制作をするうえでの構成の考え方

動画制作の成果を上げるためには、その構成にかかっているといっても過言ではありません。
ただ見栄えのよい映像を並べただけでは、視聴者に伝えたいことが伝わらず、途中で離脱される可能性が高まります。
ここでは、企業が効果的な動画構成を考える際に押さえるべき5つの重要なポイントを解説していきます。
目的やターゲットに合わせた構成にする

動画構成を考える第一歩は、動画の目的とターゲットを明確にすることです。販促や採用、ブランディングなど、動画に何を求めるのかを具体的に定める必要があります。
その目的に合わせて、ターゲットも具体的に設定しましょう。
誰のどのような課題を解決し、どのような未来を届けたいのかを明確にすると、視聴者に深く刺さる動画が制作できます。構成の軸がブレることもありません。
伝えたいメッセージを絞った構成にする
人間は一度に多くの情報を得た際、結局何を伝えたかったのかがわからず、行動にうつせないことがあります。そのため、伝えるべきメッセージを一つに絞り込むことがとても重要です。
一度に多くの情報を詰め込んでも、視聴者は情報過多になるだけで、結局何を伝えたかったのかわからない動画になってしまいます。
まずは、動画で伝えたい内容の核となるメッセージを言語化しましょう。
この軸となるメッセージを起点に伝える順序や内容を整理し、構成に落とし込むことで、一貫性のある視聴者の記憶に残る印象的な動画に仕上がります。
途中で離脱されない構成にする

動画は、冒頭の5秒から10秒で視聴者の離脱が決まるケースが多いといわれています。そのため、冒頭での興味づけは特に重要視されています。
例えば視聴者の課題を数字やデータで提示したり、既存の常識を覆すような問いを投げかけたり、見なければ損をすると思わせる演出を取り入れたりする工夫が効果的です。
また、冗長な表現や関係のない情報は極力省き、テンポよく展開する構成にすると視聴者に最後まで見てもらいやすくなります。
ユーザー目線を意識する
企業目線だけで構成を組んでしまうと、視聴者に自分ごととしてとらえてもらえない可能性が出てきます。
動画制作において重要なことは、視聴者の課題に寄り添い、その解決策を具体的に提示する構成にすることです。
例えば最初に視聴者の抱える課題に共感を示し、その解決策を提示します。さらに、その根拠や成功事例を示すことで、視聴者の行動を後押しする流れです。
このようなユーザーの行動プロセスに沿った構成は、自然と視聴者の感情に響き、高いエンゲージメントにつながります。
費用対効果も考える
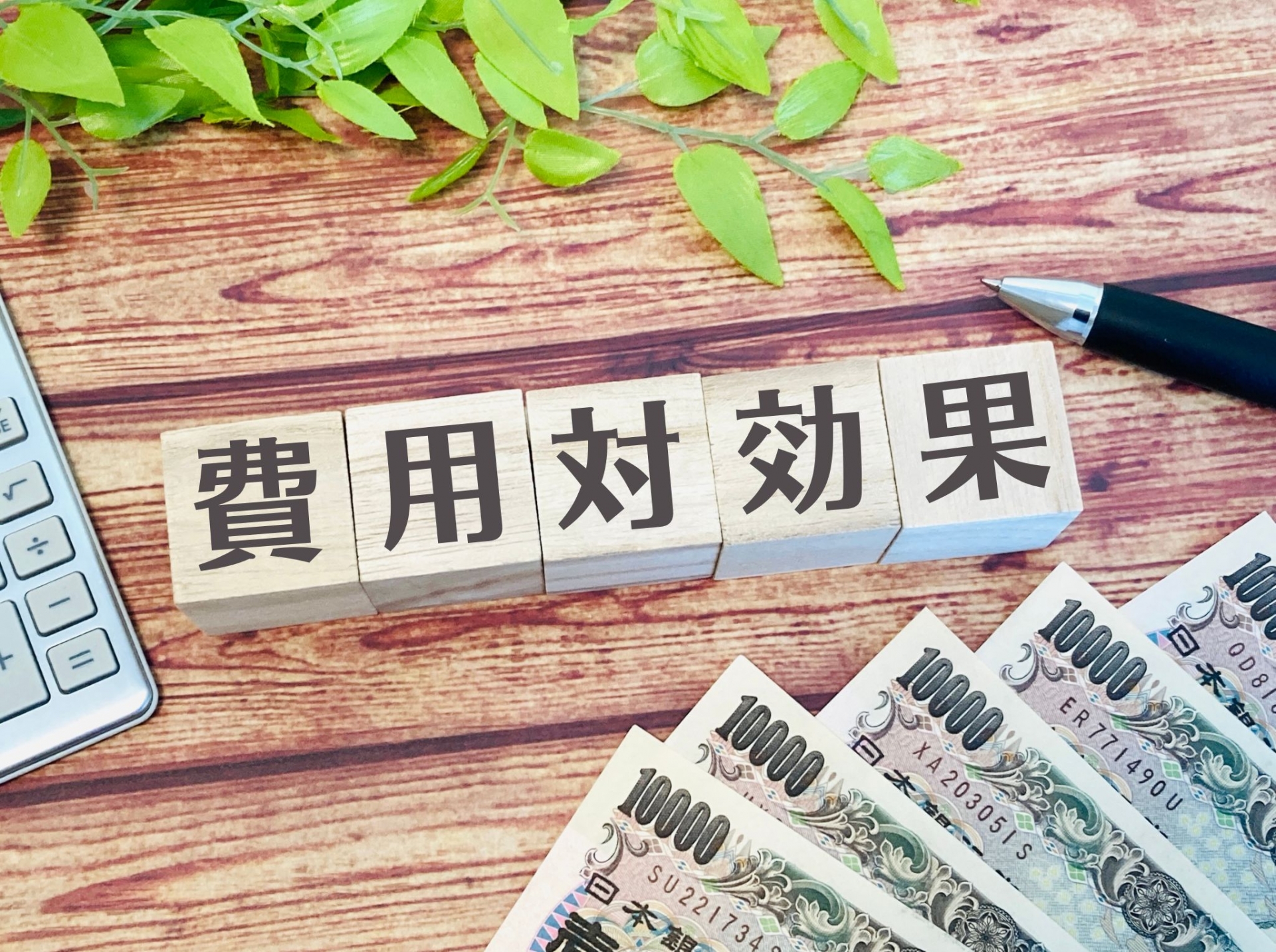
撮影や編集にはコストがかかります。そのため、構成段階で具体的に設計しておくことが、不要な撮影や修正を減らし予算内で成果を出すために不可欠です。
構成を固めることで必要な素材やシーン、情報が明確になり、手戻りや撮り直しなどの手間を防ぐことができます。
これは、限られた予算と時間のなかで動画制作を成功させるための重要なポイントです。
動画制作は、構成の考え方を明確にすれば、一気にブレのないプロジェクトへと変わります。
視聴者の具体的な悩みに寄り添い、解決するためのプロセスを軸にした構成は、視聴者の心を動かして企業の目的を達成するものとなるでしょう。
動画の構成を考える際に役立つフレームワーク

動画制作の構成をゼロから考えることは、多くの情報や要素を扱うためハードルが高く感じられるかもしれません。
そんなときに活用したいのが、構成の基礎を体系的に整理できるフレームワークです。
動画制作では、伝えたいメッセージを視聴者にしっかり届け、かつ目的の行動に導くことが求められています。
ここでは、企画段階で6W1Hを明確にしたうえで、具体的な構成を作成するための4つの代表的なフレームワークを紹介していきます。
CAMS
CAMSは、申し込みや購入など、視聴者に具体的な行動を促すことを目的とした動画に的したフレームワークです。
CAMSとはなにか、下記に詳しく説明します。
- Catch(つかみ):共感できる悩みや課題を提示し視聴者の興味を引く
- Appeal(訴求):その悩みを解決できるサービスや商品のベネフィットを紹介
- Motivate(動機付け):疑問や不安を解消する情報を伝え迷わず行動できる状態を促す
- Suggest(行動提案):今すぐ無料登録、まずは試してみるなどの行動を明示
動画が短く、全要素を盛り込みにくい場合には、AMSやASのように要素を絞った応用も有効です。
販促やキャンペーン告知、ランディングページの誘導などに特に効果的な構成といえるでしょう。
ABCD
 ABCDは、Googleが推奨する動画広告クリエイティブのフレームワークで、視聴者の心を動かすプロセスに特化した構成です。
ABCDは、Googleが推奨する動画広告クリエイティブのフレームワークで、視聴者の心を動かすプロセスに特化した構成です。
ABCDについて、詳しく下記にて説明します。
- Attract(注意を引く):冒頭5秒で惹きつける工夫を凝らす
- Brand(ブランド提示):ロゴや商品ビジュアルを使用し動画の早い段階でブランドや商品を明確に提示
- Connect(共感を呼ぶ):ストーリーや演出を通じて感情に訴えかけブランドとつながりを生み出す体験を設計
- Direct(行動を促す):割引・特典など明確なオファーやCTA(行動喚起)を提示し次のアクションへ誘導
YouTube広告やSNS動画など、短時間でインパクトを与えたい場合に向いており、動画広告初心者でも実践しやすい点が特徴です。
PREP
PREP法は、プレゼンや文章構成でも使われる汎用性の高いフレームワークで、論理的かつ簡潔にメッセージを伝えたいときに有効です。
PREP法について詳しく、下記にて説明します。
- Point(結論):最初に伝えたい主張や結論を明確に述べる
- Reason(理由):その結論に至る理由や根拠を補足説明する
- Example(具体例):事例やデータ、数字などを提示して視聴者に納得感を与える
- Point(再主張):再度結論を述べることで、メッセージを印象付け、理解を深める
導入説明やサービス説明など、複雑な情報を整理してわかりやすく伝える必要がある動画構成に適しています。
起承転結
起承転結は古くから物語構成に使われているフレームワークで、ストーリーを通してメッセージを届け、視聴者に自然な流れで感情移入や理解を促すのに適しています。
- 起:動画の始まり。問題提起や自己紹介、テーマ提示
- 承:導入した内容を発展させ、商品やサービスの具体的な情報や説明
- 転:ここで新しい展開や意外な事実、解決策となるベネフィットの紹介、強みや特長などを提示して視聴者の興味をさらに引きつける
- 結:全体のまとめと視聴者への行動喚起(CTA)
会社紹介やサービス説明、YouTuber型の企画動画など視聴者に自然な流れで内容を理解し、感情移入を深めてほしい場合に適しています。
構成がシンプルなので、動画制作初心者でも取り入れやすいのが利点です。
動画の構成の作り方
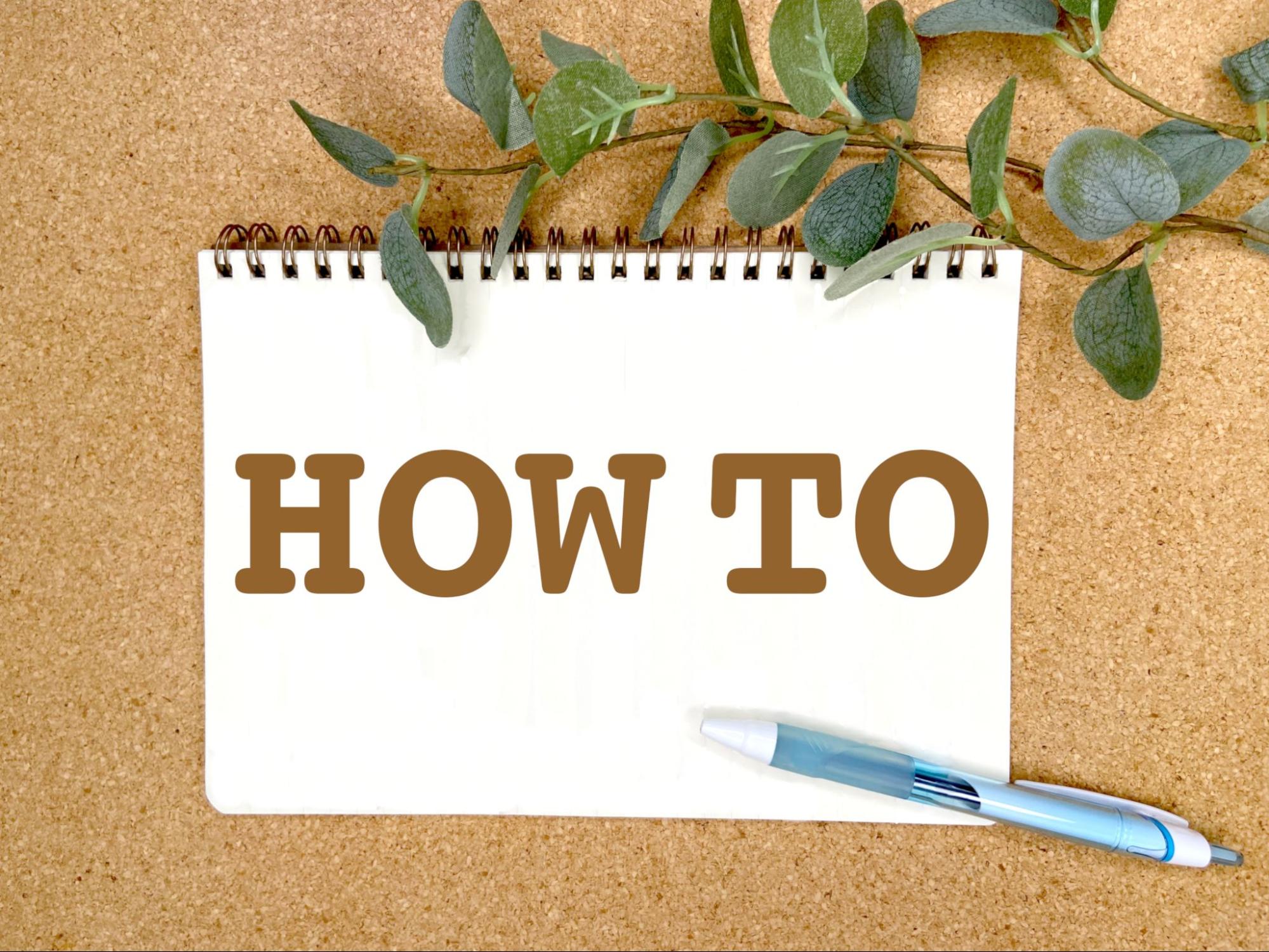
動画の構成をしっかり練ることで、視聴者にとってわかりやすく、企業の目的に沿った効果的な動画を制作できます。
ここでは、構成作成の基本ステップを5つに分けて説明します。これから構成を作成する方は、ぜひこの順番を意識しながら取り組んでみてください。
6W1Hを明確にする
構成を考える前にまずやるべきことは、動画の企画を6W1Hに落とし込むことです。
この段階で目的やターゲット、伝えるべき内容を明確にしておくことで、ブレのない構成が作成できます。
6W1Hについて、下記にて詳しく説明します。
- WHAT(何を):紹介したい商品やサービス、伝えたいメッセージの核
- WHY(なぜ):なぜこの動画を制作するのか、最終的な目的
- WHO(誰が):動画の発信者、登場人物、ナレーター
- WHERE(どこで):動画が視聴される媒体や環境
- WHEN(いつ):想定する視聴タイミング
- WHOM(誰に):動画を見てほしいターゲット層
- HOW(どのように):動画の形式やスタイル
この6W1Hを丁寧に整理することが、効果的な構成づくりの強固な土台となります。
配信先や配信方法を決める
動画の構成は、配信する媒体や視聴環境によって適切な構成が変わります。例えば、以下のように配信先ごとに構成の工夫が必要です。
YouTubeやInstagramのリール動画などのSNSでは、冒頭5秒で引き込む、つかみが重要です。短尺でのインパクト、字幕の活用、縦型対応なども考慮しましょう。
Webサイト掲載用動画では、企業のブランドイメージや信頼感を高めるストーリー構成、丁寧なナレーションや説明が重視されます。
営業ツールや展示会動画は目的が明確で、情報が整理されたコンパクトな構成が求められ、1~2分程度が理想とされています。
どこで、どのように動画が使われるのかを事前に把握し、配信方法に合わせた構成を設計しましょう。
動画の長さを決める

現代の視聴者は、スマートフォンで隙間時間での動画視聴が主流になっています。そのため、動画の長さは重要です。一般的には、次のような目安で設計します。
- SNS広告や認知目的の動画であれば30秒程度で長くて1分以内
- 商品紹介や採用動画などの本編型であれば1〜3分以内がベスト
- 深い理解を促すブランディング動画であれば3〜5分程度までが許容範囲
動画が長尺になればなるほど、テンポのよさや要点の明確さ、視聴者の興味を保つ工夫がより一層必要になります。
構成段階で長さを明確にし、各セクションの時間配分も意識しておきましょう。
動画のタイプを決める
構成が固まったら、次に検討したいのが動画のタイプです。
BtoB動画では大きく分けて実写とアニメーションがあり、伝えたい内容や見せたい印象によって適切な手法が異なります。
例えば実写は、人物や現場のリアルな雰囲気をそのまま映し出すことができ、信頼感や温かみを与えるのに効果的です。
社員インタビューやオフィス紹介、建設現場・製造現場の撮影など、リアリティが強みとなる分野に適しています。
一方、アニメーションは抽象的なサービスや無形商材の説明に向いており、複雑な内容を図解やイラストで整理して伝えることが可能です。
特にIT系やコンサルティング業では、フラットアニメーションでプロセスを視覚化し、理解を促す動画が好まれます。
どちらを選ぶかは、誰に何をどう伝えたいのかによって変わります。構成段階で想定したターゲットと目的を考えたうえで、表現手法を検討していきましょう。
動画のタイプに合った構成を選ぶことで、視聴者の感情や行動に自然とつながる、効果的な流れをつくれます。
動画の流れを書き出し時間配分をする
動画制作の構成をつくる最後のステップは、実際の動画の流れを時系列で具体的に書き出し、各パートの時間配分を設定することです。
構成表を用意すると、制作全体がスムーズに進みます。
構成を3〜4ブロックに分けて各パートの所要時間を想定しておくと、時間オーバーや伝えたいことが散漫になるなどの問題を防ぎ、効率的な動画制作につながります。
構成作成後の動画制作の流れ

動画制作の構成が固まったら、いよいよ制作の段階です。このフェーズでは事前準備から撮影や編集、公開に至るまで、いくつかのステップを順に踏んでいきます。
それぞれの工程でどのような準備が必要で、どのような点に注意すべきかを解説していきます。
撮影や素材の準備
構成ができあがったら、まずは撮影や素材の準備に取りかかります。実写動画であればロケ地の選定から機材やスタッフの手配、出演者とのスケジュール調整などが必要です。
インタビュー形式や製品紹介など、動画の目的に応じて、撮影内容を具体的に落とし込むことが重要になります。
一方で、アニメーション動画を制作する場合は、絵コンテをもとにデザインやイラストの制作が始まります。
撮影がない分、構成段階での情報整理や表現の方向性がより重要です。
編集
撮影や素材の準備を終えたら、次は編集作業です。
編集では、撮影した映像や音声をタイムライン上で整理し、構成どおりに組み立てていきます。この時点でBGMやナレーション、テロップなども加えます。
ここでのポイントは、視聴者目線でわかりやすくなっているかを常に意識することです。
情報量が多すぎたり、映像が長すぎたりすると、視聴者の多くは途中で離脱してしまいます。
伝えたいメッセージを端的に表現するため、不要な部分は大胆にカットし、テンポのよい編集をすることが大切です。
公開
編集が終わり、関係者の確認を終えたら、いよいよ公開です。公開方法はさまざまです。
YouTubeや自社サイト、展示会や営業現場での活用など、目的に応じたチャンネルの選定が重要になります。
この段階で気を付けたいのは、公開した後の活用方法まで想定しておくことです。クオリティの高い動画でも、見られなければ効果は出ません。
動画に視聴者へ行動を促す導線を設けたり、SNSやメールマガジンで動画を告知したりすることが、効果をさらに引き出す鍵となります。
構成を重視して動画を作りたいなら動画制作会社への外注がおすすめ

動画制作は、構成力が動画の成否を分ける鍵となるため、動画制作会社への外注がおすすめです。
特にBtoB領域では、誰に・何を・どう伝えるかの戦略的な設計が不可欠であり、この設計力こそが動画の成果を左右します。
動画制作会社であれば、ビジネス目標を深く理解した戦略的な構成力で動画の成果を高められるでしょう。
プロの機材と技術による高品質な映像はブランド価値を高めることが期待できます。
企画から編集までの全工程を任せられるため、社内の時間や人的リソースを大幅に削減し、業務に集中できる点もメリットです。
外部の専門家による客観的な視点と迅速な問題解決は、動画の精度向上につながるため、コスト削減も期待できます。
Funusualでは、お客様の課題に寄り添い、戦略的な企画から修正対応までワンストップでサポート可能です。
これまで対応してきたさまざまな実績と優れたディレクション力で、初めての方でも成果につながりやすい動画を実現します。
構成を重視した動画制作をお考えであれば、まずはお気軽にご相談ください。
動画制作会社に外注する場合の費用相場

動画制作を外注する場合の費用は、目的や内容や動画の長さ、どこまで依頼するかによって大きく変動します。
動画制作全体の費用相場は、一般的に100,000円から3,000,000円と幅広く設定されているのが実情です。
単なる編集のみであれば3,000〜50,000円程度、企画から編集まですべてを含む本格的な制作では300,000〜1,000,000円程度になってきます。
アニメーションや複雑なCG、表現にこだわるほど費用は高くなります。
重要なのは単に費用で選ぶのではなく、動画で何を達成したいかを明確にし、その目的をよりしっかりと実現できる構成力と品質を提供できる制作会社を選ぶことです。
FunsualはBtoB企業の多様な動画ニーズに対し、企画コンテから撮影と編集、そして修正まで一貫したサポートを行っています。
実写・アニメーション問わず、品質と成果にこだわりを持った動画制作を実現します。どこに相談したらよいか悩んでいるのであれば、まずはお気軽にお問い合わせください。
魅力的な構成の動画を制作するなら

動画制作を検討する際、どうすれば成果につながるのか、魅力的な動画制作ができるのかと悩んでいる企業担当者の方は少なくありません。
自社での製作か外注か、どちらを選ぶにしても、重要になってくるのは構成力です。いかにして視聴者の心をつかみ、目的の行動を誘導する動画にするかは、優れた構成があってこそです。
つまり、魅力的な動画制作を成功させるには、戦略的な視点とプロのノウハウが重要になります。
そのため適切な動画制作会社選びが、動画制作の成否を分けます。単に制作費で選ぶのではなく、自社のビジネス課題に寄り添い、目的達成のための構成を考え抜いてくれる動画制作会社を選定しましょう。
私たちFunusualはこれまで、多くの企業様の構成段階から一緒に向き合い、動画の成果に直結する企画提案を行ってきました。
目的や課題に応じて、適切な構成と演出をご提案することが可能です。構成づくりに悩んでいるなら、まずはFunusualにご相談ください。













