企業のブランディングや商品、サービスのプロモーション手段として、動画コンテンツの活用はますます注目されています。
社内に専門の人材や設備が整っていない場合は、外注という手段が有力な選択肢です。
一方で、外注による動画制作には少なからずトラブルがつきものです。納期の遅れや仕上がりのイメージ違い、著作権の問題が起こり、発注者にとって大きなリスクとなるケースもあります。
本記事では、動画制作を外注する際に起こりがちなトラブルとその原因や事前に防ぐためのポイント、万が一トラブルが起こった場合の対処法を詳しく解説します。
動画制作を外注に依頼を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
動画制作の外注でトラブルが起こる原因

動画制作を外注する際にトラブルが起きる背景には、発注者と制作会社との間にある情報のギャップが大きく影響しています。
動画制作に慣れていない企業や担当者の場合、専門的な知識が不足しており、適切な指示や期待値の共有が難しいケースが少なくありません。
また、感覚的な表現や曖昧な希望だけを伝えた状態で制作が進められてしまうと、できあがりに大きな差異が生じやすいでしょう。
信頼できる制作会社を選ぶことはもちろん大切ですが、発注者側もある程度の知識をもって臨む姿勢が求められます。
具体的には制作の目的や想定するターゲット層、動画の使用媒体などを明確にしたうえで、必要な要素を事前に共有し制作側と合意をとることが重要です。
制作の目的やターゲット、使用媒体などの要素を事前に共有し、制作側としっかり合意を取るという準備を怠ると思わぬトラブルに発展する可能性が高まります。
動画制作の外注で起こりがちなトラブル

動画制作を外注すると、完成物の質や進行時のコミュニケーションにおいてさまざまなトラブルが起こる場合があります。
特に、発注前の準備不足や意思疎通の不備が原因となるケースが多いです。
事前の確認や契約内容の明文化が、トラブル防止の鍵となります。
仕上がった動画がイメージと違った
もっとも多いトラブルの一つが、完成した動画が発注者の想定していたイメージと異なるというケースです。
色味や音楽の雰囲気、構成など抽象的な要素を十分に伝えられていないことで発生します。
また、サンプル動画の提示や構成案の共有といった段階を踏まずに制作が進められた場合、認識のすれ違いが生じやすいです。
イメージの共有が不十分だと、完成後に大幅な修正を依頼することになり、追加費用が発生する可能性もあります。
そのため、発注段階で具体的な参考動画やビジュアルガイドを提示し、制作者としっかり認識をすり合わせることが重要です。
クオリティが低かった

発注者が期待する品質に達していない動画が納品されるというケースも少なくありません。
制作会社のスキル不足や、担当者の経験不足が原因となることが多いです。
相場よりも極端に安い見積もりで発注した場合、十分な工数やプロフェッショナル人材を確保できない可能性があります。
また、実績やポートフォリオを確認せずに契約を進めてしまうと、完成品のレベルが事前に把握できず後悔につながることになります。
クオリティを重視する場合は、制作会社の過去の作品を確認したうえで、自社の目的に合った実績を持つ会社を選ぶことが重要です。あわせて、
動画のチェックとフィードバック体制も整備しておきましょう。
納期が守られなかった
制作スケジュールに遅れが出て、納品日が守られないというトラブルも頻繁に発生します。
制作会社のリソース不足や内部調整の不備だけでなく、素材の提出が遅く確認に時間がかかる可能性もあります。
納期を守るためには、両者がスケジュールを正確に把握し、各工程ごとの締切を共有しておくことが大切です。
また、途中で修正依頼や追加要望が入った場合の対応フローを事前に確認し、納期に影響が出るかどうかを都度判断できるようにしておきましょう。
納期遅延のペナルティについて契約書に明記しておくと、トラブルの抑止にもつながります。
予算をオーバーしてしまった
発注当初の見積もりを大幅に超えて、予算をオーバーする事態も多いです。
原因としては、修正回数の多さや後からの仕様変更、素材追加に伴う工数増加などが挙げられます。
また、契約時に費用の詳細や条件を明記していないと、後からこれは別料金ですと請求されることもあります。
このような事態を防ぐためには、見積もり段階で含まれている作業範囲を明確にしておくことが重要です。
修正回数や仕様変更に伴う費用の発生条件も明記し、双方が合意しておく必要があります。
プロジェクト全体の予算上限をあらかじめ伝えておくことも、有効な手段といえます。
動画制作をスムーズに進めるためには、制作会社との連携体制がとても重要です。
Funusualでは、企画段階から丁寧にヒアリングを行い、参考動画や構成案を共有しながら制作を進めています。
イメージのズレや納期トラブルを避けたい企業様は、まずは一度ご相談ください。
動画制作で起こりがちな権利関係のトラブル

動画制作には、著作権や使用権、肖像権などの法律的な権利が関わってきます。
これらの権利が十分に確認されていない場合、完成後のトラブルや訴訟リスクにつながることがあります。
SNSやWeb広告など、不特定多数の目に触れる媒体で動画を使用する場合、各種権利の取り扱いには注意が必要です。
著作権のトラブル
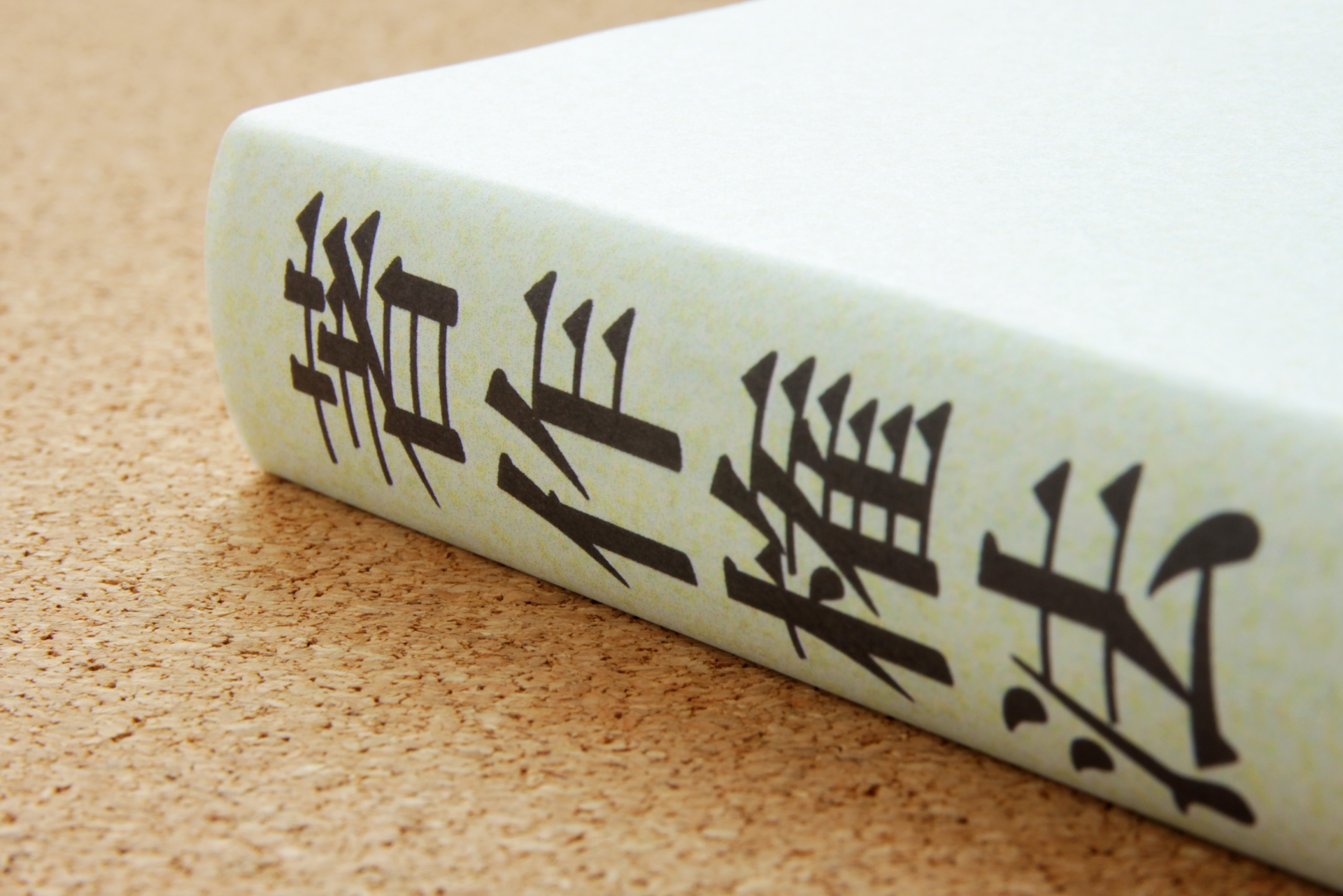
動画制作において注意が必要なのが音楽や画像、イラスト、映像素材など第三者が著作権を持つ素材を使用する場合です。
制作会社がフリー素材として利用していたとしても、商用利用が認められていない素材を使用していたことで、著作権侵害となってしまうリスクがあります。
また、過去にほかのクライアント向けに制作された動画から一部を流用するなど、知らぬ間に他者の権利を侵害しているケースも存在します。
著作権トラブルを防ぐには、まず使用するすべての素材について出所を明確にし、商用利用や二次使用の可否を確認しておくことが大切です。
発注者側も使用する素材はすべて権利クリア済みであることを契約書に明記し、証拠としてライセンス証明書や利用規約の写しを保管しておくことが重要です。
著作権の取り扱いについて事前にしっかり確認しておけば、動画公開後の法的トラブルを回避できます。
使用権のトラブル
完成した動画に関する使用権の取り決めが曖昧だったことで、トラブルになるケースもあります。
例えば発注者側が自由に使えると思っていた動画が、実は特定の用途や期間、媒体にしか使用できない契約だったという事例です。
このような場合、追加の使用料が発生したり、動画を使いたいタイミングで使えなくなったりといった不都合が生じます。
使用権の範囲については、契約書に明記することが何より大切です。
具体的には、使用できる媒体や期間、地域や改変の可否など細かい条件を明示しておきましょう。
制作会社と事前にすり合わせを行い、自社の活用予定に合致するように使用権を取得しておくことが、後々のトラブル回避につながります。
肖像権のトラブル
動画に出演している人物の肖像権に関するトラブルも、近年増加傾向にあります。
一般の方や未成年者が動画に登場している場合、本人や保護者の明確な同意を得ていないと、公開後に無断で使用されたとしてクレームや法的措置につながるリスクがあります。
著名人やインフルエンサーの場合でも、契約で明確に使用範囲が定められていなければ、トラブルが生じる可能性は否定できません。
こうした問題を避けるためには、動画撮影前に出演者全員から書面で同意をえることが基本です。
また、映像の再利用や二次使用を予定している場合は、その旨をあらかじめ説明し利用許諾を取得するようにしましょう。
出演に関する契約や合意書は、将来的なトラブルから自社を守る重要な証拠となるため、慎重な対応が必要です。
動画制作の契約書で確認しておくべきポイント

動画制作においてトラブルを未然に防ぐためには、契約書の内容が重要な役割を果たします。
契約内容が曖昧なままだと、納期の遅れや品質の問題、費用に関する食い違いなどさまざまなリスクを招くことになります。
動画というクリエイティブな制作物は、成果物の評価が主観的になりやすいため、客観的な基準を事前に設定しておくことが不可欠です。
動画制作を外注する際に、契約書で必ず確認と明記しておきたいポイントを解説します。
それぞれの項目が明確になっていれば、制作中や納品後のトラブルを大きく減らすことが可能です。
委託内容
まず初めに確認すべきなのは、何をどこまで制作会社に依頼するのかという委託内容です。
動画の企画や構成、撮影、編集、ナレーション、BGM選定など、具体的な作業範囲を明確に記載する必要があります。
また、発注者が用意すべき素材についても併記しておくことで、責任の所在が明確になります。
この範囲が曖昧なままだと、依頼しているつもりだったのに対応されていないといった認識違いが発生しやすいでしょう。
委託内容を明確にすることで、双方が同じ認識のもとで作業を進められます。
委託料の支払い方法や期限

費用に関する取り決めは、トラブルを未然に防ぐための重要な要素です。
支払いのタイミングや方法については、制作会社と発注者の間で誤解が生じやすいため、事前の明文化が求められます。
総額の記載だけでなく、支払回数や分割の有無、支払期日、銀行振込かカード決済かといった具体的な方法まで記載することが望ましいでしょう。
例えば、着手金として契約時に50%、納品後に残り50%を支払うといった段階的に支払う条件も多く見られます。
情報を明記しておくことで、双方の資金計画が立てやすくなり、未払いや請求漏れといった問題の防止にもつながりやすいです。
納期や遅延時の対応
納期は動画制作において重要な要素であり、プロジェクト全体のスケジュールにも大きく影響します。
契約書には納品日だけでなく、各制作工程の進行スケジュールも可能な限り具体的に記載することが理想です。
また、遅延が発生した場合の責任の所在や、遅延に伴うペナルティについても明確にしておくと万が一の際の対応がスムーズになります。
例えば、納期遅延が◯日を超えたとき、発注者は契約解除が可能で遅延1日あたり◯%の違約金の発生と取り決めをしておくことでトラブル時の混乱を避けられます。
発注者と制作会社双方の事情を考慮し、現実的なスケジュールを設定することが大切です。
納品の形式や検収方法

動画制作において、納品完了と判断する基準は曖昧になりやすいため、納品形式や検収方法も契約書に記載しておく必要があります。
納品はMP4形式かクラウド経由にするか、DVDなどの物理メディアにするかなど、具体的な形式を定めておくことが重要です。
納品物を受け取った後、何日以内に検収を行うのか、問題があった場合の修正対応期間はどの程度か記載しましょう。
修正可能な回数や追加費用
動画制作では、発注者が途中で「映像の内容や構成、テロップの文言を直したい」と感じることが珍しくありません。
完成イメージと実際の映像にギャップが生じることは多く、修正のやり取りは制作工程のなかでもとても重要な部分です。
そのため、修正対応に関するルールを事前に定めておくことが重要です。
発注者と制作会社の間で、どの時点やどの範囲なら修正が可能なのかをすり合わせておくことで、スムーズな進行が期待できます。
何回まで無償で修正可能なのか、それ以降の修正にはいくら追加費用がかかるのかを明記しておくと、後から揉めることがなくなります。
修正対応の範囲(ナレーションの変更やテロップ修正、構成変更など)も明記しておくと、より明確です。
著作権・使用権の扱い
完成した動画の著作権や使用権の扱いは、必ず契約書で明確にしておくべき項目です。
一般的には、制作会社に著作権が帰属し発注者には使用権が与えられる事が多いですが、案件の性質によっては著作権ごと譲渡されるケースも多いです。
著作権や使用範囲が不明確だと、公開後に予期せぬ制限やトラブルが発生することがあります。
使用媒体や使用期間、地域や二次使用の可否など、細かく設定しておくことで後の利用がスムーズになります。
必要に応じて著作権譲渡契約書を別途締結することも検討するとよいでしょう。
素材の保管・データの扱い
動画制作に使用する素材の保管方法についても、契約書で取り決めておくことが望まれます。
動画本編だけでなく、撮影した未使用映像やナレーション素材や音楽、イラストやサムネイルなどさまざまなデータが制作過程で発生します。
特に、大規模なプロジェクトや今後再編集を予定している場合、データの保管期間や再提供の可否を明記しておくとよいでしょう。
どのデータをどの形式で保管するか、保管期間終了後の扱いについても合意しておくことが重要です。
納品後◯ヶ月は無償で保管、再提供時には◯円の手数料を請求といったルールを設けておけば、双方の管理コストが明確になります。
取り決めがないと、数年後に再編集の依頼をした際に「データが残っていない」といったトラブルにつながる恐れがあります。
クラウド保管や外部ストレージを活用する場合も含め、セキュリティやデータの取り扱い方針についても確認しておくとよりよいでしょう。
秘密保持・損害賠償の規定
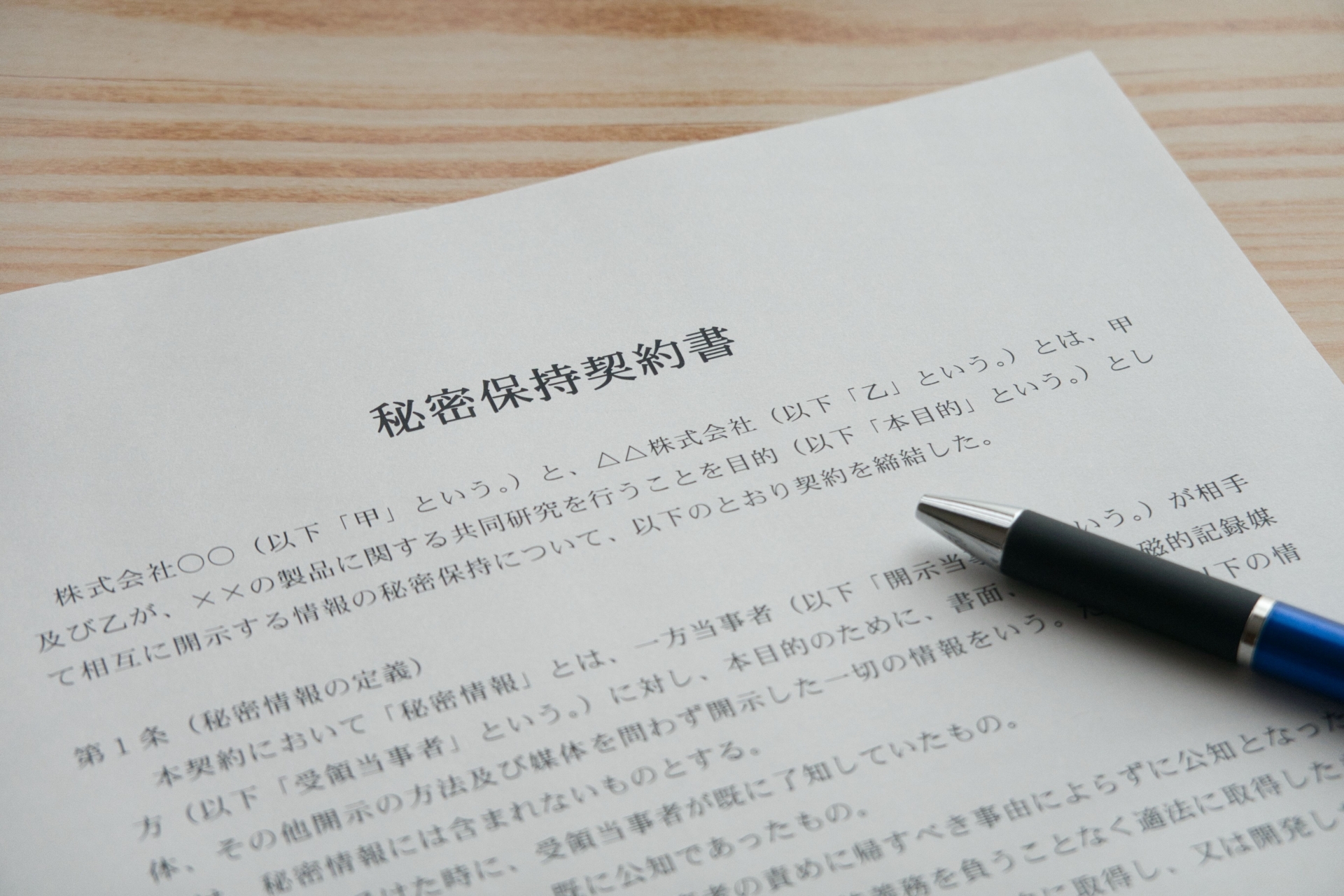
動画制作では、企業の戦略や新製品情報など、第三者に漏れてはならない内容が含まれることがあります。
そのため、制作会社との契約には秘密保持条項(NDA)を含めておくことが不可欠です。
NDAの有無で、外部流出や情報漏洩に対する対応力が大きく変わります。
また、万が一制作物に重大な欠陥があった場合や契約違反が発生した場合に備え、損害賠償に関する取り決めも必要です。
損害の範囲や上限、対応フローを明確にしておくことで、予期せぬ事態への備えとなります。
契約や納品に対する不安をなくすためには、信頼できるパートナー選びが鍵です。
契約内容の明確化は、動画制作を成功に導くうえで欠かせない要素です。
私たちFunusualでは契約時に作業範囲や修正回数、著作権の扱いなど細かい条件まで丁寧に説明し、不明点のない状態でプロジェクトを進行しています。
はじめて外注をご検討中の方でも、安心感を持ってお任せいただける体制を整えておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
トラブルを防ぐための動画制作会社とのコミュニケーションのとり方

動画制作で起こるトラブルの多くは、コミュニケーションの不足が原因です。
外注先との意思疎通が不十分な場合、発注者の意図が正しく伝わらず、動画の方向性や仕上がりにズレが生じてしまいます。
認識のズレや情報共有の不備を防ぐためには、初回打ち合わせの段階から何を作りたいのかやどのようなイメージに仕上げたいのかを、できる限り具体的に伝えることが重要です。
制作の各段階で進捗を確認し、都度フィードバックを行うことも欠かせません。
定期的なミーティングの機会を設け、チャットやメールの記録を残す、参考資料を提示するなどこまめなやりとりを心がけましょう。
信頼関係を築きながら可視化の工夫をすることで、トラブルの回避につながります。
動画制作でトラブルが発生してしまった場合の対処法

事前に準備を整えても、予期せぬトラブルが発生する可能性はゼロではありません。
動画制作の進行中や納品後に問題が発覚した場合、感情的に対応してしまうと事態がさらに悪化する恐れがあります。
冷静かつ段階的に対応することが、円満な解決の秘訣です。
一時的な感情で対立構造を深めるよりも、建設的な対話を重ねることで信頼関係を保ちつつ前進できます。
納期の延長や再編集の条件など、柔軟な選択肢を提示することで双方の合意点を見つけやすくなります。
あらかじめ「もしものときの対応方針」を社内で決めておくと、実際のトラブル時もスムーズに行動可能です。
まずは問題の内容を明確に整理し、契約書の内容と照らし合わせながら、どこに責任があるのかを冷静に判断しましょう。
制作会社に非がある場合でも、責め立てるのではなく、解決策を話し合う姿勢が大切です。
メールやチャットで経緯を記録に残しておくことで、証拠としても活用できます。
場合によっては、第三者機関や弁護士への相談も視野に入れ、法的な観点からの対応も検討しましょう。
動画制作会社選びで失敗しないための注意点

動画制作を外注する際、初めの段階で信頼できる制作会社を選べるかどうかがプロジェクトの成否を大きく左右します。
見積もりや提案内容だけで決めると、思わぬトラブルや期待外れの結果につながるリスクがあります。
価格の安さだけでなく、対応の丁寧さや実績、コミュニケーション力などの総合的な視点で見極めることが大切です。
次に確認したいのは、過去の制作実績です。
自社のイメージに一致するテイストや、構成を得意としているかどうかを判断するためにも、必ずポートフォリオを確認しましょう。
動画制作外注でのトラブルを避けたいなら

動画制作のトラブルは、知識不足や準備不足、そして確認不足によって引き起こされることがほとんどです。
必要な情報を事前に押さえ、信頼できるパートナーと適切なやりとりができれば、ほとんどのトラブルは防ぐことができます。
動画制作に関する知識と、契約やコミュニケーションにおける注意点を押さえておくことが、成功への第一歩です。
特に初めて外注を行う企業の場合、相場観や工程の流れがわからないことも多いため、慎重に業者を選定し依頼内容を明確に伝えることが重要といえます。
また、動画制作でのトラブルを回避するためには、信頼できるパートナーとの協働が何より大切です。
Funusualは、BtoB企業向け動画を多数手がけてきた経験を活かし、企業ごとの課題に応じた柔軟な提案が可能です。
「はじめての動画制作で不安がある」「これまでに失敗したことがある」という方も、まずは一度私たちにご相談ください。













