近年は、地域のPRに動画を活用する自治体が増えています。自分たちの自治体でもPR動画を活用したいけれど、失敗が気になって踏み切れない担当者の方もいるのではないでしょうか。
せっかくPR動画を作ってもあまり再生されず、視聴者の心に響かないといった失敗は実際にあるものです。
この記事では、地域のPR動画が失敗に終わる理由や成功のポイント、外注先の選び方などを解説します。自治体でPR動画の活用を成功させるための、参考にしてください。
自治体のPR動画とは

自治体で活用するPR動画とは、観光客や移住者の増加を目的とし、地域のよいところをアピールするための動画です。動画では、地域独自の魅力や特徴を紹介していきます。
例えば、目玉となる有名な観光スポットから、まだ認知度の低い穴場の観光スポットまで、その土地を訪れたいと思わせる魅力的な場所を紹介します。
地域自慢の特産品や独自の文化を紹介し、ふるさと納税の促進につなげることも可能です。移住者の増加を目指すなら、この地域に住むメリットや暮らしやすさをテーマに作成されます。
自治体や目的ごとに、PR動画の内容はさまざまです。
テキストやパンフレットでは伝えきれない雰囲気や景観も、映像ならより表現しやすくなります。PR動画が成功すれば、地域の活性化が図れます。
自治体のPR動画の効果

地域のPR動画には、以下の効果があります。
- 視聴者の記憶に残りやすい
- 興味を持ってもらえる
- 観光客や移住者を獲得できる
実際にどのような効果があるのかを知り、自分たちの地域にも役立つかの判断材料としましょう。ここからは、具体的な効果を解説していきます。
視聴者の記憶に残りやすい
映像で情報を伝えるPR動画は、文章や画像だけの伝達よりも、視聴者の記憶に残りやすいのがメリットです。
文章で細かい描写を理解するには時間がかかり、読み手によっては十分に理解できずに終わってしまう可能性もあります。
動画なら、視覚と聴覚の両方から情報伝達ができ、細かい描写や雰囲気も短時間でわかりやすく伝えることが可能です。
特に工芸品の制作過程のようなものは、文章よりも映像の方が格段に理解しやすく、記憶に残ります。動画は、文章よりも印象に残りやすい効果があります。
興味を持ってもらえる

伝えたいメッセージを文章から動画へ変えることで、情報を取り入れるハードルが低くなり、地域に興味を持つきっかけになってくれます。
多くの方にアピールしたいなら、相手が情報を受け取りやすい手段を選ぶ工夫も必要です。動画は文章を読むよりも簡単に情報を受け取れて、見る方にとって負担の少ないツールです。
動きのある映像や、音楽・音声などの音は、見る方の興味を惹き付ける力があります。
地元の方たちの声や風景の臨場感など、リアルな様子を動画で発信することで、その場の雰囲気をより直感的に感じてもらえます。
PR動画は、自分たちの地域に興味を持ってもらうための効果的な手段です。
観光客や移住者を獲得できる
自治体のPR動画で特に期待できる効果が、観光客や移住者を増やすことです。
この地域でどのような暮らしや体験ができるのかを映像でリアルに伝えることで、行ってみたい、暮らしてみたいと想いを抱かせることが可能です。
観光客向けなら、この土地特有の景観や美しい四季の移り変わり、地元のグルメなどここでしかできない体験を強みにします。
移住希望者へは、子育て世代や高齢者へ向けた自治体による支援や街並みなどを紹介することで、実際の暮らしをイメージしやすくします。
言葉よりも先に、心を動かせるのが映像の力です。視聴者の行ってみたい、暮らしてみたいという気持ちを高め、多くの方を呼び込むことができれば地域の活性化に大きな効果をもたらします。
自分たちの地域でも観光客や移住者を増やしたいと考える自治体の担当者様は、ぜひ一度動画制作会社のFunusualへご相談ください。
Funusualでは、企業や自治体のための動画を多く手掛けています。
自治体の特色を活かした映像表現を提案し、効果を重視する自治体に対して、信頼性の高いサービスを提供しています。
PR動画について詳しく聞いてみたい担当者様は、お気軽にFunusualへお問い合わせください。
自治体PR動画の活用方法

PR動画は、さまざまなシーンで活用ができます。以下は、実際に各自治体で使われることの多い場面です。
- 自治体のWebサイト
- YouTube
- SNS
- 移住促進イベント
- 観光案内所や道の駅での放映
- ふるさと納税のサイト
- 企業向けの説明会
- 外部との交流や提携の資料
PR動画をどのように活用するかは、とても重要です。一つのシーンのみの活用に留まらず、複数のツールを組み合わせて、さまざまな場面で使用するのが効果的です。
基本的な活用方法として、自治体のホームページに掲載する方法があります。
それ以外にも、YouTubeやSNSなどのインターネット上のツールを積極的に利用し、全国および海外にもアピールできる仕組みを作りましょう。
外部の市町村と学校関連での交流や、観光事業の提携を行う際にも、相手側に自分たちの地域を知ってもらうための資料として使えます。
道の駅や観光案内所など、ほかの地域の方が多く訪れる場所でも、積極的に活用するのをおすすめします。
大切なのは、作ったPR動画を適切な場面で適宜活用していくことです。活用シーンは多くあるため、自分たちにあった活用方法で発信していきましょう。
自治体のPR動画の失敗の理由

どれだけ努力しても、PR動画が失敗に終わってしまうケースもあります。PR動画が失敗する原因は、以下のとおりです。
- 演出が過剰になっている
- 情報量が多すぎる
- 面白さばかりを追求している
- 長すぎる
いずれの失敗理由も、作り手目線で制作され、視聴者の心に響く動画になっていないことが原因です。それぞれの失敗理由と、具体的に何がよくなかったのかを解説します。
演出が過剰になっている
過剰すぎる演出は、自治体のPR動画として失敗に終わります。
視聴者にインパクトを残したいという思いから、映像にCGやテロップを過剰に加えたり、派手な効果音や音楽にこだわりすぎたりする失敗があります。
間違った方法でインパクトを残そうとすると、肝心な地域の魅力がかすんでしまい、PRの目的は果たせません。
CGやテロップはクオリティを高めるために必要で、効果音や音楽も映像を盛り上げるために欠かせないものです。しかし、必要以上に作り込みすぎるのは避けなければなりません。
演出が地域の魅力を伝えるための邪魔になっていないか、視聴者目線で冷静に判断しましょう。
情報量が多すぎる
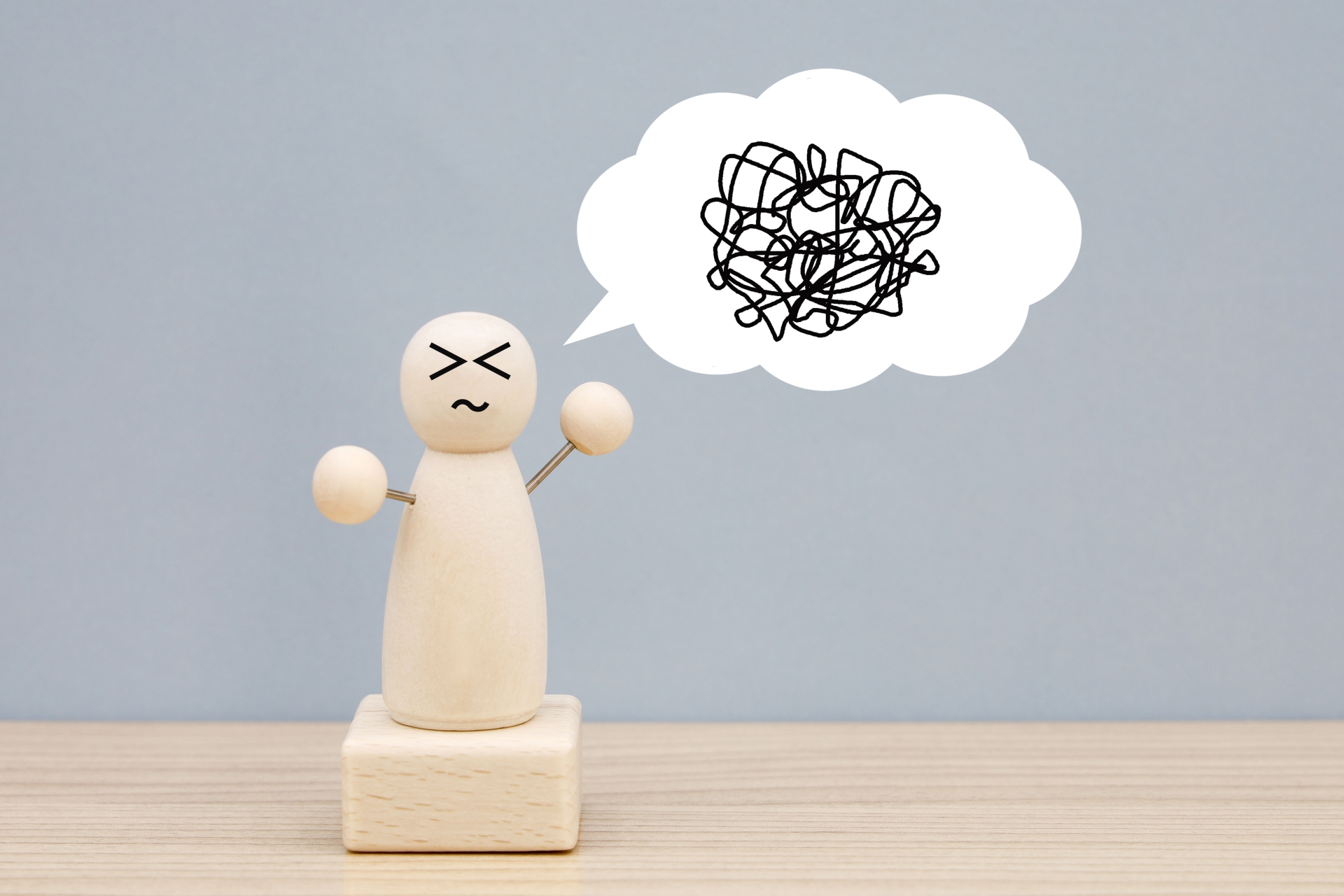
自治体のPR動画制作で起こりがちなのが、情報量を詰め込みすぎる失敗です。
地域の自慢できるポイントを多くアピールしたい気持ちから、つい情報を詰め込みすぎてしまうことがあります。
情報量が多いと視聴者はすべての情報を受け取りきれず、返って印象に残らない動画となってしまいます。
伝えたい内容やアピールポイントに要点を絞り、それを印象に残す動画に仕上げなければなりません。
伝えたい内容が観光地としての素晴らしさなのか、子育て支援の充実や住みやすさのアピールなのか、情報の種類を一つに絞ることが大切です。
届けたい魅力が多くても、情報量を詰め込みすぎるのは失敗につながります。
面白さばかりを追求している
PR動画のインパクトや話題性を重視して、面白さを極端に追及した動画にするのは失敗のもとです。
ユニークな企画や笑いが起こる動画は注目され、SNSで拡散されやすいメリットがありますが、見落としがちなデメリットもあります。
面白さに重点をおきすぎるとPR効果が薄れ、結局どこの地域の動画だったのかが記憶に残らないという事態も起こり得ます。
地域の活性化を願ったPR動画であることを忘れず、その土地の魅力を伝えることに重点をおきましょう。そのうえで、PR動画に面白さを加えるのが大切です。
長すぎる
PR動画が失敗する理由の一つに、動画が長すぎることが挙げられます。より多くの魅力を丁寧に伝えようとすると、結果的に動画が長くなってしまいがちです。
わずかな興味だけで見始めた視聴者は、長い動画を時間を割いて見ようとはしません。特に、ショート動画の多いSNSでは、3分を超える動画はユーザーが途中で離脱してしまう傾向にあります。
自治体のPR動画は短いものなら1分程度、長いものだと5分以上となります。使うシーンによって適切な長さは異なりますが、視聴者に動画が長いと感じさせることを避けなければなりません。
最後まで飽きずに見てもらえる動画が作成できれば、自治体によい印象が残りやすく、PRの役割も果たせます。
一方で、長いと感じるPR動画はつまらない印象を与えてしまうため、適度な長さに収めましょう。
自治体のPR動画を成功させるポイント

PR動画で成功を収めるには、企画や制作過程が重要です。以下は、PR動画を成功させるためのポイントです。
- 目的を明確にする
- ターゲットを絞る
- 多言語化にも気を配る
- SNSを意識する
- 地方のPR動画に長けた外注先を選ぶ
- ほかの地方との差別化を図る
ここからは、どのようなことが成功につながるのか、具体例をあげながら解説していきます。
目的を明確にする
PR動画を制作する前に、何を目的として作るのかゴールを明確にすることが大切です。
PR動画と一言でいっても、観光客の増加や外部からの移住者の呼び込み、特産品の購買促進など目的は自治体ごとにさまざまです。
どのような目的でPR動画を作るのかをはっきりさせておかなければ、制作途中で方向性がぶれてしまう可能性もあります。
制作に関わる担当者全員が共通の認識をもって臨むためにも、目的は明確にしておきましょう。
ターゲットを絞る

PR動画を成功させるためには、情報を届けたい相手が誰なのかを絞り込む必要があります。
狙うターゲットが決まっていなければ、どのような動画が視聴者の心に響くのか、効果的なコンセプトが見出せません。
どの年代に向けて発信するのか、家族層なのか単身者向けなのかといったことを明確に設定します。
ターゲットを細かく設定することで、どのような構成や表現方法が心に響くのかが、具体的な手段がわかってきます。
家族層に子育て支援の充実を伝えたり、若い世代向けに観光ルートを提案したりと、動画に盛り込む内容も自然と決まってくるでしょう。
ターゲットを絞らずに多くの方に見てほしいと思っても、ターゲットが明確でない動画は、誰の心にも響かない動画となってしまいます。
PR動画で効果を得るためには、ターゲットを絞り込むことが大切です。
多言語化にも気を配る
海外の観光客や移住希望者も視野に入れるなら、PR動画を多言語に対応させることが必要です。素晴らしい動画を作っても、言語が理解できなければ十分な魅力は伝わりません。
近年ではさまざまな観光地や公共交通機関などでも、英語や中国語、韓国語に対応しているのが一般的になってきました。
これらの言語以外にも、タイ語やベトナム語、フランス語などできるだけ多くの言語をカバーするのがおすすめです。
字幕対応以外にも、音声での言語切り替えも取り入れると親切です。多言語に対応することで、より多くの海外の方に動画を見てもらえて、幅広いアピールができます。
SNSを意識する
最近では、SNSの公式アカウントをもっている自治体も多く、PR動画や画像による発信をSNSで行うのも珍しくありません。
SNSは拡散力が高く、多くの方にアピールする機会が得られるため、PR動画の掲載場所としておすすめです。
SNSで拡散されるPR動画を作るには、心に響く動画にするのはもちろんこと、動画の長さにも気を配らなければなりません。
ショート動画が主流のSNSは、数十秒から数分程度の動画が多く掲載され、短い動画をテンポよく見ていくのが特徴です。
そのなかに長いPR動画を入れても、ユーザーが最後まで視聴をしてくれる可能性は低いでしょう。
自治体のホームページには長めの動画を載せても、SNSへの掲載時には短くカットしたバージョンを載せるといった工夫が必要です。
PR動画を制作する際にはSNSを利用することを前提に、短い動画の制作も行いましょう。
地方のPR動画に長けた外注先を選ぶ

動画制作を外注する場合には、自治体のPR動画に強い制作会社を選ぶことが、成功のポイントとなります。
動画制作会社にも、それぞれ得意とする分野があります。ライブやイベント動画の編集が得意な会社や、企業のマーケティング動画を得意とする会社など、得意なジャンルはさまざまです。
どれだけクオリティの高い映像を作れる会社でも、自治体のPR動画に関するノウハウをもたない制作会社では、効果的な制作は望めません。
単に映像がきれいなだけではく、地域の個性を魅力的に表現する手法を熟知している制作会社を見つけることが重要です。
どこの制作会社に依頼すればよいかわからない方は、Funusualへご相談ください。
Funusualは、企業や施設、自治体などのPR・広報・紹介動画を数多く手掛けています。
担当者が丁寧にヒアリングを行い、クライアント様が抱える問題や目指すゴールを理解したうえで、適切な提案を行います。
地域の魅力を引き出す動画制作は、Funusualへお任せください。
ほかの地方との差別化を図る
ほかの自治体と似たような動画では、自分たちの地域を視聴者に印象付けることはできません。
ほかの地域にはない、自分たちの土地ならではの特徴や個性を前面に出し、この土地でなければできない体験があると思わせることが大切です。
きれいな景色や地元のグルメ、特産品などを紹介するだけでは、ほかの自治体のPR動画と同じになってしまいます。
観光スポットを取り上げるなら、地元の方だけが知る通な観光ルートや絶景ポイントなど、知られざる場所を紹介します。
ここにしかない価値をアピールすることで、土地そのものの価値を高め、差別化を図ることが可能です。
自治体のPR動画の成功事例

ここからは、実際に自治体が作ったPR動画の成功事例をあげていきます。まずは、ユニークな企画を打ち出した大分県別府市の動画です。
この動画が100万回再生されたら、遊園地を温泉施設と融合させるという斬新な企画を立てています。
ゴンドラやジェットコースターさえも、温泉に浸かりながら乗っている驚きの映像です。次々と登場する驚きの光景につい見入ってしまうでしょう。
続いて、神奈川県小田原市で制作した、移住促進を目的としたPR動画を見ていきましょう。
小田原市のPR動画は、穏やかで心温まるストーリー性のある動画です。
小田原市の動画は、地域プロモーションアワード2022や、ふるさと動画大賞などで受賞しています。
地域の特色を活かしたユニークな別府市の動画や、心を揺さぶるストーリーの小田原市の動画は、ほかにはない記憶に残るPR動画です。うまく差別化を図り、PRに成功しています。
失敗しない自治体のPR動画を作るための外注先の特徴

PR動画作りを成功させるためには、どの制作会社に外注するかがとても重要です。依頼前に、以下の点を見極めましょう。
- 適切な提案ができる
- ブランド価値を向上させるノウハウがある
- ストーリーメイクや構成力がある
- 遊び心をくすぐる動画制作が可能
ここからは、PR動画を成功させられる外注先の特徴を紹介していきます。
適切な提案ができる
地域の特色を活かせるよう、提案力のある制作会社を選びましょう。
PR動画の目的が一つであっても、その目的を達成するためにどのような方向性から訴求し、どのような手法を使うのかはさまざまです。
しっかりとヒアリングを行い「こうすれば魅力が伝わりますよ」とニーズにあった提案をしてくれるかどうかが大切です。相談の段階で、制作会社の提案力を見極めましょう。
ブランド価値を向上させるノウハウがある

アピールしたい特産品や地域そのものをブランド化できれば、地元の価値を高めることに成功します。
そのために制作会社ではどのようなことをしてくれるのか、ブランド化できるだけのノウハウがあるのかを見極めましょう。
例えば、◯◯市といえば優れた繊維産業といったような、イメージの確立も効果があります。
制作会社が対応した過去の事例も交えながら、会社がもつノウハウでどのような効果が得られるのか、しっかりと説明を受けましょう。
ストーリーメイクや構成力がある
映像は見た目のきれいさだけではなく、構成やストーリーが重要です。
どのような構成とストーリーを作るかで、視聴者の心に響く動画となるかどうかが大きく異なります。
優れた外注先は、ストーリーメイクが得意です。地域の人々の思いや文化、未来への希望などを物語にすることで、感情を揺さぶられる動画へと仕上がります。
ストーリーメイクや構成力は、過去の制作実績を見ることでも確認できます。
遊び心をくすぐる動画制作が可能
自治体のPR動画であっても真面目になりすぎる必要はなく、遊び心を取り入れるのもおすすめです。
遊び心のある動画は最後まで飽きずに視聴でき、インパクトを残すことにも成功します。
制作会社により、遊び心を取り入れた動画が得意かどうかは異なります。
過去の制作実例を紹介してもらったり、どのように遊び心を取り入れていくかを聞いたりしながら、成功に導ける制作会社を見極めていきましょう。
自治体PR動画の成功はパートナー選びで決まる

多くの自治体でPR動画が活用され、観光客や移住者の増加で効果を得られている成功事例もあります。
最終的には、どの制作会社をパートナーとして選ぶかが重要な鍵となります。
動画制作会社であるFunusualは、これまでに多数の自治体や企業と向き合い、それぞれの目的に応じた動画を企画・制作してきました。
地域の魅力を引き出す提案力や構成力を強みとし、自治体の課題やターゲットに合わせた映像をご提案しています。
「何から始めればよいかわからない」という初めてのご担当者様にも安心感を持っていただけるよう、具体的な完成イメージが湧く絵コンテを無料でご用意しています。
PR動画の活用を検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。













