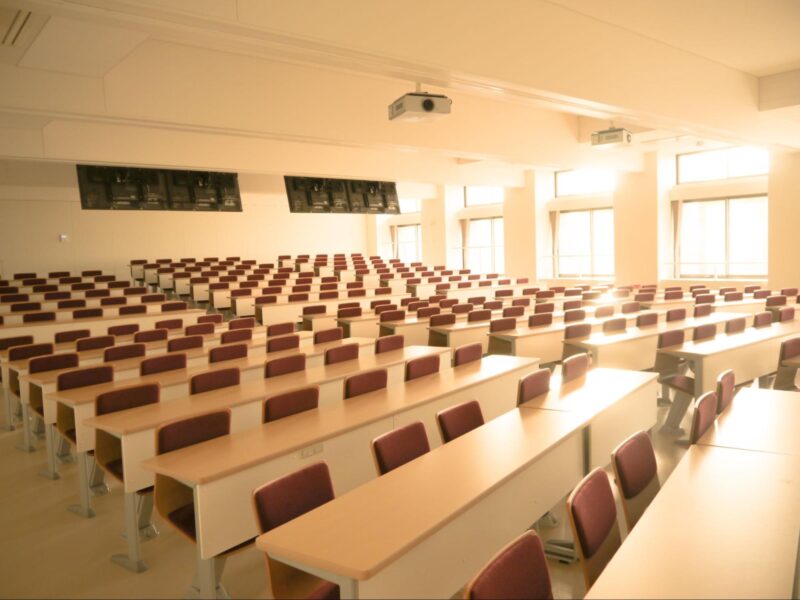大学や短大、専門学校の広報活動で、動画を活用する動きが広がっています。
パンフレットやWebサイトだけでは伝えきれないキャンパスの雰囲気や学生の表情を、動画を活用することによってより臨場感をもって届けられるためです。
一方で何から始めるべきか、どのように進めればよいのかがわからず、判断を迷っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では大学広報が動画を取り入れるべき背景と活用のメリット、制作にあたってのポイントや注意点、実際の事例までを整理してご紹介します。
検討のきっかけづくりや、学内での提案資料をまとめる際の参考として、ぜひお役立てください。
大学広報が動画を制作するべき理由

パンフレットやWebサイトなどの既存の広報手段に加えて、動画を活用する大学が増えています。
背景にあるのは、受験生やその保護者の情報収集スタイルの変化と、大学側の魅力がうまく伝わらない点です。
ここでは、大学広報が動画を制作するべき理由を、具体的な活用シーンごとに整理していきます。
大学の強みや様子が伝わりやすい
大学の魅力は、規模の大小やカリキュラムの内容だけでは測れません。
実際にキャンパスで過ごす学生の表情や授業の雰囲気、教員との距離感などの日常の空気感こそが、大学の魅力の一つといえるでしょう。
こうした要素は、写真や文章ではなかなか伝わりにくいです。動画であれば、空気感や温度感をそのまま映し出すことができ、言語化しづらい魅力もダイレクトに伝わります。
その結果、受験生にとってはこの大学で学ぶ自分を具体的にイメージするきっかけとなり、進学先の選択を後押しする材料になります。
全国の誰もが視聴できる

受験生の居住地に関係なく、同じ内容の情報を届けられるのは、動画ならではの利点です。
特に地方や離島に住む高校生にとっては、大学説明会やオープンキャンパスへの参加が難しいケースも少なくありません。
こうした物理的な距離が、進学先の選択肢を狭める一因です。
動画を公開すれば、遠方に住む生徒にも大学の雰囲気や特色を視覚的に伝えることができ、情報の不均衡を解消する一助となります。
これは、地域や経済的な事情に左右されず、進学を公平に検討できる環境づくりにもつながります。
SNSでの拡散が期待できる
若年層にとって、SNSは情報収集の手段であると同時に、関心のある話題を共有しあう場でもあります。
大学に関する動画がSNS上でシェアされれば、受験生本人だけでなく、家族や友人など周囲の方にも自然と広がっていきます。
特にYouTubeやInstagram、TikTokなどの動画系SNSでは、短くテンポのよい動画が視聴されやすいです。視聴完了率が高まることで、リーチの拡大にもつながります。
リールやショートなどの縦型動画の活用で、スマートフォンでも快適に視聴できる形式になります。
SNSでの展開は、制作物の鮮度や演出に工夫が求められる一方で、広告費をかけずとも多くの接点を生み出せる点がメリットです。
広報活動の幅を広げる手段として、動画とSNSの連携は有効に機能します。
インターネット上だけでなく学校説明会でも使用できる

動画はWeb上での公開だけでなく、対面の説明会やガイダンスなどの場でも活用できます。説明担当者の話に加えて、映像を交えた紹介で、情報の伝わり方が格段に変わります。
特に初めて大学を訪れる生徒や保護者にとっては、視覚と音声を通じて、大学の空気感をより具体的に伝えられるのが映像の特長です。
動画の活用で、会場の空気を和らげる効果も期待できます。短時間で印象を残せる点でも、動画は効果的なツールです。
また、パワーポイントやパンフレットと異なり、ナレーションや音楽などの演出を加えられる点も特徴です。大学の世界観や理念を、感覚的に伝えやすい利点があります。
オンライン・オフラインを問わず一つのコンテンツを複数の場面で活用できることは、制作コストの面でも合理的です。
大学の魅力をより多くの方に、正確かつ印象深く届けたいとお考えなら、動画を活用してみませんか?
Funusualでは、教育機関の特性や目的にあわせた広報動画を、企画から撮影・編集までワンストップでご提案しています。
理念やキャンパスの雰囲気が伝わるよう動画に落とし込み、視聴者の心に残る映像をつくり上げます。
まずはどのような構成がよいか相談したい、事例を見ながら検討したいなどの段階でも構いません。ぜひ一度、私たちにご相談ください。
大学広報動画で紹介できるコンテンツ

動画を活用しようと考えたとき、どのような内容を撮るべきか、何を伝えればよいのかに迷うケースは少なくありません。
ここでは、多くの大学が実際に取り入れている代表的な動画コンテンツのパターンを紹介します。
それぞれの目的に応じて、どのような表現が効果的なのかを見ていきましょう。
大学紹介動画
大学紹介動画は、学内の設備や授業風景、キャンパスライフの様子などを総合的に伝えるコンテンツです。
来校が難しい受験生に対して、大学全体の雰囲気や特徴を視覚的に届ける手段として活用している学校も少なくありません。
構成は校舎や講義の様子に加え、在学生や教職員のコメントを織り交ぜることで、より具体的なイメージを持ってもらいやすくなります。
特に学生の日常や表情が映し出されるシーンは、リアルな学生生活を想起させ、視聴者の共感を生みやすい要素です。
また、大学の多様な学部や施設の様子をバランスよく紹介すれば、幅広い層に訴求できる汎用性の高い動画になります。
学校紹介の入り口としての役割を果たすため、初めて大学を知る方にもわかりやすい構成が重要です。
大学のコンセプト動画
大学の理念や教育方針、ビジョンなどを軸に構成されるのがコンセプト動画です。
パンフレットの冒頭や、Webサイトのメッセージページに書かれているような想いが映像になることで、視聴者の理解と共感を促します。
例えば、地域との共生やグローバル人材の育成などの価値観は、テキストではうまく伝わりません。
映像であれば街と連携した取り組みの様子や、海外研修の現場などを映し出すことで、メッセージを具体化できます。
だからこそ演出やナレーションのトーン、構成全体のストーリー性が重要です。
言葉では伝えきれない大学らしさを映像で表現するためには、目的と対象を明確にし、丁寧に設計された動画づくりが求められます。
大学のCM

大学のCMは主にテレビやYouTube広告、交通広告内での放映などを目的とした、短尺かつインパクト重視の動画です。
視聴者の注意を瞬時に引きつけ、限られた時間のなかで印象を残すことが求められるため、映像や音楽、コピーのすべてで高い完成度が求められます。
ブランドカラーやスローガンを際立たせる演出が多く、具体的な情報よりも大学のイメージを伝えることに重点を置くケースが一般的です。
例えば挑戦、多様性などのキーワードをもとに、抽象度の高い映像で世界観を構築する手法が用いられます。
ほかの動画と比べて自由度の高い表現が可能である一方、メッセージの焦点がぼやけないよう、明確な目的設定と一貫したトーン設計が重要です。
大学の顔として外部に広く露出されるからこそ、ブランディング視点での企画設計が求められるジャンルでしょう。
大学広報動画を作成する際のポイント

伝えたい魅力がたくさんあっても、それをただ順番に詰め込むだけでは、印象に残る動画にはなりません。
丁寧に制作しても、見る側に届かなければ意味がなく、かえって情報が散漫に映ってしまうこともあります。
ここでは、視聴者に届く動画をつくるために押さえておきたい基本的なポイントを紹介します。
情報設計や演出、表現のすべてを目的から逆算して丁寧に組み立てていくことが、質の高い広報動画づくりの鍵です。
目的や伝えたいメッセージを明確にする
動画制作を始めるうえで、重要なのは伝えたい内容を明確化することです。
目的が曖昧なままだと、構成や演出がぶれやすく、結果として結局なにを伝えたかったのかがわからない動画になってしまいます。
すべてを詰め込もうとせず、主軸となるメッセージを一つに絞ることで、視聴者の印象にも残りやすくなります。
また、完成後の活用場面をあらかじめ想定しておくことも大切です。説明会で使うのか、Webサイトで常設するのか、広告として流すのかによって尺や構成、導入のテンポも変化します。
メッセージと使用目的をセットで整理すれば、設計段階から動画の精度が高まります。
ターゲットを明確にする
誰に向けて動画を届けたいのかが明確でなければ、伝えるべき言葉や演出の方向性も定まりません。
大学広報動画では受験生、その保護者、高校の先生、在学生や卒業生など、複数のステークホルダーが想定されます。
そのため制作初期の段階でターゲットをはっきりさせることが重要です。
例えば受験生をターゲットにするなら、学部選びの悩みに寄り添うような構成や、キャンパスライフを疑似体験できるような映像表現が効果的です。
一方で保護者を意識する場合は、教育理念や就職実績などの安心材料を伝える内容が求められるでしょう。
誰にどう届いてほしいのかを明確にすれば、動画全体の一貫性と説得力が高まり、目的達成につながるコンテンツに仕上げることができます。
見ていて飽きない工夫をする

どれだけ丁寧に作られた動画でも、途中で離脱されてしまっては意味がありません。特に若年層に向けた動画では、冒頭数秒で引き込めるかどうかが鍵になります。
テンポや構成、演出にメリハリを持たせ、最後まで見てもらえる工夫が必要です。
映像と音のリズム、テロップや図版の使い方、カメラワークの変化など視覚的な動きで飽きを防ぐ設計が求められます。
また、エピソード性や感情を伴う構成にすれば、物語のように引き込まれる動画に仕上げることも可能です。
退屈させない意識は、視聴者への配慮であると同時に、大学の伝える力そのものを映し出します。
限られた時間のなかで情報を印象づけるには、演出の工夫と編集の設計力が大きな差を生む要素になります。
客観的に見て入学したいと思えるような動画にする
動画制作では、どうしても伝えたいことを優先しがちですが、それが伝わるかどうかは別の話です。
大切なのは制作者や大学関係者の目線ではなく、受験生や保護者など外の方から見たときに、魅力的に映るかどうかの意識です。
視点を一歩引き、客観的に編集・構成する姿勢が欠かせません。第三者が見てここで学んでみたい、この空気感に惹かれると思えるような動画を目指すことが、結果として入学希望者の心に届く広報につながります。
自己満足にとどまらない、見る方の気持ちに立った構成が、動画の説得力を高めてくれます。
大学広報動画を制作する前に決めておくべきこと

動画のクオリティは、撮影や編集の技術だけで決まるものではありません。実は、制作に入る前の準備段階で、仕上がりの良し悪しが大きく左右されます。
まずは撮ってみようと手を動かす前に、いくつかの基本的な要素を整理しておくことが、スムーズな進行と満足のいく成果を得るために重要です。
ここからは、制作前に整理しておきたい代表的な項目を一つずつ解説していきます。
予算
どれだけ質の高い動画を目指しても、現実的な予算と折り合いがつかなければ実現は難しくなります。
制作費を把握せずに動き出してしまうと、途中で規模を縮小せざるを得なかったり、必要なクオリティを担保できなかったりなどの事態に陥ることもあります。
予算を決める際は、動画の尺や用途の明確化が大切です。
あわせて、企画や撮影、編集やナレーションなど外注する範囲と構成内容を照らし合わせながらの検討が重要です。
完成後の運用も見据えたうえで、費用対効果を意識した設計にすると判断しやすくなります。
スケジュール
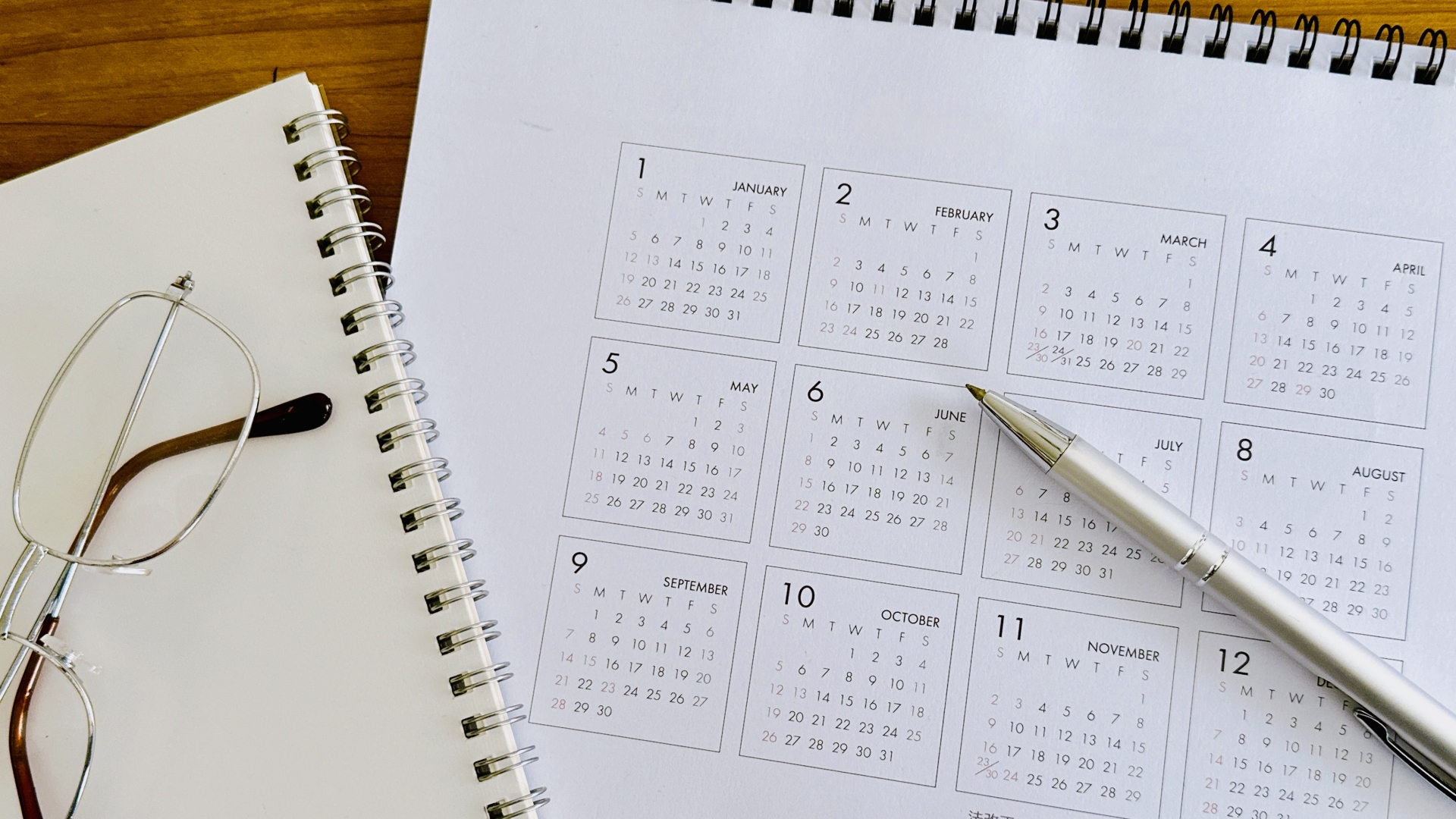
大学広報動画の制作には企画から撮影、編集、納品まで一定の時間がかかります。
特に、学内での調整や確認フローが多い大学では、思っていたより時間が足りなかったなどの事態が起きやすいです。
そのため、公開予定日から逆算し、余裕を持ったスケジューリングを行いましょう。
例えば、学校説明会やオープンキャンパスにあわせて動画を活用したい場合は、日程に間に合うように準備を進める必要があります。
撮影時期や編集スパンを逆算し、各工程の所要時間を見積もることが大切です。
天候や出演者の都合によって撮影が延期になる可能性も踏まえ、バッファを設けた設計が現実的です。
また制作会社に依頼する場合は、スケジュール感の共有も欠かせません。最初の打ち合わせでいつまでに、どこまでを完成させたいかを明確に伝えることで、無理のない進行計画を立てられます。
出演者や撮影場所
動画の印象を大きく左右するのが、出演する方と撮影する場所です。
登場する学生や教職員の表情や話す内容、背景に映るキャンパスの風景など、一つひとつの要素が視聴者の共感や憧れにつながります。
出演者の選定では、話し方や表現力だけでなく、その方が語るメッセージと大学の魅力が自然に結びつくかが重要です。
例えば、受験生に向けた動画であれば、在学生や卒業生のリアルな声が説得力を持つことがあります。
台本を読み上げるのではなく、自分の言葉で語れる環境づくりも含めて準備を進めると、映像の温度感が変わってきます。
撮影場所も同様です。建物や教室、図書館、研究室など大学の個性や空気感が伝わる場所を意識的に選ぶことで静止画や文章では伝えきれない魅力を補完できます。
天候や時間帯によって印象が変わるため、事前のロケハンやタイムスケジュールの調整を行っておくことで、狙った雰囲気の映像を撮影しやすくなります。
大学広報動画を外注する際に注意すべきこと

動画制作を外部に依頼する際、きっとプロだから大丈夫だろうとすべてを任せきりにするのは危険です。
完成してからイメージが違う、伝えたいことが反映されていないと気付いても、修正には時間もコストもかかってしまいます。
だからこそ、制作会社とのすりあわせと準備が、成果の分かれ目になります。
まず大切なのはなぜ動画を作るのか、誰に何を届けたいのかなどの目的を学内で明確にし、制作パートナーに正確に伝えることです。
依頼側の想いが言語化されていないと、構成や演出にズレが生じるリスクが高まります。場合によっては、簡単な企画書や参考動画を共有すると、イメージの共有がスムーズになります。
また、契約時には納期や修正対応の範囲、使用する音楽や映像の権利関係なども事前に確認しておくことが必要です。
特に大学の広報用途では、長期間使用するケースがあるため、再編集や転用の可否なども含めて話し合いましょう。
外注は丸投げではなく伴走です。信頼できるパートナーと並走できれば、自校らしい動画を制作できます。
Funusualでは大学広報ならではの視点や課題に寄り添いながら、構成や演出、撮影から編集までを一貫してご提案します。
ヒアリングを重ねながら、担当者の意図や学生・保護者に届けたいメッセージを明確にし、自校らしい動画づくりをサポート可能です。
想いをうまく映像に落とし込めるかといった不安や、限られた予算でも効果的な動画が作れるかなどのお悩みがあれば、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
大学広報動画の制作費用相場

動画を作りたいけれど、どれくらい費用がかかるのか見当がつかないと悩む大学広報担当者は少なくありません。
動画制作には企画や撮影、編集、ナレーション、CGなどさまざまな工程があり、それぞれの内容や品質によって費用は大きく変わります。
例えば、スライド形式の簡易動画は100,000〜300,000円ほどが目安です。
対話やインタビューを含む構成では300,000〜800,000円、密着型やコンセプト演出を伴う動画では800,000〜2,000,000円前後になるケースもあります。
特に大学紹介動画では、用途と制作規模によって費用の幅が広く、おおむね300,000〜800,000円が標準的な費用相場です。
ただしCGやドローン空撮を加えた高度な演出、複数日程での撮影を行う場合は、1,000,000円以上の費用を見込む必要があります。
こうした相場に対して、大学の広報担当者が留意すべきは単に安く抑えることよりも、目的に沿った適正な投資を行うことです。
例えば入学希望者の増加や認知度向上、ブランド再構築などの目標があるなら、制作にはそれに見合った予算を割くこと自体が合理的であるといえます。
納得したうえで進めることで、後からの認識ズレや余分なコストを避け、成果につながる動画制作が可能になります。
大学広報動画で成功した活用事例

ここでは、実際に動画をうまく活用し、広報効果やブランディングに成功している大学の事例を紹介します。
それぞれが自校の個性や戦略にあわせて動画を活用しており、取り組み方次第で多様な成果が期待できることが見えてきます。
九州大学
九州大学の動画はつながりをテーマに、学生生活や研究環境、グローバルな交流の魅力を短時間で凝縮して伝えています。
約2分半の映像は、美しいカメラワークとリズム感のある編集で構成され、視聴者を一気に九大の世界観へと引き込みます。
この動画の大きな特徴は、情報を伝えるよりも印象を残すことに重きを置いている点です。
メッセージ性とデザイン性を両立させた好例でしょう。
明治大学
明治大学の動画は生田キャンパスの豊かな自然を舞台に学び、集い、成長する学生たちの姿を詩的な映像表現で描いているのが印象的です。
動画のなかでは建築や緑地、学生の動きが静かに交錯しながら、大学が持つ場の力が丁寧に映し出されていきます。
派手な演出ではなく、あくまで空気感や温度を大切にする映像だからこそ、見る方の内面にじんわりと響く動画に仕上がっています。
早稲田大学
早稲田大学のプロモーション動画では、大学の取り組みや魅力が多角的に紹介されています。
学生たちがキャンパスでの学びや研究活動に取り組む様子が描かれ、早稲田ならではの活気と多様性が感じられる動画です。
このような映像構成は視聴者の感情に訴えかけるものであり、特に大学選びに迷う受験生や保護者、留学生候補者にとってとても有益な情報となっています。
大学広報が単なる説明にとどまらず、ストーリーとして人の心に残る、伝わるコンテンツとして作られている好例でしょう。
大学の魅力を伝える動画を制作したいなら

ここまでご紹介してきたように、大学広報動画の活用は、キャンパスの雰囲気や学びの魅力をリアルに伝える有効な手段です。
ただし、ただ映像を撮ればよいわけではありません。伝えたい価値を見極め、届けたい相手にあわせて設計し、見る方の記憶に残る構成に仕上げる必要があります。
そのためには目的に応じたコンセプト設計や絵コンテやシナリオの構築、撮影、編集、BGMの選定に至るまで、細部にこだわった設計が欠かせません。
そして何より、大学のらしさを映像に落とし込むためには、客観的な視点と映像化の技術が必要になります。
だからこそ、大学広報動画の制作には、信頼できるパートナーの存在が欠かせません。
Funusualでは、教育機関に向けた動画制作の豊富な実績を活かし、それぞれの大学が持つ個性や魅力を伝えるお手伝いをしています。
どのような映像が合っているのかわからない、まずは相談だけでもしてみたい、そのような段階でもどうぞお気軽にお問い合わせください。