近年注目されているマーケティング手法の一つに、ブランデッドムービーがあります。
動画広告とは違う、ブランド価値を高めるストーリーテリング型の動画のことです。注目されている背景にはSNSの利用者が増えたことが影響しています。
これから活用を検討しているものの、運用方法に悩んでいる方も多いでしょう。
本記事を読めば、ブランデッドムービーの活用方法や企業の売上にどう影響するのかがわかります。さらに、メリットやデメリットを紹介しつつ、具体例とともに解説します。
ブランデッドムービー制作を検討中の方にご参考になれば幸いです。
ブランデッドムービーとはどのようなものか

ブランデッドムービーとは、企業ブランドの価値を確立し、イメージ向上をはかる目的で制作される動画のことをいいます。
通常は1分程度の短編で、一般的な動画広告と異なり商品やサービスの説明は行いません。ここでは、企業のブランデッドムービーの狙いと動画広告との違いを詳しく解説します。
企業・ブランドの価値の確立が狙い
ブランデッドムービーの制作には以下のような狙いがあります。
- 企業ブランドの価値を確立する
- 企業や商品のイメージ向上
- ものづくりに対する共感を高める
- ファンを増やす
企業の価値を確立するために、共感を得ながら感情に訴えかけてイメージ向上につなげる狙いがあります。
一般的な動画広告とは何が違うのか
ブランデッドムービーは、企業のブランディングを目的としています。
一方、一般的な動画広告の目的は、商品やサービスの認知度を高めつつ消費者の購買行動を促す目的があります。
動画広告は視聴者が意図しなくても流れてくることが一般的です。
例えば、YouTubeを視聴中に突然動画広告が流れ、コンテンツが中断されて不快に感じた経験がある方も多いでしょう。
このように動画広告は強制的にアピールする性質があります。それに対してブランデッドムービーは、視聴者が見たいと思って再生する性質のコンテンツなため、視聴途中で離脱される可能性が低くなります。
ブランデッドムービーが注目される背景

なぜ近年ブランデッドムービーが注目されるようになったのでしょうか。
その理由として、動画広告が嫌われるようになったことや、SNSの利用者が増えたことなどがあげられます。
ここでは、ブランデッドムービーが注目されるようになった背景を3つのポイント別に解説します。
動画広告が嫌われるようになった
動画広告とは、視聴中の動画に挿入され、強制的に商品やサービスを訴求するものです。
同じ広告が繰り返し流れてくることで、企業の商品の認知度を高めて購買促進するはずが、かえってブランドイメージを損なうことになりかねません。
本来視聴中の動画に流れてくる動画広告は、押し付けがましく、スキップしたくなる視聴者もいるでしょう。
SNS利用者が増えた

ブランデッドムービーは、以下のような配信チャネルを利用して配信されます。
- 自社サイト
- SNS
- 動画サイト
これらのサイトで流れるブランデッドムービーは簡単に拡散できます。
近年増加しているSNSの利用者をターゲットにすれば、拡散力が向上するでしょう。
拡散されればされる程、再生回数を伸ばすことができ、企業ブランドを不特定多数に広めて認知させることができます。
エンゲージメントの強化がのぞまれている
消費者が特定のブランドに対して示す、積極的な関与や感情的なつながりのことをブランドエンゲージメントといいます。
消費者のブランドエンゲージメントを強化すると、消費者は、このブランドだから使いたいと思うようになるでしょう。
企業のイメージアップがファンの獲得につながり、ファンになってもらえれば長期的にブランドに対してのポジティブな反応を期待できます。
例えば、新商品や新しいサービスをリリースしたときなどに好意的にとらえてもらえる可能性があります。
ブランデッドムービーの事例

ここでは、実際にブランデッドムービーを制作して成功した事例を紹介します。
株式会社ユニクロ
引用元:www.youtube.com/@UNIQLO
株式会社ユニクロによるLifeWearをコンセプトに異なるシーンで商品を着用しているシリーズ動画で、映像とBGMだけで魅せるシンプルなブランデッドムービーとなっています。
BGMと映像だけを使用して日常で着られているユニクロの服をさりげなくシンプルに登場させているのが特徴です。
SNSでの拡散に成功しており、服の旅先という動画でBRAND SHORT 2021ナショナル部門を受賞し、ブランド価値を高めたといえるでしょう。
株式会社Z会
www.youtube.com/@zkaipr
通信教育大手株式会社Z会の受験生応援動画で、2人の学生がZ会の通信教育を利用して合格を目指すストーリーとなっています。
新海誠監督とのコラボで制作されたアニメーションで、オリジナル楽曲を使用されているのが特徴です。
再生回数1,300万回を超えて大きく注目を浴びるとともに、ストーリーに対する共感からブランドイメージの向上にも成功した事例です。
ブランデッドムービーを活用するメリット

ブランデッドムービーを活用するメリットは主に以下の4つの点があげられます。
- コンテンツ自体の価値を高められる
- SNSでの拡散が期待できる
- ブランドへの共感が生まれやすい
- 長期的に自社ブランドを想起してもらえる
ここでは、これらのメリットを一つひとつ詳しく解説します。
コンテンツ自体の価値を高められる
ブランデッドムービーの視聴を通してファンを増やすことができれば、企業ブランドや商品に対してよりよいイメージを持ってもらえる可能性があります。
また、一度制作したブランデッドムービーは企業にとっての大切な資産となります。
広告動画が一過性のPRであるのに対して、ブランデッドムービーは公開し続けることができる持続可能な価値のあるコンテンツです。
SNSでの拡散が期待できる
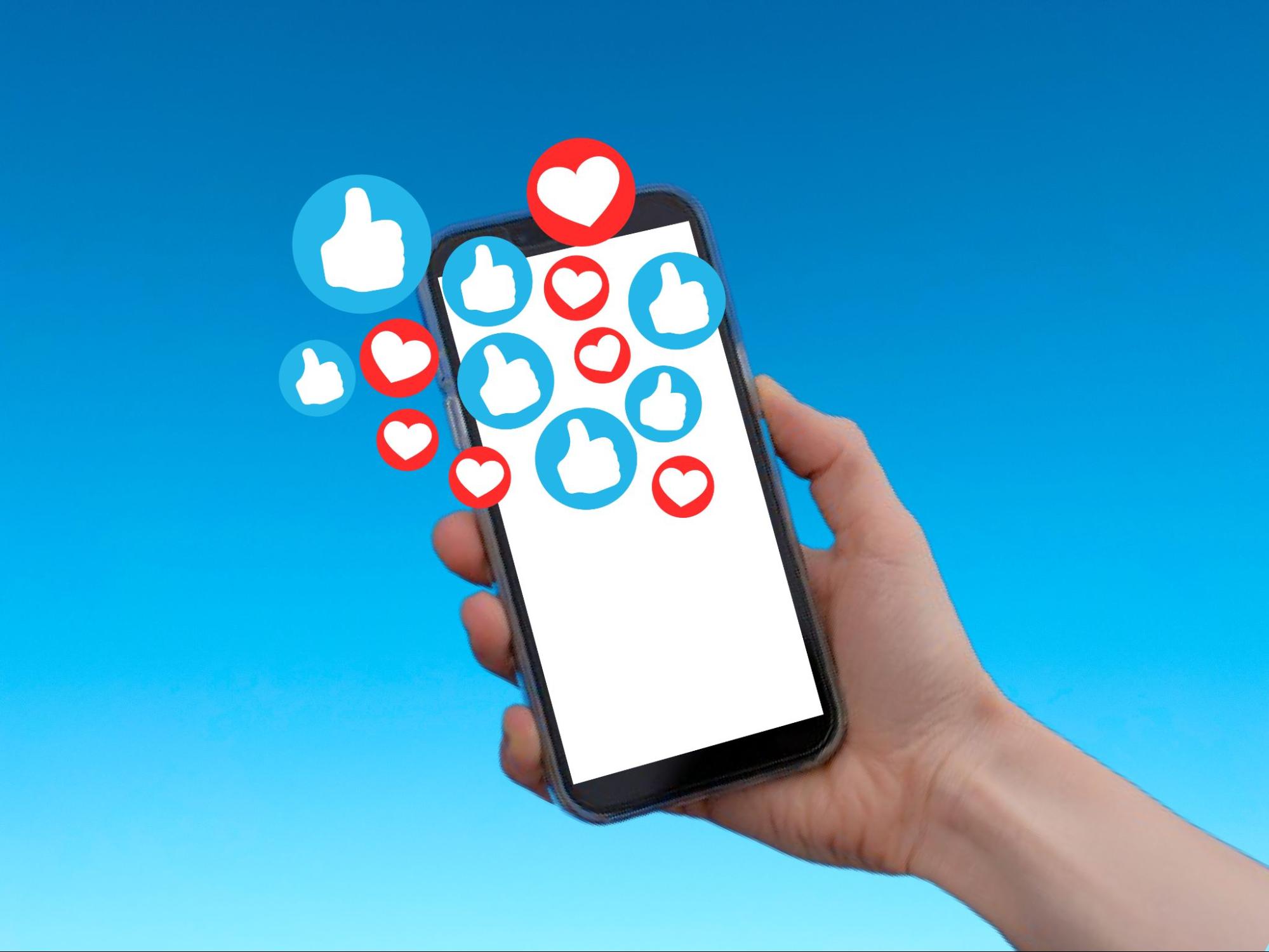
ブランデッドムービーを視聴するには、視聴者が自らコンテンツにアクセスして再生をする必要があります。
そのため、初めからその企業に対しての興味や深い関心がある状態です。
視聴者が動画を見て気に入れば、SNSで拡散してもらえる可能性が高くなります。
例えば、動画が感動的なストーリー仕立てであったり、企業に共感できるような内容になっていたりすれば拡散したいと思ってもらいやすくなるでしょう。
ブランドへの共感が生まれやすい
ブランデッドムービーは強制的な広告と異なり、視聴者が自発的に見るため、企業ブランドの理念や想いに共感されやすい特徴があります。
その結果、ブランドのファンになってもらえる可能性が高くなります。
一度ファンになってもらえれば、継続的に企業ブランドの商品やサービスに対して前向きな行動が見込めるでしょう。
長期的に自社ブランドを想起してもらえる

ブランデッドムービーは、ブランドへの共感を促したり価値を高めたりするものであるため、短期的な売上向上を期待するものではありません。
短期的な利益は得られませんが、長期にわたり自社ブランドを想起してもらえます。
ブランデッドムービーの役割は消費者のみにとどまりません。採用活動でも有効です。
求職者に企業の雰囲気を伝え、働く姿をイメージしやすくすることで、就職後のミスマッチを減らせます。
視聴者に共感を与えると同時に、企業理念を伝えて価値を高めるためにはストーリーの脚本が重要です。
また、ブランデッドムービーを作る目的やターゲットを明確にしなくてはなりません。
長期的に自社ブランドを想起してもらえて、価値を高める質の高い動画制作は専門家に依頼するのがおすすめです。
Funusualでは、企業の意図やメッセージをしっかりと反映した戦略的な動画制作を行い、ブランド力の向上に貢献しています。
スタイリッシュで洗練された映像表現はもちろん、視聴者の心に残る構成・演出の提案力にも自信があります。
「ブランドの世界観を表現したい」「印象に残る映像で企業の存在感を高めたい」など、ブランデッドムービーの制作に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にFunusualまでご相談ください。
ブランデッドムービーのデメリット

ブランデッドムービーは、動画広告に比べて好意的に受け入れられやすい一方、いくつかのデメリットもあります。
ブランデッドムービーは、短期的での効果が期待しにくく、制作にコストと時間がかかる点が課題です。
ここでは、デメリットの詳しい説明とその克服方法を解説します。
短期的な効果を出しづらい
ブランデッドムービーは、企業価値を確立し、ものづくりへの共感やイメージを向上させる目的で制作されます。
そのため、直接的な売上につながりにくい側面があります。この点が動画広告と大きく異なる点です。
ブランデッドムービーは長期的な視点で見た場合に、間接的な売上向上が期待できます。
ブランドへの想いに共感してくれるファンが生まれれば、長きにわたり愛されるブランドに成長するでしょう。
短期的な売上には直結しにくいものの、ブランド価値の向上につながるため、長期的な視点で考えることが重要です。
動画制作にコスト・時間がかかる

ブランデッドムービーの制作費用は一般的に、500,000〜3,000,000円(税込)程度です。費用の目安は次のとおりです。
- シンプルなイメージ動画:500,000円(税込)以内
- ストーリー性のある動画:500,000〜1,000,000円(税込)
- 複雑なストーリーテリングのある動画:1,000,000〜3,000,000円(税込)
- ハイクオリティな動画:3,000,000円(税込)以上
動画の内容以外にも、キャスティングやロケーションによって費用が変動します。
ブランデッドムービーによるプラスの効果を発揮するためには、一定以上の品質は保たなくてはなりません。そのため、動画制作のための予算確保が重要です。
また、ブランデッドムービーの制作は企画から納品までおよそ1〜2ヶ月かかる場合が一般的です。
シンプルな動画であれば1ヶ月程度で仕上がるものもありますが、アニメーション動画などは制作工程が多くなるため時間がかかります。
短期的な売上ではなく、長期的なブランド価値向上を目的に活用することが重要です。
ブランデッドムービー制作のポイント

ブランデッドムービーのメリットとデメリットを理解したところで、具体的な制作ポイントを理解しておきましょう。
動画を通じて視聴者に何を届けたいのか、そしてブランドイメージとはどのようなものなのかを制作前に明確化しておくことが重要です。
ここでは、ポイントを4つの項目に絞って解説します。
共有されることを意識する
近年、SNSが有効な拡散手段であることはいうまでもありません。拡散、共有されやすい動画には次のような特徴があります。
- 感動・共感される動画
- エンターテイメント性があっておもしろいと思ってもらえる動画
- ターゲットを明確にしてその層に刺さる動画
- SNSで拡散しやすいように、適切なハッシュタグや共有ボタンを活用する
これらの要素を取り入れることで、SNSで拡散されやすい動画を制作できます。
ストーリー・世界観を確立させる

企業の理想とするブランドイメージを伝えるには、ストーリーや世界観を確立することが重要です。
ストーリー性のある動画をショートムービーにするために大事なことは、ペルソナの設定です。
ペルソナは、架空のターゲット像を具体的に設定する手法です。年齢・性別・居住地や職業・趣味などを設定します。
ペルソナが設定できれば顧客目線のマーケティングに役立つでしょう。誰に対してどのようなメッセージを伝えたいのかを明確にしましょう。
編集スタイル・フォーマットを統一させる

編集スタイルやフォーマットが統一されていない動画制作は視聴者に企業イメージが定着しにくい可能性があります。
視聴者が企業のイメージを思い浮かべたときに、統一性のない動画を見ていたら企業のイメージがぼやけてしまいかねません。
ブランデッドムービーの制作にあたっては、一貫した編集スタイル・フォーマットを意識しましょう。
年に複数回リリースする
1本の動画によって企業のブランド価値を確立したり、共感や好意を高めたりするのはそう簡単ではありません。
テーマを変えつつストーリーや世界観を損なわないように動画を何度も発信しましょう。
複数回の発信で消費者にブランドイメージが浸透していきます。
「どのように構成すれば伝わる動画になるのか分からない」「編集やスタイルをどう統一すればいいか悩んでいる」そのようなお困りごとは、Funusualが解決します。
Funusualでは、お客様の目的や課題に合わせて適切なストーリー設計と映像表現をご提案いたします。
「説得力のあるストーリーで企業の魅力を伝えたい」「見た人の記憶に残る動画を作りたい」とお考えの方は、ぜひFunusualへご相談ください。
ブランデッドムービーの効果測定方法

ここでは、ブランデッドムービーの効果を具体的にどうやって測定すればよいのかという疑問にお応えします。
測定方法は、指名検索数やUGCを調べる方法や購買単価を調べる方法があります。
一人あたりの購入頻度の変化を調べる方法も有効な測定方法です。
これらの測定方法を使用して、ブランデッドムービー運用の参考に活用しましょう。
指名検索数やUGCを調べる
指名検索とは、特定の企業名や商品・サービス名を指名して検索することをいいます。指名検索数の調べ方は以下のとおりです。
- Googleトレンド:簡易的で期間内の最大検索数を100としたときの相対的な数字
- Googleキーワードプランナー:実際の検索数がわかる
- Googleサーチコンソール:直近の検索数をより正確に調べられる
指名検索を行った消費者は、購入意欲の高い見込み顧客といえます。
消費者の購買行動をうながすためにも、指名検索数を増やすことと、自社サイトへ誘導する対策を講じる必要があります。
UGC(ユーザー生成コンテンツ)とは、消費者が自発的に発信するコンテンツのことを指します。例えば、以下のようなものがUGCと呼ばれています。
- Instagramに投稿された動画や画像
- Xを含めたSNSへの投稿・共有
- ECサイトの商品レビューや評価
- ブログでのレビュー
UGCは消費者のリアルな意見なので、共感されやすく信頼されやすい情報になっています。
商品やサービスを購入する際にはこうした意見投稿やレビューを参考にして購入する方も多く、UGCのマーケティングに対する役割はとても重要です。
指名検索数が増えたり、UGCで高評価を得たりしていれば、ブランデッドムービーの効果が出ているといえるでしょう。
購買単価を調べる

購買単価とは、顧客が一回の購買行動で支払う平均金額のことを指します。顧客が購入する商品のうち、単価の高い買い物が増えたかどうかを調べます。
少し高い金額を払ってでも、商品を購入したいと考えるのは企業やブランドに対する共感が得られたからでしょう。
このように、購買単価を知ることでブランデッドムービーの効果を測定できます。
一人あたりの購入頻度の変化を調べる
ブランドに対してのイメージが向上したり、共感が得られたりした場合は、顧客の購入頻度が増加します。
既存顧客であっても、もっとこのブランドの商品を買いたいと思ってもらえれば購入頻度が変化するため、動画の効果を測定できるでしょう。
ブランデッドムービーは重要!プロの技術を活用しよう

ここまでブランデッドムービーの狙いや現在注目されている理由、活用するメリットや動画制作のポイントを解説してきました。
短期的な売り上げにはつながりにくいですが、長期的に売り上げを伸ばすことができるブランデッドムービーは時代の流れに合致したマーケティング手法です。
戦略的にブランデッドムービーをつくり、ぜひ企業のブランド価値を高めてファンを増やしましょう。
初めて動画を制作する場合は、どの制作会社に依頼すればよいのか不安に感じる方も少なくありません。
Funusualでは、短時間で視聴者の心を動かし、印象に残る動画制作を得意としています。
会社紹介映像・展示会用プロモーション動画・ブランデッドムービー・アニメーション動画まで、幅広いジャンルに対応しながらも一貫して高品質な仕上がりをご提供することが可能です。
専任のプロデューサーとディレクターが丁寧にヒアリングし、企画から納品までをしっかりリードしたうえで、企業の想いやストーリーを伝える映像で、ブランドの価値を映像で表現します。
「ブランドを映像で表現したい」「感情に訴える動画を作りたい」とお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。













