近年、多くの企業が採用活動の一環として動画を活用するようになっています。
求職者にとって、企業の雰囲気や働く環境を視覚的に理解できる採用動画は、求人サイトの文章や写真だけでは捉えきれないリアルな情報を把握できる強力なツールです。
しかし、「どのような採用動画が今の求職者に響くのか?」「成功事例はあるのか?」「どう作れば効果的なのか?」と、疑問を持つ企業の採用担当者も多いのではないでしょうか。
また、動画を制作するにあたって、自社で作るべきか、外注するべきかの選択に悩む方も少なくありません。
本記事では、採用動画のトレンドを紹介するとともに、トレンドを活用した成功事例と求職者の関心を引く採用動画の作り方を解説します。
さらに、採用動画の効果や制作のコツも詳しく説明し、自社制作と外注した場合の違いを比較します。
採用動画の導入を検討している企業の担当者の方は、ぜひ本記事を参考に今の求職者に響く採用動画のトレンドを理解し、自社の採用戦略に活かしてみてください。
採用動画とはどのようなものか

採用動画とは、企業が求職者に向けて発信するブランディングツールの一つです。
文字や写真だけでは伝えきれない企業の雰囲気・価値観・働く環境を、動画を通じて視覚的に伝えられる点が大きな特徴です。
また、動画はストーリー性を持たせることが可能です。
単なる事業説明だけでなく、「どのような方たちが働いているのか」「日々どのような業務に取り組んでいるのか」などを、求職者がイメージしやすい形で伝えられます。
近年、企業の採用活動は競争が激化しており、求職者が企業を選ぶ際の基準も多様化しています。
そのなかで、採用動画は企業の魅力を効果的に伝える手段として注目されているのです。
特に、遠方に住む求職者やオンライン選考を希望する人材に対しても、場所や時間を問わず企業の魅力を届けられることが大きなメリットです。
さらに採用動画を活用することで企業のブランドイメージ向上も期待でき、自社の理念やビジョンを映像として発信することで、「企業と求職者の相互理解」が深まる結果につながるでしょう。
採用動画は単なる人材募集のためではなく、自社にマッチした人材を引き寄せ、ミスマッチを防ぐための効果的なコミュニケーションツールです。
Funusualでは、企業の採用課題やターゲットにあわせたオリジナルの採用動画を制作しています。
採用動画のトレンド

採用市場の変化に伴い、企業が求職者にアプローチする手法も進化しています。
特に、採用動画のトレンドは年々変化しており、求職者の関心を引くには、新しいトレンドを押さえることが重要です。
現在、企業の採用動画にはリアルな職場の雰囲気を伝えるものや求職者とのエンゲージメントを高めるものなど、さまざまなスタイルが登場しています。
採用動画のトレンドについて、以下で詳しく解説します。
社員の本音と職場の実情を伝える動画

求職者は、企業の実際の雰囲気や社風を重視しています。そのため、社員のリアルな声や職場の実情を伝える動画が人気です。
社員インタビューや座談会を通じて、仕事のやりがいや環境をありのままに伝えることで、求職者が自分の働く姿をイメージしやすくなります。
また、企業側にとっても文字だけでは伝えきれない社内の雰囲気や職場文化をアピールできるため、ミスマッチの防止にもつながります。
こうした動画は、YouTubeやSNSで拡散されやすく、多くの求職者の目に留まる点も大きなメリットです。
プロモーションを伝えるアニメーション動画
近年、アニメーションを活用した採用動画も注目されています。特に、IT企業やスタートアップなど、デジタルに強い企業が導入するケースが増えてきました。
アニメーション動画の魅力は、企業の文化や魅力をビジュアル的にわかりやすく伝えられる点にあります。
実写と違い、映像の自由度が高いためストーリー性のある演出が可能であり、視聴者の記憶に残りやすいのが特徴です。
また、制作コストを抑えやすい場合もあり、予算が限られている企業にとっても導入しやすい手法のひとつです。
さらに、アニメーション動画はSNS広告との相性がよく、ターゲットに応じた広告展開がしやすい点もメリットとして挙げられます。
求職者に向けた社長のメッセージ

企業のビジョンや理念を伝えるには、社長や経営陣のメッセージ動画が効果的です。特に、企業の方向性や価値観を重視する求職者にとって、トップの考えを直接知ることはとても重要です。
経営者自らが企業の未来や求める人材像を語ることで、求職者に対して信頼感や共感を生み出すことができます。
また、新卒採用は、経営者の価値観が企業選びの重要なポイントとなるため、こうした動画は採用活動の強力なツールです。
インタラクティブ動画
最近では、視聴者が選択肢をクリックして内容をカスタマイズできるインタラクティブ動画も注目されています。
通常の動画とは異なり、視聴者が興味のある内容を選んで進められるため、よりパーソナライズされた情報提供が可能です。
インタラクティブ動画は求職者の関心を引きやすく、視聴完了率が高い特徴です。企業側も、求職者が選んだ選択肢を分析し、関心の高いコンテンツを把握しやすくなります。
海外では、GoogleやAmazonなどの大手企業が採用活動にインタラクティブ動画を取り入れており、IT業界を中心に活用が進んでいます。
このように、採用動画のトレンドは求職者のニーズに応じて進化を続けており、柔軟な対応が不可欠です。
特に職場のリアルな雰囲気を伝える動画や、企業のビジョンを表現するアニメーション動画・インタラクティブ動画など、多様なスタイルの動画が活用されるようになりました。
トレンドを踏まえた採用動画の事例

ここでは、実際にトレンドを取り入れた採用動画の成功事例を紹介します。
企業ごとに異なる目的やターゲットに応じて、さまざまな手法が活用されています。
どのような採用動画が求職者の関心を引き、効果を発揮しているのかを具体的に見ていきましょう。
リクルート
社員インタビューや座談会形式の動画は、求職者に企業のリアルな姿を伝え、自分が働く姿をイメージさせる効果があります。
どのような先輩社員がいるのか、どのような働き方ができるのかを紹介すれば、企業の魅力も具体的に伝わります。
リクルートの採用動画では、社員が実際に働く環境を動画で紹介しながら、座談会形式で本音を語る採用動画を制作しました。
動画内では、入社の決め手や仕事のやりがいを社員がリアルに語っており、求職者にとって自分が働くイメージが湧きやすい構成になっています。
引用元:www.youtube.com/@recruitholdings
トヨタ
企業のオフィスや職場の雰囲気を映像で伝えることで、求職者に対する企業イメージの向上が期待できます。
トヨタの採用動画ではオフィスの様子や工場での作業風景を取り上げ、職場のリアルな環境を映し出しながら、どのような仕事をするのかを具体的に示しているのが特徴です。
特に若手社員が登場するシーンでは、成長できる環境であることを強調しており、新卒求職者に向けたメッセージ性の強い動画となっています。
引用元:www.youtube.com/@netzmie_recruit
三菱地所株式会社
プロモーション動画は企業の理念やブランドイメージを効果的に伝え、求職者の印象に残ることが期待できます。
三菱地所株式会社の採用コンセプトムービー は、NANIMONOというキャッチコピーを用いて、多様な人材が活躍できる企業であることを強調しています。
リズミカルな編集とスタイリッシュな映像で、視聴者に強い印象を与えているのが特徴です。
引用元:www.youtube.com/@mec.recruit
視聴者が選択肢をクリックしながら進めるインタラクティブ動画は、求職者の関心を引きつける革新的な手法です。
Googleの採用動画では、視聴者がエンジニア向けやマーケティング向けなど、自分に合ったキャリアを選びながら進められるインタラクティブ採用動画を導入しています。
求職者は自分が働くポジションをイメージしやすくなり、適切な部門への応募を促す仕組みです。
トレンドを取り入れた採用動画の事例を紹介しましたが、いずれの企業も求職者に働くイメージを持たせ、企業の魅力を伝えることを目的としています。
引用元:www.youtube.com/@LifeatGoogle
トレンドを踏まえた採用動画で期待できる効果

トレンドを取り入れた採用動画は、企業の採用活動にさまざまなメリットをもたらします。
特に、求職者に企業の魅力を効果的に伝えられるだけでなく、エンゲージメントの向上や採用プロセスの効率化にもつながる手法です。
トレンドを活用した採用動画によって期待できる効果を紹介します。
実際に働いている姿をイメージしてもらえる

採用動画を活用すれば、求職者は会社で働く自分の姿を具体的にイメージしやすくなります。
特に社員インタビューやオフィスツアー動画などは、職場の雰囲気や働く環境をリアルに伝えることができ、入社後のミスマッチを減らす効果があります。
またインタラクティブ動画を活用すれば、求職者が自分に合った職種を選びながら情報を収集できるため、より一人ひとりにあわせた採用プロセスの実現が可能です。
企業の認知度拡大が期待できる
採用動画は、企業の認知度向上にも大きく貢献します。特に、SNSやYouTubeで拡散されることで、従来の求人広告ではリーチできなかった層にもアプローチできるのが大きな強みです。
さらに、アニメーション動画を活用すれば、ブランドの世界観や企業文化を表現しやすく、視聴者の印象に残りやすい点が特徴です。
トレンドを取り入れた採用動画を活用し、求職者に働くイメージを持たせ、企業の認知度を向上させる効果が期待できます。
トレンドを踏まえた採用動画制作のコツ
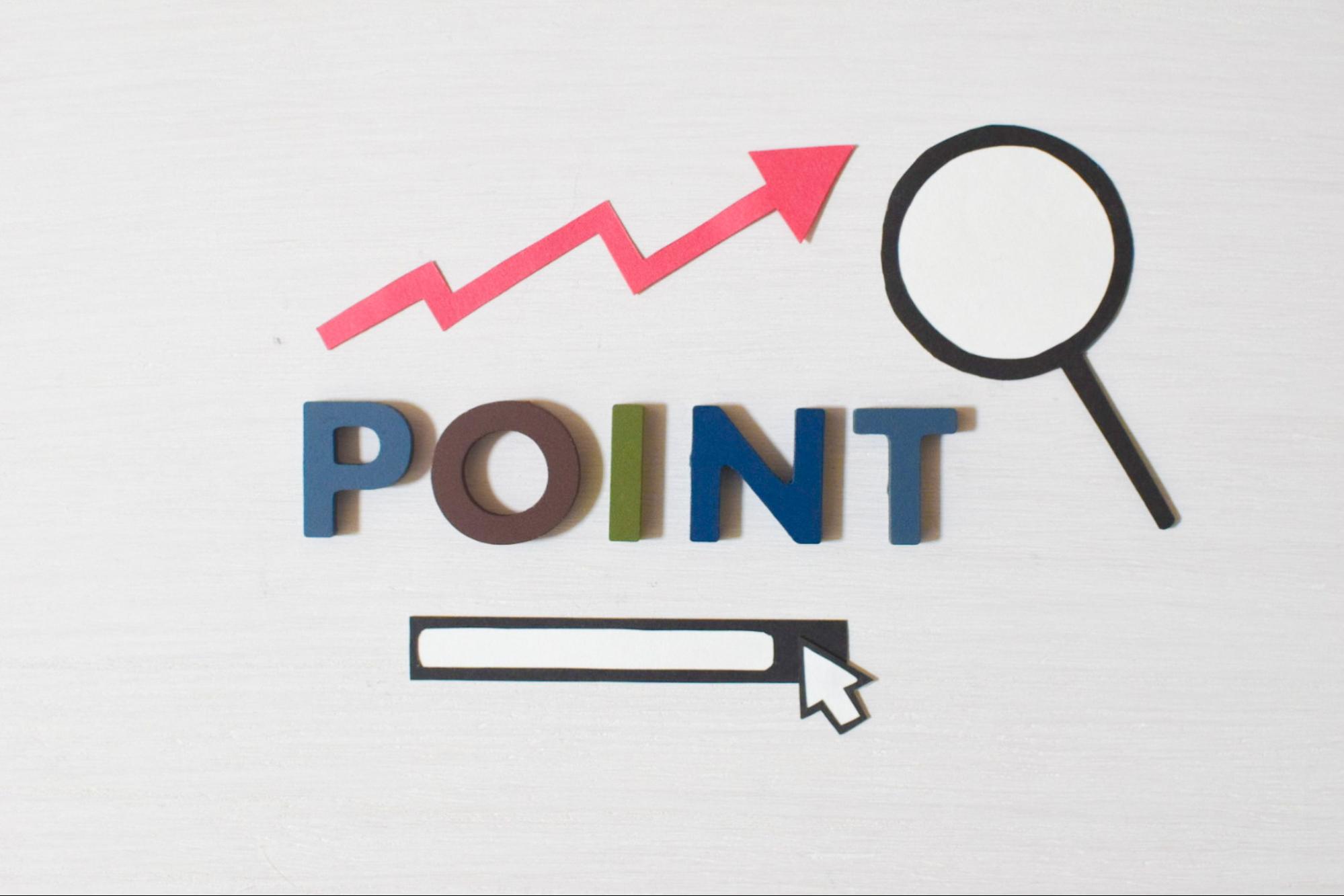
トレンドを取り入れた採用動画を制作する際には、単に映像を作るだけでなく求職者の関心を引き、企業の魅力を効果的に伝えるための工夫が必要です。
成功のカギは、ターゲットを明確に設定し、発信するメッセージの内容を具体的に定める点にあります。
採用動画を制作する際に押さえておくべき4つのポイントを紹介します。
ターゲットを明確にする

採用動画を制作する際には、まずどのような層の求職者に向けた動画なのか?を明確に設定する必要があります。
新卒採用向けの動画と中途採用向けの動画では、求職者が求める情報が異なるため、それぞれに適した内容を設計する必要があります。
例えば、新卒採用の場合は会社の文化やキャリアパス、若手社員の働き方に焦点を当てると効果的です。
一方で、中途採用では即戦力としての活躍の場や企業の成長戦略、評価制度などの情報が求められます。そのため、より具体的な仕事内容や企業のビジョンを伝える内容が適しています。
求職者の知りたいことに寄り添う
採用動画を作る際には、企業側が伝えたい情報だけでなく、求職者が本当に知りたい情報を提供することが重要です。
求職者が関心を持つポイントは、以下のような要素が挙げられます。
- 企業のリアルな雰囲気(職場環境や社員同士の関係性)
- 実際の業務内容(仕事内容や1日の流れ)
- 働き方・キャリアパス(成長の機会や研修制度)
- 企業のビジョンや将来性(どのような方向に成長していくのか)
例えば、社員インタビュー形式の動画では、実際に働く社員が入社して良かったことや苦労したことを率直に語ります。
こうした内容によって、求職者にとってリアルで信頼性の高い情報を届けることが可能です。
企業として伝えたいことを整理する

採用動画は、企業の魅力を伝える重要なツールですが、情報を詰め込みすぎると、視聴者にとってわかりづらい動画になってしまいます。
そのため、動画で1番伝えたいメッセージは何かを明確にし、シンプルかつインパクトのある構成に仕上げることが重要です。
例えば、社員インタビュー形式の動画では、実際に働く社員が入社して良かったことや苦労したことを率直に語ります。
こうした内容は、求職者にとってリアルで信頼性の高い情報となり、応募への後押しにもつながるでしょう。
また、ストーリー性を持たせることで、より記憶に残る動画を作ることができます。
例えば、入社1年目の社員が成長するストーリーや企業の創業から現在までの歩みなど、視聴者が共感しやすい内容を取り入れるとよいでしょう。
活用方法を決めておく
採用動画は制作して終わりではなく、どのように活用するかが重要です。
特に、ターゲットに適したチャネルで配信すれば、より多くの求職者へのリーチが可能です。
下記は主な活用方法です。
- 企業の採用サイトに掲載(求職者が情報を探す場所)
- YouTube・SNSで拡散(幅広い層にリーチできる)
- 採用説明会で上映(求職者に直接見せることで興味を引く)
- 求人サイトの企業ページに埋め込む(応募を促進する)
また、動画の長さも、活用方法にあわせて調整する必要があります。SNSや広告用なら30秒~1分程度の短い動画が効果的であり、採用サイトや説明会向けなら3~5分程度の詳細な動画が適しています。
トレンドを踏まえた採用動画は内製か外注か
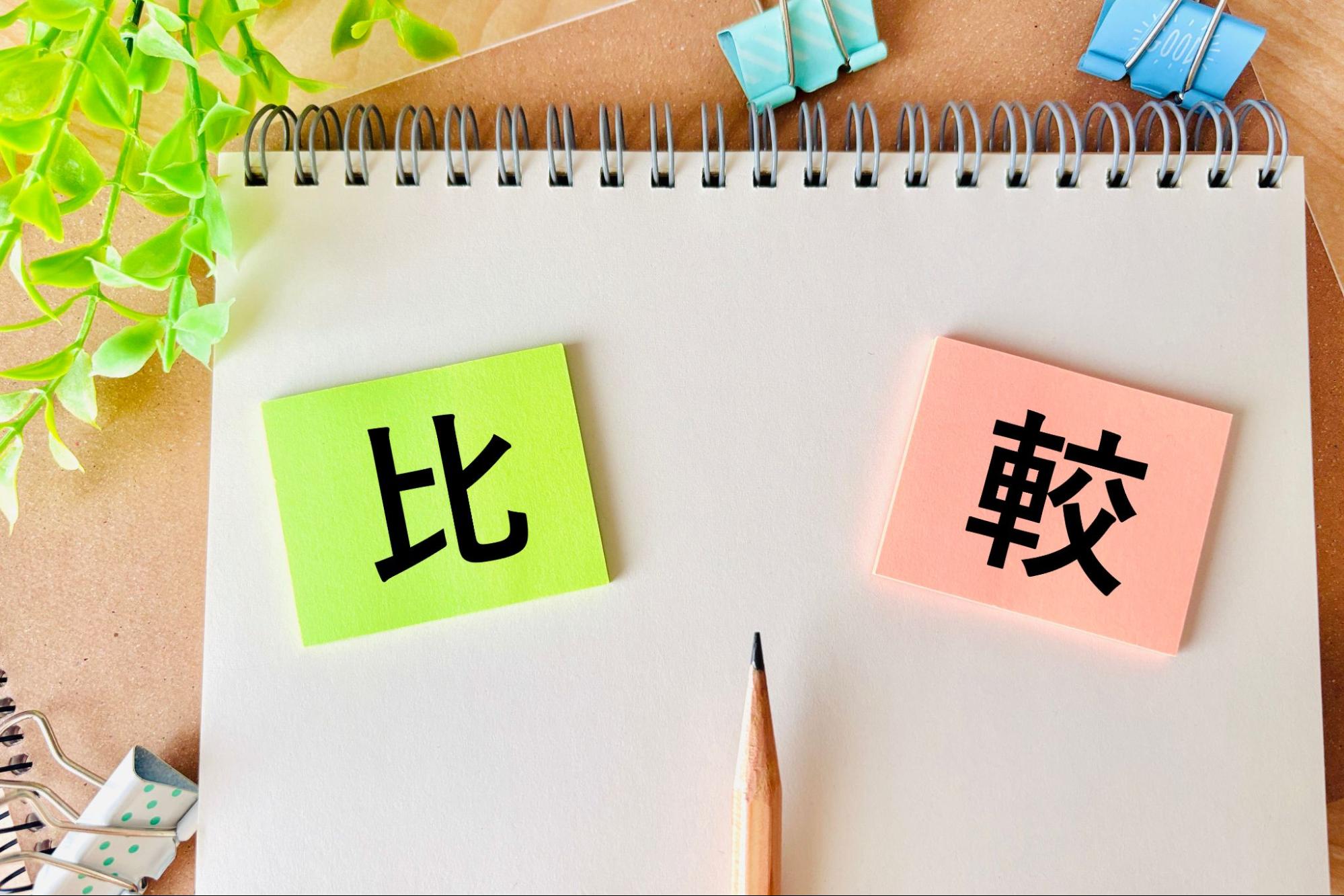
採用動画を制作する際自社で作成するべきか、あるいはプロに依頼するべきか、と悩む企業も多いでしょう。
自社制作とプロへの依頼のいずれが適しているかは予算・求めるクオリティ・かけられる工数などの要因によって異なります。
内製と外注のそれぞれの長所と短所を比較し、適した選択を検討します。
内製する場合のメリットとデメリット
内製のメリットは、コストを抑えられることです。
外注に比べて制作費が大幅に削減でき、特に採用予算が限られている企業や、継続的に動画を更新・追加したい企業にとっては大きな利点となります。
また、外部とのやり取りが不要なため、スピーディーな制作や修正が可能です。
例えば、急な採用ニーズや制度変更に合わせて、即時に動画の内容を見直すこともできます。
さらに、社内で企画・編集を行うことで、その企業らしさや独自のカルチャーを反映しやすい点も魅力です。
社員のリアルな声や日常の様子など、外注では拾いきれない細かな部分まで盛り込むことができます。
一方で、クオリティの確保が難しく、制作に時間がかかるといった課題もあります。
動画編集や撮影のノウハウが社内にない場合、情報を詰め込みすぎて伝わりづらい・映像が素人感満載といった問題が起こりやすいです。
また音声や照明、構成など細部に配慮が欠けると、かえって企業の印象を下げてしまう恐れもあります。
さらに、内製だと市場や求職者のトレンドを取り入れる視点が不足しがちで、結果的に時代遅れの印象を与えてしまうリスクも否めません。
特に若手層やデジタルネイティブ世代をターゲットとする場合、動画のクオリティが応募率に直結するため注意が必要です。
そのため、内製を選ぶ場合は、社内に一定のノウハウを蓄積することや、簡易的な制作を目的と割り切るなど、目的に応じた使い分けが求められます。
外注する場合のメリットとデメリット

外注のメリットは、プロの技術とノウハウを活かした高品質な動画を制作できる点です。
映像や編集のクオリティが高いため、採用ブランディングの一環として企業イメージの向上が期待できます。
さらに、新しいトレンドや視聴者の好みに沿った動画表現が可能なため、特に若年層やデジタルネイティブ層への訴求力も高まります。
また、制作を専門会社に任せることで社内リソースを大幅に節約できるため、人事担当者が本来の業務に集中できることも大きなメリットです。
一方で、コストが高くなりがちな点は注意が必要です。特に複数の動画を制作・更新する場合、予算への影響は無視できません。
また、完成までに一定の期間を要するため、急な採用ニーズや変更へのスピーディーな対応が難しい場合もあります。
さらに、制作会社のディレクションや理解度次第では、企業の独自性や雰囲気が十分に反映されない可能性もあるため、依頼先の選定と事前のすり合わせが重要です。
このように、スピーディーかつ低コストで制作したい場合は内製、ブランドイメージを重視した高品質な動画を求める場合は外注が適しています。
いずれにしても、予算・社内リソース・動画の目的を踏まえて、適切な方法を選択することが重要です。
Funusualでは、企業の採用課題やターゲットにあわせたオリジナルの採用動画を制作しています。
「自社の魅力をもっと具体的に伝えたい」「求める人材からの応募が増えない」「他社と差別化した採用コンテンツを作りたい」といった課題をお持ちの方は、ぜひご相談ください。
Funusualでは、企業様それぞれの個性や強みを丁寧にヒアリングしたうえで、求職者の心に響く採用動画をご提案いたします。
採用活動を強化したいとお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
採用動画の外注先を選ぶポイント

採用動画の制作を外注する場合、依頼する制作会社の選び方が、採用活動の成果を大きく左右します。
制作会社ごとに得意分野やクオリティ、対応範囲が異なるため、適切なパートナーを見極めることが重要です。選定のときにチェックすべきポイントを紹介します。
制作事例が豊富であること
多くの動画を手がけた経験のある会社は、さまざまな業界や目的に応じたノウハウを持っているため、より適切な提案を受けることができます。
過去の制作事例を確認し、自社の採用動画の方向性に合うかをチェックしましょう。
撮影技術のバリエーションがあること
企業の魅力を伝えるためには、撮影技術の幅広さも重要です。
実写・アニメーション・インタラクティブ動画など、トレンドを活かした表現ができるか確認しましょう。
特に採用動画では社員インタビューやオフィス紹介など、リアルな映像表現が求められるため、技術力の高い会社を選ぶことがポイントです。
コミュニケーションが円滑なこと
動画制作は、企画から撮影・編集・修正まで長期的なやり取りが発生するため、制作会社との相性も大切です。
スムーズな意思疎通ができるか、細かい要望に対応してくれるかなど、初回の打ち合わせで確認しましょう。
特に、採用動画では企業のブランドイメージを正しく伝えることが重要なため、密にコミュニケーションを取れる制作会社を選ぶことが成功の鍵になります。
トレンドを踏まえた採用動画制作はプロに任せよう

採用動画は、企業の魅力を視覚的に伝え、求職者の関心を引く重要なツールです。
特に、トレンドを取り入れた動画は、より多くの求職者の目に留まり、採用活動の成果を向上させることが期待できます。
ただし効果的な採用動画を制作するには、戦略的な構成・撮影技術・編集スキルが必要となり、内製では限界を感じることもあるでしょう。
そのため、トレンドを押さえた質の高い動画を制作したい場合は、プロの制作会社に依頼するのがおすすめです。
Funusualでは、企業ごとの採用課題やターゲットに合わせたオリジナルの採用動画を企画・制作しています。
これまでに培った豊富な経験と確かなノウハウを活かし、企業の魅力を最大限に引き出す映像コンテンツをご提案いたします。
「求職者に刺さる採用動画を作りたい」「企業の想いをしっかり映像で伝えたい」とお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。













